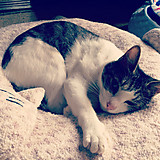僕たちは希望という名の列車に乗ったのレビュー・感想・評価
全81件中、21~40件目を表示
最も恐ろしこと
若者の決断
たった2分間、黙祷をしただけで。
この現代ではただそれだけのことが、東ドイツという国で帯びる意味。最初は内々に済まそうという展開だったはずが、あっという間に追い詰められていく若者たち。追い詰め方が半端ない。何としても首謀者を見つけ出そうとする政府。「言論の自由がない」という状況をリアルに実感させられる。
自分たちだけではなく、家族にも影響が及ぶ尋問。決断し行動すること、思っていることを言うことが、あの時代、あの国ではまさに命がけと言っても良い。
最初選んだように弁解し逃げ切るのも取り得る道ではあったと思う。まあ、それはあっという間に塞がれてしまうのではあるが...。私だったらどうにか逃げようとしてしまう気がして、とても葛藤した。
若者それぞれの、親との関係性も非常に興味深かった。親への反発、畏敬、そして真実。本当に「上の者」は情報を巧みに扱うのが上手い。若者を的確に揺さぶる。
その中でも、母の言葉、父の表情、握手の重みが親の感情をひどく感じさせた。行く方も残される方も、覚悟が要るのだ。
しかし最後に提示されるのが「希望」でよかったと思う。とても難しいけれど、唯々諾々と生きるより、自分で考えることは大切なのだ、と感じた。
自由、自由、自由!
信念を貫く
しばらく席から立てず
ハリーポッターシリーズで好きな作品といえば「不死鳥の騎士団」なのですが、更にその好きな部分を濃縮したような作品でした。
まだベルリンの壁ができる前の東ドイツ、社会主義国家ソ連占領下。高校の生徒たちは授業開始後、同じくソ連占領下のハンガリーにて自由を求めた人へ追悼の意を込めた2分間の黙祷をする。
その行為が社会主義国家への反逆とみなされ、最初は学校の教師から、校長、教育局員と徐々に事態が大きくなり、教育大臣までもが、誰が首謀者か尋問に乗り出す。信念を貫いて仲間とともに歩むのか、友人を裏切りエリートコースを進むのか。
祖父の墓参りと同じような気持ちだったのだろうか、社会主義への反骨精神だったのだろうか、ただ単に興味本位で多数決に乗っただけなのだろうか...
個々の生徒がどのような気持ちで黙祷していたか分からないが、"たった2分間"が許されない状況になる社会主義の怖さを感じました。
史実を基にした社会派映画であることに加え、こんな青春したかったと思わせるぐらいに、青春ものとしても濃度が高い。家庭と学校、友情と恋愛、社会的地位と自由、困難や葛藤に対し、自ら考え、互いに主張し合う。
本作に出てくるキャストそれぞれ個性のある登場人物を演じ、それぞれにしっかりと焦点を当てて、描写が丁寧なため、キャラが生きていた。特にパパさん2人が良かった。対照的ながらもやはり自分の子供は可愛いのだなと。後、教育局調査官のケスラー。醸し出る冷徹な雰囲気や表情が凄まじかった。生徒の集会所であったパウルの叔父宅への訪問シーンは、終始全ては映されないが想起される非情な仕打ちが怖い。
国家に睨まれる深刻さを表現しつつも、ラストは親子関係に話が展開するのも見事でした。
ハッピーエンドなのか、バッドエンドなのか、列車に乗った後はどうなったのか、色々と思いが巡り、エンドロール後もすぐには席を立てず。
ドイツの若者は強い❗
星🌟🌟🌟🌟🌟ドイツ映画はあまり見ないのですが…凄く良かったです❗東ベルリン、西ベルリンの頃はあんまり知らなくてベルリンの壁も途中で出来た事を初めてこの作品で知りました❗もしベルリンの壁のあとの出来事だったら希望と言う名の列車に乗れず違った人生を歩んでいたと思うと感慨深いです❗観終わったあと思ったのですが高校生位の子達が家族を残してでも西側に行く決断をしたのは凄いと思う❗もちろん家族の援助も有ったと思いますが…壁がなくなった今は一緒に暮らす事が出来てるのでしょうか?ちょっと気になりました❗なにはともあれ最初から最後まで展開が気になり惹き付けられて観た良い映画でした❗演じる若者たちもイケメン美人を揃えていて違った意味でも見応えがありました❗
「言い逃れをする人は嫌いなの」
この内容のどこまでが史実に則っているのかは分らない。監督の発言でも、事実とサスペンス要素とのバランスに気を遣ったということなので、あくまでもエンタメとしての出来を重視した結果だと思うし、それがかなり高レベルで実現されている作りだと感じる。きちんと伏線は回収されているし、なによりも若い俳優達の力量の高さを窺える。但し、独語が分らない(※第二外国語専攻は独語なのに…苦笑)ので、どこまで台詞回しが出来ているのか、棒読みなのかは不明。
悪ふざけが社会主義国内での厳格さ故、融通が利かない、否、それを利用して成り上がろうとする大人に利用される子供達の波瀾万丈話という筋書きである。イデオロギーなんてものは、結局人それぞれの資質の問題に集約していくのであって、本来ならば人間は原始的なアナーキズムが一番ストレスフルなのは明白だ。それを示唆する台詞がラスト前の「自分で決めろ」という台詞である。そういう意味では、登場人物のアナーキストの大叔父の立ち位置が目指すべき、在るべき姿なのかもしれない。まぁ、あんな風に自由に生きられるのも、結局“地獄の沙汰も金次第”ってことなんだろうか(苦笑
ストーリーに戻すが、登場人物達のそれぞれがしっかりとバックボーンを帯びていて、それが原因と結果を表現しているし、物語の関連性をまるでパズルのピースのように繫ぎ合せている緻密さに感心する。脚色が非常に高度なのが誰が観ても明らかだ。表題を例に出しても、男を裏切った女はそれなりにその理由が納得出来る作りなのだ。それぞれにそれぞれの意志とそこに至るまでの原因が納得出来るから、しっかり考えさせられる。まるでモグラ叩きみたいにそれぞれの正義を理解できてしまい、一体この騒動の元凶がなんなのかが揺らいでしまう、そんな良く練られた演出に驚愕である。特に、告げ口をする教師と郡学務女性局員の二人の立ち回りは、“シュタージ”を彷彿させる、いやもしかしたらそのものなのかもしれない怖さを充分知らしめてくれた。保身のため、出世のためならば、周りを奈落に貶めても遂行する、人間の弱さを突きつけられた激辛の作品である。主人公の父親である市会議員が、心替えして、最後に息子を助ける件は、もう少し丁寧に表現して欲しかったと、少しばかりの残念な部分を付け足しておく。
自己判断
自由という名の駅を目指して。
冒頭、テオの脳タリンチャラ男感に、正直、不安になり。こんなノリなんか?若気の至りの話???じゃ終わらなかった。良かった。とっても!
社会主義の管理抑圧からの解放の欲求。家族からの想いと家族への想いが交錯するクラス。ドラマが重いです。
平等だから「同士」と呼ぶルール。明白に上下関係有りますけどね。マヤカシの革命。
「反革命分子」。イヤイヤ、単なる反体制です。革命前より息苦しく、生き難く、言い難い革命政府へのレジスタンス。
希望ってなんなんだろう。
よしんば、あのまま高校大学を卒業したとしても。彼等の最大の政治的な不満はソ連の支配下にある事。自由の無い社会主義体制。その体制のヒエラルキーの上位に地位を求めるのが、希望なのか。ハンガリーへの共感者が半数を超えていた事は、当時の東ドイツの内情を映したものなのだと思う。
労働階級に甘んじず。だが上位に上がるためには体制には逆らえない。この位は大丈夫だろうと言う甘さが見逃されない程に、体制側も神経を尖らせてたのだ。「壁」が完成するのは、それから5年後のこと。この時代、テオ達は何を考え、どう生きたのだろう。
自由からの孤立。希望からの隔絶。それが「ベルリンの壁」。
二つの家族。二人の父親と、二人の母親が、同じ様に子供を送り出すのが印象的。ここには希望が無いから。無くなってしまったから。子を思う気持ちから。だけじゃ無い。
俺の様になるな。はテオの父の想い。だから高校を卒業して大学へ進め。
俺の様に生きろ。クルトの父。
二人の父親の下した結論は、同じだった。
隅から隅まで、些細な小ネタまで、胸に刺さるもんで。列車の中の景色が好き。遠足にでも行く様にクラスメイトが集まっていて。一人では下せなかったであろう選択、行動。やっぱり、仲間なんだ!一緒だから踏み出せるんだ!
本当に良かった。
「事実」は最高のストーリーテラー
特に若者に見てほしい
傑作
今年は3月から4月後半まで映画を観られなかったので、アカデミー賞関連の作品や良作をかなり見過ごしちゃった気がする。
そんな状況だったけど、この作品はここ数年間でベスト5に入るほど心に残る素晴らしい作品だった。
.
邦題が作品の行く末を示してるなぁと思っちゃったけど、そんな想像も何のその。
彼らの無意識に取った行為が、どんどんと予想外の事を招き、親子の関係や友情さえどうにかしてしまう展開にストーリー半ばから
もうボロ泣き。。
.
これが史実だと考えるだけで、涙がまた溢れてきそうな位、
余韻がまだ残ってる。
.
舞台は敗戦国であり、東西に分断された東ドイツ。
戦後の複雑な国家関係や、国柄による階級、
主義も混沌としたなかで、主人公となる18歳の高校生の
彼らの若者らしい正義感を失わない姿や、爽やかな関係性と、時に残酷な状況に陥っても決して友を見捨てる事無く連帯してゆく
姿に感動が止まらなかった。
そして18歳の彼らに将来の選択さえ与えない権力に対し自ら道を切り開いてしまう彼らの勇気と行動には尊敬さえ感じてしまった。
戦後社会の重厚な背景のなかに若者の将来性、国柄の歴史を示す夫婦関係、そして親子の強い絆さえも描いていゆくバランスの取れた傑作。
サントラもピアノの旋律や重低音のような音の強弱が作品に色を添えているのが心を揺さぶる要因の一つでもあった。
.
主義や思想、環境によって血の繋がった親子でも考え方は大きく相違する事や、階級によって家庭環境の差も生まれてしまう社会も
上手く描かれていて脚本、脚色が本当に素晴らしい。
.
原作にどこまで忠実に描かれているのかはわからないが、
監督の手腕と若い俳優さん達の熱の伝わる作品なのは
間違えない。
.
原題は「静かな教室」だそう。行く末が判ってしまうと
書いたけど、最近の邦題ではピカイチだと思う。
まだ公開はしているので、
時間があれば是非観ていただきたい作品です。
われわれも「希望」という名の列車に乗りたい
東西冷戦下の1956年の東ドイツ。
ソ連の影響下にあった東ドイツであったが、ベルリンの壁はまだ建設されておらず、西ベルリンにも市電で行くことが可能だった。
そんななか、東ドイツのエリート高校に通うテオ(レオナルド・シャイヒャー)とクルト(トム・グラメンツ)は西ベルリンの映画館でハンガリー民衆蜂起のニュース映像を観、市民たちに多数の犠牲者が出たことに衝撃を受ける。
翌日、犠牲者たちへの哀悼の意を込めて、授業開始の前にクラス全員で2分間の黙とうをささげたところ、この行為が国家に対する反逆だと目されてしまう・・・
といったところから始まる物語で、『沈黙する教室』(映画の原題「DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER」に同じ)という自伝・実記の映画化。
映画の中心となる少年たちは主に4人。
ひとり目の、黙とうを言い出す少年は、市議会議長の息子で、いわばエリートの中でもエリート。
ふたり目、彼の友人の少年の父は労働者階級で、一族で初めて大学に進学する者が出るのではないかと期待を寄せている。
三人目は、労働者階級の少年の彼女。男性ふたりの間で、心を揺らしていく。
四人目、先の三人と距離を置いている少年。彼の父親は社会主義に順じて戦死したことを誇りにしており、彼も社会主義に殉じるのが当然と信奉している。
人物配置のバランスがよく、特に、徐々に映画中心が、言いだしっぺのリーダー的少年ではなく、彼の友人に移っていくあたり、映画話術として抜群に上手く、映画に深みを与えている。
また、四人目の少年も、ただ単に社会主義信奉という役割だけでなく、センシティブなストーリーもあり、胸狂おしくなります。
黙とうという些細な行為が、徐々に国家への反逆と捉えられ、事態が扇情的になっていくあたりは、社会主義国家のコワサであるが、社会主義国家特有のものでもないので、日本タイトルの「希望という名の列車」というのは安直な感じがしました。
ですが、われわれも「希望」という名の列車に乗りたい、とも思いました。
全81件中、21~40件目を表示