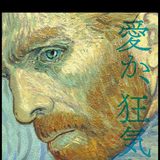永遠の門 ゴッホの見た未来のレビュー・感想・評価
全118件中、81~100件目を表示
ジュリアン・シュナーベルが好き
何かが足りない
ウィレム・デフォーの演技が素晴らしく、まさにゴッホそのもの。
ただ、狂気を孕んだ天才芸術家の人生を描くのですから、もっとハチャメチャに、“普通”の観客では理解出来ずに置いてきぼりにしてしまうような演出も必要だったかと思うのですが。
また、孤高の天才ゆえに愛(神とでも人とでも)を求め続けたゴッホなのですから、その最愛の弟・テオとの幼少期からの絆の部分は省いてはいけない、必要不可欠なもののはず。
そして、“友人”ゴーギャンとの複雑な関係性や出会いと別れの描き方があっさりと浅すぎるため、その他大勢の一人みたいになってしまい……。
ゴッホの本当の孤独を表現しきれていないと思います。
これならテレビの特集番組とかで、ウィレム・デフォーに再現ドラマをやってもらったほうが、よりゴッホを感じられるのではないでしょうか。
永遠を感じた
どうしても病んでいた孤独な画家として客観的に語られてしまいがちなゴッホの晩年を、ゴッホの内面から映しだした作品。
シュナーベル監督の『潜水服は蝶の夢を見る』の主人公と同じように、ゴッホの目線で映し出す周りの人々とのやりとりに窮屈さを感じたり、自然の中に解放されたゴッホの息づく姿に彼の絵画の空気を感じた。
この映画の中で語られるゴッホの心情は、本当に彼がそういう思いだったかは実際のところわからないわけだけど、実際に彼の歩んできた画家人生を彼の作り上げてきた沢山の絵画とともにたどっていくとこれに近いものはあったんじゃないかと自分も思う。彼は画家として苦しみの中に光を見つけ、永年の命を手に入れたんだと思う。
悲劇の天才画家
ゴッホ役のウィレム・デフォーが素晴らしかったです。ウォルター・ヒル監督が1984年に手がけた「ストリート・オブ・ファイヤー」でのギャング団のボス、レイブン役での強烈な個性を感じてから30年以上経ってついにはゴッホ役!をこんなに素晴らしく演じる事になるとは当時は想像してなかったです。
デフォーの何かに取り憑かれたような演技、弟のテオの精神的かつ金銭的にも献身的な援助と交流、ゴーギャンとの出会いや確執と別れ、自分の耳を切り取る行為など、追い詰められていく精神状態の中で最後は毎日1枚のペースで作品を描いていった最後までの異常なほどの創作意欲。
全てにおいて素晴らしかったですがアルルの、のどかな風景と音楽で途中何度か睡魔に襲われてしまいました、、。
ここ数年、ゴッホ関連の映画作品ホントに多いですね。ゴッホほど生きていた時に評価されず生活も困窮したのに、死後異常なほどの再評価、作品価格の高騰を見ていると生前のゴッホは天国からどんな気持ちで見ているのか感慨深いですね。本作の中でもたびたび雑に扱われている世界的名作を見てると「やめてくれー、それは将来一枚数億円するのにー!!」と叫びたくなりました(^^)
孤絶の生涯が磨いたゴッホの才能
ゴッホすきな人は絶対みるべし
「絵は一刷けで描くものだ」
あの独特の技法と、当時は「不愉快・醜い」とまで言われた構図とデザイン、そして画家の数奇で過酷な運命。人物そのものが“ドラマ”そのものである、ゴッホの伝記映画である。ゴーギャンと共同生活を送るアルルへの移住直前から自殺とされる終焉までの期間が描かれている。
ゴッホ自体の伝記作品は、今作だけでなくテレビ番組も含めれば数多ある題材であり、教科書や読み物等も通して、大体のストーリーは知っている筈である。悪名の高い耳の切り落とし事件を例に出せば、それだけでもう彼の奇行、その元となる精神異常を思い起こさせるのではないだろうか。今作はそういう彼に巣くってしまった精神状態にスポットを当て、それを観客に追体験に相似したアングルや視覚技術で構成されている内容である。近すぎる顔のアップ、彼目線の映像の中央水平の線状ピンぼけ、経った今交わした台詞が心の声のように聞こえるリバース。ネガのような映像になったり、色彩設計の激しさが伴う自然描写と、どんよりと雲が敷き詰められたグレイが強調の屋内や街並。撮影レンズの傾きや回転も演出されていたりして、なるべく主人公の目から映し出す情景を作り出そうとする意図を強く感じる。なので、益々不安感や、不快感を以て映像を追ってしまう。それは作品そのものの否定ではなく、それだけ感情移入が激しいことの証明であろう。アルルの暖かい気候とは程遠い冬の季節特有の吹きすさぶミストラルの冷たさ、種を取られ枯れたひまわり、その景色の中を黙々と構図を追いかけるゴッホは、確かに宗教家、又は求道者、行者そのものである。英語とフランス語を駆使する語学力も兼ね備えているので、単純に学習能力の低さではなく、純粋に気質とメンタル面での脆弱さが最後迄彼を苦しめたのだろうと、今作で学んだ。後はそれぞれの転機の出来事、創作した絵画のモデルや風景等を散りばめながら、悲壮な幕引きへと近づく。126年間眠っていたゴッホの未公開スケッチや、自殺ではなく子供の暴発による事故といった、未だにコントラバーシャルな論議を落とし込むところの野心さも伺え、挑戦的な構築はされているが、今作の一番のメッセージ性は、“ゴッホ”という、絵画を体系立てて習得してこなかった天才が独学でオリジナリティを確立させた裏には、類い希なる深く哲学的で、しかし狂気にも足をかけた非人道さ、決して社会にはコミットできない苦悩を何とかして観客に感じて貰いたいという願いが、ひしひしを伝わる出来映えであった。本当に都合良く自ら起こした事件の記憶を忘れることができるのか、それとも弟に頼ってばかりの家族の鼻つまみ者という位置づけなのか、それともキリストのように未来の為に絵を描いた聖なる子なのか、今作の記憶を辿る度、その答えが固定できず心が揺れることであろう。哲学的な格言も台詞として多く、解読の難解さと、同じような場面のリピート(療養所への往復)の為、時間感覚や場面認識のおぼつかなさやぼやけが顕著になってしまうのだが、それも又この偉大な画家の追体験の一つなのかもしれない。「抑制などするものか! 熱狂していたい!」ゴッホがゴーギャンに言い放ったこの狂言は、あの厚く重ねられた油絵の具の一刷き、一刷きに込めた純粋さそのものであり、凡人である自分が垣間見ることさえ許されない、神の光=太陽の黄色なのかもしれない。
ゴッホの伝記とか読みたくなった
不遇の天才を辿る先にあるもの
自分は芸術の世界はよくわかりませんけど
後に評価された作家の絵が何十億もで取引されて
回ってる業界には嫌悪があります
その作家が苦しい生活で一生を終えたとなれば尚更
フィンセント・ファン・ゴッホはまさに
その不遇さを代表する芸術家だったと思います
でも不遇と言ってもそれは一般社会から見た世界
からの話で、当のゴッホ自身は自分の世界から見える
美しい世界を辿り着いた技術で描ききったのだと
いう崇高さをこの映画では存分に表現していました
情熱の作家、狂気の作家と表現される所以を
感じ取ることが出来る一作でした
半分ぼやけたフィンセントの主観でカメラが回る
シーンでは心臓の鼓動や病の影響から来る幻聴の
ようなノイズが入り、これが結構没入していきます
昨今芸術という言葉に関して
やれ表現の自由だ補助金だという単語が飛び交い
およそそういう世界とほど遠い連中が跋扈していますが
芸術だからどうこうではなくこうした
妥協なき姿勢で自分の力で表現を貫いてきた
人々の結晶こそ芸術と呼べるのではないでしょうかね
何十億もで取引する世界を嫌悪とは言いましたが
広く世界でそうした芸術家の名が知れ渡り人類史に
名前が残った事に関しては素直に喜ばしい事だと思います
公開してる劇場もあんまり無いようですが
もし機会があればおすすめしたいです
色々と話し過ぎダス!お喋りし過ぎダス!
いやぁ、画には思い切り期待してたんだけど。思いっ切り裏切られた。風景も自然も、もっーーと芸術的に撮れんのんかと。ゴッホの有名な絵画がバンバン出て来て、ハッとするのも最初のうちだけ。
実は結構、イージーな映画じゃないのか疑惑が、沸々と湧き上がりだしてしまって。
生涯を通じて、一本の評論で絶賛された事を除いて、全く評価されず冷遇され続けたゴッホ。描くことへの情熱と自信は、社会からの孤立に、いとも簡単に変化し、孤独感は狂気へと、徐々に置き換わって行く。
何のために描くのか。と言う命題は、ジヌー夫人、ゴーギャン、牧師、二人の医師との対話を通じ、ゴッホ自身が語ります。が。あんまりハッとする要素が無いんだす。地味に。むしろ、左耳のアレに至る過程に至っては、異常性の描写が物足りない。ブラックアウトで、覚えてないです、って何なん?ってなりました。自己願望が叶わない諦めから、鬱に入ったアル中患者、ってわけでもないでしょうし…
デフォーは、全くもって素晴らしかったです。
『永遠の門 ゴッホの見た未来』観ました!
絵具は粘土のようで、絵は彫刻のよう
それにしても、ゴッホの絵から抜け出たような俳優陣とメイクだ。
ゴッホだけではく、郵便配達人、アルルの女(ジヌー夫人)、そして、医師ガシュ。
前に、ある美術評論家の人がテレビで、美術館のエキシビジョンの鑑賞の方法と言うのを話していた。
始めに全体を歩いて見てから、直感で好きな作品、印象に残った作品、特に自分の家に置けたらいいなと思う作品を見つけて、それらを中心に鑑賞すると良いと言っていた。
特に反論はないが、付け加えさせてもらえたら、所有してたまに出して、じっと見て、頭の中に焼き付けておきたい作品も加えたい。
ゴッホ作品でいったら、「麦秋のクローの野」や「ローヌの星月夜」は、リビングの壁にかけて、ゆっくりくつろぎながら眺めたいが、「星月夜」や「オーヴェルの教会」はそんなわけにはいかない。
どちらかと言ったら、大切に保管しておいて、たまに出して、じっくり鑑賞して、吸い込まれるような感覚を味わいたい。
ゴーギャンがゴッホに、
「お前の絵は、絵の具が粘土のようで、絵は彫刻のようだ」と言う。
付け加えさせてもらえれば、晩年の作品は、構図や線は歪んで、脳裏に巻きついて締め上げるよう感覚を覚えるし、タッチは針でも飛び出しそうだ。
そして、あのずっしりとした大胆な色彩。
ゴッホには何が見えていたのだろうか。
やはり、ゴッホは唯一無二だ。
ゴッホの生涯は悲劇的で、言い方は良くないかもしれないが、ドラマチックだ。
生前は絵が売れなかったこと、弟テオとの交流、ゴーギャンとの親交・確執、耳の切断、精神疾患、テオも決して豊かではなかったがゴッホを最後まで支えた。そして、死。
死の真相は定かではない。ただ、2年前に公開された、ゴッホの絵のようなアニメ「ゴッホ 最後の手紙」でも示唆されたように、自殺などではなく、事故だったのではないかと信じたい。
オーヴェルに移った時は、精神疾患は良くなっていたと信じたい。じゃないと、あれほど多くの作品を残せないだろうと思う。
ポスト印象主義は、後世のアートシーンに大きな影響を与えた。
ピカソは、セザンヌのガルダンヌと言う風景画を見て、これは完成作品なのかと驚き、全体は個の本質の集合(→もっと違った表現だったかもしれない)という考え方を背景にキュビズムを追及する。
これに対して、ゴッホの感情を揺さぶる大胆ともいえる作品は、感情をキャンバスにぶつけるようや表現主義やフォビズムなどに受け継がれます。
やはり、ゴッホは作品を観ましょう。
そんな気になります。
ポスト印象主義に浮世絵の影響が見られることや、白樺派が彼らをプッシュしたこと、東郷青児美術館が大金で「ひまわり」を落札したこともあって、日本ではゴッホは大人気で、エキシビジョンも多く、目にする機会は沢山あります。今は、クオリティの高い画集だってあります。
ゴッホが作中で語るように、彼は絵の中で、作品とともに生きているように思うのです。
全118件中、81~100件目を表示