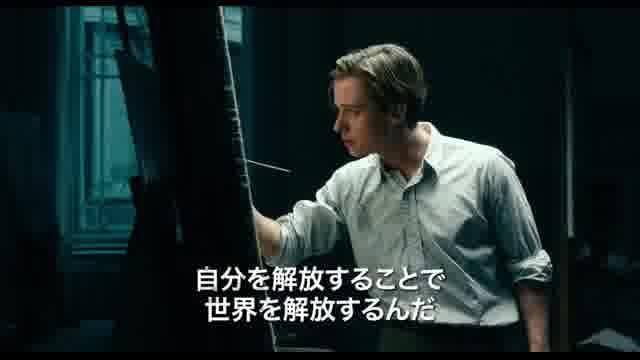ある画家の数奇な運命のレビュー・感想・評価
全55件中、41~55件目を表示
撮影者なき写真
芸術好きの叔母が、精神疾患を理由にナチスから粛清されてしまった少年クルト。成長し、より芸術を学ぶため進学した大学にて出逢ったエリーに恋に落ちるが、その父親こそが…
といった、まさに数奇な運命を辿る画家の物語。
3時間越えの超大作!ながい!
私的には2時間10分を超える作品はよほど興味がひかれないかぎり見る気が起きないのですが、意を決し(?)仕事帰りの疲れた体で鑑賞を敢行!!
しかし、絵画等の芸術に疎い私でも充分に楽しめる作品だった。
芸術云々もそうだけど、ストーリー自体が面白く、長いがダレることなくスーッと観られる不思議。
とはいえやはり3時間。本作の目玉シーンともいえる場面に至るまでは、もはや序盤にだけ出てきてた叔母さんのことなどすっかり忘れてしまっていた(笑)
ストーリーとしては、辛い現実を手で覆い隠したくなる気持ちは誰にでもあろうことかと思うけど、叔母さんの教えに反するともいえるクセが、ラストに紡ぐまでの流れはまさに爽快。
確かに、これこそが彼がみた風景(真実)。
ただ、文字通りの「真実」に気づいたのは教授だけだったのかな?クルトはいかに。
絵画の中の彼が指さしてに教えようとしているようにも見えた。。
とにかく長い映画だったが、ナチスの悍ましさ、ソ連少佐との秘密の関係、社会主義にあえぐ芸術家の苦悩、エリーとの恋…等々、面白いと思えたポイントも多いし、意外にも笑わせにくる所があったり、各所に散りばめられたBGMもとにかく美しかった。
清掃するのも、これまた数奇な運命。
ベストシーンは、模写している時の風のいたずら。不意打ちのファンタジーだった。
あれはきっと叔母さんが…。
芸術に疎い私なので、理解しきれない部分も多々あれど、理屈抜きで素敵な作品だった。
いわば映画も芸術のひとつか。。
アート作品として
人間不在の絵には生命がない
エンドロールの途中で席を立つ人がいる。急ぎの用事があるのかもしれないから、一概に否定するつもりはない。しかしアンミカがテレビで言っていた「アメリカではエンドロールなんか見る人いない。みんな席を立つ」という発言には不快感を覚えた。アメリカのすべての映画館のすべての観客がエンドロールを見ずに席を立つという明確な証拠でもあるならまだ容認できるが、証拠もなしに発言していたなら感心できる話ではない。当方はエンドロールまでなるべく全部見る派である。エンドロールも人の手間と時間がかかっている作品の一部なのだ。
本作品のエンドロールは文字ばかりの普通のエンドロールだったが、BGMがヒーリング音楽みたいで大変心地がよかった。おかげでこの長編映画をゆっくりと反芻することができた。189分の映画だが観ている間は長いと思わず、観終わるとずっしりと来る作品である。それは優れた作品の特徴のひとつだ。
当方は絵画に縁がない。子供の頃から絵が下手だった。絵が上手な子は教師から褒められるが、下手な子の絵は笑われる。自然と絵を描かなくなり上手な子との差はますます広がっていく。だから絵を描く楽しさが分からない。そこが残念で仕方がない。絵を描く楽しさが分かっていれば、下手なりに絵を描き続けていたかもしれないし、本作品の捉え方も違っていたかもしれない。
とは言え、本作品は絵が下手でも美術に造詣がなくても理解できるように作られている。ひと言で言えば、人間不在の絵には生命がないということだ。政治的なイデオロギーによって描かれる絵は、見た人に訴えかけるものが何もないのだ。主人公クルト・バーナートは東側のソ連傘下に入った東ドイツではイデオロギーの枠の中の絵しか描けない。
西側では自由に描けるはずだが、今度はテクニックに惑わされてしまう。クルトの作品にはクルト自身が見えないと教授に指摘されると、クルトは創作者が一度はハマる、頭が真っ白になる状態になる。クルトは何かを創り出せるのだろうか。
物語はクルトの幼少時から始まる。自由人だった叔母の影響でクルトも既存のイデオロギーやパラダイムに支配されない自由な精神性を持っている。その叔母はナチスドイツの優生思想による政策でガス室に送り込まれた。送り込んだ医師ゼーバントはナチス党員であり、権威主義、国家主義者であった。
クルトが青春を迎えたある日、かつて叔母が世界の真実を悟ったと叫んだようにクルトも世界の真実を悟ったと叫ぶ。若いときにはこういう日が一度はある。当方も高校生の頃にドストエフスキーやショウペンハウエル、ニーチェなどを読んで、世界を理解した気になったものだ。しかしそれが勘違いであったのと同様に、クルトの悟りもおそらく勘違いだったと思う。
その後東ドイツの美術学校で出逢ったエリーが偶然にもゼーバントの娘だったが、エリーの家族もクルト自身もそれに気づかない。そして西側の美術学校でちょうど創作に行き詰まっていた頃にいくつかの出来事が重なり、クルトは持ち前の映像記憶力でそれらを組み合わせ、大戦時に叔母に起きた事実とゼーバントとの関係、ぜーバントとナチスの関係を洞察する。そしてそれをキャンバスに表現しはじめる。そこからがクルトの本来の芸術のスタートとなる。
芸術家としてのクルトの成長と、恋愛から結婚に至る個人的な生活が物語の両輪で、主人公クルトと恋人エリーに対し、国家主義や優生思想などの象徴としてのゼーバントという権威主義者の俗物を対立軸として置くことで、立体的な作品に仕上がっている。精神的な自由を重く扱った映画であり、世界の人々が再び陥りそうになっている危険な思想への傾倒に警鐘を鳴らす作品でもあった。いかにもドイツ映画らしい作品だと思う。
自由は辛くて厳しい。人間は放っておくと自由を投げ出して権威の前にひれ伏し、代わりにパンと家を手に入れようとする。そこを踏ん張って自由を守り続けるには勇気が必要なのだ。自由を投げ出して共同体に同化すると国家主義になる。戦争をするのは決まって臆病者たちなのである。
【ミケランジェロ、24歳、ピエタ】
若い頃に才能を開花させないとと紹介される、ミケランジェロ、24歳の時のピエタは、バチカンのサン・ピエトロのピエタだ。
サン・ピエトロ寺院の入ってすぐ右にあるピエタ。
磔刑から下ろされたキリストは死して尚、復活を示唆するみずみずしい筋肉を保ち、悲しみに暮れるマリアは、我が子が自らの腕の中に戻り安心しているようにも感じられる。
だが、最後の作品となったロンダニーニのピエタは、荒削りで、ある意味、現代彫刻のようでもある。
これは、正面からは、死んだキリストを必死で抱き起こそうとするマリアに、背後からは、老いたマリアをおぶうキリストのように見えるのだ。
作品中で、ファンヘルから、脂とフェルト生地の原体験の話をされるクルト。
クルト自身の原体験としての叔母エリザベト・マイの裸体。
同じ名前をもつエリーとの肌の触れ合い、裸、乳房、セックス。
意味のない数字が意味をなすとは。
エリザベト・マイがつれさられる様をぎょうしできかなかった怖さ。
写真の模写とぼかし。
自身の原体験が作品のエネルギーとなり、作品に変化をももたらしていく。
クルトの叔母を安楽死に送ったのがエリーの父であるという運命にフォーカスが当たるのだと思うが、実は、この作風の変遷が数奇な運命なのだと、僕は感じる。
バスのホーンが、エリザベート・マイと聞いていた音として、今でもクルトの頭の中に響き続けているのだ。
ミケランジェロは、サン・ピエトロのピエタで名声を確立したが、最後の作品もピエタだ。
ピエタは、ミケランジェロの原体験とも通じるものがあったに違いない。
だが、最後のロンダニーニのピエタは、タッチも求めるテーマも異なる物だ。
この作品のモデルであるゲルハルト・リヒターの作品の変遷もそうであるように感じる。
ドイツの歴史の暗い部分もあるが、芸術や、それを生み出す人の力も感じて欲しいと思う。
因みに、僕は、壁崩壊直前に、東ベルリンの美術館に行ったことがある。
労働者を賛辞する絵は、映画のクルトの作品と非常に類似していた。
退屈なものだった。
グルグル廻る意図は?
数奇な事柄を見事なまでに集約
2020年ベストムービー!⭐️⭐️⭐️✨
今年1番の映画作品!💖
物語にはナチスを告発する部分もありますが、その視点(テーマ)はもっと広く、ある画家の人生を通して、人の営みや原体験の大切さ、そして、そこから生まれる芸術作品の素晴らしさが、"我(自我)"というキーワードと共に語られます。
そして、人生をどう生きるのか?・どう生きたのか?を私たちに問いかけて来ます。
主人公の叔母が残した「それでも真実はすべて美しい」という言葉が耳に残ります。
(ストーリーはわかりやすく、美術や芸術への入門編という感じです)
*ドイツ語の原題『Werk ohne Autor』は、「作家(作者)なき作品」の意。なお、英語タイトルは『Never Look Away』で「目を逸らさないで」の意。これは、主人公の叔母が精神病院へ連れて行かれる時に、主人公へ言った言葉から(正確には、「真実はすべて美しい。だから、目を逸らさないで」)。
退廃芸術
1932年ドレスデン生まれのドイツ人画家、ゲルハルト・リヒターの1966年までの人生。
芸術的センスを持った血筋に生まれた主人公。
幼い頃に叔母が統合失調症で連れて行かれ、って断種とか、ホント胸クソ悪いし更には!!!
一度診断されたら、もうOUTだったのでしょうね。
彼女の名前にも特段触れないし、そこからは特筆すべきことが余りない若者の出会いと恋と…ってエリーパパ!?
色々と制約のある東か自由な西か、堅実に生きるタイプの主人公じゃないし、そりゃ西に行きたいわな。からのベルリンの壁が出来る前にギリギリ西へ。
流れているドラマ自体はつまらなくはないし、テンポも悪くないのでみていられたけれど、30歳を前に学生を続ける主人公の悩み的なものも少しはあるものの余り深くは描かれず。
白いカンバスを払拭したところは痛快だったけど、何で知っていたのでしょう?意図したものではなく偶々?まあ、若干間違っているし、偶々なのでしょうね。
主人公がどうのってことではないけれど、芸術って何でしょうかね…溢れ出るものか、アイデアか、少なくとも奇をてらえば芸術って訳ではないよね。って理屈を捏ねてる時点で自分はセンス無いの確定ですね。
ゲルハルト・リヒターを知らないし、現代美術はもとより芸術が良くわからない自分にはこの作品の良さが理解出来なかった。
感性の先に
物語はクルトの幼少期から始まりはじめは彼の家族の描写から始まる。
若くして叔母は不必要な人間と政府に判断され殺され、父も自殺をする。空襲で他の家族も失う。
クルトは学生になりエリーと出会い恋に落ちる。そのエリーの父親が叔母を殺した元高官である事は観客側にはすぐ伝わりこの後何が起きるのか、伏線を張られてるような展開に緊張感が高まる。
この辺りまでは面白く鑑賞できたのだがそこからの展開に残念ながら僕はあまり興味を唆られる事はなかった。
模写から真実に近づいていくシーンなんかも一瞬は興味を惹きつけれるのだがその後の表現が非常に感性的であり残念ながら僕の感性が未熟であり作品の理解に追いつくことができなかった。
最後はエリーは再度妊娠をしハッピーエンドで終わったクルト。
今回は少し中盤から興味を失ってしまったが個人的にはまた機会があればといった作品ではあった。
話は作品とはそれるが3時間作品ということもあり体は疲れた。上映している劇場も箱が小さいところが多く疲労感を感じた。
現代画家の巨匠リヒターの半生
ルハルト リヒターという美術界で、「ドイツの最高峰の画家」といわれている画家の半生。88歳。現存する作家のなかで世界で最も注目されている現代画家と言われて、日本でも人気が高い。
リヒターは、ナチ政権下のドレスデンで多感な少年時代を過ごし、敗戦で生まれた土地が完璧に破壊される過程を目撃し、ロシア軍の進駐によって再建された芸術大学で学んだ。優秀な画家の卵は、やがて自由な表現を求めて東西の壁ができる寸前に西ドイツに逃れ,前衛作家として成功する。文字通り激動の時代のドイツを生きた画家だ。
現代美術の旗手で、抽象画、シュールリアリズム、フォトリアリズム、ハイパーナチュラリズム、などの作風をとり、油絵だけでなく彫刻、ガラス作品など製作している。初期の作品群であるフォトペインテイングは、写真を大きくキャンバスに模写し、画面全体をぼかして、さらに人物などを描きこんでいくという独特の作風だ。また、モザイクのように256もの色を並べた「カラーチャート」、キャンバス全体を灰色に塗りこめた「グレーペインテイング」、様々な色を織り込んだ「アブストラクト ペインテイング」、ガラスをたくさん並べ周囲の風景を映すガラス作品、5千枚以上の写生や写真からなるパネルを並べた「アトラス」などが代表作で、いまは油絵からエナメルや印刷技術を用いた作品制作している。また「線」を描かずに、先に鉛筆をつけた電気ドリルを使って絵描く方法を取っていたりする。
2002年にリヒターは、ドイツのケルン大聖堂のステンドグラスを製作依頼され、113メートル四方の聖堂の南回廊を、72色のステンドグラスではめ込んで、これを2007年に完成させた。リヒター本人はこの仕事でいっさい報酬を受け取っていないが、長い年月と506000ドルという法外な費用がかかたため沢山の人の寄付を仰がなければならず、完成後、ケルン市長は余程機嫌を悪くしたらしく、こんな作品はカトリック教会でなくモスクとかほかの宗教に似合ってるんじゃないか、とコメントしている。ケルン聖堂は、世界最大のゴチック聖堂で人気が高いので、ヨーロッパ旅行者が必ず訪れるところでもある。
日本では瀬戸内海の無人島の豊島にリヒターの「14枚のガラス」が展示されている。全長8メートル、縦190センチ横180センチの14枚のガラスがハの字を描くように少しずつ角度を変えて立ち並んでいる。2011年に島を訪れたリヒターが、この静かな海に囲まれた土地が気に入って作品を恒久展示することに決めた。作品を収める箱形の建物も彼がデザインして製作したそうだ。
2012年オークションで、エリッククラプトンが所有するリヒターの抽象画「アブストラクテルスビルト」が26憶9千万円で落札、翌年には別の作品が29憶3千万円で取引されて、生存する画家の作品として史上最高額を記録したという。
映画監督、フロリアン ヘンケル ヴォン ドネルスマルクは、この映画を作るにあたって数週間、リヒターとの対話をテープに取り、話し合いの末、映画を製作した。だがいざ映画が完成してみると、本人リヒターは、自分は伝記なんか作ってもらいたくない、映画を見る気もないし、全く興味もない。映画がリヒターの伝記だなんて言ってもらいたくない、と主張。そういうわけで、この映画の解説にリヒターのリの字も出てこない。ただ映画の紹介に、現実の画家にインスパイヤ―されて製作した、と記述されているだけだ。
一人の画家の成長の物語として素晴らしく、画面の美しさも映画作品として完成度が非常に高い芸術作品。3時間の長編映画だがまったく飽きない。2018年代75回ベニス国際映画祭で、金獅子賞候補作。映画祭で13分間スタンデイングオベーションで拍手が収まらなかったと報じられた。ゴールデングローブ、91回アカデミー賞でも最高外国語作品賞候補となった。
ストーリーは、
1937年、ナチ政権下のドレスデン。
5歳のカートは美しい伯母に連れられて美術館に行く。ユーゲン ホフマン(EUGEN HOFFMANN 1892-1955)の彫刻「青い髪の少女」に、魅入られたカートに向かって、叔母は、これらの作品がどんなに美しいか、一つ一つを見逃さないようにじっくり観るように言う。 ナチの美術館案内人は、これらホフマンなどの前衛芸術は、退廃的で社会的ではない、と批判的だが、叔母はそういった表面的な解説をまったく意に介さない。美しいものに純粋に身をゆだねるように生きる叔母は、カートの一番の理解者だったが、やがて精神分裂症と診断されて、ナチの病院に連行されシーバンド医師により去勢手術を強制され、その後ガス室に送られて殺される。
戦争が終わり、街の小学校の校長先生だったカートの父親は、進駐してきたロシア軍によって、ナチ政権に与したものとされて、小学校の掃除夫を命ぜられる。ナチ信奉者は、ユダヤ人ばかりでなくドイツ人の精神病者や身体障害者を沢山処分した。カートの叔母をガス室に送ったシーバンド医師は、犯罪人として刑務所に入れられる。しかし、刑務所のなかでロシア人将校の妻の出産を助けたことで、将校に母児の命の恩人として扱われ、釈放されてシーバンド医師が犯した罪に関する書類は、すべて廃棄される。
カートはドレスデン芸術大学で絵画を学ぶ学生となり、同じ大学でデザインを学ぶ、エリという美しい学生と出会う。彼女は熱烈なナチ信奉者だったシーバンド医師の一人娘だった。シーバンド医師は娘が可愛いので、カートとの関係を認めない。娘が妊娠しても自分のところに引き留めるために娘に妊娠中絶を強制する。やがてシーバンド医師を釈放し保護してくれたロシア人将校が帰国することになったのを機会に、シーバンド一家は西ドイツに逃れる。カートも東ドイツの社会主義的な芸術感に堪えられず、自由な表現を求めて東西の壁ができる寸前の緊迫する国境を越え、西ドイツに逃れる。
西独に移り、ドッセルドウ芸術大学に入り、教師だったジョセフ ベイス(JOSEPH BEUYS 1921-1986)から現代絵画を学ぶ。才能を認められるが、本人は自分の表現に苦しむ。30歳を過ぎても社会人として働くでもなく絵が売れるでもなく、自分のスタイルができるわけでもなく、表現することに四苦八苦していたが、彼の義父シーバンド医師が戦争犯罪で、いつ逮捕、追及されるかわからない恐怖にかられる姿をみて、彼の写真をキャンバスに模写して、その上に人物を重ねて描くフォトリアリズム手法を考え付く。それを機に、カートは新聞や写真をキャンバスに模写して絵を重ねるハイパーナチュラリズム、フォトリアルといった自分のスタイルを見つけていく。
幼い時から美意識の高い伯母から、NEVER LOOK AWAY 見過さないで芸術作品から目をそらさずによく見てよく観察しなさい、と言いきかされていた少年が、成長と共に画家となり、観察するだけでなく自分で作り出し、人に伝えようとして、表現者としてもがき苦しむ姿が描かれている。
若く瑞々しい美少年と、美しい伯母、叔母にそっくりな姿の可憐で美しい妻。一人の画家が成長していく姿が良く描かれている。背景も自然描写も秀逸。3時間が少しも長くない。いつまでも美しい画面を見ていたくなる。
カートは、30歳すぎても妻の裕福な父親シーバンド医師に食べさせてもらって画学生を続けているから、義父に皮肉を言われる。 「レンブラントは30歳で数えきれないほどの弟子をもっていた。モーツアルトなんか30歳といえばもう死んでいた。」そんなふうに、画家の生活力のなさを非難されても、カートは何一つ言葉を返せない。それでもひたすらキャンバスに向かうカートの姿は胸を打つ。
リヒターの芸術大学の教師だったジョセフ ベイスが、絵に取り付かれた魔物みたいに、映画でもものすごく魅力的に描かれている。教室で古典派の画家の写真をキャンバスに立て、それに火をつけて燃やしながら、呆気に取られている学生達を前に、講義を始める。本物を見つけろ、とリヒターを激励するために、いつも被っている帽子を取って、自分が死にかけてタタール人に救われた爆撃機事故のときの頭のひどい傷を見せたりする。映画には出てこないエピソードだが、1974年彼はアメリカに招待されたとき、「コヨーテ私はアメリカが好き、アメリカも私が好き」という作品を展示した。それはニューヨークの画廊で、1週間フェルトや新聞、干し草の積まれたギャラリーの中に籠ってアメリカ先住民の聖なる動物コヨーテとともにじゃれあったり、にらみ合ったりして無言の対話を続けるといった展示だった。
リヒターを演じた役者も絵を描く人だと思う。おおきな刷毛で床に置いたキャンバスに、何度も大きな円を描いてみせる。彼がキャンバスに描かれた本当の写真みたいに模写された油絵を、板で強くなぞってぼかしていく。絵がぼやけるに従って過去の写真が、心に映った本当の過去の姿になぞられていく。魔法をみるようだ。
一心に絵を描く人の姿は、美しい。5歳の少年を前にして素裸でピアノを弾く美しい伯母、何台ものバスの運転手に頼んで力いっぱい警笛を鳴らしてもらって、その音の渦に身を浸す美しい伯母が美しい。ガス室で死んでいった叔母が、一番の芸術家だったのかもしれない。
とても良い映画だ。
投稿者 DOGLOVER AKIKO 時刻: 1:07
Don't Look Away!!!
この映画で心に残ったことが主に二つある。
一つ目は、トム シリングが演じる主役カート。
カートのおばさんである芸術肌なエリザベスの言葉でこの映画の題でもある目をそらすな!見ているのはありのままでそれが美しいというような物の考え方に共感した。それが困難なこと
で目を背けたくなるようなことでも、心を入れ直視せよということだと思う。そこから芸術が生まれてくるとでも言いたいようだと思う。
結局カートは自分が見つめた経験、心の中のことを直視したことを絵で表現したことによりマスコミに注目される。彼は自分の心の中を描いた作品を説明したけど彼とメディアとの理解は違うものであった。
もう一つはカートのおばさんエリザベスはナチの優生学の断種法のもたらした結果の被害者となった
エリザベスを精神の病気統合失調症として扱いガスチェンバーに送って殺してしまう。これに診断を下した医者がカートが成長した後に、愛した女性ポーラ ベアーが演じるエリザベス(エリー)の父親だ。この父親はカートを劣勢として扱い 、一家の優秀で気高い純潔を守るためエリーを卑怯な手段を使って堕胎したりもう子供をみごもらさないようする。
二人はベルリンの壁ができる前に西側に移つる。
ナチ崩壊後主犯格の医者はロシア側に犯罪者として拘束されて、エリーの父にもこの手が伸びてくる。悪名高いナチス優生政策が葬られていく
歴史上では、この断種法により、ドイツの精神的肉体的障害者が無残に一掃されてしまう。ナチの鋼鉄のような精神と規律がその後のドイツを作っていくが、その反面、ユダヤ人を救ったりしたヒューマニストもドイツを支えていく。
日本は戦後すぐに優生保護法が制定された。ある側面ではこの優生保護法の歴史が現在も身障者との共存を阻む原因にもなっていると思う。
全55件中、41~55件目を表示