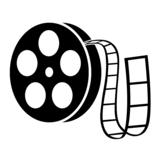メアリーの総てのレビュー・感想・評価
全74件中、1~20件目を表示
作家はフィクションでこそ嘘をつけない
フィクションは架空の物語だが、だからこそ作家の本性が刻印されるものだとよく言われる。コラムやエッセイよりも、作家の奥深くの本性がより強くでるのはフィクションを書かせた時なのだ。ならば『フランケンシュタイン』を10代の頃に書いたメアリー・シェリーのいかなる本音がその物語には刻印されているのだろうか。本作の一番の関心はそこにある。
映画は、メアリーの家庭環境、自由本坊な詩人パーシー・シェリーと出会い、振り回され、その才能を抑圧された半生が描かれる。直接のアイデアの着想のシーンも描かれてはいるが、そこに本題はない。怪物を産み落とした彼女の心の内側があくまで主題だ。
フランケンシュタインの怪物は、自分を生んだ科学者に対して花嫁となる怪物をもう一体作ることを求める。恐ろしい怪奇小説だが、同時に愛を求める悲痛なロマン小説でもあるこの物語は、最終的には生みの親の死を嘆く怪物の姿が描かれる。父と夫に振り回された彼女の半生の苦しみと小説は、確かにリンクしている。
エル・ファニングの内面渦巻く感情に、ただただ圧倒される
「フランケンシュタイン」の物語は、怪奇ホラーという言葉では片付けられないほど悲しく、哲学的で、「人間とは?生命とは?」といった領域にまで思索の幅を広げてくれる。これがとあるお屋敷で行われた暇つぶしの執筆ゲームとして誕生したこと、その執筆者が女性であったことで「真の書き手は誰だ?」と好奇の目で晒された逸話は有名だ。
本作は、一人のうら若き女性が世にも恐ろしい幻想譚を書き上げるまでの心の叫びを丹念に描き出した秀作である。女性ならではの苦難を等身大の感度で演じるエル・ファニングの熱演もさることながら、他にも男女問わず、あらゆる登場人物たちが為す悩みや悲しみに押し潰されそうになりながら生きる姿が胸を締め付けてやまない。手掛けたのがサウジアラビア初の女性監督という点も特筆すべきところだ。本作から発せられた光は、過去の一点のみならず、現代や未来さえも貫き、普遍的なテーマをありありと照らし出している。
エル・ファニングを起用できた幸運
メアリーが第一子を出産し結婚したのが18歳、本作の撮影開始時(2016年2月)にエル・ファニングが17歳。役との実年齢の近さを含め、無垢な美しさをまとった少女から意志と覚悟を感じさせる凛とした気品を伴う大人の女性へと日々成長するタイミングで、彼女をキャスティングできたことは製作陣にとっても観客にとっても幸運だった。第三子まですべて幼いうちに失うというメアリーの悲劇性を、エルの透明感ある儚げな美貌が際立たせる。
メアリーを襲った数々の不運と困難、そして「ディオダディ荘の怪奇談義」として知られる別荘滞在時の出来事など、彼女が「フランケンシュタイン」を着想し執筆した背景と経緯がドラマチックに描かれる点も大いに興味をそそられた。サウジアラビア出身の女性映画監督、ハイファ・アル=マンスールによるフェミニズムの視点も作品に奥行きを与えている。
作者の心理的地獄がモンスターに乗り移った!?
名作「フランケンシュタイン」の頭に必ず表記される"メアリー・シェリーによる"というフレーズの真相に、恐らく初めて踏み込んだ本作。なぜ、女性がこのような怪奇小説を執筆したか?という謎が、ある種の時代的必然に代わっていくプロセスは、即行で今に通じるもの。父の再婚相手である義母によって虐げられ、さらに、生来恵まれた執筆の才能も封印されたメアリーが、妻子ある詩人、パーシー・シェリーとの出口のない恋愛関係から来るストレスの発露として誕生させたモンスターは、彼女の心の地獄を体現している分、おぞましさと怒りに充ち満ちているのだった。そんなヒロインの切実で行き詰まった心情を、相変わらず愛らしく、一点を見据えるような表情で演じるエル・ファニングにとって、これは代表作と言えるもの。彼女の存在はテーマとしてのフェミニズムを和らげる役目を果たしていて、疑う余地なく適材だと思う。
エルファニングを拝む
怪物を作り出す人間の心
まさかまさかの作品に驚いてしまった。
相変わらず事前情報なしで見ていたが、まさかこんな物語だとは思ってもみなかった。
しかし、秀逸な作品だった。
当時の情勢 この「世の中」というものは人間性というのか思想というのか、または善悪というのか、時代時代の価値観が明確で面白い。
原題名の「メアリーシェリー」
そもそも事前情報など知られていることを前提にしている。
「すべて」を「総て」とした意味 日常的なのと文語的なニュアンスを仕込んだのだろうか?
邦画「ゆきてかへらぬ」のような詩とか言葉やその深い意味が中心になって物語が進む。
女性がその言葉に感じた理想
しかし、男はそれを現実逃避や遊び、または都合のいい解釈を持って自分を正当化していたように感じた。
口先ではいい言葉を連ねて女性を惑わしながら、お金にルーズでだらしない生活を送る。
その根源にあったのが「売れない」事実だろう。
メアリーは理想と現実という言葉を遣ったが、身一つで駆け落ちした顛末がクララを死なせてしまう。
ほんの数日間だけ新婚のような生活を楽しみ、あとはみすぼらしい生活になる。
(ある意味で)真面目の働こうとはせず、聞こえのいい言葉を並べ立てて得意げになる。
「君には責任がないとでもいうのか」
このシェリーの言葉は日本人的には男の言葉ではないが、それにもメアリーは真正面から答えた。
「ゆきてかえらぬ」は、この言葉というものの意味や概念と遣い方を巧みに操ろうとする中村中也達と、感情を上手く言葉にするのができない主人公が対照的で面白かったが、この作品は、言葉というものは日本的に無力でただの道しるべに過ぎず、その言葉を経験によって「自分の声」にすることで初めて力が宿り、それが「フランケンシュタイン」を生み出したという壮大なストーリーとなっていた。
この怪物誕生と、怪物が感じた理不尽さ、そして怪物に対する共感を持った多くの人々がいた。
虐げられるということ。
怪物とはまさに一人一人の人間で、親ガチャという言葉があるように望んで生まれてきたわけではない。
それなのに社会による弾圧や虐げられることなどが多く、生きていくことさえままならない。
このひとりひとり、ここではメアリーが感じた一つ一つのことが悲しみ、苦悩、怒りなどの感情を伴った怪物を作り出した。
コッポラ監督のフランケンシュタイン 「愛もないのに、なぜ創った」というコピーを思い出した。
人間のいい部分だけをつぎはぎすれば、理想的な人間が作れるのではないかという発想
まさに昨今のDNA
さて、
このフランケンシュタインの背景をこの物語が描いている。
登場人物たちの言葉に感じる「愛」の概念
昭和時代の歌詞に多用された愛と恋の混同
当時のイギリスも、日本と同じような感じだったのだろうか?
また、「自由」の概念
都合が悪くなれば自由主義者で済ませるシェリー
メアリーは彼の言葉の奥に隠された偽善を知り、失意のどん底に落ちた。
感情に溺れることと魂の衝動とはいったい何が違うのだろうか?
これは体験しなけば難しいが、そのうち体験する。
しかし若干16歳のメアリーにはその違いはわからなかったのだろう。
また、
メアリーの父の言葉は、この物語の中で非常に重要な役割を果たしていた。
「自分の娘を捨ててしまう男だ」
「メアリーのは幸せになって欲しい」
最後にメアリーが大作を書けたのも、父が「他人の思想や言葉を振り払え。自分の声を探せ」と父が言ったことを思い出し、彼女自身が母から「受け継いだのは魂のの炎」と明言したからだろう。
物語は、シェリーは匿名で出版された「フランケンシュタイン」を書いたのは妻のメアリーだと正直に打ち明けたことでハッピーエンドが確定した。
しかし、
ラストシーンのナレーションでは、メアリー・シェリーが「再び女児を出産した」ことが語られているが、映像では彼女が手を引いて歩いているのは男児であり、この子は実際には彼女の息子 パーシー・フローレンス・シェリー であると考えられる。
この意味はわからなかった。
事実と映画としての象徴なのだろうか???
ただ、
「自分が作り出した怪物に喰われてしまってはいけない」というセリフは良かった。
メアリーが感じた様々な絶望
それはまさにフランケンシュタインであり、怪物
同時にそれは自分自身が作り出した感情という怪物であるのは間違いない。
ここにこの物語の普遍的な事実が忍ばされていた。
これは人類の非常に大きなテーマであるとおもう。
これこそがこの作品が最も言いたかったことなのだろう。
素晴らしかった。
フランケンシュタインの著者の伝記
フランケンシュタインの著者メアリーの伝記。メアリーが16歳で妻子持ちの作家であるパーシーに出逢い駆け落ち。酒飲みで女癖も悪く自由恋愛ばかりを主張するパーシーには嫌悪感しかないが、義理の妹のクレアのポジションも理解できない。出てくる男女が最低でクズすぎる。
Elle Fanningの魅力に圧倒された。
例えば哲学や思想は千差万別があるように、この映画に対する評価も各々 置かれている立場や状況によって是非が分かれると思います。そもそもGender視点とは何かという問いに自分自身明確な解答を持ち合わせていません。 公式サイトは余り気に留めない事が多いのですがこの映画だけは違って細部にわたり注意深く読みました。 文学者の廣野由美子さんとライター・翻訳家の野中モモさんによる映画公開記念トークショーの記事は読み応えがあるのでお薦めします。この作品は映画「ピアノ・レッスン」と同様に監督・脚本・主演が女性の手によるものです。情熱的であるけども現実的合理性を備えているような!?人と人との距離感?間合い?男性が制作する硬い作品よりも興味を引きます。私個人の意見ですが。 本編は18歳のMary Shelleyの役を18歳?のElle Fanningが演じていますがあどけない部分と大人っぽいところの両方を垣間見る事が出来てそれが危うさだったり脆さだったりとNon Fictionの中の人物を観ているのかと思うほど適役でした。主人公はFeministである母親からの影響を強く受けていると感じます。THERE IS SOMETHING AT WORK IN MY SOUL, WHICH I DO NOT UNDERSTAND.(私の魂には不可解な衝動がある) 冒頭の部分ですが自分が思っている以上に深い意味があるのかも知れません。
求めていたものが違っただけかもしれないが
メアリー・シェリーが「フランケンシュタイン」を生み出すまでの物語なんだが、肝心の執筆パートはものすごく短い。
逆を言えば、執筆を始めるまでがメッチャ長い。
何なら、ほとんどが恋愛映画と言っても過言じゃないくらい。
真実の愛を求めて駆け落ちしたけど、結局都合のいい女扱い。自由を仄めかす男と愛を貫けると思ったのもつかの間、自由とは無責任であり、愛とはともに堕落することなのか。
乱暴な言い方をすれば「若気の至り」ですな。
メアリーが「若気の至り」のツケを払い続ける、不幸な結婚の犠牲者(パーシーの前妻・ハリエットみたいな)にならなかったのは、彼女が創作の中に己の魂の叫びをぶつけられたからだ。
実際に「フランケンシュタイン」を読んだ訳ではないから想像だが、「怪物」の魂は表面的なストーリーを突き破って、読み手の心を揺さぶるような「言葉」に彩られていたのだろう。
にしても、「パーシーの作品なら出版しよう」という「女だから評価されない」シークエンスは食傷気味だ。
さらに言うなら、最後に「父と旦那に評価してもらえてハッピーエンド」風なのも、より一層の「なんだかなぁ」感がある。
今までの気持ちを理解してもらえれば、それでいいのか?メアリー!
時代が時代だけに仕方ないのかもしれないが。
墓に佇むメアリーのジャケットはとても印象的だが、肝心の中身はあまり印象に残らない。
メアリーの内面のドロドロした感情をストーリーに乗せてくれたら、もっと興味深いのに。
ちょっと残念な出来である。
良いお話なのだが何となくブルー
フランケンシュタインという物語を生むほどの苦悩
シェリーにも、妹にも、バイロンにもついていけない。
フランケンシュタインが完全したとき、これを希望の物語にするために天使を作ったらどうかと言った時には観ているこっちがどうしようもないなと思った。何も分かってない。
実際2人はその後結婚しているわけだし、結局は分かり合えたということで良いのだろうか。
詩人の美しい言葉
思っていたよりも重くなく見やすい
フランケンシュタインという怪奇小説を生み出した女性の話、と聞いた時はバッドエンドで暗い話なんだろうなと思いましたが
思っていたよりも暗すぎずエンディングもバッドエンドという程ではなかったです。
ただ強いて言うならフランケンシュタインという小説の誕生よりも19世紀における女性の人権問題について、という主題の方がしっくり来る内容です笑笑
かの「フランケンシュタイン」を生み出した女性のお話なんですね…知らなかった
子供の頃にしか「フランケンシュタイン」は観たことがなく、悲しい物語だなぁって印象しかなかったけど、それを書いた人物メアリー・シェリーの波乱に満ちた物語ということで、興味を持った。
驚いたのが、この作品を作ったのは十代だったってこと!
両親もなかなか才能のある方達の様で、そんな中で育った彼女には、元々凡人とは違う感覚が備わっていたのではないかと思った。
バイロン邸での出来事がきっかけで、「フランケンシュタイン」の執筆を本格的に始めたとのこと。
そのバイロン邸でバイロン卿の侍医として屋敷に居たポリドリ…そっちの方が可哀想だなーって!
結局〜あの「吸血鬼」を書き上げるも、自身の作品だとは認められなかったとか…。
でもまぁ、調べれば調べるほど面白いのはバイロン卿の方かな(笑)。
「事実は小説より奇なり」。
っていうか、ダグラス・ブースのパーシーより、ベン・ハーディのポリドリの方が好き(笑)!
観ていて少し疲れたけれど…
美しい映像。含蓄のある言葉。繊細な演技。吸い寄せられる。
その一方で、ろう人形の演技を見ているような型にハマった硬直感のようなものを感じて、少し疲れた。
こういう演出だと思えばそれまでなのでしょうけど。
「母は強い女だったけれど、愛には脆かった」
人間は完璧ではないのだ。気まぐれだし、愛情も充分ではなく、傷つけ合う。
メアリーは、情熱にまかせてこの真っ只中に飛び込み、失望しながらも強く生き抜いた。そして作品を生んだ。
やはり女は、その気になれば、強く、賢いのだ、と思わされる。
この映画が事実にどこまで忠実なのかよくわからないけれど、あの個性的で奇抜な小説の背景には、並々ならぬ環境があった、ということは納得。
作者に想いを馳せる
WOWOWにて、前知識なく視聴。
テーマは「選択と責任」かな…。
暗い画面の中の小道具や衣装、本の装飾など細かいところにこだわりを感じる。スコットランドの自然も美しく、映像美で魅せる。
全編的に静かに物語は進み、死への直接的な表現や感情的な言い合いなどはなく、淡々と進む。ドラマティックなストーリー展開を望む人には受け入れづらいかも。(途中、ちょっとウトウトした…)
精神の孤独によって言葉は洗練され、届ける相手を探すように筆を進める。
シェリーと一緒に行くことを選択したメアリーには、全てをシェリーのせいにすることはできない。クレアを連れて行く選択をする際の間も、クララを抱いて雨の夜に出て行くか迷う間も、メアリーが選択したことを意味しているのか。
相手や環境のせいではなく、自分の選択により今がある。
だから「女性だから」という理由で出版できないことはメアリーにとっては負けたくないこと。だから物語中、唯一シェリーに声を荒げたのか。
自分の選択に責任を持たなきゃいけない。ということを思い出すために数年に一度はまた観たい。
あと「フランケンシュタイン」読みたい。
以下、印象的なセリフ。
「読者がいなけりゃ思想はただの言葉だ」
「不満はないのに気持ちは焦る、自分の夢に近づいているのか」
「家族が健康で幸せなら人生は満たされるのか」
「選択には必ず責任が伴う」
「女は死や裏切りや喪失とは無縁とでも?」
フランケンシュタインを読んでからみるべき
PG12(何故レイティングがかかったのか?)エル・ファニングの中世モノとしてみるとちょっと辛い。
女性の権利向上黎明期という感じ。
タイトル通りメアリーシェリーの伝記モノ。
フランケンシュタインて女性が書いたの?
ていうレベルで、オリジナルのフランケンシュタイン映画もみてないのに何も語れるわけない、すみません。
イギリス
売れてない本屋の娘
妹は夢遊病?あと弟
怪奇小説流行り母は作家、継母と折り合いがつかず一人スコットランドへ
降霊術
お産が原因で死
ハンサムで過激な詩人
久々に実家へ、妹の仮病
詩人に妻子あり噂にしかも駆け落ち
愛が冷めたらもううええやんて
妹みたことある女優さん
魂の炎
自由恋愛
わざわざ父に言うとは
妹は健気、空約束
セントパンクラスへ
いいのか?無理にはってせこい
父から勘当されて文無し
自分の父も貧困
無駄遣い
軽いベッドシーンのみ
詩人はファンが多い
子が出来た。母を知らない私に育てられると?ってそのタイミングで前妻に会う?
妹が奔放に
ホッグが家に、焚き付けた?
自由恋愛の履き違え
私は孤独を知るために生まれて来たのだ
あれ?宗旨替え?
バイロン卿
生体電気フランケンシュタインの発想のきっかけか
バイロン卿と妹
クララ誕生
取り立てから逃げた結果娘を失う
すぐ気晴らしって
バイロン卿のとこで医者と
詩人同士はグダグダ
男尊女卑
何週間も土砂降り
君は遊び相手だって
ロンドンから電報、前妻が自殺
傷ついたら負けよ
夢多いね
妹は養育費だけは貰える
自分の声を探せ、父の言葉
フランケンシュタインは一気に書き上げたってか
希望や理想を語るな
18歳なの⁉
ここでも性差別が
怪物の苦悩に共感するはず
なかなか取り上げてもらえず
匿名と旦那の序文
ついに旦那こき下ろした
お父さんが読む
医者の吸血鬼もバイロン名義に
父が出版記念会を!
旦那が懺悔とは
私の選択が私創った
後悔はしてないわ
その後息子が。第二版
お前は波にさらわれ
はるかな闇に消えるだろう
石段を駆け上がっていくラストは何を意味するのか
全74件中、1~20件目を表示