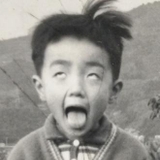教誨師のレビュー・感想・評価
全72件中、41~60件目を表示
対話で紡ぐ物語、対話で導く真理
全編を通してほぼ、密室で繰り広げられる会話場面。
観た人の中には退屈だと思われた方もいらっしゃると思います。
ですがわたしはむしろ、「もの凄いものを観た」と思うほど、
演者たちの一挙手一投足に集中して観ることができました。
『ソクラテス式問答法』という対話法があります。
〈 対話によって相手の矛盾・無知を自覚させつつ、より高次の
認識、真理へと導いていく手法 〉の事を指すんだそうです。
対話によって、死刑囚たちの心の闇に、わずかでも一筋のひかりを灯せる事ができたなら、執行され魂となった彼らは等しく安らぎを得る事ができるだろうか?
そのことに尽力した牧師・佐伯(大杉漣さん)がそんな彼らの闇を見つめながら実は、佐伯自身が一番心に闇を抱えている事を認識し受け止めていったのではないのでしょうか?
わたしが今年観た映画のなかで一番、あとからじわっときました。
大杉漣さんが最期に私たちに出した『人生の宿題』みたいな
作品だと思いました。
見終わってキャッチコピーを見て、「んっ?」と。
斬り込んだ映画でした。
大杉さんがもう「死の側」にいらっしゃることで、また新たな意味合いが生まれてしまっているとも思います。いや、悪く言っているわけではありません。
大杉さん、なぜこの映画を作りたかったのでしょうか。本人からぜひ聞きたいのですが……。
ただ…、あのスペースだけの映画でここまで思わせることがあるとは、と感じていたのですが、キャッチコピーを見て、何を考えていたか忘れてしまったというのが本音。
「『なぜ生きるのか』という問題提起の解答を本文から探してね」という中学生の国語のテストの一問のようなものがメインテーマではないような気がします。強烈な生の物語……?
これは大杉さんの本望なのか………?
まぁいいや。
強烈な会話劇。ここから我々が何かを感じとるのです。
追伸:光石研さんのお気持ちを考えたら、開始早々涙が……ということで「泣ける」
大杉漣さんの辞世の句…のような映画
まず,“教誨師”という言葉を初めて知った。
『おくりびと』を観た時に,“納棺師”という言葉を知ったのに似ている。
死刑囚が,悔い改めて,心穏やかに,死刑執行の日を迎えられるように面談を行うのが,その役割だが,囚人の経緯も様々であれば,現在の心境も色々,宗教だって,一般の日本人だとすれば,仏教,あるいは神道,キリスト教位で,無宗教だというものもいるだろう。
主人公の教誨師はプロテスタントの牧師であり,ミスマッチも多いと考えられる。
“死”,“死刑”を前にした人に,聖職者であれ,向き合うことは,とても難しいことだと思う。
犯罪を犯し,死刑を前にして,いかに死に向き合うかというのは,簡単に答えの出るものではない。
そのように促すことは,自分自身の罪悪感(原罪)の記憶を呼び覚ます。
有限の存在としての人間,死刑制度,人間の業,深く考える間もなく映画は終わったが,答えは見つからない。
ところで,映像の中でよく倒れる卓上カレンダー,ここ数年,自宅で使っているものとそっくりでびっくりした。Quo Vadis製かと思ったが,自宅のものと比べると少し横長だったので,違うものだったかもしれない。
でも,大杉さん,良い役者だ。
ご冥福をお祈りいたします🙏
深み
6人との会話から問う、死刑制度の是非
教誨師。"きょうかいし"と読む。今年2月に急逝した大杉漣さんの"最後の主演作品"にして、初めてエグゼクティブ・プロデューサーも務めている。まさに思い入れある作品が遺作となってしまった。
"教誨師(きょうかいし)"とは、受刑者に対して、徳を教え諭し、心の救済へと導く宗教家のこと。国内では、刑事収容施設法に基づいて法的に規定されているが、ボランディアである。宗教もさまざまで1,000人以上の教誨師がいる。
大杉漣が演じる佐伯は、半年前から死刑囚の教誨師を務めているキリスト教の牧師。佐伯が出会う6人の死刑囚との対話が、拘置所内の同じ接見室を舞台に展開される。
原案・脚本も務める佐向大(さこう だい)監督の綿密に作られた設定が秀逸だ。6人それぞれの死刑囚の人生と、佐伯牧師自身の不幸な過去が浮き彫りにされていく。ひとりの牧師をホストとした、接見室を舞台にした群像劇のようだ。
創作なのであたりまえだが、登場する6人の死刑囚は年齢・性別や性格が異なるばかりでなく、各々の罪状もダイナミックに異なる。具体的な罪名や犯罪経緯には一切言及せず、死刑囚と代わる代わる対峙する佐伯が、6人と交わす会話の中から徐々にそれらを読み解く面白さがある。
佐伯は死刑囚と、"また2週間後に"と話したり、"神父様じゃなくて牧師です"と正したりしているので、プロテスタント系の牧師で、隔週で拘置所に通っていることがわかる。
本作には6人の死刑囚のほかに、佐向監督の面白い仕掛けがいくつかある。
まずは、映画がスタンダードサイズ(4対3=1.33:1)で作られていることだ。横幅の狭い画面は、外界から隔たれた拘置所内の閉塞感や息苦しさを感じさせ、それがエンディングで佐伯牧師が拘置所を出ると、ビスタサイズ(1.85:1)に一気に拡大される。
漫然と観ていると画面の変化は気づかないかもしれないが、なんとなくエンディングでホッとする。これは潜在的に心を開放する効果をもたらしている。
また、時間の経過を細かく演出している。殺風景な接見室のシーンが延々と続く本作で、時間の経過を表現するのは難しい。安易にテロップで、"〇〇日目"や"〇月〇日"と表示してしまう手法もあるが、それでは芸がない。
そのひとつが卓上カレンダーだ。死刑囚との面談中、霊的な現象のごとく、ときどきパタンと倒れる。そのとき、"ハテ?"と月表示を見てしまうことになる。また、佐伯は一貫して黒系のスーツだが、ネクタイが変わる。同じネクタイの日が同じ接見日であることがわかる。
本作は、強烈に死刑制度を問うテーマを抱えている。会話の中から死刑廃止論について考えさせられるエピソードがいくつも提示されている。
また、初めて知るトリビアが多く紹介されていて、知識欲も満足させる。不謹慎だが、死刑あるある話にもなっている。
最後にひらがなを教えた、文盲だった死刑囚が残したメモが、佐伯に問う。
"あなたがたのうち、"
"だれがわたしに"
"つみがあると"
"きめうるのか"
(2018/10/18/スバル座/スタンダード(一部ビスタ)
教誨室の外側へ
この映画のキーワードを挙げるならば「霊性」だろう。
6人の死刑囚たちと、大杉漣演じる教誨師の佐伯との密室の会話劇。
ほぼ全編で本作の舞台となる教誨室には霊の気配が漂う。
大杉漣(エグゼクティブ・プロデューサーとしても名を連ねる)が急逝した、ということも相まって、なのは事実だけど。それを差し引いても、本作には、いまはもうこの世にいない死者の存在が強く感じられるのだ。
死刑囚ということは、全員が人を殺している(はず。厳密には死刑となる犯罪は内乱罪などもある)。
誰かを殺したから、彼らはそこにいる。
そして佐伯にも事情があった。彼もまた、その事情により牧師を職業に選び、ここに来ている。
死者たちに招かれ、出逢った死刑囚と教誨師。
そこに死者の気配が漂うのは必然であろう。
そして、この映画に登場する教誨室は不自然な形をしている。なぜか長い三角形をしているのだ。そのため、佐伯を捉えるカメラの背後には、いつも暗がりが映る。奥行きのある暗い空間が、何かの存在を思わせる演出が効いている。
そして本作は、「国家による殺人」とも言える死刑制度についても、大いに考えさせられる。
物語のスタートでは密室劇だった本作だが、やがて少しずつ「部屋の外」が映画に登場してくる。
始めは外の天気。やがて、佐伯の過去。そして死者たちが、スクリーンを侵食してくる。
それとともに、教誨師を務める佐伯の言動も、徐々に制度や枠組みの中だけでは抑えきれなくなる。
ラストに、ようやくカメラは教誨室、そして拘置所さえも出て、外の景色を捉える。
命という人間の根源と、法という国家の基盤が交差するのは、拘置所の中だけではない。私たちの日常とも繋がっていると感じさせるラストである。
大杉漣さんだったから重みがあった。
タイトルなし(ネタバレ)
☆☆☆★★
神に仕え、教誨師として死刑囚に寄り添って行こうとするも。なかなか自分の理想と現実との狭間に苦しみ、1人心の中で葛藤する教誨師の姿。
上映終了後にイベント有り
1つだけ!
元々演じる事を念頭に書かれただけに。大杉漣演じる教誨師が、そのまま彼の人生そのものとなっている。
但し、観客にこの主人公の人生背景を詳しく伝える為に入れられたと思えた回想場面。そしてそれに繋がるのが卓上カレンダー。
ここは寧ろ、回想場面を無くし。カレンダーが勝手に…と描いた方が、神に仕える者としての普遍性が増したのでは…と、思ったのだが。
6人の死刑囚の中では、烏丸せつこが絶品だった!
あ?2つになっちゃった(^_^;)
2018年11月1日 スバル座
罪人の意味とは
忘備録として印象的だった台詞を。
人を知るというのは理解することではなく側にいること。
同じ言葉で言い表わしても自分と相手の中で思い描くものが同じであるとどうして言えるか。
死刑囚と教誨師ってこういう感じなのかと
きれいごとではない世界
今見るべき。ネタバレ含みます。
人の命を奪った死刑囚、死刑囚の命を奪う政府。矛盾した現実をストレートにぶつけられ苦悩する教誨師。フィクションだが今も現実に起きている事象であり、色々と考えさせられる。若者と教誨師のシーンは特に見所で禅問答を思わせるような言葉のぶつけ合い。屁理屈にも取れるが妙な説得力もある。実際に起き日本中が衝撃を受けたあの事件を連想させる人物も出てくるので見るなら絶対今だろう。
眠れなくなりました
人の生死を人が決める死刑制度。私は死刑肯定派です。だって「日本では」被害者は武器を持てないまま弱い立場で殺されてしまうのだから。
そんな有利な状況で2人以上を殺す人は、やっぱり死刑という罪を受け入れるべきと思う。
ただ、この映画で宗教的な意味で神に罪を許された死刑囚について、人は許さないことはいいのだろうかと考えてしまうとよくわからなくなりました。
色々難しい。
重苦しさのなかに一筋の光も
希望
大杉さんの遺作に相応しく、生と死について深く考えさせられる作品!
私は、個人的に教誨師と言う職業に凄く興味が有ったので、この作品とても気に入りました!
ですが、本作を自分は好きだから、みなさんに、どうぞ観たら良いよとドンドン薦められる様な性質の作品でも当然無い訳です。
決して万人向けの作品ではないのですが、教誨師の行う仕事内容を判っていて、尚本作を観られた方々はおそらく、私同様にみなさん満足して、映画館を後にする事が出来たのではないだろうかと想像していますが、どうでしょうか?
主人公の職業上、映画の95%は教誨師と死刑囚との1対1の会話が続くわけです。
映画では、死刑囚が6人も登場するので、それぞれの受刑者に個性を持たせて描いていれば、観客は飽きずに楽しめるだろうと言う事でも決して無いです。
確かに本作では、なるべく観客が飽きない様な工夫は施されてはいましたし、多くの場面で笑いが出るように作られていました。でも所詮は塀の中の人々の言い分を描いている事なので、一般の観客である我々がそう簡単には、彼らの話に感情移入すると言う事も中々困難です。
そこで当然、観客の殆どの人達は自然と大杉さんの演じる教誨師に自己を投影する事になる。
そうするともう自然と劇中の話の総てが他人事ではなくて、自分に投げられた直球に変化して来るから不思議ですね。
作品の中で交わされた会話の総てが自分へ語られた言葉になる。
どんどん会話の世界に引き込まれていく事になるのです。
すると、カメラが固定されていて変化に乏しい筈の画面を観続けていても、決して飽きません。
更に、教誨師が対峙する様々な死刑囚との会話の中で生まれる彼の葛藤や心理的な変化、やがて明らかになる教誨師の抱える苦しみも、気が付くと観客も追体験しているような錯覚になります。
何だか、急逝された大杉さんが、初めてプロデュースしてまで、本作を撮りたかったと言う気持ちも迄も理解出来る気がしてくる。
本作は映画ではあるけれども、物語の性質上、舞台劇であっても全く不思議ではありません。
最近公開された「累」も舞台劇の様な要素が沢山有りましたが。本作には「累」の様な派手シーンは全くありません。あちらが仮に動の世界なら、本作は静の世界でしょう。
本作はあくまでも静かに会話だけが交わされていくのですが、きっと観客の心の内は静の世界から動の世界へと大きく揺さぶられる事になったと思います。
この秋じっくりと、自分の感情を見つめて過ごしてみようと考えておられる方には、本作は最高のプレゼントになるのではないでしょうか。
そしてこの作品のラストがとても効果的な終わり方で、とても気に入りました。
是非、御一人で過ごすお時間が有ったら本作観て欲しい気がします。「何だ、結局お前は本作を薦めているだけで、これはレビューでも何でもないじゃないか」と思われるでしょう。でもやはり私は本作の世界を堪能して欲しい!あなたにもこの死刑囚たちに出会って欲しい。それが本作に触れた私の正直な気持ちです。
大杉さんの早過ぎる死を悼み、ご冥福を心からお祈りします。
いやぁ,こういう趣旨での1人1人は難しいんとちゃうの⁉︎
全72件中、41~60件目を表示