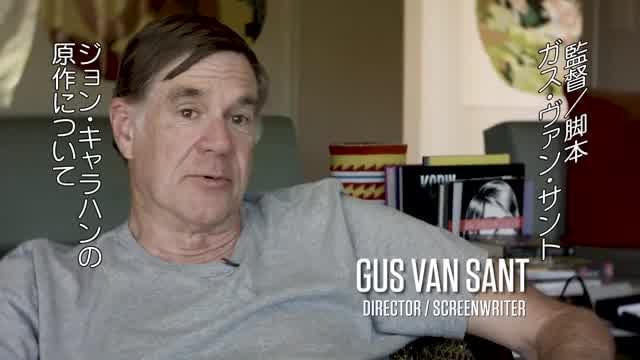「アメリカ映画に多い再生物語の背景について考えた」ドント・ウォーリー 琥珀さんの映画レビュー(感想・評価)
アメリカ映画に多い再生物語の背景について考えた
最近の悪い癖でどうしても時代背景とか、日本だったらどう周りの人達が接するだろう、とか考えてしまう。
まず驚いたのが、この時代のアメリカでの社会福祉の手厚さ。事故に遭うまでの主人公がどんな仕事をしていたのか、定職についていたのかよくわからないのだが、事故原因(今の日本だったら、自業自得で保険も適用されないような運転手、同乗者ともの泥酔)に関わらず、電動!車椅子が手配され一定の生活費まで出ているらしいこと(もしかしてヘルパーの費用も?)。
次に、やはりアメリカはチャンスの国であったということ。
いいと思えば、絵を持ち込んだ人の事故やアルコール依存症の経歴などと関係なく、発表の場を与えてくれる。辛めの内容であっても多様性の中で許容される範囲であれば多少の批判を覚悟で掲載を続ける。日本のメディアだったら、学生新聞のレベルであっても、作品内容の前に作者の人格とか履歴的なものを掲載の判断において優先するのではないだろうか。
宗教は、偏狭な原理主義に陥るととても危険な事態をもたらすことがあるが、告解とか罪として受け入れる行為を神の名の下に、実際には神父さんとか、セラピー的な場で第三者に吐き出すことで、自分ひとりで抱え続けなくても済むような環境を作ってくれる。
例えば、日本で我々が個人対個人(会社の中の人間関係であろうが、友人同士であろうが)で『許す・許される』などの言葉を当事者同士で使うことは、なにを上から目線で偉そうに、とか、自分にはおこがましくて、とかの心理が働いて、そもそも話し合いが成り立たないと思うが、神が見ておられる、神がお許しになる、という前提があれば、この映画のドニーのような人に諭されても割と素直に受け入れることができるのではないだろうか。
一方で、最後は神に許しを乞えばいいや、ということで、始めから規律とか自制心が甘くなる、ということもあるのかもしれないが。
アメリカ映画では、事実に基づく再生物語が多いが、こういった背景も少なからず作用するのだろうなと個人的に納得出来る作品だった。