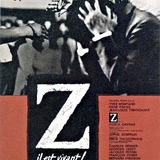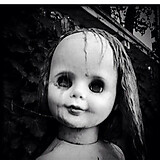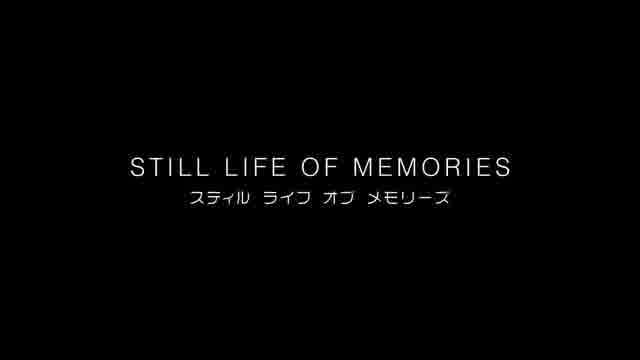スティルライフオブメモリーズのレビュー・感想・評価
全17件を表示
「芸術」の捉え方
怜は美術館のキュレーターであり母親は画家、小さい時から芸術に関わってきた。その母も死期が迫り、生と死にも向き合い、人として産まれ出る女性器を感銘を受けた写真家に撮ってもらおうと撮影を依頼した、ということなんだろう。
実在のフランス人写真家はモデルは愛人のようだが、映画の中の春馬と怜はそうではない。撮影も終わる頃関係を持とうとした春馬を頑なに拒み、カメラを持たせて毅然と足を開く怜。あの時の怜の顔がいちばん美しく強く逞しい。
夏生にも関心する。芸術として春馬の行動を理解出来る寛容さ。
子供のオムツをかえ、長いトンネル、、、子宮からの誕生を意味する、と理解していいのだろうか?
エンドの写真はボカシは必要ないように思える。制作側もボカしたくはなかったのでは?とはいえ、ボカさない訳にはいかないでしょうが。
満開の桜や森、湖など風景もキレイで、モノクロから少しずつカラーになっていくところもキレイ。言葉は少ない。好き嫌いは別れそうな映画だろう。芸術もどう捉えるかは人それぞれ。否定するつもりは全くないが、怜の行動は理解しがたい。
安っぽいエロ映画だと思ったら芸術作品だった
美術館、博物館は月曜が休館日
女性器撮影ばかりが目立つこの作品。性的なものじゃなく、芸術的に撮った写真も見たことあるけど、不思議と原点回帰してしまう錯覚というか、やはり真理そのものじゃないでしょうか。と妙に納得させられました。死期の迫った母親と美術館勤務の娘。それがなぜ自分の性器を撮りたいのかわからなかったけど、モデルとなった瞬間は母親になりきっていたような気もします。
このくらいの映像を映画館で流すことができる時代になったなんて、大島渚が生きていたら歓喜したことでしょう。芸術、メタファなどと理由をつけ、セックスとはかけ離れたものだと訴えれば何でもありなのでしょう。そう、安藤政信が演ずる写真家にしても、花びらとか木の祠とか女性器を想像させるものばっかりでしたから、全ては自分が産まれてきた場所、そして人生最後に見る風景を求めていたのでしょう。長いトンネルに吸い込まれていくうちに、胎児に戻ってしまうかのような錯覚にも陥り、もしかしたらこのまま死ぬんじゃないかと思う二面性もあるのかと感じます。
そうした芸術性を高めるため、オール山梨県ロケというこだわりもあり、特に透明度の高い湖が気になって調べてしまいました。一応、富士五湖は暗唱できるのですが、ここがどこなのかさっぱりわかりません・・・みつけたのは四尾連湖!山梨に住んでたことあるのに一度も行ったことがありません!一度行ってみたいと思います・・・
静物と女性の境界
ピントが合わず...
新進気鋭の写真家・春馬と、彼に自分の秘部の撮影を頼んできた美術館キュレーターの怜との奇妙な邂逅を描いた作品。フランスの高名な写真家とその愛人の実話が下敷きになっているとのことですが、その話について全く知識の無い私からすれば、怜が何故そのような風変わりな撮影を望むのか、そのことと関連がありそうな場面が断片的に挿入されてはいたのですが、私の中では上手く繋がりませんでした。下敷きになった外国の話についてもう少し予備知識があればもっと簡単にこの作品の世界に入って行けたのかも知れませんね。そのため、女優さん方の演技は本当に体当たりで見事だったですし、カメラワークも相当に苦心されたであろうことは、素人目にも分かったのですが、申し訳ないことに印象が薄い鑑賞になってしまいました。
アーティスティックな大人のメルヘン
非常に遅れてのレビューになるが…
自分を観ることの不可能性
中華圏の映画についての本も書いている四方田犬彦の「映像要理」が下敷きとなっている。この夏、台湾映画の特集上映に通ったときに、毎回この作品の予告を観ていたので、今日の本編を観ても新鮮味がなかった。予告編の記憶の確認作業という意味以外のものを見つけることは難しかった。
ただ、予想以上に女性器を接写する場面の回数が多く、まさに映画のテーマがそこにあるという作り手の強い意志を感じた。女性器への執着について、美術館で講演をしていた先生が、クレジットに出演者として名前のあった四方田氏自身であろうか。
この世に生を受けて最初に見る女性器は母親のものである。この言説には同意しかねる。生まれたばかりの赤子には、女性器を視認する視力がまだ備わっていないではないか。
この世で最後に誰の女性器を見るのか。なるほど、年を取ると女性器を見るたびに、これが最後なのかもしれないと思うものなのかも知れない。完全な男性目線の物言いではあるが。
映画の中で最も印象に残ったのが、「なぜ画家は自画像を描くのだろう。」という写真家のセリフである。
写真家は自分の顔を撮影することは物理的に不可能だ。鏡を用いても、そこにはカメラを構えた自分が映る。かと言ってタイマー撮影をしても、それはカメラが機械的にシャッターを切るのであって、写真家の意志によってボタンが押されるわけではない。
写真家の不可能性についての一考察であり、これはまた、自画像ならぬ自「性器」像は、現像・プリントの技術がなければ観ることができないことと対を成している。(デジカメのある時代には、成立しない言説かもしれないけど。)
カメラというものを通して、自分を観ることの不可能性について考えさせられた。
面白い映画も少ないこの夏。四方田氏の著作に触れてみるのもいい。
心が離れる瞬間
女性の身体をやたらと「神秘的」だなんだと持ち上げて特別視することが苦手だけど、この作品は意外とすんなり入ってきたので良かった。
被写体の特別感というよりも、撮られる側と撮る側の人間関係と感情の動きにスポットが当てられているような気がした。
冒頭からスライドショーのように流れる春馬(が撮った設定)の接写のフィルム写真がとても魅力的で、自分の一番奥の部分をこんな風に美しく撮って欲しいという気持ちは少し分かるかも。
死に向かう母親を見て、今の自分の何かを残したいという気持ちも。
携帯のメモリやSNSに気軽に自分の痕跡を残せる現在だけど、手に取れる質量のある写真を残すことに意義があるような気がする。
それこそ写真のような構図の画が多く、綺麗だなと思った。モノトーンから徐々に色づく演習が好き。
登場人物全員の台詞の音読感があまりにも強いのが気になった。
そもそもの演技力の問題なのか、あまりリアルにしない敢えての演出なのか…
かなりアートな作風だからこそ日常に寄せた部分を口調や表情で感じたかった。
ボロ小屋に倒れていたものの正体や意味が気になった。
陽炎のような映画
安藤くん見たさに大阪アジアン映画祭で初めて観て、また昨日ケイズシネマで観賞しました。
こんな映画はいままで観たことがない、こういう映画体験は生まれて初めてかも、としかいいようがない。
観るたびに印象が変わるんですよ。二回目はひとつひとつシーンに「こういうことだったのか」という発見があり、二度目は前回聴こえなかった音が、画面に映らない音のざわめきが聞こえた。
それに二回目は映画の途中で物語の時間が消えて、主人公たち(写真家と図書館司書)がこの世にいるのか、あの世にいるのかわからなくなりました。「骨を砕くような音」と安藤くんが言っていたシャッターの音が響くたびに二人の心の迷いが深まり、此岸と彼岸の境がだんだん透明になっていきました。
凄絶といっていいほど美しい映像。
男と女、性の儚さをまるで陽炎のように描いた映画。
最近ワイルドな役柄が多かった安藤くんですが、彼が持ってるスピリチュアルな本質がこの映画には写しだされています。
途中で終わってほしくない、ずっと続いてほしいと思った初めての映画。
儚くも切ない、生が垣間見える瞬間
カメラマンと被写体の美しくセクシーな関係
とてもセクシーで美しい作品でドキドキしたなー
安藤政信演じるカメラマン 春馬は、個展を観に来た女性から、写真撮影の依頼を受ける
現場に行った春馬は、その女性からとてもショッキングな依頼を受ける
その依頼主の女性は、
母が寝たきりになってしまったことで命に限りがあることを知り
自分自身を写真に残しておこうと考えた
自分の全てをさらけ出した女性と、レンズ越しに向き合うカメラマン
その向き合う瞬間、瞬間がとても静かで、セクシーな空気が流れた
そのセクシーさにドキドキしてしまった
この映画は「命」についての話でもあった
女性の身体とは、命が生まれ、育む場所である
カメラマンは、その神秘に魅入られのめり込む
進んでも進んでも理解できずに進み続けるという熱さがとても印象的なカメラマンだった
私は、その撮影を依頼した女性のような行動はできないけれど、身内の死をきっかけに、時間を意識したり、何かを残しておきたいと思う気持ちは分かる気がした
芸術家の作品というのは、そういう凡人には理解できないところから生まれるものなんだろうなぁ
全17件を表示