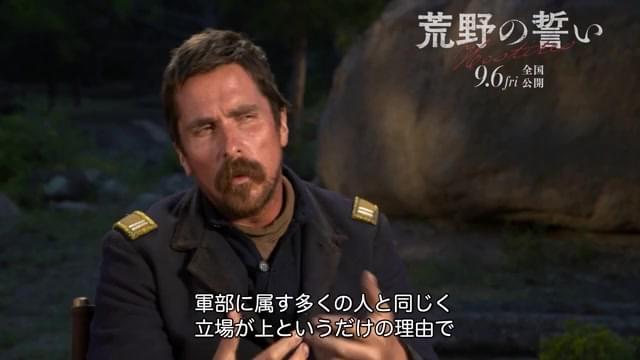荒野の誓いのレビュー・感想・評価
全23件中、1~20件目を表示
長い長いミッションの果てに
クリスチャン・ベール扮する主人公ブロッカー大尉と個性的な部下たちとの関係性が丁寧に描かれており、作品に深みを与えています。
ブロッカーの盟友で、積年の過酷な軍勤務がもとで鬱を病んでしまったトミー。黒人のヘンリーとは人種の違いを超え、厚い相互信頼が存在します。さらに、かつての部下で一緒にインディアンを殺しまくった死刑囚のウィルスには、ブロッカーの今の変節を「見損なった」と非難されてしまいます。
一方でシャイアン族の首長イエロー・ホークとの関係性には、少し違和感を感じてしまいました。部下や友人達を殺され、地球上誰よりも憎んでいたはずなのに、護送途中の割と早い段階で共闘してしまうところなどです。和解すること自体は本作の主題なので問題ないのですが、そうであれば、前段の憎しみの深さをもう少し描いた方が、より説得力が増したのではないでしょうか。
ニューメキシコからコロラドを経てモンタナへと連なる中西部縦断の途中で、登場人物のほとんどが、憎しみの連鎖により死んでしまいます。
現代にも通底する憎しみの連鎖。ブロッカーの長い旅路の果てに生まれた贖罪の念と相互尊重は、これからの未来にも、生かされることはないのでしょうか。
ほとんど語らない主人公が格好良い
これは面白かったです。
中々に悲惨な西部劇。
家族や信頼する仲間が次々と失われていく展開。最後まで生き残るのは、主人公とヒロインだけという都合の良い展開ですが、そこに僅かな救いがありました。
ほとんど語らない主人公が、西島秀俊さんみたいで格好良いです。
徹底的に白人主観の視点で描かれてはいるのたけれど、だからこそ現代の排外主義についても考えさせられてしまうというアクロバティックな魅力があります。
永い言い訳
背景は侵略と抵抗と風化というアメリカ開拓史であるが、いわば人類史の縮図に過ぎず古今東西、人間の営みには血の臭いが付きまとっている。
冒頭から牧場一家の襲撃が描かれる、子供ばかりか赤ん坊まで殺される非道の描写、何の因果でこんな残虐な事件の目撃者にさせられるのか、本作を選んだ自身を悔やまずにはいられない。
クリント・イーストウッドの「アウトロー (1976)」も似たようなティストだったが本作よりは単純、目の前で家族を惨殺されれば復讐の鬼と化しても不思議はない、宿敵は北軍ゲリラの犯罪者だし銃が掟だったからまだ観ていられた。確かに復讐も戦闘も遂げてみれば訪れるのは虚無の闇、本作は先住民と侵略者の軋轢、勝者の視点、理屈で懺悔交じりに描いているが永い言い訳を聞かされているようで興醒めする。
邪鬼が人間に戻れるとしたら為すべきは償いの善行なのか、犠牲者の寛容や慈悲でもなく、ただ風化しかないのだろう。
確かに演者は熱演だし、タブー視されるテーマに挑んだことは評価を受けて当然だが生理的に合わない映画でした。
静かな物語
淡々と進み、とにかく静かにクリスチャン・ベールの物悲しい表情が印象的。かつては先住民との戦いで沢山の殺し合いをしてきたベールだが、その間も仲間を多く失う。敵であった酋長の死期が近く、故郷に護送することになり、当初は反対していたが、様々な敵からの襲撃を受けるうちに助け合うようになるが、その間も部下を亡くしていく。次第に戦うことの無情さ、過去への反省、先住民への思いが芽生え、変わっていく。全てベールの表情が物語り、ラストは、3人で暮らすのだろうか?ハッピーエンド。
ご婦人に撃つ度胸があるかな
映画「荒野の誓い」(スコット・クーパー監督)から。
産業革命後の開拓地を舞台にしたアメリカの西部劇。
先住民のインディアンと開拓者との戦いが壮絶だったことは、
メモを見ないまでも、明らかで目を覆いたくなるけれど、
これもまた現実だと理解して観始めた。
同じインディアンでも、シャイアン族とコマンチ族は、
本当に違う戦い方をするのかもしれないな、と思いながらも、
あまり、メモする台詞は見つからなかった。
逆に、先住民インディアンの土地を、我が物顔で闊歩し、
「大統領令です」と指し示したにもかかわらず、
「ただの紙切れだ。たとえ大統領でも俺の土地には口を出させん。
ここは俺の土地だ」と言い張りインディアンを攻撃する白人。
それに怒りを覚えた主人公の女性が、彼に銃口を向けても、
なお「ご婦人に撃つ度胸があるかな」という態度で接した。
その傲慢な態度に終止符を打ったのは、
迷わず引き金を引いた白人女性、カッコ良かったなぁ。
「自業自得」って言葉が浮かんだ瞬間だった。
荒野で一緒に苦労を重ねてきて好きになるのはわかるけれど、
「どんな未来であれ、幸せを祈ってるわ」と別れたのに、
ラストのハッピーエンドは、ちょっとなぁ。
今や大人気のティモシー・シャラメが真っ先に退場。
インディアンを総じて野蛮人として扱っていたかつての西部劇とはかなり違ってきている。いつの頃からか、NHKで放送される西部劇では「インディアン」という言葉は使われなくなって「先住民族」という言葉ばかりだ。差別用語を使わないようにしてるのはわかるけど、どうしても違和感が残る。金沢にはインディアンカレーという有名なカレー屋さんもあるのだけど、これも放送禁止か?と考えていたら、さすがにインディアンズの大リーグ中継はやっていた・・・
退役目前のジョー・ブロッカー大尉が上司からシャイアン族の酋長をモンタナ州居留地まで護送するよう命ぜられる。断ったら年金も与えないと脅されて、渋々大嫌いなインディアン一家を送ることになった。途中、コマンチ族によって家族を皆殺しにされた寡婦(未亡人という言葉も最近は使えない)ロザリー・クウェイドを保護し、旅の一行に加えることとなる。ここで家族の仇でもあるインディアン一家を出会ったロザリーの反応も鬼のような形相がまずは見どころのひとつ。インディアンは全て敵だという固定観念が抜けないでいるのだ。
そしてガラガラヘビのごとく、彼ら一行を襲撃してくるコマンチ族。ここでフランス人のシャラメくんが殺されてしまうのだ。英語とフランス語のチャンポンが和ませてくれたのに、もう笑えるキャラがいなくなった感じで、ここからは相当シビアなロードムービーとなる。映画館では10人未満の観客だったけど、シーンと静まり返る館内。『クワイエット・プレイス』や『ドント・ブリーズ』の比ではないくらいに音を立てづらい雰囲気なのだ。何しろ人間と馬を発見したら、こっそり忍び寄って襲ってくる敵。もう敵だらけ、原題そのままなのです。
コロラド州の中継地点ではちょっとのんびり。しかし、インディアン一家を惨殺した男、しかもジョーの元部下でもある男の護送も頼まれるのだ。そこからは居留地問題やインディアンが皆残忍であるという偏見の問題も含め、ジョー自身の過去の闇も暴かれてゆく。兵士となった以上、敵を殺すのが仕事。冒頭のD・H・ロレンスの言葉にもあるように、アメリカ人は人殺しなのだというテーマにも繋がってくる。本来、自分たちが侵略者であるにもかかわらず、先住民を殺したことによって復讐の連鎖が続いていた頃の話だ。しかし、とりあえず、シャイアンも加わって話し合いによって解決しようと説得され・・・
終盤クライマックスでは、モンタナに到着した御一行がそこで病死した酋長の葬儀、埋葬。白人たち、キリスト教信者たちの儀式とは全く違う光景がとても新鮮だった。文化の違いも興味深いものがあったし、コロラド州の美しい大自然を背景に癒しの映像も満載。こんなに美しい場所なのに、人々の心は殺伐としているというコントラストが絶妙に描かれているのです。そして、皮肉なことにインディアンたちとの和解の後にやってきたのは・・・という虚しさ。あの威張り腐ったオヤジがトランプに見えてしょうがなかった。
ラストでは汽車に乗って去ろうとするロザリーとシャイアンの子。このまま別れていいのか?ジョー。と、列車に飛び乗るジョーが何とも言えず男らしいというか、これぞ照れ屋の男。まさしくシャイやん!というオチでした。
米国の本質を内省・巡行する秀作
1892年、米国ニューメキシコ州。
インディアン戦争の英雄ジョー・ブロッカー大尉(クリスチャン・ベイル)は、隊長から収監されているネイティブアメリカンのシャイアン族首長イエロー・ホーク(ウェス・ステューディ)とその家族を居留地まで護送するように命じられる。
ブロッカー大尉と首長は、かつて戦場で戦い、多くの仲間が殺し殺された関係である・・・
といったところから始まる物語で、監督は『クレイジー・ハート』『ブラック・スキャンダル』のスコット・クーパー。
この本筋に入る前に、入植者の一家がコマンチ族に皆殺しにされ、命からがらひとり妻のロザリー(ロザムンド・パイク)だけが生き延びるという描写がある。
このシーンは、往年の(といっても60年代ぐらいまでか)西部劇でよく描かれていたもので、ブロッカー大尉一行がロザリーを発見し、彼女を安全な土地まで送るといのも、かなりオーソドックスな西部劇の枠組みといえる。
ということで、かなりオーソドックスな西部劇の風貌をしているが、目指すところは娯楽映画としての西部劇ではない。
冒頭、引用されるD.H.ロレンスの、アメリカを評する言葉、それを探るのがこの映画の主題。
「アメリカの本質は、孤独で人殺しだ。それは和らぐことはない」
つまり、アメリカの本質をアメリカ人が探り、内省するロードムービーである。
映画は大きくふたつに分かれている。
一行が途中、町へ到着するまでと、その後である。
ここへたどり着くまでに一行の兵士は半減し、ロザリー一家を襲ったコマンチ族も征伐されているので、ほとんどハナシは終わったようなものだが、町を管轄する隊長(ピーター・ミュラン)から、ネイティブアメリカンの一家を惨殺した男の護送を依頼される。
そして、その男は、ブロッカー大尉の元部下である
一行が送り届ける対象(つまり、敵)が、ネイティブアメリカンという外部から、元部下という内部へと変化するわけである。
アメリカの本質についての内省がより深く進んで行く・・・
この「内省の巡行」、観ているうちに別の映画を想起しました。
ダブって見えたのは『地獄の黙示録』。
『地獄の黙示録』は、最終的に「闇の奥」の闇しか見つけられなかったが、ブロッカー大尉は自分自身の本質を、和らぐことのない孤独な人殺しということに辿り着き、それを直視する。
和らぐことがないのは、相手を知らない、理解しようとしないからだったということに・・・
オーソドックスな西部劇の枠組みを借りながらも、骨太で現代にも(未来にも)通じる秀作でした。
ただし、道中の描写が同じような繰り返しで(物語上、仕方がないのかもしれないが)、まだるっこいところもあるので、そのあたりは減点かしらん。
なお、日本人撮影監督マサノブ・タカヤナギの映像は秀逸。
ロング・ライダーズ
“悪い”インディアンを白人がやっつける構図の西部劇は、「ソルジャー・ブルー」「小さな巨人」などを経て、先住民の権利という概念を意識せざるを得なくなった。そもそもアメリカン・インディアンにとって白人は侵略者以外の何者でもなく、いわゆる“西部開拓史”は土地が収奪されていく歴史でしかない。
この映画もそういった意味で勧善懲悪の西部劇とはほど遠い、終始沈鬱なムードに覆われた作品だ。主人公の大尉は同僚を殺したインディアンの酋長とその家族を郷里まで送り届けるという屈折した任務を命じられる。馬で旅する長い行程の間に、同行者は一人減り二人減り…と次々と命を落としていく。改めて思うのは、この時代のアメリカは無法地帯だったということだ。途中で敵も味方も何人も人が殺されるが、法で裁かれる気配はない(最後の対決も冷静に考えると正当性を主張するのは難しそうだ)。
道中でインディアンと協調していくところは、クリント・イーストウッドの「アウトロー」にも似ている。シャイアンの酋長は、生きていたらチーフ・ダン・ジョージの役どころだったかもしれない。
クリスチャン・ベイルの髭づらはなかなか渋い。
白人側の一方的な反省物語
評判の高さとあらすじを見て、西部劇というジャンルに対する、現代ならではのストーリーの描き方を期待してました。
しかし、、結論からいうとテーマの重さに対してあまりにも浅い話だと思いました。
まず、白人vs先住民の構図を作っておきながら、先住民サイドを人間として描く気が全くありません。
最初から最後まで、”寛大な心で許し、協力的な”都合のいい”一面的なインディアン。
一方で主人公たち(白人)は二面性がありしっかり”人間的”に苦悩。喧嘩両成敗ですらなく、白人が反省さえすれば解決という話になってます。
クリスチャンベールのしかめっ面を大仰な音楽で撮りまくる尺があるなら、先住民側の心理描写を描けば?
ラストサムライでも日本人がやられてた、典型的な”悟りを開いたように深げなセリフしか言わない非西洋人キャラ”としか描写されていません。これ2017年製作ですよ?
一番ビックリしたのが、
冒頭に40〜50年代の西部劇のような、先住民が完全に悪役として描かれる襲撃シーンがあるのですが、「ここから先住民側の素性とかが明らかになってひねりになるんだろうな〜」と期待していると、、
まさかの「あの部族は凶暴だから」の一言で回収。しかもそれを先住民に言わせる。その後の部族同士の偏見とかの展開もなし。
これは驚きました。それなら”駅馬車”や”リオグランデの砦”のアパッチ族も「あいつら野蛮だから」で済ませられるのでは??
今作では、主人公や戦友の曹長が一方通行的に反省して、贖罪の為の機会を都合よく与えられてます。(白人の囚人と終盤の自称地主たち)
違う映画ですが、”一方的に復讐の連鎖断ち切った気になるなよ”ということを描いてる”アメリカンヒストリーX”は、改めて多視点という点では名作だと思いました。西部劇ですらないですが、、
他にも言いたいことはありますが、好きな点としては、ロザムンドパイクの”ゴーン・ガール”的な強さと脆さの両面的な演技は流石でしたし、アクションシーンの迫力と緊張感は素晴らしかったです。
ちなみに、先住民を人間的に多面的に描いた映画なら、同年製作の”ウィンドリバー”がオススメです。これこそ2017年に作る価値がありました。
最後に、
監督の狙いが、偽善だらけの”古き良き西部劇”の復興にあるのだとしたら大成功じゃないでしょうか?
本格西部劇ロードムービー
本格路線の西部劇をみるのは久しぶりだったので楽しめました。
映像やディティールのリアルさに素直に驚嘆です。戦闘シーンなども凄くちゃんとしていました。全体的にとても丁寧で、全く手抜きを感じない映画です。
しかし、描かれている内容や主題はちょっと陳腐かなと感じました。普通のキャラクターが普通の行動を選択するだけとしか思えないストーリーでした。しかしその行動に疑問を感じるところもちょくちょく、、、
ひとつひとつ言うと、
序盤ではかつての敵への恨みから任務を一旦断りつつ、後半では過去の自分の行動を「仕事」だったと語っている。死の直前の和解もちょっと強引。軍人が任務の途中で寡婦の寝床に入るか?戦争での自分の壮絶な過去を匂わせつつ、今更戦闘や仲間の死に動揺している。つまり最初は凄い仕事をするんだと思わせつつ、普通にポンコツっていうのが違和感です。
視点というものがあまりに白人に寄って描かれていると感じます。この映画で良いインディアンとして描かれるのは常に白人に友好的な部族で、他のインディアンは猟奇的な快楽殺人者のように扱われています。現実にそんな訳はないし、そうなった経緯が語られないので浅く感じました。
奥さんの方も、アーメンを口にした次の日に敵の死体を辱めるというね笑 その後も自らの信仰について語ったり、あまつさえ自殺を計ったり!なんか聖書との矛盾が甚だしすぎて、よくわからなくなります。壮絶な体験から信仰を捨てる(神との決別)というのなら全然理解できるんですけどね、、、
何の為に、血を流れたのか‥
殺した側、殺された側、そして死を待つもの、死に場所の為に、犠牲を払い、相手を知る事で、人間らしさを取り戻していく、最後の銃撃戦で起こるきっかけは、欲にまみれたエゴ、彼が守る物は、人間らしさ、その為に、背中から人を撃つ。
矛盾をしているが、荒野で最後まで人でいる為の引き金。
最後のカットは、それで少し変われた人間が、幸せを知る為の勇気の行動。
時にアート的に、時にリアルに見せる西部劇、引き金を引いた時の音が、思いの強さを出してる気がする。
久々に骨太な西部劇
一応ネタバレありにしておきます。ほとんど内容に触れてませんが。
派手なガンアクションや胸踊る展開はないけれど、暗くて残酷で淡々と物語が進行してゆく骨太な、けれどある意味退屈であるとも言える作品。
インディアンや黒人が出てくるけど別に人種差別NOを声高らかに謳ってるわけでもなく、ただ物語の中の現実を淡々と映し出してゆく。
そこから何を感じ取れるか、何を考えるかは観る人次第。
クリスチャン・ベールの感情を押し殺したような眼で訴える演技はバッチリハマってる。
ただ役柄から受ける印象よりは線が細いイメージ。も少し無骨さが必要かな、と。
ウェス・ステュディの酋長役はハマり役以外の何者でもない。単にインディアンの血筋と言うだけでなく、酋長としての威厳、重厚さを感じられる。素晴らしい。
ロザムンド・パイクは年齢を重ねてより素敵になった印象。
どことなく品のある、けれど真の強い女性を好演。こちらも違和感なし。
胸熱な展開も派手なアクションもない、純粋な娯楽作品でも、問題作でも芸術作品でもないけれど、観ればきっと何か感じるところ思うところがあると思う。
ぜひ音響の良い劇場で、大スクリーンで鑑賞して欲しい作品。
☆-1点の理由は、やはり盛り上がりに欠けると感じたところ、かな。
レヴェナントなどと比較すると色々辛いけど、同じ土俵で語れる、語るべきものでもないと思うので、そこは不問で。
あなたが死ぬ時、私の一部も共に死ぬ。
この顔を見てまず一声。
あ、バッドマンだ
そういう人も多いと思う。映画界きってのダークヒーローを演じたクリスチャン・ベールが、またしても複雑な葛藤を表現する。
舞台は1892年のアメリカ。定かではないが、1890年にフロンティアは消滅したという有名な学説があったと思う。
西部開拓時代の末期もしくは終焉後という事だ。
序盤の展開と演技は素晴らしく、一瞬で映画に取り込まれたし、冒頭のシーンは大成功と言っていいと思う。けれどだんだんと微妙な感じになっていった。丁度、ジョーが収容所を出発するまでがピークだったように感じる。
ロザムンド・パイク演じるロザリーの息を殺すシーンなどは画面に釘付けになったし、ものの十数分だったと思うが、家族を失って心が壊れていく様をまざまざと見せつけられた。
ベール演じるジョーが護送の任を受けるかどうかで葛藤するシーンも、割とありがちな手法だけれど、あえて音声を切って映像だけで見せる事で"声にならない叫び"をよく表現していた。
いわゆるインディアン戦争を生き抜いた彼らにとって拳銃は魂の一部だったりする。戦友の銃に口づけしたり、信頼の証に弾を抜いた銃を互いに突きつけ引き金を引く。それが誓いの儀式にもなる。
その拳銃を前に彼は葛藤する。友の仇たるイエロー・ホークを護衛する任務。任を受けるくらいなら或いは……。
その辺りの解釈は人それぞれだろう。
こういう、人によって解釈の違いを生む表現や演技が芸術の醍醐味と言っても過言ではない。素晴らしい。
徐々に微妙になっていったという理由の一つに、あまりに死人を出し過ぎたことがある。雑魚ならともかく、割と丁寧に描かれてたキャラもコロッと死ぬ。
物語において、文字通り"名のあるキャラクター"はなるべくなら殺さない方がいい。
もちろん、そのキャラクターが死ぬ事で感慨深いシーンになる事もあるし、素晴らしいシーンになることもある。しかし、2時間ちょっとの映画なら多くて3人、4人死ぬのでさえ少しやり過ぎな感がある(ホラー映画やスリラー映画はそのほどではない)。
今作では、例えばイエロー・ホークの死は必要だった。主人公らの行進の目的なわけだし、インディアンにとって神聖な地で生を終えることの意味とか執着をもっとちゃんと描いても良かったと思うくらい、必要な死だ。
また、最後のアメリカ人領主の死も必要だ。今までは仕事と言って"インディアン"を殺してきた主人公がインディアンらを(もしくは自分の新たな信念を)守るために"アメリカ人"を殺す。
この葛藤とジョーの決意たるや……。
あと一つ、逃げ出した囚人を殺し自らも死を選んだ仲間。(名前忘れた)彼の死も必要な死だ。最終的に彼はジョーと同じくインディアンを赦し、逃走したアメリカ人ーーしかもかつての同胞を殺す。だがその結果、主人公とは対極的に自らも死を選ぶ。この対比は映画に深みをもたらした。
と、外せないのは彼らの死くらいで、後のデジャルダンとかインディアンの女性達とか楽器弾きのマロイとか、死んではないけど黒人との師弟関係+別れとか。
パーティから離脱して行ったそれらの人らは全て蛇足に感じるし、日中に行進→インディアン襲来→夜営→インディアン奇襲
というワンパターンな展開の中でかなり集中を阻害する。
さらに、主人公への理解という部分で(あえて言葉を選ばなければ)人付き合いでその人の人となりを知るということがあると思う。
もちろん、その事だけで人を判断するのは良くない(笑)しかし、いち要素である事は間違い無いと思う。
物凄く簡単に言えば、他のキャラがひれ伏してればその人は威圧感のある偉い人なんだろうし、陰口を言われていれば侮られる何かがある人という事になる。
加え、これは考えてどうこうとかいう事でなく、直感的に(頭をあまり使わずに)その人を知れる手段でもある。限られた時間内で主人公を理解する必要がある映画において、これがわりと重要だったりするわけだ。
名脇役のいる映画が名作となり易いのもこの辺りが理由だろう。
長々書いたが、結局は、キャラを殺しすぎるのは良くない。と言いたい。ww
キャラを殺すなら、それは観客に何かを感じさせる必要がある。
ジャンルが全く違くて申し訳ないが、今までの映画体験で鮮烈な印象を残したキャラの死というものがある。ハリーポッターシリーズのセブルス・スネイプ(アラン・リックマン)の死だ。
ハリーポッターシリーズは殆ど本を読んでから映画を見たが、最後の「死の秘宝パート2」だけは何故か映画から観た。つまり、セブルスの過去や事情を知らないままに彼の死に遭遇した。
その時私は「言語化できない理由のまま直情的に心揺さぶられる」という体験をした。
多分、あのシーンは二度目を観た時に本当の感動に襲われる種類のシーンだったが、私は全ての事情を知った二度目よりも何も知らないで観た一度目の感動の方が大きく感じた。
今作のあらゆるシーンでも感動はしたが、彼にとってこれはこういう意味なんだろうな、とか、この葛藤はここに起因しているんだろうな、とか、自分なりに理由を想像した上での感動だった。
「なんか分からんけど真っ直ぐに心揺さぶられる」というシーンにならなかったのは、彼の周りがあまりに死んでいくから、ジョーを直感的には理解できておらず、思考力を用いて理解する必要があったから。だと思っている。
あの大長編シリーズに出てくるセブルスほどの理解と愛着を持たせろとまでは言わない(笑)
ただ、2時間の中で彼を直感的に視聴者に理解させるには彼の周りを殺し過ぎたな、と感じた。
最後にもう一つだけ素晴らしかった点を。
拳銃の音だ。
一発一発の重みというか、威力というか、そこにかける覚悟というか。ものすごく重厚でリアルで、鳴り響くごとに胸が高鳴った。
『ウォーキング・デッド』のスコット・ウィルソン最後の戦闘シーンという事もあるし、ラストの銃撃戦は是非味わってほしい。
しぶい
最近の西部劇ではいないことにされがちなインディアンと向き合った内容。アート作品のようなテンポでうとうとしたのだが、急に緊張が走るアクションで目が覚める。撃ち合いはお互い必死の殺し合いのようなリアルさでスリリングだ。それにしても子どもが殺される場面は心が痛い。インディアンと一口で言っても部族によってさまざまなことが分かる。
互いの罪と正義
潔いくらいに人が死ぬ、登場人物の殆どが特にT・シャラメとB・フォスターの呆気なさが潔い。
静かに淡々とした時間が流れ、急に銃撃戦が起こる場面は凄まじく、全体的に漂う雰囲気が渋い。
序盤、インディアンの残虐性から白人のそれを描写する演出に深い意味合いが。
互いが寄り添い理解し合える関係が築ければ、国や人種間の問題など、争う必要はなくなり。
それぞれに正義があり、罪も根深く互いに被害者であり加害者でもある、アメリカの争う歴史が今を変えているようで、何ら変わらない現実も多少に怖い。
ラスト、二人の元へ戻る姿に哀愁が漂い、ハッピーエンドに進む終わり方ではない何かを背負ったままに。
重厚な演技
インディアンとの関係の変化があっけなさすぎて、そんなに簡単に良好になれるならとっくに地上から戦争はなくなっているだろう、と脚本にはツッコミどころはあるものの、そのおかげで「もしかしたらやっぱり裏切るかも」と思ってサスペンスフルな見方をしたからか、飽きることはなかった。映像や音響は重厚で、○ィズニー映画全盛の時代に骨太な映画を観ることができたのは嬉しい。クリスチャン·ベールとロザムンド·パイクの演技は脚本の甘さを補ってすさまじい迫力だった
キツイ!暗い!
余命少ないシャイアンの酋長を故郷まで
連れて行く仕事を受けた。
複雑な気持ちだ。戦争とはいえ、ネィテブアメリカンを殺しまくった退役前の大尉。そこに、家族をコマンチに
殺された婦人が加わる。
そこにあるのは、それぞれの正義だが。
お互い協力できなくてはならない出来事が。
暗く、辛い映画だが
観る価値は、ある!
共に死に、共に生き続ける。
イエロー・ホークにジョーが言う。「私の一部はあなたと共に死ぬ」。足りてないと思う。「あなたの一部は私と共に生き続ける」。
あまりにも広大で、狩る獲物に事欠くことの無いアメリカ大陸の先住民には「土地を所有する」と言う概念が無かったとされています。所有の概念が無ければ、土地を巡って戦う必要も無い。戦争のために組織化する必要も無い。結果、欧州やアジアの様な「階級社会」の存在しない、完全なる「民主主義」で人々が生活していたのが、コロンブスの時代の事。
モンタナに到着した一行は、土地所有を主張する「地主」に追い立てられます。
「撃て。撃て。撃てよロザリー・クウェイド!」
先住民が戦う火力を持たなかったアメリカ大陸は、南北ともに欧州に侵略されてしまったけれど、あの時戦う事を知っていたら、どうなっとりましたでしょうか、なんて事を考えてしまう場面だった。
人も動物も殺しすぎの北米大陸。「オレ達以外は全部敵文化」の根底にあるのは、キリスト教信者以外はヒトに非ずな教会原理。アメリカって、200年掛けてドンだけ進化したんだろうね。
最後の無銭乗車の仕方がカッコ良くて、嬉しくて、泣けました。
良かった。すごく。
あれ、クリスチャン・ベールって、この間チェイニーやってなかった?中々に社会派なんですね。
原題タイトル、Hostilesに込められた意味
重厚感のある物語だ。
おそらく今観るべきと言って良いかもしれない。
ストーリーの背景は、よく知られたアメリカの歴史、つまり、アメリカ原住民との争いだ。
そして、そのなかで、ひとりひとりの生死や物語が描かれる。
殺し合いの果てに、トラウマを抱え精神を病むもの、殺戮が当たり前のようになるものがいる。
家族を殺されたロザリーは、なぜ復讐心をしまうことができたのか、そんな心の変化も是非感じて欲しい。
「神の試練に耐えられなくなることがある。」
いや、違う。試練は人間自身が自らもたらしたものではないか。
「親切をありがとう。あなたの心は私の中で生き続けます。」
そう。世界中に多くの神はいるが、実は神は一人で、私達ひとりひとりのなかにいるのではないか。それは、優しさだったり、道徳心だったり、正義とか公平とか、共生する気持ちだったり、そんなもののひと塊りのようなものではないのか。
「過去に囚われるのはやめよう。私の一部はあなたとともに死んでいく。」
そう、それは、全て忘れ去ることではなく、憎しみや復讐心を捨て去ることだ。
「どんな未来であれ、あなたの幸福を祈ります。」
ジョーは、熊(ベア)の名前を持つ少女にジュリアス・シーザーの本を渡す。神の物語や聖書などではなく、ひとりの人間の物語を。
ロザリーに別れを告げ、立ち去ろうとしたジョーは、思い直して、動き出した列車にそっと乗り込む。
未来は、幸福な未来は、すぐそこにあったのだ。
Hostiles(敵)とは、何だろうか。
肌の色や、民族の違う相手のことだろうか。
自分達と異なる神を奉じるものだろうか。
いや、同じカテゴリーのなかにあっても、自らの利益のために、ルールなど関係なく、他の全てを敵とするものもいる。
敵、それは試練と同じで、人間が自分で作り出したものだ。
困難な時代だ。
だが、振り子は必ず反対に振れると信じている。
全23件中、1~20件目を表示