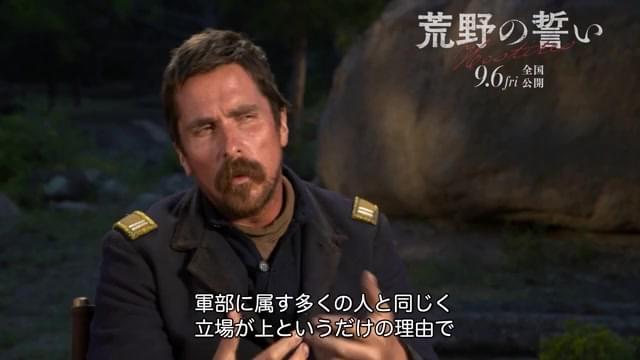荒野の誓いのレビュー・感想・評価
全65件中、1~20件目を表示
人はいかに絶望を乗り越えることができるのか。ベイルの凄み溢れる演技にまたも圧倒される。
元来、クリスチャン・ベイルの主演作を観るにあたっては、かなり精神的な体力を要するのが常だ。それは内容そのものがハードであるというよりも、むしろ彼演じる主人公の歩む道のりがあまりに長くて険しいもので、彼と共に我々もまた大きな心の距離移動を余儀なくされるからだろう。
本作でベイルの演じる役柄もまさにそのような類いのものだった。かつてネイティブ・アメリカンと壮絶な戦いを繰り広げ、多くを殺め、また多くの仲間を殺された兵士がいる。彼が辿るべきなのは懺悔か、復讐か、それともまた別の道なのか。静かな存在感ながら、その体内には言いようのない葛藤と苦しみ、そして凄みが潜み。これが危険な任務を遂行する中で、少しずつ少しずつ、昇華されていき、その果てに到達する境地、表情にはとても胸迫るものを感じずにいられない。また、脇を固める俳優陣もそれぞれが素晴らしく、極めて味わい深いヒューマン・ドラマに仕上がっている。
西部開拓時代の終焉を描いた大傑作
1892年、インディアン戦争の英雄で退役間近のジョー・ブロッカー大尉(クリスチャン・ベール)は、収監しているシャイアン族の酋長とその家族をインディアン居留地があるモンタナへ護送する任務に就いた。
そう、かつての宿敵とニューメキシコからモンタナへ、まさにアメリカ🇺🇸を縦断する長い旅。タフな状況を協力し切り抜け、信頼が生まれた。
これより50年前の開拓時代前期を描いたケリー・ライカート監督の破格の傑作「ミークス・カットオフ」を思った。その50年を思った。
途中、一行に加わったのはコマンチ族に家族を虐殺されたロザリー(ロザムンド・パイク)。ジョーとロザリーの不器用な恋が出色だった。最高のラストシーンが生まれた。
アメリカの持っている良心が引き継がれている
1892年、退役を控えていた陸軍騎兵隊のジョー・ブロッカー大尉が、米国の南西部にあるニューメキシコから北西部にあるモンタナまで、インディアンの酋長と、その家族を送り届ける物語。美しい山野を背景にして、10人くらいの一行が、馬を駆って、野営しながら進む。さまざまな事件が起こり、その道筋は順調ではなかった。その頃には、米国中西部にも、鉄道の敷設が及びつつあり、一方、駅馬車の廃止が進んでいた、インディアン戦争の終結の頃。
一番驚いたこと、先住民であるインディアンに対し、謝罪の気持ちを持つ人が出てきて、女性に目立ったこと。べトナム戦争の後、南べトナムや近隣のカンボジアなどから、多数の難民が米国に辿り着いた時、上院議員の夫人などが提唱して中心となり、歓迎の式典が催されたことを思い出した。自分たちもまた、何代か前に米国に移住してきた祖先をもつことをよく自覚していたのだろう。その背景には、やはりキリスト教があるように思えてならなかった。「だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい」
ジョー大尉が、インディアンに対してやってきたことは、反対のことばかりだったけれど、最後は、そこにゆくのかと思った。今の米国も、かつての繁栄を支えていた自由と、後から来るものに対する恩恵を思い出してほしいものだ。
確かに、この映画のストーリー自体は、途中で誰が生き残るのかは読めるなど、物足りない点もあるが、私の全く知らなかったこの映画を選択してくれた方に感謝したい。緊張感を持ったストーリー展開が続くことは事実である。
長い長いミッションの果てに
クリスチャン・ベール扮する主人公ブロッカー大尉と個性的な部下たちとの関係性が丁寧に描かれており、作品に深みを与えています。
ブロッカーの盟友で、積年の過酷な軍勤務がもとで鬱を病んでしまったトミー。黒人のヘンリーとは人種の違いを超え、厚い相互信頼が存在します。さらに、かつての部下で一緒にインディアンを殺しまくった死刑囚のウィルスには、ブロッカーの今の変節を「見損なった」と非難されてしまいます。
一方でシャイアン族の首長イエロー・ホークとの関係性には、少し違和感を感じてしまいました。部下や友人達を殺され、地球上誰よりも憎んでいたはずなのに、護送途中の割と早い段階で共闘してしまうところなどです。和解すること自体は本作の主題なので問題ないのですが、そうであれば、前段の憎しみの深さをもう少し描いた方が、より説得力が増したのではないでしょうか。
ニューメキシコからコロラドを経てモンタナへと連なる中西部縦断の途中で、登場人物のほとんどが、憎しみの連鎖により死んでしまいます。
現代にも通底する憎しみの連鎖。ブロッカーの長い旅路の果てに生まれた贖罪の念と相互尊重は、これからの未来にも、生かされることはないのでしょうか。
ほとんど語らない主人公が格好良い
これは面白かったです。
中々に悲惨な西部劇。
家族や信頼する仲間が次々と失われていく展開。最後まで生き残るのは、主人公とヒロインだけという都合の良い展開ですが、そこに僅かな救いがありました。
ほとんど語らない主人公が、西島秀俊さんみたいで格好良いです。
徹底的に白人主観の視点で描かれてはいるのたけれど、だからこそ現代の排外主義についても考えさせられてしまうというアクロバティックな魅力があります。
テーマにストレートすぎて
30分で映画が終わってしまってる感じがした。30分ぐらいのところが一番感動した。あとは長~い蛇足みたいな感じがしたがラストシーンが良かったので良かった。フイルムで撮られているので写真がとても綺麗だった。 同じテーマのダンスウィズウルブス(1990)の方が良かった。
以下、映画が退屈だったのでうんちくを垂れてみることにした。
こういうタイプの映画は長い間作られなかったわけだが実はジョン・フォードが一本作っている。それは捜索者(1956)という映画だ。捜索者は一見すると一種の牧歌的な映画に見えるが実は違う。猟奇的にインディアンを殺す男の話だ。当時はそういう映画を作ることはタブーだったのだろう・・上手にミステリーチックに隠されていて分かる人にだけ分かるようにできていた。私がそこのところを解説しているのでよろしかったらどうぞ。
ちなみにこの映画の背景は1892年。歴史に詳しいわけではないが多分、南北戦争の20年後だ。1881年には OK 牧場でワイアットアープが悪党どもと戦った。それは「いとしのクレメンタイン(1946)」という素晴らしい映画になっている。その映画が撮られた頃はまだワイアットアープが生きていてジョン・フォードは直接取材したことがあるそうだ。ワイアットアープが決闘した頃、大草原の小さな家のローラインガルスは中学を卒業する年だった。彼女は3年ぐらい飛び級で学校の先生の資格を得た。あの一家がインディアンの襲撃を受けたかったのはただ運が良かっただけかもしれない・・多分そうなんだろう・・・
ほとんどのインディアンが死んだのは白人に鉄砲で撃たれたからではなくインフルエンザに感染したからだという情報がある。コロナで騒いでいる今の状況を見ると多分本当だったんじゃないかと思われる。
それにしてもコロンブスのアメリカ大陸発見は1500年頃のことだ。この映画の背景となった時代まで400年間も白人はインディアンを殺し続けてきたということになる・・・なんてこった・・・馬くらいくれてやらんかい。
永い言い訳
背景は侵略と抵抗と風化というアメリカ開拓史であるが、いわば人類史の縮図に過ぎず古今東西、人間の営みには血の臭いが付きまとっている。
冒頭から牧場一家の襲撃が描かれる、子供ばかりか赤ん坊まで殺される非道の描写、何の因果でこんな残虐な事件の目撃者にさせられるのか、本作を選んだ自身を悔やまずにはいられない。
クリント・イーストウッドの「アウトロー (1976)」も似たようなティストだったが本作よりは単純、目の前で家族を惨殺されれば復讐の鬼と化しても不思議はない、宿敵は北軍ゲリラの犯罪者だし銃が掟だったからまだ観ていられた。確かに復讐も戦闘も遂げてみれば訪れるのは虚無の闇、本作は先住民と侵略者の軋轢、勝者の視点、理屈で懺悔交じりに描いているが永い言い訳を聞かされているようで興醒めする。
邪鬼が人間に戻れるとしたら為すべきは償いの善行なのか、犠牲者の寛容や慈悲でもなく、ただ風化しかないのだろう。
確かに演者は熱演だし、タブー視されるテーマに挑んだことは評価を受けて当然だが生理的に合わない映画でした。
静かな物語
淡々と進み、とにかく静かにクリスチャン・ベールの物悲しい表情が印象的。かつては先住民との戦いで沢山の殺し合いをしてきたベールだが、その間も仲間を多く失う。敵であった酋長の死期が近く、故郷に護送することになり、当初は反対していたが、様々な敵からの襲撃を受けるうちに助け合うようになるが、その間も部下を亡くしていく。次第に戦うことの無情さ、過去への反省、先住民への思いが芽生え、変わっていく。全てベールの表情が物語り、ラストは、3人で暮らすのだろうか?ハッピーエンド。
クリスチャン・ベールに尽きる
某ラジオのインディアン特集で薦められていた一本。かつて散々にインディアンを殺したブロッカー大尉が、大統領令によりシャイアン族の酋長イエロー・ホークとその家族を彼らの故郷モンタナまで送り届ける物語。途中でコマンチ族に家族を虐殺された女性、脱走兵を拾いつつ、様々な困難に遭遇し、部隊は一人、また一人と欠けていく。
昔のアメリカ映画にあった、邪悪で未開なインディアンを、ヒーローのアメリカ人が成敗するという描写はそこにはない。ブロッカーの戦友トミーは、同じ人間を殺しているという悩みからうつ病に苦しむ。
主人公のブロッカーは矛盾を抱えた人間だ。インディアンには冷酷に接し、殺害は任務と割り切る。その一方で黒人の部下に対しては友情の涙を流す。インディアンへの対応の変化も唐突過ぎてよくわからない。おそらく、差別主義者ではないということを示したかったのだろうが、最後までよくわからない人物だった。
色々なことが起き続け、アップダウンの激しい映画だった。戦闘シーンの凄惨さは目を見張る。その中でクリスチャン・ベールの抑えた演技は常に碇の役割を果たしていた。彼の演技を観るだけでも一見の価値はある。
ご婦人に撃つ度胸があるかな
映画「荒野の誓い」(スコット・クーパー監督)から。
産業革命後の開拓地を舞台にしたアメリカの西部劇。
先住民のインディアンと開拓者との戦いが壮絶だったことは、
メモを見ないまでも、明らかで目を覆いたくなるけれど、
これもまた現実だと理解して観始めた。
同じインディアンでも、シャイアン族とコマンチ族は、
本当に違う戦い方をするのかもしれないな、と思いながらも、
あまり、メモする台詞は見つからなかった。
逆に、先住民インディアンの土地を、我が物顔で闊歩し、
「大統領令です」と指し示したにもかかわらず、
「ただの紙切れだ。たとえ大統領でも俺の土地には口を出させん。
ここは俺の土地だ」と言い張りインディアンを攻撃する白人。
それに怒りを覚えた主人公の女性が、彼に銃口を向けても、
なお「ご婦人に撃つ度胸があるかな」という態度で接した。
その傲慢な態度に終止符を打ったのは、
迷わず引き金を引いた白人女性、カッコ良かったなぁ。
「自業自得」って言葉が浮かんだ瞬間だった。
荒野で一緒に苦労を重ねてきて好きになるのはわかるけれど、
「どんな未来であれ、幸せを祈ってるわ」と別れたのに、
ラストのハッピーエンドは、ちょっとなぁ。
西部劇かと思ったら
明らかに悪い奴が出て来てバンバン打ち合う西部劇かと
思ったら、
クリスチャンベイルがそんな単純な映画に出るわけもなく、
序盤から「え?」の連続。
しかし勧善懲悪のないリアルなのかな。
正義もないし、悪もない。
みんな生きて行くのに必死与えられた仕事をしてるだけなのに続く負の連鎖は止まる事はなくラストを迎える。
ティモシーシャラメがこの物語の過酷さの象徴のように
なってて、いきなり度肝を抜かれた。
今もアメリカでは白人の警察官が黒人を射殺し問題に
なっている。その前は先住民。
同じ事を繰り返してるように思うし、
その動機は恐れのように感じました。
ラストに残ったのは戦争で先住民を殺しまくった大尉、
そして子供を殺された母親、家族を亡くした先住民が
一つになる。
負の連鎖の後の一つの小さなアメリカを示す、
監督からのメッセージかなと思いました。
戦争は何も解決しないし、何も生み出さない。
銃と病原菌と鉄で欧州人はアメリカの先住民を放逐した。
そして先住民の反撃は途方もなく残虐で過酷だったのだろう。そんな戦争の最前線で戦いを続けてきた騎兵隊大尉の退官間際の話。兵隊の仕事は敵を殺すこと。当たり前の話だ。しかし、殺し方にトラウマを抱えて苦しみながら生きていく方法が見つけられず死に時を探している。おまけに、時代の変遷期。個人の思考も変換せざるを得なくなる。果たして、彼は生き方を変えることができるか?
この映画のラストシーンは見事だ。
どんな人間もいかに多くの経験をし、その経験を積みあげても、それで自分を肯定したり、満足することなどできやしない。現在ある状態のなかで、自分の望ましい生き方をし、そのなかに意義をみいだしてゆく、そういうほかに生き方はない。
そんなことを教えてくれる映画だった。
全65件中、1~20件目を表示