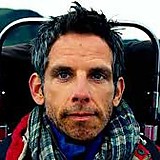志乃ちゃんは自分の名前が言えないのレビュー・感想・評価
全75件中、21~40件目を表示
良いが重い
たまたまNHKのBSで放送していたのを観ました。
番組表のあらすじで、文化祭に向けて頑張る青春ドラマかと思っていましたが、予想外に重い内容でした。
ストーリー自体は荒唐無稽なところもなく、地に足着いた等身大の高校生の生活が描かれていて好感を持てましたが、やはり障害の描写が痛々しく、何とも重苦しい気分になりました。
ラストも、結局は飛び入りでステージに上がってハッピーエンドになるのかと思っていましたが、そういう訳でもなく、辛い感じでした。
ウザい男子高校生役は、自分自身にもコンプレックスを持っているとはいえ本当にウザく、途中からイライラしました。
良い作品だとは思いましたが、自分には重過ぎました。
みんなハンディキャップはあるよ
志乃ちゃんは高校一年生、みんなの前では緊張してうまく喋ることが出来ず、ひとりぼっちだった。
同じクラスの加代ちゃんは音痴、いつも怒っているようで、ひとりぼっちだった。
こんな二人が友だちになり加代ちゃんとふたりでバンドを作ることに。
うまく行っているように見えたが、同じクラスの過剰コミュの男子が近づいてきて・・・。
みんなハンディキャップはあり、乗り越えるか、うまく付き合うしかないと思う。
主演2人が魅力的
特技と不特技
もうこの映画に関して言いたいことは一つ、南沙良の演技が素晴らしいということ。こんなにも志乃ちゃんを好演出来る役者は他に居ない。言葉が出てこない、焦りを覚える、悲しくて辛くて涙が出そうになる。胸が苦しくて仕方なく、感情移入どころの騒ぎじゃない。本当に凄かった。
蒔田彩珠も萩原利久もとてもいい演技。
2人にイライラしたりムカついたりもするし、心温まったりもする。キャラの落とし込みがお上手で、彼らがココ最近邦画に引っ張りだこな理由も分かります。「朝が来る」「左様なら今晩は」でもいい演技してたし。
シンプルなストーリー展開だが、志乃ちゃんの笑顔に思わず目に涙が溜まる。ちょっとした笑いも丁寧で、どうか幸せになってくれと母親かのように願っちゃう。ありがちだけど、選曲や優しい映像にグッときちゃいます。
Amazonプライムで配信終了間近だったため、鑑賞したのだけど、想像以上にいい作品でした。面白いとか楽しいとかいう映画じゃないんだけど、全員の演技がとても繊細で、笑顔や悲しみで心いっぱいになる映画。ぜひ。
志乃ちゃん(南沙良さん)の名演技に涙が出ました。
意味不明。
メイン3人が特に素晴らしかった
笑うなってったって
素敵な青春ではある
それぞれが抱える悩みがあって、それを忘れさせてくれたり、励ましてくれる友達がいて、歌というものがあって。
それは素敵な青春だと思う。
ただ、1本の作品としては個人的には面白くない。
もともと期待して観始めたわけではないけど、しのかよが盛り上がってきて、笑顔で何かをやり遂げた二人を思い浮かべてしまったから。
一度しのかよが壊れてからもギリギリまで笑顔のラストを期待してしまった。
志乃は自分の弱さを認め、付き合うことを決意する…というのが一人で勝手に完結していて腑に落ちない。
意図してこのような表現なのでしょうけど…
感動的なシーンを作れと言うわけでは無いが、この後のやり取りが無いというのはすごく気持ち悪い。スッキリしない。
成長するってこと
志乃ちゃんは自分の名前が言えない
よくある主人公がいったんはポジティブになったけど、何かがきっかけで絶望して、最後には結局ハッピーエンドという流れかと思ったけど最後が違った。
最後もう一回2人で歌うのかと。
このラストには驚き。見方によってはみんな1人ぼっちになったみたいな感じだけど、最後のありがとうを言った後の志乃の表情からは彼女たちの未来に対する希望を感じずにはいられない。
来年3人で文化祭で歌っている姿が容易に想像できる。
入学して時が経つにつれるクラス内の人間関係の変化がリアル。アイネクライネナハトムジークでも演じていた通り萩原利久は高校生役が似合う。
吃音という言葉を一切使用していないのも興味深い。
自分が恥ずかしがるのを恐れて逃げずに立ち向かう。
学校の周りや町の景色が綺麗すぎる。
涙と鼻水と青空
児童文学にまで引き上げる様な実写化アレンジ
後味の残る作品
どんどんわるくなる
いつもの日本映画なんだろうな、と思って見た。
が、抑制があった。
素朴な田舎の高校生である。
それを描写する映画も、お涙頂戴や承認欲求や岩井俊二風や、吃音に対する特別な問題提起を用いていない。
また、ここでの演技があがなわれることで、別のステージが拓けるアイドルが演じているわけでもない。
無欲で、ピュアな映画だと思った。
のは、菊池君の加入までである。
孤独が躁になって顕れてしまう奴はいるし、志乃が心を閉ざすきっかけとして、分かり易いが、あまりに過剰だった。
人と対峙したとき、感情をつかさどるのは、相手のデリカシーである。どもりがあろうとなかろうと。
すなわち彼が必要悪となり、そのオブセッションを乗り越える曲線が描かれるはずだった。ところが菊池君、あまりにけたたまし過ぎて、志乃だけでなく、観る者の感情をも著しく乱してしまうのである。そこで、雰囲気を崩したついでに文化祭の演劇風さらけ出しで、凡庸な映画になった。
実体験に基づく原作であることを顧慮したい気持ちが無いでは無いが、個人的には菊池君が強すぎた。文部科学省選定映画が関山であろうかと思う。
寂しげな志乃、クールな加代。海辺で、光りのおびただしい土地である。顔にあたる光彩がまばゆい。うつむいて泣いたとき、鼻水の条がきらきらと輝いた。かえすがえすも残念だった。
【”ずっと独りぼっちだったけれど、もう魔法はいらない・・” 葛藤しながらも自らのコンプレックスと向き合い、新たな一歩を踏み出す少年少女の姿が心に沁みいる作品。】
■今作の魅力
1.キャラクター設定の妙と演じる若き俳優さんたちの姿
・志乃(南沙良):人前に出ると、緊張のため吃音になってしまう高校一年生の少女。美しい唄声を持つ。
・加代(蒔田彩珠):音楽が大好きで、ギターを奏でる事で自分の居場所を保つ少女。少しだけ、音痴のため友達と距離を持つ。
・菊池(荻原利久):おバカキャラを出そうとするが、クラスの中で浮いてしまうちょっとイタイ男子。中学時代に苛められていたらしい・・。
という、様々なコンプレックスを抱えた高校一年生を演じる、南さん、蒔田さん、荻原さんの姿。取り分け南さんが演じる志乃の姿は沁みる。
白眉は、ラストに近いコンサートでの志乃の魂の叫びのシーンであろう。
又、ツンデレだが、心優しき加代を演じる蒔田さん。イタイキャラを演じる荻原さんの姿も印象的。この三人が奏でる演技のトライアングルが素晴らしいのである。
2.1970年代のフォークソングの使い方
・随所で奏でられる”あの素晴らしい愛をもう一度” ”翼をください”のメロディが醸し出す風合。
3.1990年代のJ-POPの使い方
・曲数は少ないが、”ザ・ブルーハーツ”、”ミッシェル・ガン・エレファント”と、上記フォークソングとの相乗効果。
4.盤石の”足立紳”の脚本
・3名の若手俳優の名演を引き出す安定の脚本。劇中の音楽の使い方も素晴らしい。
今作の素晴らしさは、足立紳の脚本と南沙良さんを筆頭とした若手俳優3名の方々の演技に依って成り立っていると言っても、過言ではないであろう。
<ある視点から、様々なコンプレックスを抱えた若者たちを描いた青春映画の秀作。改めて、足立紳の書く脚本の凄さを認識した作品でもある。>
<2018年9月 シネマテーク高崎にて鑑賞>
ー鑑賞当時、激しく心に沁み入ってしまい、とても恥ずかしい思いをした挙句、鑑賞記録を紛失・・。-
<2020年6月 別媒体にて再鑑賞>
南沙良さん凄い
全75件中、21~40件目を表示