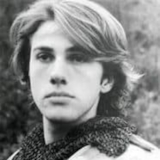フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法のレビュー・感想・評価
全182件中、41~60件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
子供達の瑞々しい演技
カラフルなフロリダの街
でも実情は貧しく問題を抱えて生きている人ばかりのマジックキャッスル
ヘイリーは子供を愛してるけど
それだけでは母親失格になる。
しかめ面のボビーは厳しくも愛情があり
最後はムーニーを預かるのかと期待したけれど
そこまで踏み込まないのがまたリアルでもある。
ラスト夢の国へと逃げるのはあまり好みではなかったけど全体的にはとても好きな作品
ポスターの印象とまるで違った
予備知識なしで鑑賞。
フロリダの安モーテルに暮らす貧しい人々。そこに住む6才の少女も当然育ちが良くない。眉をしかめざるを得ない悪鬼ぶりだが、しばらく見ていくとその逞しさが好ましく思えてくる。
彼女を取り巻く大人たちは表向きは厳しいようでみな優しい。モーテル支配人のウィレム・デフォーが実に良い。その距離感。
沢山の子供が出てくるが全く演技を感じさせない。普通にそこに居る感じ。これ重要だよね。
物語が進むにつれ厳しいドン詰まりな様相に。そしてラストシーン。これは観客への問いかけと受けとりました。どう捉えるかは各々で、と。重くも鮮やかさのある映画でした。
題名と表紙に騙されてはいけません
真夏の魔法?
夢の国と貧困
粋なおやっさん
大人が泣く時 わかるんだ
ムーニー、きみの言う通りでした。
この貧乏長屋の物語は、そのまんま落語の世界。店子と大家の泣き笑いの日々だね。
夢の国ディズニーワールドの門前町で、大人たちは生きるために闘い、子供たちもコミュニティを作って互いに支え合う。
チープな町にも虹は立つ。
やんちゃな子供たちの映画と言えばスウェーデンのラッセ・ハルストレムの十八番だけれど、今回のアメリカの「フロリダ・プロジェクト」はもっと大人寄りの哀しみのあふれるストーリーでした。
親たちの慈味あふれる眼差しの先にはち切れんばかりの子供たちのエネルギーが光ります。
親と子ががっつりタッグを組んでいるところは是枝監督に近いかも。
あと「泥の河」も久しぶりに見たくなりました。ムーニーがお風呂でゆっくりお人形を洗ってやるシーンで固まったし。
お母さん役は素人とか、信じられない演技ですね。娘を手放す覚悟をしてからの時間の過ごし方が迫真!
管理人のウィレム・デフォー、アカデミー助演ノミネートは納得です。
でもあの子たち・・
タトゥーとマリファナの匂いとテレビとジャンクフードにまみれて、子供のための絵本の一冊も無い。
一足飛びに大人になってしまうのだろうか?脱出した先も大人たちの虚構の夢の国「シンデレラ城」だった事がね・・、ラストは胸が痛くなってしまった。
一度も泣かなかったムーニー。
最後に泣いた顔はたった6歳の子供の顔だった。
打ち上げ花火、どこから見るか
鮮度が高い映画
鮮度が高い映画って感じがする。
ようするに、撮る側と見る側の途中過程が少なく、撮ってすぐ届けられたような、そんな印象。
映像的には現時点でいうと、退化する方向を選んでいるとも考えられるが、技術ではないところで美しさを表現できる、それを示した。こういう作風は増えるかもしれない。これまでも撮っている人はいたんだろうけど、映画作品として配給が認めるようになる、そんなターニングポイントになりそうな作品。
映り込む背景がとても魅力的。ストーリー的に人を追っているが、画は人を追っていない。その映像も新鮮に感じた。虹や倒木にシーンははっとする美しさがある。
て、シナリオ褒めてません。普通です。さらに、詰めれてません。
ただ、抜群のキャスティングと子供にこれだけの自由度を与えて撮る演出は見事です。
最後の数分の出来事だけで、涙が止まらなくなってしまった、まじか、魔法?
最後の数分前までは、詐欺宣伝の詐欺映画だと確信していた。
貧乏な母娘の、生でだらだらとした生活を、とめどなくスマホで撮影して。
売春、傷害、無銭飲食、窃盗、押し売り、その他もろもろ。
貧乏なのに、綺麗な服を着て、髪もいつも綺麗にセットして、肌もつやつや。
家賃も払えないのに、たばこや麻薬は切らすことがない。
それが、それがですよ、最後の数分に、児相に子供を取られそうになり、娘と友達が、まさかの、ディズニーランド逃避行。
その、行動よりも、子供たちの演技に、泣いてしまった。
それまで退屈で嫌悪感しかなかったのに。
たったの数分で印象が逆転した。
こんなことある、ないよね、魔法かな?
感動した、数分だけで、騙された?
でも、心地よい、鑑賞でした、ありがとうございました。
アメリカの是枝裕和
色々なコントラストがうまく表現されている皮肉映画
インスタやディズニーのようなカラフルで美しい映像、笑い合う母親と娘、嫌味なおじさんに子供同士のちょっとした冒険。
一見ポップで明るい内容だけど、少し触れば壊れてしまいそうな何とも言えない緊張感がずっと流れていた。役者が表現する優しさと厳しさの裏表、夢と現実の裏表が凄くうまく表現されている。
徐々に終わりに近づく生活の中で、母親はそれを分かりつつも娘のためにできることをしようとしていたと思う。それでもどうしようもなく訪れたラスト、カメラに向かって叫んだシーンは監督から世の中に対する悪態だろう。
おふざけや汚い言葉で自分を守っていた娘が親友に別れを言おうとするも、突き付けられた現実に初めて泣いてしまう姿を見て、思わず私も号泣してしまった。
最後のディズニーの城は、ディズニー映画のオープニングを最大限に皮肉っていると思う。映画が終わり、視聴者の夢のような世界が始まるのだ。
良い映画でした。
タンジェリンの監督×子供
あんなにもリアルな世界を生々しくも可笑しく描いたタンジェリンの監督が、子供を使って映画を撮るとこんなにファンタジックに見せかけることが出来るのか。
ただしそれは見せかけに過ぎなくて、嫌な影がちょいちょい姿を見せて…。大人には判るけど子供には理解できないその境界線が非常にうまく作られているなと思った。
ムーニーが一人お風呂に入るシーンとかね。子供が映っているシーンであんな嫌な見せ方するってすごいよね。
問題はラストシーン。オチを求めてしまっていた自分にとって、あれはどうなんだろうと思ってしまった。ただね…鑑賞後かんがえれば考えるほどあれでよかった気もするのね。あれって結局ムーニーの将来すら観客に考えさせていると思う。ムーニーは大人になったとき、きっとこの夏のことを思い出す。本当にたくさんの嫌なこともあったけど、それを塗り替えるくらいのマジックがあそこにはあったのかもね。見れなかった世界を見るってのは、人生経験上たいせつなことだしね。
この監督の凄さはさ、あまりにも"映画風じゃなく"描いているところだと思う。意識的なのかは不明だけど、起承転結とか、伏線とかわざとらしいストーリーとかが無くて、どっかの町の小さなニュースをずっと繋いでいる感じに見えるのね。でもそれが、大事な視点というか、ちゃんと現実ってことを観客に教えてくれてるんだよね。
ちと辛い
冒頭からちびっ子たちの下品なイタズラ。
その子が帰る家にはグータラな母のみ。
その母は友人のお店から食料を恵んでもらい、
家賃のお金はその場凌ぎの犯罪紛い。
これはひょっとして、こんな感じがずっと続くのか?と心配していたら、ホントにその通りだった。
常々「社会的弱者」への焦点を、偽善者ぶって声高に唱える自分ではあるが、今作での「社会的弱者」は生活困窮者。しかもいつも責任転嫁して反省しない学習能力ゼロな母親。正直言って自業自得、感情移入はゼロであった。
しかしその子どもには罪は無い。
(でも空家の件はマズイよな・・・)
それはボビーにも他のみんなにも分かってるし、観客も知っている。
ムーニーの視点で描かれる今作は、そんな罪の無い?子どもの何気ない日常であるが、それを見せられるにつけ、自分の親としてのスタンスの整合性を確認してしまう。
最低な母親ならば、子は反面教師で真っ当に生きていくのかもしれないが、ここでの母親は子にとっては最高な母親なのである。だから社会で直面する現実にも、子は反省する事を拒否してしまう。考える事を放棄してしまう。これは少なからず間違っている。
はたして、自分もムーニーの母親の様になってしまってはいないだろうか?
自分は子に、考える事を放棄させてはいないだろうか?
好きな映画ばかり勧めて、そればかり観てれば良いと押し付けてはいないだろうか?
モーテルで暮らす貧困層の現実含めて、反省を掻き立てられる辛い作品でした。
全182件中、41~60件目を表示