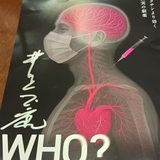台北暮色のレビュー・感想・評価
全20件を表示
よく覚えてない、が、覚えている必要なんてあるだろうか?
観た。すごくよかった。しかし時間が経ってみると、本当に断片しか思い出せない。街を歩くシーンにストーカーのような怖さがあったこと、ハシゴを持ってくるシーンが妙に微笑ましかったこと、ヒロインに動物的な若さがあふれていたこと、高速道路のラストにわけもなく多幸感を感じたこと。街そのものが主人公、というのは陳腐な表現だし、実際、この映画の主人公は街ではなく人だと思っている。でも、彼らの人生をドラマとして捉えることはなく、知り合いそうで知り合わなかった人たちの生活を垣間見ただけであり、でも、垣間見たことで、ほのかな希望が自分の人生にも宿ったような気にさせられる。あの高速道路の車のどこかに、自分も乗っていたかも知れない。その、一粒に過ぎないという感覚がとても心地いい映画だったと思う。あんまり覚えてないけども。いつかまた観たいと思うし、その記憶もさらさらと流れていくのだろうけども。
【大都会、台北で心に蟠りを持ちながら生きる男女3人の姿を軸に、3人と関わる人々の姿も絡めて描いた、趣ある作品。】
ー 台湾映画を観ると、何故か懐かしい気持ちになるのは私だけであろうか。人種的に親和性があるからかもしれない。-
■内容&感想
1.「ジョニーはそこにいますか?」という間違い電話を何度も受ける一人暮らしの女性シュー(リマ・ジタン)
彼女は、台中に元恋人がいるが、孤独に一人で買って来たインコと暮らしている。
2.軽いコミュニケーション障害を持つ少年、リー(ホァン・ユエン)。が、彼は心優しい。
3.車中生活を送る中年男性フォン(クー・ユールン)。が、彼も心優しいが、幼い時に両親が離婚し、その事が心の傷になっている。
□今作は、そんな3人の男女が出会い、お互いにコミュニケーションを取るようになり、距離を少しだけ縮める様を、抑制したトーンで描いている。
特に、フォンがシューが住むアパートを修理して上げた事で、二人の距離が縮まりシューが秘めていた哀しみを口にするシーン。
”7歳の娘が香港に居るの。””寂しくない?””電話で時々話すんだけど・・。”
そして、彼女は地下鉄の中で娘に”学校はどう?”と電話した後に、フォンのボロッチイ車に同乗するのである。高速道路の道でエンストしてしまうが、二人は力を合わせて車を脇に寄せようとするのである。
<今作は、大都会、台北で心に蟠りを持ちながら生きる男女3人の姿を軸に、3人と関わる人々の姿も描いた趣ある作品である。>
陰と陽
自分の歳を感じてしまう作品
ホウ・シャオシェンのアシスタントを務めたホアン・シーの監督デビュー作ということで、配信でたまたま見つけたので鑑賞しましたが、如何にもホウ・シャオシェンプロデュースという感じの作品でした。
本作の監督には申し訳ないのですが、私世代の映画好き人間はついついホウ・シャオシェンの名前を先に出したがるのは仕方ない事なのです。
80代前半までは日本ではまだ他のアジア圏の作品など殆ど紹介されていなかった時代にミニシアターブームが起こり、突如隣国の名作が続々と紹介された時の映画ファンの驚きはある意味カルチャーショックだったのです。
その時代に現れた特に若い監督達の中の筆頭格がホウ・シャオシェンであり、エドワード・ヤンであり、ウォン・カーワァイであり、その後も続々と若い才能が発掘されて行きました。
彼らは本作の様な種類の作品の言わばパイオニアなのでどうしても、彼らの時代の作品と比較してしまうのです。
彼らの作品の共通項として、国そのものが発展途上国から先進国へと移り変わる時代を生きた証人としての作品が殆どで、その中でもそれぞれの国に明確に先進国型の“大都会”というモノが生み出され、その中で生きて行く人間の生態を描いた作品が量産された訳です。
本作もその流れの中の一本となる訳ですが、時代はその頃から既に40年近く経ち今の大都会に生息する人間達の生態を描く場合、やはり当時と同じテーマでは難しく(それなりの変化を感じさせる作品ではありましたが)“今の時代”の表現というモノが弱い様な気もしました。
更に今のアジアにはホン・サンス監督の様な奇才もいるので、この手の作品を今現在も作るなら昔の手法ではもうワンオブゼムとなり埋もれてしまうのでしょうね。
しかしなあ、本作はワンオブゼムを描いている作品なのだから、それはそれでアリなのかなぁ~
ラストの余韻も実に良い
これで終わり?
最後に小鳥を飼っていた女性が、 車中泊を続ける男性と付き合うようになって良かった。ただそれだけの映画でした。
ただ、「人間関係はある程度の距離を保った方が良い関係になる」というようなセリフが、なぜか印象に残り、共感できた。
みんなひとりぼっち
アンストを起こすボロ車に乗っているフォンは.高校時代の恩師の家に家族同然に往来する。
その家の中では家族である人々がギスギス暮らしている。
インコを飼う女性も訳ありで台中にパトロンのような愛人がいるが実は香港に子どもとその父親がいる。
ポストイットに書かれた時間と用事を見るように見ないと忘れてしまうからと母親に諭される男子は兄を亡くしているのか、ポストイットを拒絶し新聞やラジオで人、家族、家に関わるような話を切り取り書き写している。異様におしゃれな部屋はお兄さんの部屋だったのかな。
フォンはいう、距離が近すぎると。
距離が近すぎると愛し方がわからなくなる、忘れてしまうと。フォンも両親が離婚し苦い母親の思い出。家を出てから帰ってない。
家族とか親族なんかである必要はなくて、それでも、ふと気づけば隣に誰かいたりまたいなくなったり、嫌でも家族だから一緒にいたり。
妻や息子や孫に不機嫌な父親と、インコを飼う女性の愛人は人を支配しようとあれこれ命令する。近すぎる距離、被害と加害を生む距離。
台湾の家族と家族以外が混じる食事のシーン。
車、地下鉄、雨、景色はいつもしっとりとして人に寄り添うようだ。台湾という土地の、良いイメージの通り。
ホオシャオシエン監督の後継というより、雰囲気はウォンカーウェイという感じの洗練されたおしゃれな映像でもあるが日本語タイトルになっている台湾暮色の通り台湾の湿度ある温もり冷たいけど温度がありひとりぼっちだけど完全にひとりではない感じ。
ジョニーに間違えてかかってくるジョニーと繋がる人たちもなんだか心強いではないか。みんなひとりぼっちだけどみんなそれなりにリーンオンできていたりする。
超絶薄い
タイトルなし
YA・O・I
高崎映画祭にて鑑賞。
ストーリーの2/3位以降で動き出す気配を見せての、でも結局何も起らない展開である。なのでこの手の作品が一番好き嫌いが分かれるのではないだろうか?自分がどうかというと、実は自分もよく分らないというのが実感である。決して嫌いではないのだが、しかし自分の読み解き力の貧弱さも又痛感させられるので、感情を上手く飲み込めず口の周りを汚してしまうイメージである。今作品が決して親切ではないことは充分理解したのだが、だからといって不思議と拒絶感は感じない。まるで環境映画のようなカテゴリなのかと思ったりしたのだがそれとも違うような・・・ だから、表題の『やおい』が一番しっくりしたのである。“ヤマなし 落ちなし 意味なし”と言えば、制作側が異議を唱えるだろうし、それなりに緩やかな展開はあるはあるのだが・・・
ヒロインがこれまたまるでモデルだし、そのパトロンである男の大胸筋等も含めて、今の台湾のセレヴ感がかなり強い。それに引っ張られる様に、この群像劇の他のパートもそれ程猥雑で不衛生な負の部分の台湾の影がみえてこない。本来ならばもっと多湿な気候がスクリーンに映し出す筈なのだが、まるで日本のようなイメージである。しかし、台湾の人達の家族主義的行動、占いや儀式を重んじるさりげないシーンや台詞、しかし、そんな古えの迷信と対比するような、近代化される街並、そして崩壊ギリギリの家族といった今の台湾の現状を丁寧に演出している点は興味深い。鳥と自分の境遇の親近感を抱きながら、急に後半ぶっ込んでくる子供がいる設定等、少々無理矢理感も否めないが、もう一人の主人公である内装業の男の『距離が近すぎると衝突する』という台詞は心に重くのし掛ってくる。車のエンストも、渋滞の中で起ってしまうことで衝突する危険が出てくる。しかし、ラスト、カメラがパンした先に、動き始めた車が通りすぎることで、ほんの少しだが希望を観客に抱かせるというニクい演出もクセモノの監督である。日常は何も変わらないし、益々苛立ちは募る。それでも希少な希望で人は前に進んでゆけるというメタファーなのであろう。
ちなみに、解説での間違い電話におけるジョニーの件は、ヒロインはそんなに気にしていないので、解説は間違いであり、故に原題もミスリードになってしまうから、邦題に変更したのは正解だと思う。“思慕”を抱きつつそれでも人は進んでいく、切ないながらの希望を表現した作品である。
心に残る映像
「恋する惑星」のストーリーを思い出せなくても、エスカレーターのシーンを思い浮かべない人はいないだろう。素晴らしい映画にはそういう記憶に残る名シーンが必ずあるものだが、この映画では高速道路のトンネルのシーンと歩道橋を走る二人のシーンの疾走感が強く印象に残った。まるで王菲(フェイ・ウォン)の主題歌が聞こえてきそうな感じだった。
侯孝賢(ホウシャオシェン)と楊徳昌(エドワード・ヤン)の遺伝子を引き継ぐ映画と紹介されているが、私は王家衛(ウォンカーワイ)の遺伝子もちょっと入っているような印象を受けた。
複雑に入り組んだ高速道路。どう交わっているのかよく分からない高架鉄道。それらの映像と同じように複雑きわまりない台北の街に生きる人々。彼らの日常を映画は淡々と描く。
複雑な街を生きる人たちの暮らしは複雑なピースでいっぱいだ。主人公の女性徐子淇(瑞瑪席丹リマ・ジタン)は小鳥たちと暮らしてている。1羽は逃げ、1羽は残った。そして彼女にはしょっちゅう間違い電話がかかってくる。「ジョニーはいますか?」(映画の原題にもなっている) もう一人の主人公張以風(柯宇綸クーユールン)の車は何度もエンストを起こす。コミュニケーションの苦手な少年(黃遠ホアンユエン)にはピースがいっぱいある。壁に貼られた多数のポストイット。新聞の切り抜き。水たまりと自転車。
徐々に彼らの現在の家庭環境や背景が明らかになっていくのだが、共通しているのは「離婚」や「別居」ということ。家族だと思っていた登場人物が他人であったり、他人だと思っていた人が家族だったりする。この3人の人生はちょっとした偶然から交わり合っていく。「距離が近づくと愛し方が分からなくなる」とうような台詞が出てくるが、この映画を象徴している台詞だと感じた。台北という都会で暮らす人たちの家族との微妙な距離感。それを維持できないのがこの3人だ。
切なく、もの悲しい孤独な魂の姿が、入り組んだ台北の街と雨音を背景に描かれる。ピースはたくさんあるけれども、私にはそれらのピースを組み立てることはできなかった。いや、作者はそれを望んでいないのかもしれない。そんなに簡単に組み立てられるほどこの映画に描かれている人生は単純ではない。深い哀しみと切なさの残る映画だ。
「台北暮色」(原題 「強尼·凱克」)
2017年 台湾映画 監督 黃熙(ホアンシー)
人は近すぎると、愛し方を忘れるものだよ
世間を見渡せば、何気ない日常を過ごしているように見える人たちであふれているが、それでいて誰しも、他人には知り得ない過去を抱えて生きているものだ。
ある家族のいさかいを目にした男は、女に、人は近すぎると衝突するんだと言った。そして、人は近すぎると愛し方を忘れるのだと。
直近にまさにそれと酷似した事案を抱えていた僕は、まるで自分に向けて言っているのか?とさえ思った。そのセリフがストンと僕の胸に着地し、歩道を駆けていく二人を眺めながら、はらりと涙がこぼれてきた。二人がただ走り、疲れて座り込み、意味なく笑いあう。それでなんで泣けてくるのだろう? しかも、涙を流している僕の感情は悲しさや寂しさではなく、二人の感情を共有できた満足があった。音楽のせいもあるだろう、女優の表情のせいもあるだろう、台北の景気のせいもあるだろう。そんな、スクリーンに映されている映像が、とても心地よかった。
薄い関わりしかない他人同士でも、近くにいるだけでその人の人生に関わっている。人は、ひとりじゃ生きていけないって本当だなあ、と優しく教えてもらえたようだった。
台北という街に抱かれる人々。
瞬間を繋いで生きる人々に寄り添う作品
台北の街に住む、男と女と少年とその周りの日常。ひたすらに日常。
停止した瞬間と瞬間を繋ぎ合わせ、過去も現在も未来もひっくるめてみんな生きている。
孤独さも表現されているけど、それよりも暖かく包み込むような優しい目線を感じてとても心地良く少し泣きそうになった。
3人の背景は微かに触れる程度しか語られない。
最初はそれぞれがどんな関係なのか、これからどう関わってくるのか全く予想がつかなかった。
少しずつ少しずつ紐解かれたり絡まったりする人間関係の模様や心の内を考えながら興味深く観ていた。
彼らの生活をそのまんま覗き見しているようなドキドキ感がありつつ、あまりに自然な空気にリラックスもできる。
好きなシーンがたくさんある。というか、好きなシーンと好きなカットしかない。
リーが何度も往復する大きな水たまりの水紋、インコと戯れるシュー、車の側で歯磨きするフォン、フォンとシューの奇妙でエモーショナルなドライブ、リーとシューのどっちつかずな会話、リーとフォンの「瞬間と動」に関する会話、などなど。
全部好き。全員好き。全編好き。
台北の今を切り取り、この瞬間を生きる全ての人達に寄り添う映画だと思った。
電車の中でLINEやメールや電話の着信音がさりげなくあちこちで鳴っているシーンがとても印象的。
この映画でメインに取り上げられず画面にすら出てこないモブの人達にも、それぞれの人の繋がりがあってコミュニケーションを取っているんだなと感じる。
電車内ではマナーモードにしてよ、なんて至極真っ当にツッコミ入れたりしつつ。
大量に走る車の一台一台の中にそれぞれのプライベート空間が広がっていて、それぞれのドラマが繰り広げられていること。
ただ歩いてる人も電車に乗ってる人も誰かと一緒にいる人も独りの人も、誰もが物語を持っていること。
当たり前のことだけど、スクリーンに映し出される数々のカットから身に沁みて感じられた。
自分の中で、映画を観た後のあるあるとして「街の様子がさっきと変わって見える」というものがあるんだけども。
この台北暮色の鑑賞後は街の見え方が強烈に変化していて驚いている。
目に入る全ての光景が劇場的に思えて、自分の視界をスクリーンに見立ててカメラワークのように視線を流してみたりして。
いつもはうるさくて煩わしい渋谷の喧騒がこんなにも面白く感じるようになるなんて。
日常感は強いけれど、いかにも映画的なシーンやキャストを含め全てのカットがお洒落でスタイリッシュなのでどこか非現実的な雰囲気もあるのが見ていて飽きない。
欧米や中東など遠くの国が舞台じゃないのも良いと思う。
台湾という日本からとても近い国、街の雰囲気も人間の見た目も日本と似ているけどきちんとした異国で。
インコが可愛すぎる。
観たい映画がないので観てみた。
観たい映画がなくて、制作にホウ・シャオシェンが関わっていて作品名が「台北暮色」。
小津安二郎の1957年の作品「東京暮色」のオマージュかなと思いきや、全く違っていた。
ホアン・シーという方の処女作であった。監督の初作品であった。ホウ・シャオシェンの助監督を務めていたという影響からか、画面の一つ々々が、一つのピースのようで美しかった。
この映画は、3人の若者を通しして今の台北に住む人々を現実を活写しているなと感じた。
最初と最後で、なぜか車がエンコする場面が出現するが、ラストの台北を行き交う車の無数の車のライトと台北の壮観な景色が雄大であった。話が十分理解出来ているか怪しいが、画面の美しさ圧倒されて、最初から最後まで飽きずの見られることが出来たのは、わたしには、充実した作品であり時間であった。
立ち止まること
全20件を表示