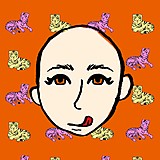静かなる情熱 エミリ・ディキンスンのレビュー・感想・評価
全13件を表示
詩が《詠み人知らず》になるまでの、必要な時間と忍耐
テレンス・デイヴィス監督作
「遠い声、静かな暮らし」に続けて鑑賞した。
屈折した家族の痛々しい歴史にこだわって、目を逸らさない監督の視点は、ここでも同じ。
・ ・
「作品の詩は素晴らしいけれど、作者にはずいぶんな問題があったんだよ」と、彼女の実態をつまびらかにしている内容でした。驚くべきことに。
「作者と作品は不可分一体なのか」という古からの命題が、ここには関わってきます。
昔から、作者の好ましいプロフィールや、逆に作者の不遇なエピソードなどというものは、残された作品の評価を安直 (チーフ)゚に高めさせる効果がありました。
つまり、嫌な言い方をご容赦頂きたいが、これは僕の事でもあるし、どなたにも身に覚えがある感覚だろうが、「その芸術作品」が⇒「女子供や老人や、夭折や不遇。またハンディキャップを負う作者によって作られていると」、勢い心象的には作品への評価とかシンパシー度がUPしてしまう件。
作品そのものへの評価が、何か別の同情的付加価値によって舞い上がってしまう、その反応。
しかし
この映画「静かなる情熱 エミリ・ディキンスン」は、そこを逆行させています。これは伝記映画としては挑戦的で 、なかなか興味深いと思った次第。
つまり簡単に言えば
この映画は「作品の詩は素晴らしいけれど作者はサイテーだったよ」と、彼女の実態を暴露している内容になっているからです。
たとえば「薬物事件」や、「差別発言」をしでかすと、そのアーティストへの幻滅と低評価が起こりますね。
ディオールのデザイナーだったジョン・ガリアーノの”あの事件”について、僕を含め、世の中は当惑し、混乱したばかりです。
・彼と彼の作品は同格なのか?
・デザイナーが駄目だと作品も駄目なのか?
・作者と作者の残した作品は同一不可分なのか?
と、デザイナーのガリアーノ氏との場合とか、シンガーソングライターのМ原 某氏との場合とか。
「作者がダメなら作品も、過去の作品も含めて発禁なのか?」という難しい問いが、この映画でも我々に投げ掛けられたと思います。
つまり
痛々しい詩人エミリ・ディキンスンの「人生」と「残された作品の価値」についても、等価交換が出来るのか。そこが問われるのです。
・この映画は作者についての神話を壊してしまう。
・この電気はエミリー・ディキンソンの作品の価値を高めるものではない。
・むしろ冷水を浴びせかけるものだったかも知れない。
・・・・・・・・・・・・・
草原を作るには、
蜂蜜とクローバーが必要だ
エミリ・ディキンスン
この《絶品のコピー》に出会ったのは、先日観た蒼井優主演の「蜂蜜とクローバー」の冒頭で でした。
この詩の、おちゃめな言い回し。そして独特の着目と鮮やかな発想。
詩の作者であるエミリ・ディキンスンに俄然興味がわき、今回の鑑賞となりました。
どんなにポエミーで愉快なお人柄なんだろうなァ♪と。
一家揃ってとにかく本をよく読み、
家族同士でいつの時にもディスカッションし、他者の語る言葉には傾聴し、自らの立ち場をそこに表明できるやり取り。
そうして家族との日常の会話の中から、自立する人間としての基礎を培われていったエミリ。
自由な発想と思索の深さ。そしてあの弁論術の巧みさと、返す問いの鋭さ・・
彼女のそういう所は、お父さんやエリザベスおばさんの影響なのでありましょう。
けれど劇中、たくさんの詩がエミリの台詞や独白として画面に流れます。
それはやや硬くて、
ポエムというよりはどこか格言のように響く彼女の詩は、冒頭の詩の断片のラブリーな雰囲気とは少し異なる感じでした。
総じて強硬で、どこか攻撃的で、裏返しな“否定的な言い回し”が多い。
映画のストーリーが進むにつれて、それは顕著になります。エミリーの人となりが僕の当初の想像とは違っていたので、僕は少々身を引いてしまいました。
「作家に対する死後の高評価なんてものは、生前その作家が無視されていた事の証左だ!」と吐き捨てるなど、彼女の病的な自己主張。
⇒「私を無視して苦しめているのはあんたらだ」と両親や兄妹を糾弾。
そして口を開けば辛辣な皮肉と毒舌は、機関銃のごとくに周囲の人々すべてに向けて浴びせかけられる。
妹エミリが兄オースティンに対して喰ってかかるあの一言も、なるほど、そうなのかと僕に思わせるものがあったが。
「兄さんも一週間女になってみれば判るわ」。なるほど。
でも、男である兄に対してのみならず、同性の=女性の妹に対しても、そして義妹に対しても、エミリの一切の言動は、破壊的で殺傷的で、前向きではなかった。
そんなエミリという壊れた人格が劇中で延々と暴露されていました。
彼女の臨終で幕を閉じる本作は、
エミリの伝記映画ではあるのですが、つまるところ、“資質的に相当の問題のある彼女を支えて、なんとか最後まで介護し通した一家=妹や兄やお父さんの物語”でもあったのだ、と思いますね。
生前はたった8編の作品しか残さなかったというエミリー・ディキンソン。
家に閉じこもり、死後に1800もの遺作が“発見”されたのだそうだ。
発表されるに相応しい徴 (トキ) を待って、世に求められ、世に芽吹いた遺作だったのかも知れません。
「原始、女は太陽であった」と檄を飛ばした平塚らいてうは、女たちをば味方と見た。
本作の主人公は、はねっ返りの女詩人エミリだから、感情を抑えられていた女性読者たちの心には地震のような感動を与えたのでありましょうが、
残念ながら生前の家庭人としての彼女は女たちを仲間とは見なしていない。すべての他者が彼女の敵であり、家族をも家族と思っていないのです。
だから、散々の苦労をさせてくれた彼女がやっとこの世を去り、家族はほうほうのてい。
長らくの時を要して、作者の陰険な声が徐々に薄れて、
やっと残された詩だけがその単体で浮かび上がってくるその日までは、
「1800の詩は封印されていたことが幸いした」と言えるかもしれない。
そうなんだろうと思えるのです。
つまり、死後発見された詩群といえばなんだか聞こえは良いが、
描かれてはいないが、エミリーに辟易としていた遺族は、彼女の死後、彼女を思い出したくなくって、死者の作品を (廃棄はせずとも) 封印し、うっちゃってあったんではないのかなと
映画を観ながら僕は想ったりしてしまうわけで。
そして時を経て、作者への幻滅を超えて、ようやく一周回って
「いい詩を書くひとだったね」と、彼女を知らない人々は、やっとそう思えるようになるのかも知れないのです。
・・・・・・・・・・・・・
To make a prairie it takes a clover and one bee,
One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do, If bees are few.
草原をつくるなら クローバーとミツバチを
クローバーひとつ ミツバチ1匹
そして夢想する
ミツバチが ぜんぜんいなくても
思い描く それだけで草原はつくられる
·
静かなフェミニスト映画
エミリ・ディキンスンについては、アメリカの女性詩人という知識しかないまま鑑賞した。女性が表現活動をしたり、家庭の外へ出て活動したりすることが制限されていた時代、どのような葛藤や困難があり、それに対処したのか。
彼女は学校でも家庭でも地域でも「反抗的」だとされ軋轢を生むが、それは自分なりの意見やポリシーがあるだけなのだ。封建的な家父長制の中では、従順でなければ「反抗的」とされる。
1800年代のアメリカは、とても保守的で、とくに女性にとっては、婚前は父親に従い、結婚後は夫に従うという窮屈な暮らしぶりだった。エミリが夜中に一人起きて詩作することについて、「誰にも迷惑をかけないから」と父親に許可を求めているのが印象的だった。
とはいえ、彼女が結婚しないで育った家庭に踏みとどまり続けたのは、魂の自由を守れるのは世界でそこだけだったからだ。当時としてはリベラルな父親で、奴隷制度に反対の立場だったし、家の使用人には尊厳を持って接するように(奴隷ではないのだから)と諭す。それに、彼女を理解し、慕ってくれる妹がいる。
エミリは今どきの言葉でいえば、「こじらせ女子」。
彼女に憧れ好意を寄せてくれる異性が現れても、ああでもないこうでもない、と言っては遠ざけてしまう。恋愛への憧れはある一方、愛を信じて傷つきたくないと臆病になってしまう。彼女が選んだのは、魂の自由を守り続け、ひそやかに1700篇以上もの詩作を続けた人生だった。
伝記映画としては良作
エミリ・ディキンソンは引きこもっていたため、自宅周辺での話が多いです(派手なエピソードがない)。
そのおかげで、伝記映画にありがちなエピソードの羅列に陥らず、本質的な部分に踏み込んだ作品になっていると思います。
歳を取るとともにどんどん頑なになって、周りとの関係がうまくいかなくなってくる。
しかし詩は冴えてくる。
自分の死までも見越した詩作には、何か時間を超越するスケールを感じました。
本作は細部までこだわっているようで、衣装・美術はもちろん、キャスティングも良く、台詞回しも凝っていたようです。
英語がわからないなりに、言葉に耳を傾けて楽しみました。
伝記映画としては、かなり良い方だと思います。
そして詩はやっぱり音で聴くのがいいですね。
詩人映画
苦手
認められなくても
私は詩人であり、私は詩を書く。
しかし、未明の詩作に父の許可を得たり、友人と弟のロマンスを許せなかったりするあたりには、時代の中に生きていた人を感じた。
南北戦争の頃の北東アメリカは、まさに清教徒の国だった。お茶さえ贅沢だからか、拒絶する牧師夫人の頑なさに、社会の狭すぎる了見を感じた。
エミリ・ディキンソンの詩は、魂の自由を静かに語るが、それを演技で見せるのは至難の技だ。
所々の詩の朗読が良かったが、彼女の手稿などもあればもっと興味を引く映画になったと思う。
伝記映画と割り切って
アメリカのある犯罪ドラマの冒頭とエンディングで、古今東西の有名人の言葉や詩が引用されるんですが、そこでエミリ・ディキンソンの詩を初めて聞いたとき、詩に興味のない私の心にディキンソンの詩の言葉がグッと入ってきて自分でもびっくりしたのがエミリ・ディキンソンとの出会い。「こんな詩を書く人ってどんな人なんだろう?」と思っていたのだが、映画を見て、内面はこんなに激しい人だったのね、と認識を新たにした。
映画を見る前に、彼女の詩を何編かでも読むことをお勧めします。ディキンソンの予備知識なしに見ると、いつも家族で口論しあって意外にうるさい(笑)シーンが多くて、映画のエンタテインメント性だけを期待していくと裏切られると思う。
容姿に自信がなく異性から疎まれるのではないかという恐怖感、心を許した親友が先に結婚して離れていくときの喪失感や自分を愛してくれた伴侶や叔父叔母や両親に先立たれた時の心にぽっかり穴が空いて立ち上がれないほどの喪失感など人生の様々な喪失感は誰でも覚えがあるだろう。その自分の喪失経験を映画に重ねながら見ると、共感できるシーンが多々あるかと思う。
ディキンソンが生きた時代は、今みたいに様々な生き方ハウツー本なんてなかったわけだし、キリスト教のガチガチの教義に基づく信仰しか道しるべはなかった。そんな中で、彼女が信仰に対してあえて反抗的にふるまったのは、彼女の悩みが信仰だけでは解決できないことを知っていたからであり、ガチガチ教義の支配下にあるような生活の中で、信仰に頼らず自分の内面から力を引き出そうともがいた結果があの詩の数々だということを映画を見て認識した。
映画は、あくまで伝記映画と割り切って見る方が良いでしょう。
現代の照明を使わず、当時と同じロウソクやランプの光のみで撮影された(ように見える)映像の美しさ、衣装や室内インテリアなどは一見の価値ありかと思います。
孤独な魂を支え続けた勇気
19世紀のアメリカは、まだまだ英国文化が色濃く残っており、話す言葉もアメリカンスラングではなく、クイーンズイングリッシュに近かったと考えられる。言葉は思想や情緒、風俗に大きな影響を及ぼす。従って当時のアメリカ人の価値観は英国式の古臭い道徳の範疇から逸脱することはなかっただろう。
本作品は、そんな窮屈な倫理観に凝り固まった社会にあって、断固として精神の自由を貫こうとした孤高の詩人の物語である。キリスト教の価値観から1ミリも抜け出すことのない周囲の人間たちとは、当然いさかいを起こすことになる。
金持ちの家に生まれたから働かないで一生詩を書いて暮らせたのか、それとも当時は女性が働くことはなかったのか、そのあたりは不明だが、経済的環境は恵まれていたようだ。しかし金持ちは現状の社会体制が継続するのを望むはずで、同時代の価値観を疑わない傾向にある。にもかかわらずエミリが時にはキリスト教の価値観さえも相対化してしまう自由な精神を維持しえたのは、おそらく幼いころに獲得したであろう自信と勇気の賜物である。
映画の冒頭から、シスターによって同調圧力に従うかどうかを試されるシーンがある。あたかも踏み絵のようだ。エミリは自分の真実の声に従って対応する。この行動のシーンにより、観客は主人公が若いころから勇気ある女性であったことがわかる。そしてその勇気が、詩人を一生支え続けることになる。
イギリスの詩人、W.H.オーデンは「小説家」という詩の中で、詩人について、次のように書いている。
『彼等は雷電のようにわれらを驚愕し、または夭折し、または長い孤独に生きのびる。(深瀬基寛 訳)』
若いころに女学校のシスターを驚愕せしめたエミリ・ディキンスンもまた、長い孤独に生きのびた詩人であった。
詩作の裏側
美しく、深い
静かな?情熱
全13件を表示