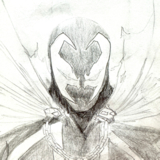ハクソー・リッジのレビュー・感想・評価
全420件中、181~200件目を表示
草食系向けプロパガンダ映画
造りは無骨で物語としても破綻はなく戦場シーンの描写も白眉である。
しかしながら人を殺したくない人々でも今の軍は歓迎するといった旨のプロパガンダ映画としか思えなかった。
主人公は非暴力、殺人のモットーを持ちながらも志願して軍に入隊するが規律を乱す厄介者であり、軍法会議にかけても親の力で逃れるような人物だ。
このように書くと単なる問題児のようだが本人の高い能力と信念、そして親の権力の全てを兼ね備えていることで主人公は活躍する。
上記の通り色々な条件が重なったことで主人公は活躍出来ているのだが非暴力主義でも活躍している様は非暴力主義の愛国者には響くことだろう。
銃を持たないと臆病者?
出すぎれば個性。
つくづくメル・ギブソンって凄い俳優&監督だと思ってしまう。
まさに映画的最終兵器(ないですこんな言葉)じゃないけど何度
も沈んで這い上がる運の強さが正にハクソー・リッジみたいだ。
偶然の産物か、またもガーフィールドが信仰心の厚い役を演じ、
これがまたよく嵌っている。ラストに本人の映像が出てくるが、
こんな人がいたとは…と驚くこと必至。だけど思うのは、もし
日本にもこの「良心的兵役拒否」が認められる制度があったなら
何人の息子が志願しただろう、家族がそれを願っただろうかと。
彼の信念は決して揺らがず、どんな虐めやリンチに遭おうとも
それを貫き通し、結果周囲がそこに動かされる。何度も断崖を
行き来し負傷兵を治療、救った行為は確かに素晴らしく尊いが
戦争そのものを批判することは決してなかった。そんなことが
言える時代ではなかったかもしれないが、やはり矛盾が生じる。
軍曹や大尉が何を言ってるんだ?コイツと思うのも無理はない。
昔ある本で読んだ一節に「出る杭は打たれるが、出すぎた杭は
個性とみなされる」というのがあった。読んだ時になるほど~
と思った行為をここで観た思いがする。そして演出がお見事だ。
前半のアットホームな恋愛劇から後半の肉片飛び散る戦場へと
一気に場面が変わって緊張が続いても、要所要所でドラマ性を
確立、どうして彼の演出は弱き者に優しいのかと涙が出る場面
も多く見受けられる。作り方が巧い。やっぱり最終兵器は彼だ。
なによりも…
観るのには覚悟が必要
人の命を奪うということに抵抗があるにもかかわらず、戦争を否定することはせず己の信仰心を貫き通し衛生兵として前線にたった男の話。
人と変わっているが、変わっていることを貫き通す。貫き通したことで男は英雄になった。
自分の信じるものは信じ続けろ、というメッセージを感じた。
戦闘シーンは壮絶で戦争ものをみると毎回思うがこれが人間がやってきたことなのか、と胸が痛くなるばかりか唖然としてしまうほどの迫力。
ハクソー・リッジから負傷兵を降ろし続け、助け続けるシーンでは涙が止まらなかった、、
気軽な気持ちでオススメはできないが、心に残るものはとても大きかったので是非観ていただきたい。
戦時下で貫いた信念の強さ。戦争の中で痛感させられる、命の尊さ。
【賛否両論チェック】
賛:“武器を持たずに負傷者を助ける”という信念を、どんなに虐げられても決して曲げなかった主人公が、極限状態の戦闘下の中で、多くの命を救っていく姿に、深い感動を与えられる。命の儚さや尊さを痛感させられるのも印象的。
否:戦闘による人体の損壊等、かなりリアルでグロテスクなシーンが多いので、苦手な人は観られない。
人を殺すことが当たり前の戦場にあって、己の信念を貫き通し、どんなに虐げられても武器を持つことを拒み続けて、負傷者を救うことに専念し続けた実在の主人公・デズモンド。師団が撤退し、敵だらけの孤立無援の中で独り奔走し、1人助けるともう1人、もう1人助けるとあと1人と、命ある限り歩みを止めないその姿には、敬意を越えて畏怖すら感じさせるような雰囲気すら漂います。
そんなデズモンドを最初こそ軽んじていた周りの戦友達が、次第にその信念の強さに気づかされ、敬服していく様子も、また感慨深いものがあります。
しかし同時に、人が人を殺す戦争の真の悲惨さも、かなりリアルな描写を通して描かれていきます。劇中で語られる、
「平時には息子が父を弔い、戦時には父が息子を弔う。」
という言葉が印象に残ります。
全く軽い気持ちでは観られませんが、命の尊さを思い知らされるような、そんな作品です。
単なる戦争映画ではない
第二次世界大戦で日本で唯一の地上戦があった沖縄で活躍したある米軍の衛生兵の話。実話なので最後に本人インタビューが出てくる。
最初は信仰と信念で銃を持たないで入隊する若者に邪魔者扱いしていたが、色々あっても最後は過酷な戦地で負傷した仲間を救う、勇気ある行動に感動する。戦闘シーンは本当に過激で過酷ですごい迫力。観て良かった。
涙腺崩壊
こんなに健気な英雄像は初めて見ました
これでもか、と迫力ある描写に引き込まれてあっという間に時間が過ぎていました。
もともと題材である沖縄線に興味があったので、前田高地戦の一部分しか描かれなかったのは少し残念ですが、一衛生兵の姿を追ったお話なので仕方ありませんね。
しかし、それを抜いても素晴らしい見るべき映画でした。
戦争という狂気の中、一人信念を貫き『あと一人だけ。。』と自らを奮い立たせる姿に涙しました。
軍対信念、狂気対信仰、対立してなお折れない精神の強さ。
時代や流れに身を任せるのが楽な中、自己を保つことがどれほどに過酷なのか考えさせられました。
魂が震えるってこういう事?
救出シーンが良かった!!
前半、特に恋愛部分が長すぎて、「ハクソー・リッジ」というタイトルに違和感を感じます。きっかけは父を撃とうとした事くらいで他は恋愛ばかりの印象で、人格形成の描写はいまいちだと思います。お父さんが准将をどう説得したかのシーンが省略されていてがっかりしました。沖縄戦で洞窟に逃げ込んだ民間人を大量に焼き殺した火炎放射器が登場して戦慄しました。日本兵には見えない網が気になりました。救出シーンは良かったです。時代ごとに異端とされる生き方はありますが、拘りがあるなら突き抜けて見せよというメッセージは感じました。
変人が人助けする物語
主人公の変人ぶりに大きな違和感を感じたが、最後に本人のインタビューが出てきて、納得がいった。
本当にこんな変人がいたんだ!というリアリティ。。。
変人がゆえに、あれだけの利他的な行為ができたともいえるし、あの利他的行為自体が変人そのものだといえるのであるが。。。
ああいった行為は、誰もがマネできるものではないから、勲章をもらったのだろう。誰にでもできるものではない、という意味でも変人であるが。
戦場の描写は凄まじく、血や内臓が飛び散り、兵士の死肉をドブネズミが漁るわけだが、それをもって「二度と戦争をしちゃだめだ!」「戦争反対!」「いのちの大切さを学びました、テヘッ」、、、などという脊髄反射は禁物である。
むしろ、戦場の血生臭さや戦闘開始数分でお亡くなりになる戦友、、、といった描写を疑似体験することそのものに意味がある。
善戦したかにみえる旧日本軍であるが、戦略立案、ウェポンの性能、兵力、物量において圧倒的に不利な状況のもと敗退していく。
我々、現代のニッポン人は、戦場のイメージと戦争に負けるというイメージのリンクに対する想像力をもっと養うべきだ。
軍事的に弱いと、映画での描写のような戦場で、圧倒的に「負ける」。それは一体どういうことか。。。日米地位協定の不平等を容認し、軍隊を持たないで平和を謳歌してきた戦後のわが国は、戦場で負けるということについての想像力があまりにも貧困になってしまっている。
本編の主人公のような変人(良い奴)は、ふだんもそんなにいないし、戦場ではもっといるわけがないだろう。だからこそ、映画にできる。。。
映画にできて、はじめてああいう戦場のシーンを描くことができるのである。戦場のイメージとそこで負けるイメージを人々に思い起こさせる装置として、変人が主人公に設定された、とも読めた。
リアル
オンとオフ
戦争の良し悪しではなく、人としての正しさを問いかける。
何処まで行っても熱心なクリスチャンであることに一切ブレがないメル・ギブソンらしく、この映画は戦争映画というよりもどちらかと言えば宗教映画・クリスチャン映画。メル・ギブソンにかかれば、戦争さえもクリスチャン映画になってしまう、と意地悪なことを思いつつも、けれども、「パッション」の時のように、敬虔なクリスチャンだけが理解できればいいというような向きではなく、クリスチャンの教えを改めて反芻して全人類にも問いかけ直しているというような感じで、戦争とキリスト教を通じて、人の正しい行い、より善い人の在り方を考えさせる、そんな映画だったように思う。
だから、この映画は戦争の勝ち負けなどは問題にしていないし、戦争そのものに対しても、軽はずみに好戦的とも反戦的とも言わない中立性を感じる。何しろ、ハクソー・リッジでの接近戦は、人を選ばずに一瞬にして次々に命を奪っていく戦争だ。その人の過去も家族も人柄も背景もすべてお構いなしに次々に殺されてしまう。もちろん敵も味方も関係なく、否応のない死が襲い掛かってくるような状況だ。思わずその無情さに心痛の思いがし、簡単に反戦の意をぶり返してしまいそうになるが、この映画の本当に信念は、ハクソー・リッジから撤退した後の主人公デズモンドの行動にこそある。「もう一人」「もう一人」と念じながら、敵も味方も関係なく救える命を命を懸けて救おうとする姿。戦争というものに於いて安易に「英雄」という言葉を使うのには大変慎重になるが、彼のとった行動は極めて英雄的であったと思うし、救われた人々にとって彼が英雄だったのは間違いないだろうと思う。口先だけの平和主義ではなく、それを行動に移せる強さであったり、その信念の誠実さを感じては、言い訳を作っては傍観しているだけの自分を顧みてしまった。アンドリュー・ガーフィールドの繊細で純真な佇まいと演技がまた素晴らしく、真っ黒になりながら人を救うガーフィールドの健気さと勇敢さに、なんだか目頭が熱くなりそうだった。これは実在の人物の物語だという。彼の生きざまは、今の時代に問いかけ直す意義のあるものだと思う。
メル・ギブソンの人となりについては、語られるいくつかの逸話や舌禍を思い出して何とも言いにくいが、やっぱり映画監督としての才能は認めざるを得ない。ナイーブな青年の心理描写から後半の残虐なまでの戦地の描写まで、とんでもない力量を感じて感嘆するばかり。その上で、とっつきにくそうな題材に一つまみの娯楽性も落とし込んでいるように思え、戦争映画に不慣れな人でも見られるのではないかと思う。まぁ、さすがに観るのが辛くなるようなシーンも少なくない(特に前線のシーン)ので、体調を整えてから鑑賞することを薦めたいとは思うが。
本当は☆5でも良かったが、やっぱりメル・ギブソンの宗教臭の強さが気になって☆4.5で。
きれいな二部構成でどちらの部も素晴らしい
前半はドラマ部で信仰心、家族、恋人、軍での訓練生活を軸に主人公を多角的に描きとり、最後の法廷劇で全てを一つにまとめあげるという信じらないくらいの完成度で前半だけで一本の映画を観た気持ちになれる。役者の演技もとてもよい。
後半は一気にプライベート・ライアンかスターシップ・トゥルーパーズばりの残酷描写で、前半で作り上げた主人公の人格・信念を揺さぶる。それでも自分を貫き通し、偉業を成し遂げた主人公。音響もすごいので映画館で見るべき価値のある映画である。
あくまで主人公の世界を描いたまさしく映画的な作品であり、戦争の真実を描く系の歴史考証ばっちりで誰に対してもフェアな視点を貫く類いの映画ではない。
主人公と一緒に悩み、悔やみ、恋をし、仲間と衝突し、家族を知り、愛を知り、自分を信じ、成長する。そんな映画だと思うし、私はそんな映画が好きだ。
全420件中、181~200件目を表示