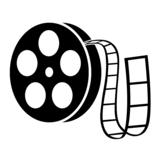ティエリー・トグルドーの憂鬱のレビュー・感想・評価
全21件中、1~20件目を表示
他人を蹴落とすことでしか自分の生き場所を確保できない残酷
昨日のヤフーニュースは、
コンビニのレジのバイト君が、お客のレシートのポイントを自分のスマホに横流ししていて摘発された、というものだった。
不正を防止するためにレジ機能は改良されたらしい。
そのニュースを見て、
フランス映画
「ティエリー・トグルドーの憂鬱」を思い出した。
スーパーの警備員トグルドーが、レジのパートのおばさんの[レシート持ち帰り]の不正を見破って上司に報告する話。
そのパートのおばさんは追い詰められて自殺 してしまう。辛い映画だった。
警備員もパートもぎりぎりの生活だ。なんとかその職で食いつないでいる。
なけなしの、(お客が捨てた)レシートで小銭を得ていた貧しいパート店員の悲劇。
そして彼女を摘発しないと自分もやっとのことで得たその職も、そして住居さえも失なってしまう警備員・・・
集められたパート店員たちの表情が暗い。
余裕が無さすぎるこの世の現実。どうすればよいのだ。
・・・・・・・・・・・
我社でも、創業以来初のリストラがあった。
息も絶え絶えに、解雇・賃金引き下げの“脅迫”を切り抜けた頃に観た映画だ。
うちの部所だけ助かりたい。
よその部所だけにして欲しい、リストラは。
誰かがヘマしてコケてくれるのを期待する。
自分だけは助かりたい。
― 本当に僕はそう思ったんだ。
観てから今日までレビュー出来なかったのはそういう理由だったと、思い出した。
弱者に鞭打つ社会の責任、なんですかね
憂鬱な映画
壮年になって解雇された人の就職活動やら
就職先の描写を通して、フランスの貧困などを描いた映画、と思われる。
しかしテーマがどうでもよいほどに退屈。
万引きGメンの仕事シーンを延々と30分も映すシーンに象徴されるが
1つの描写にかける時間が長すぎる。
強く伝えたいから長時間映すのか知らないが、
だらだらと似たようなシーンを見せ続けなければ伝えられない時点で問題外。
憂鬱を画で表現することと、鑑賞者を憂鬱(退屈)にさせることは違うと思う。
内容はシンプルですが・・
さも分別のありそうな、何もできないオッサンの話。
去年観た「サンドラの週末」もそうだったが、貧困、失業をテーマにしたフランス映画は、やけに気が滅入る。
主人公ティエリーに、職探しに頑張ろう!という気分はなく、覇気もない。見ているこっちまで暗くなる。さも自分は善人だというような意識を持っているようだが、何もやれない何もできないだけじゃないか。自分の今の境遇は自分が今まで生きてきた結果だということをわかっていない。そういうのを相手にしている職安の職員さんにこそ同情してしまう。最後なんて、自分は人を人として見ることができないところでは働かない、と大見えを切ったように見えるけど、何も言えない奴が職場放棄しただけの話でしょう?
おまけに、不正をしても白々しく自分の正当性をごり押ししてくるパートのおばさんなど、僕の嫌いな人種だ。
こんな映画を100万人も観たというフランスの社会全体が現代病に病んでいるのだ強く感じた。
文明国が直面する諸問題
現在、もはやどの文明国も大きな成長を望めない段階にきている。右肩上がりは20世紀でほぼ終了し、下り坂の時代になったのだ。そこにグローバル化の波が押し寄せ、人も金も物も国境を越えて自由に行き来するものだから、国家という枠組みでは制御しきれない状態になった。そこで20世紀の後半から、各国政府の代表はサミットだとか、G20だとかで問題の解決を図ろうとしてきた。しかし発案者の意図とは違って、各国の政治家は旧態のままで相変わらず自国の利益優先だ。だから何度会議をやってもグローバル化による問題は解決せず、世界はいつまでも安定しない。それは取りも直さず各国の国民が世界の安定よりも自分の利益を優先していることに等しい。
主人公トグルドーもそんなグローバル化と下り坂の影響で生活に支障をきたしているが、腐らずに淡々と向き合おうとする。だが他人の小さな悪事に目を凝らす仕事に鬱々とする日々が続く。
フランスはさすがに哲学の国だ。救いようがない状況をそのまま描く。そして安易な希望は抱かない。映画は見ている時間だけではなく見終わってからも何日も何か月も余韻が残り、主人公の後ろ姿がいつまでも目に浮かぶ。
邦題「ティエリー・トグルドーの憂鬱」は、安直でお手軽な発想ではあるが、この映画に限っては邦題として秀逸である。原題の「La loi du marche」は無理に和訳すると「市場の法律」みたいになる。巨大スーパーの警備係の苦労話に矮小化しているみたいで、映画のタイトルとしては珍しく邦題の方が優れていると思う。
イギリスの詩人Wystan Audenの作品「THE NOVELIST」に次の一節がある。
For, to achieve his lightest wish, he must
Become the whole of boredom, subject to
Vulgar complaints like love,
どんなに軽い望みを達するためにも
小説家は憂世の倦怠の全量に化さねばならぬ、
恋みたいな凡俗の嘆きにも身をかがめ、
(深瀬基寛訳)
友人や同僚たちの悩み、家族の不幸を背負ったトグルドーのやりきれない背中を見るだけでも価値がある映画だ。
リアリティ
過剰な期待は禁物
普通とは言い難いけれども、この世の中に確実に存在するであろう憂いを、ひとりのフランス人が代弁しているといった印象の映画。
敢えて不自然なカメラ目線で出来事が捉えられ、それが非常に効果的であり、リアリティーをもってこちら側に迫ってくる。
普段、自分たちがやり過ごしている憂い、抱えている憂い、耐えられなくなっている憂い等々、すべてをトグルドー目線で見せてくれている。
淡々と嫌な事柄が並べられ、劇的なことが起こらないまま終わる。そのことを頭に入れて観賞しないと、過剰な期待をする恐れがあるかもしれない。自分もその一人であり、ああこれで終わるのね…といった思い。
内容は優れているんでしょう、たぶん。いかにもフランス映画(?)といった感じで、憂鬱という感情を描き出すための構築が重厚です。しかも政治問題みたいなものも絡ませて、非常に知的であり、哲学者が題材として取り上げるにふさわしい映画(だと勝手に思いました)。
結末の捉え方も人それぞれに委ねられているし、一生懸命思考しながら映画を見る人にとっては、たまらない作品(なのだろうか…)。
観賞中、後方からバリバリ菓子を食う喧しい音が聞こえてきたが、そういったものとは相容れない作品。ものを食いながら映画を見たいという人は、決して見ないでください。
憂鬱な世界を覚悟を持って生きていこう
勤めていた会社をリストラで追われた男が、再就職の為のセミナーや職業訓練を受ける。役所の担当者が勧める職業訓練は再就職の役には立たず、セミナーでは他の受講生たちに模擬面接での様子を酷評される。
同じ中年労働者としては、見ていてひりひりするほどに辛い情景である。自分も同じ境遇になれば、これと同じ辛酸を舐めることになるであろうことは想像に難くない。
サービス業志望でもないのに、面接中の笑顔や声の明るさなどをとやかく言われるシーンは居たたまれない。観ているこちらがカメラが早く次のカットに移ることを願わずにはいられないほど。人生の過去や背景などには全く興味を示されず、現在の標準とされる求職者像を求められてじっと我慢をする主人公の姿からカメラはなかなか目を逸らさない。それは、主人公の閉塞した心理を表現するというよりも、そんな彼の姿を観客に見つめさせるための長廻しに思える。
後半になってスーパーマーケットの警備係になった主人公は、今度は今までの自分のような境遇の人々を追い詰める立場へと入れ替わる。
同業者である私のモラルからすれば、ポイントカードや割引券の不正行為は立派な詐欺である。だから、不正を犯したレジ係が退職に追い込まれることは当たり前のことだと思う。
しかし、その被害金額の些細なことに比べれば、彼女たちレジ係の生活が破壊される結果はあまりに重大である。
安心して生活を送れる立場にいるということが、常に不安定な状態の人々を生み出している。これが市場の原理であり、我々の生きている世界の現実なのである。
その薄ら寒い現実をどんな形であれ生き抜くためには、何かしかの覚悟を持たなければならない。主人公の乗った車のテールライトが消えていくラストシーンにそんなことを思った。
市場の原理
原題、La loi du marché「市場の法則、原理」。
—
長年勤めてきた会社を首になり、心が裂けてしまった主人公ティエリー。会社を訴える気力も残っていない。それでも、再就職するための研修や面接を必死で受けている。
そこで出会う人々。
「ローンを返せないのだったら家を売るしかないですね」と言う銀行マン。
「あなたを採用する見込みはかなり低いですよ」と言う面接官。
彼らは悪くない。仕事として当たり前の事を言ってるだけだ。
ティエリーの半生を費やしたキャリアや家への思いは、そこでは全く考慮されない。そんな個人的な心情よりも、ローンを返す方が先決だし、会社の効率を考えたら若い人を雇った方が良い。市場の合理化に照らしあわせてみれば何ら間違ったことではない。
ティエリーは断腸の思いでトレーラーハウスを売ろうとする。彼にとっては大切な思い出を売る辛い決断で少しでも高く買ってもらいたい。それでも買手は値切ろうとする。当たり前のことだ。安く買えた方が良い。個人の心情など、損得の前ではどうでも良いことだ。
市場の法則の前では、個々の人間性など無視されてもしょうがない事なのかもしれない。それをどうこう言うべきことではないのかもしれない。
—
ようやく再就職が決まったティエリー。
スーパーの警備員。客の万引防止だけでなく、従業員の不正も監視する。人手が余って効率が悪いスーパーは従業員をカットしたい、その口実を見つけるのが仕事だ。ティエリーは市場の法則を行使する側にまわる。
経営側が悪い訳ではない。厳しい市場競争を勝ち抜くためには合理化を進めていった方が良い。それが市場の法則だ。しかも辞めさせる従業員は些細な事とはいえ不正をした者だ。それの何が悪い。
解雇された従業員は店内で自死する。それでも店側は新たな解雇者を見つけ続ける。
—
市場の原理の前では、何ら間違っていない当たり前のことなのかもしれない。それを受け入れなくては、やっていけないのかもしれない。
だが、最後、ティエリーはある決断をする。
市場の原理よりも、本当はもっと大切なことがあるでしょうと、声にならない声をあげる。
ティエリー1人が決断しても、世の中を変える力がある訳ではない。結果的には、またティエリーが負け犬の側にまわるだけだ。現実的には甘くバカな決断だ。それでも、この世の原理に歯向かわずにはおられない。踏みつけにされてきて、もう立ち上がる気力もないように見えた男が最後、静かに立ち上がる。
静かな、アウトサイダーな、ヒーロー。ティエリーという男が、私にはそう見えた。
—
静かな男を支える家族の描写もいい。辛い状況にあっても、ヘタクソだがダンスを楽しんだり、高校生の息子さんは生物の専門学校を目指していたり(フランスの教育課程を考えたらものすごく優秀な子だ)、頑張って前に進もうとしている。
この家族なら、経済の効率性より人間性を選んだお父さんをこれからも支えてくれるのではないかと、そんな気もする。
—————
映画は、まるでティエリーを追うドキュメンタリーといった体で撮られている。
ほぼどのシーンにもティエリーが映っている。目線の高さのバストショットが多い。(例外は見下ろす角度で撮られた防犯カメラの映像。)
ティエリーを追った映像が炙り出したのは、「ティエリー個人の憂鬱」というりも、社会全体の問題なんだと思う。
そしてそれは、見下ろす角度からは撮れない、人の目線でしか捉えられない事象なんだろうとも思う。
社会派映画。
憂鬱
観ている側も憂鬱になるほどの生きにくさ
51歳のエンジニア、ティエリー・トグルドー(ヴァンサン・ランドン)は働いていた工場が閉鎖されて失業して1年半になる。
職業安定所の紹介によりクレーン操縦士の資格を得たが、就職の目途はない。
彼には、パートで働く妻と、専門校への進学を目指す障害を抱えた息子がおり、まもなく失業手当が減額されてしまうから、生活は一層厳しくなる。
そんな中、ようやく得た職場はスーパーマーケットの監視員。
万引き客の摘発だけでなく、同僚の不正行為も摘発しなくてはならず、徐々に憂鬱さは増していく・・・
といったハナシを、ドキュメンタリータッチで描いていきます。
スーパーの現場で彼が目にするものは、愉快犯的な客の万引きや生活に窮した老人の万引き、レジ係のクーポン券のネコババやポイントの不正取得など。
事件の規模からすれば、かなり小さなもの。
しかし、原題「LA LOI DU MARCHE」(スーパーマーケットの規則)どおり、それらは小さいけれど、みな許されるべきものではない。
ただ、ティエリーからみれば、困窮した者のちょっとした出来心からの行為は、お目こぼしがあったもいいんじゃないか、とも思う。
規則規則で、人間の心が削られていると感じている。
そういう「生きにくさ」「生きづらさ」をひしひしと感じる映画である。
であるが、映画としては傑作・佳作とは言いづらい。
思うに、事実は写し取っているが、「映画的な真実(決定的な瞬間)」が欠けているように感じる。
同じように、社会の生きにくさ・生きづらさを描く監督にダルデンヌ兄弟がいるが、彼らが撮る映画には、主人公の決定的に輝く瞬間・転機の瞬間が描かれている。
この映画でも最後の最後、ティエリーはある種の決断をするのだが、その決断の内容は明らかでなく、観客にゆだねられている。
ゆだねられているが故に「いい映画」になる場合もあるが、この映画では、ひたすら憂鬱になるだけだ。
まぁ、それは観ている側のわたしが、ティエリーの決断行為を前向きにとらえていないからなのだけれど。
とはいえ、あまり憂鬱な気分なまま劇場を出るのは、あまりいただけない。
憂鬱になったのはこっちの方だった。 何がいいたかったの? 障害のあ...
仕事
全21件中、1~20件目を表示