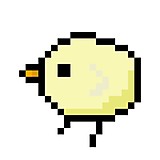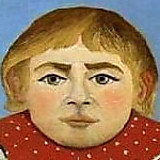イレブン・ミニッツのレビュー・感想・評価
全55件中、41~55件目を表示
登場人物が全員不快
一つの出来事も視点を変えればドラマになる
特に設定等の説明もなく始まり、最初は時系列を整理するのが難しい。
時系列を整理したのに、また同じシーンが出てきたり、たまに見ていてストレスがかかる。
ラストシーンは「えーーそうなるのーーー」と思ったものの一瞬。
小さな出来事でも、その事が起きる前後のドラマは全員にある。
個人的には「あの点」が最後ああなったのは、こんな出来事も世界からしたらニヤッとしてしまった。
観終わった後に、一人一人の流れを11分通しで観たくもなりました。
根源となったあの夫婦の流れは特に。
地響きのような音響の使い方。
不穏な空気を肌で感じる。定番の手法だけども煽り上手。煽りすぎ感もあった。
ラストシーンを見て、「低空飛行の飛行機は日常の風景だったのか」とビックリした。
墜落するのかと思っていました。
【エンドロール】
とてもいい!
音楽は一切なく、小鳥のさえずりや車の音などの生活音の中、フォントも凝ってる。
11分の出来事を81分かけて観たことで、若干疲れた脳がいい意味で安らぐ。
この映画でエンドロールが一番好きだった。
狙いすぎたか
登場人物の全員が俗物であり類型的である。だから誰にも感情移入できない。人物が映画に登場するためには、多かれ少なかれ、理由が必要だ。典型に対する類型、正義に対する悪、または特別な生い立ちや体験など、映画のシチュエーションに合った人物でなければならない。
しかしこの映画では、そこら辺にいそうな俗物たちが、それぞれの小さな欲望のために利己的に動くだけだ。並列的に描かれるので、誰を中心に見ればいいのかわからず、注意が散漫になってしまう。簡単に言えば退屈ということだ。
ラストシーンも期待外れで、この映画を作った意図が理解できない。偶然の事故に巻き込まれる話なら、震災の被害者を取材した短いドキュメンタリーの方が、まだ状況を理解できるし、同情も共感もできる。
ピタゴラススイッチ
一生懸命作った人には申し訳ないけど、なんでこんな映画をわざわざ有楽...
期待は大きかったが...。
ミクロとマクロ
無関係な筈の11人、それぞれの11分間を描く。11人いれば11通りの時間の流れがある。
これ自体は手垢のついた手法なのかもしれない。だけども、何故かスリリング。
衝撃のラスト。陳腐すぎて、ええッ?こんなオチで良いの?という衝撃でもある。陳腐なんだけど、何故かウワっともっていかれる。
言葉で説明しだすと、まどろっこしくて意味のない映画。小説では絶対この感じは出せない、映画だからこそ成立する。すごく面白かった。
—
一人の男ヘルマンが街を歩いている。街には騒音があふれている。
犬の鳴き声、救急車のサイレン、屋台の物売りの声。ヘルマンには関係ないノイズ。犬も救急車もその時は画面に出てこない。街のありきたりな音。
その後のシーンで、犬の飼い主や救急隊員のエピソードとなる。単なるノイズの先にあるもの。
だから、ちょっとした音が聞こえても、これも何かあるのではないかと身構えてしまう。単なるノイズが厚みを持ってくる。音が重層的だった。
まるで落ちそうなくらい建物ギリギリに飛ぶ飛行機の音、水に落ちる音、ガラスの割れる音、高圧洗浄機のシューっという音…。日常的なノイズを敢えて誇張していて面白い。
—
妻の居るホテルの部屋を窺う男ヘルマン、ホットドック売りを遠くから窺う女(ポスターのように街並に同化していて後から人だと気付く)、河を眺める日曜画家など、何かを「見ている」登場人物が多い。だが、彼らも誰かから「見られている」。
ホテルでのヘルマンはあまりに不審で客やホテルマンから「何この人?」という感じで、視線を向けられている。
「見ている」と「見られている」の混在(同じ時間帯を11通り示すことでそれは誇張されている)。
空に浮かぶ黒い粒を見上げる者と、
黒い粒の視点から見下ろす者(モニターの羅列でそれは示される)。
「見ている」と「見られている」を行き来するダイナミズム。
仰視(見上げる者)と俯瞰(見下ろす者)が交差するカタルシス。
—
この映画を観ていると、人や建物が粒みたいに小さく映っている航空写真を思い出す。
粒にクローズアップしていくと、そこに人が居てそれぞれの生活があって、単なる粒ではなく別個の時間が流れている。100万人いれば100万通りの時間の流れがある。
その100万通りの人・時間を限りなくズームアウトしていくと、単なる粒になってしまう。
ミクロとマクロを行き来する。緻密で大胆な映画だったと思う。
—
追:こういう映画のオチに意味を求めて陳腐とか言ったりする方が陳腐だなあ。
ピースは埋まったが、ピースは埋まらない
ポーランド(かどこか)の都会、午後5時。
教会の鐘が五つ鳴り響く。
映画のオーディションに、監督の待つホテルの部屋を訪れる女。
嫉妬深い彼女の夫は、彼女の後をつける。
ホテル近くの道端でホットドッグを売っている、刑務所から出所したばかりの男。
4人の尼僧が残りわずかのホットドッグを買い、そののち、犬を連れた若い女が残りの二つを買う。
人妻と情事に耽っていた配達員の青年は、5時の鐘とともに慌てて飛び出し、荷物の配達に向かう・・・
と一見関係なさそうな男女十数人が、最終的に、ある悲惨なアクシデントにより一堂に会してしまうといったハナシは、まぁ、これまで幾度となく見てきたハナシ。
この手のハナシだと、並行して描かれる男女のハナシに面白み(個人的な面白み)がないと、かなり退屈してしまうが、残念ながら退屈してしまった。
出てくる男も女も、ほとんど共感を抱けないし、なんだか買ってしておくれ、みたい。
なので、その手の、いわゆる「群像サスペンス」としては、いまひとつ。
なんだけれども、どことなく、脳裏に(まさしく、脳の裏側あたりに)漠然とした不安のようなものが貼りついてしまって剥がれない。
その不安の元となるものが、映画では直接描かれないから、少々やっかい。
そいつは、登場人物の何人かが目撃する「空中の黒い点」である。
「空中の黒い点」って、なんとも不条理な・・・
これが、M・ナイト・シャマラン監督だったら、「あれは宇宙船、もしくは未来からやってきた飛行船。普通は見えないが、見えると災厄をもたらすものだ」とかなんとかいって、常識的な怪奇映画に落とし込んでくれるので、観ている方としても安心できる。
しかし、スコリモフスキ監督は具体的に描かない。
描かないので不安になる。
起きてしまう出来事は、天変地異かテロか・・・なんて気になってしまう。
でも、起こるのは、いわば「すっとこどっこい」なことが原因の災厄なのだ。
その災厄が起こった後が、この映画のいちばんの見どころ。
災厄の写る画面が、いくつにもいくつにも細分化されていき、最後には災厄が起こったかどうかがわからなくなってしまう。
その細分化されて、何が写っているのかがわからない画面は、モニターの一部で、そのモニターには一部のドット滑抜け、「空中の黒い点」がくっきりと映し出される。
劇中、何度も何度も鳴り続ける5時を報せる鐘の音は、教会の鐘。
何が写っているかわからない画面は、たぶん、神の目からみた世界の暗喩なのだろう。
「空中の黒い点」は、たぶん、神の啓示の暗喩ではありますまいか。
いや、もしかしたら、災厄は「神の不在」によるものかもしれない。
はたまた、神の目から見たら、ひとびとの災厄なんて、「ないに等しい」のかもしれない。
並行して描かれる物語のひとつひとつのピースはカチリと埋まったけれど、それでもピースが抜けている。
この映画は、そんな「不安を掻き立てる」映画であることは確か。
<追記>
とはいえ、カチリと嵌ったピースそれぞれが、あまりにもつまらないので、81分という短い尺ながら、半分ぐらいのところで飽きてしまったのも事実。
不思議な感覚
その瞬間に向かって
2014年7月11日17時11分に起きる出来事に向かう様々な人達の11分間の様々な行動を、数十秒〜数分毎の細切れで同じ時間軸を繰り返し、サスペンスタッチでみせて行く作品。
そう珍しい作りではないけれど、一つ一つのシーン、時間軸がかなり短く、天変地異の前触れかと想わせる煽りに、ハラハラドキドキが加速して行き楽しめた。
ラストを観る為の全篇
全55件中、41~55件目を表示