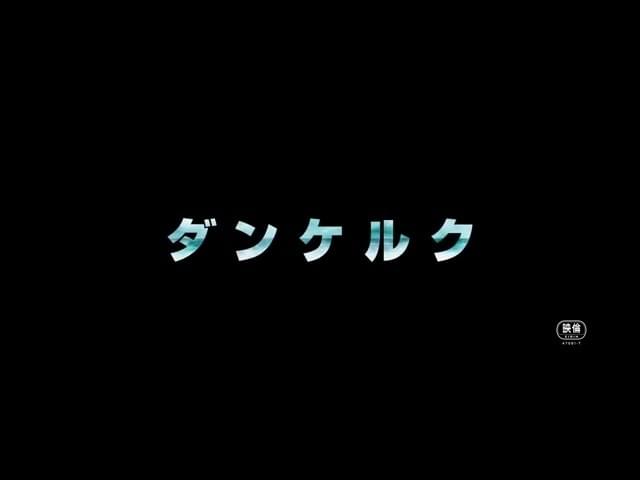「3つの視点の臨場感と生死の境」ダンケルク parsifalさんの映画レビュー(感想・評価)
3つの視点の臨場感と生死の境
砂浜1週間、救助に向かう船1日、空軍1時間を平行して描きながら、最後に時間軸が交わって合わさるという手法。無駄なセリフや説明を極力省いた映像、カットでシチュエーションや心情を描く。砂浜には、救助を待つ40万人の兵士。相手の攻撃に対しては無防備で、怯えていて戦う意
欲は低い姿で描かれる。船の視点は、民間人が様々な船を持ち寄って徒手空拳で救助に向かう感じ。途中、兵士を拾うが、メンタルやられていて暴力振って、そのとばっちりで弟が亡くなるも、一言も責めない。戦争のせいでそうなった理解していても、ちょっと不自然?父が早く関われば、何とかなったのでは? 船の視点は、兵士を第一に考える、何でも助けてあげたいという心情か。空の視点では、限られた燃料、壊れた燃料計に関わらず、自分のことは後回しにして、メッサーシュミットや相手の爆撃機を撃墜していく英雄的な扱い。実際、最後はエンジンが止まった後も良い仕事をする。
兵士を乗せた掃海艇(砂浜から脱出した脱出した兵士含む)が爆撃されるところで、3つの時間軸が交わる。あのシーンをそれぞれの視点から見ると、こういうドラマが進行していたのかっていう面白さ、物語の交わる感じがあった。神の視点で見れば、こんな感じなのかもしれない。
自分は、満潮を待つ船のシーンが印象に残った。船の横腹に穴が空き、敵の射撃訓練?と騒ぎつつ、穴から浸水。穴を塞ごうとした兵士は銃弾に倒れる。船から出れば人がいることがばれる。そのままいても浸水して沈没。エンジンを動かすが、人がいることがばれるわけでハチの巣へ。上官がいずに、助かろうとしている場面では、合理的な判断ができずに、「お前が先に行け」という、なすり合いになるっていうのがリアルだった。
また、戦場における生死の境は、数十センチ。ちょっとずれていれば砲弾や銃弾の餌食になっていたって描き方も、戦場を雄弁に語っていた。
こういう戦地からの脱出劇をリアルに描いたという意味では、恐らく始めてであろうし、3つの視点をリアルかつ丁寧に描いていて、戦場にいるかのような、確かに監督が言う通り体験的な映画であった。
感情が揺さぶられるということよりも、実際の戦場で脱出しようとする際に起こっていることを重層的に描こうとしたという映画か。