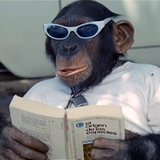ザ・コンサルタントのレビュー・感想・評価
全317件中、21~40件目を表示
アナケンの出番少ない
数学に強くて人とのコミニケーションが苦手な会計士の裏稼業は凄腕のスナイパーというギャップが良い。途中爺さんばっかりでテンポが悪くなった気がする。あとアナケンドリックの出番が思ったより少なかったのも残念。
ジョンウィック風だけど、ベン・アフレックが良い
もう一度見たくなるほど練りすぎなストーリー
キャラクター設定がおもしろい
面白い
高い評価も納得の良作
【鑑賞のきっかけ】
劇場公開時には、その存在に気づいていなかったが、動画配信で高い評価を受けているのを発見し、鑑賞してみることとしました。
【率直な感想】
<これまでにない設定>
ベン・アフレック演じるクリスチャン・ウルフは、会計士を職業としながら、裏の顔は、殺し屋という役どころ。
彼は、自閉症という精神疾患であるというところが、これまでにない設定でした。
その卓越した数的なセンスで、会計士としての仕事をこなしつつ、殺し屋という裏の顔を持つ人物。
自閉症の人物を映画で描く場合には、どちらかと弱い立場、場合によっては、被害者的な立場に立たされていることが多いように思います。
でも、本作品では違います。
自閉症を障害と捉えるのではなく、個性のひとつとして捉え、天才的な数学的センスも自閉症であるために備わった能力と本作品では描写されています。
さらに、殺し屋として、凄腕のスナイパーでもあるのですが、冷徹に標的を捉えるのが得意なのも、もしかすると、自閉症であることから、自分に関心のあることへの集中力が並外れていたためなのかもしれません。
本作品の原題は、The Accountant(会計士)なのですが、なぜ、邦題を「ザ・コンサルタント」としてしまったのでしょうか。
コンサルタントは、会計という緻密な計算を行うというよりも、企業経営の手法などをアドバイスする、コミュニケーション能力を要求される仕事。
自閉症の人物は、他人とのコミュニケーションは得意ではなく、ベン・アフレックも、この主人公を他人との関わりが苦手な人物として演じています。
でも、会計士は、会計という緻密な計算を地道に行うことができる人に向いている(もちろん、コミュニケーション能力があった方が有利でしょうが)。
主人公のウルフは自閉症ではあれけれど、特に「数学」には興味を強く持っていたため、「会計士」の仕事が向いているとして、制作サイドは人物設定をしたのではないかと思っています。
<人物の相関図もなかなかのもの>
金融犯罪取締ネットワーク部局のキング長官という人物が指揮を執りながら、「会計士」の正体を探るというのがサブ・ストーリーなのですが、このキング長官の過去が語られるところから、本作品の脚本の緻密な構成が光り輝いて見えました。
【全体評価】
アクションのことには触れてきませんでしたが、一応の水準はキープしており、ここにこれまでにない設定の主人公が活躍する物語展開は、緻密な脚本に裏付けられて、高い評価を得ているのも納得の一作品でした。
会計処理の映画かと思いきや
Make America Great Again!
2016年製作の作品
本当のアメリカ人の心意気について描かきたかったのかなと思った。
古き良きアメリカ
この作品の制作時に監督が知ったのが、もしかしたら日本人の気質だったのかもしれない。
特に漫画やアニメに見る人間性
その根源は、もしかしたらあの時代のアメリカにもあったのではないか?
監督の、もう一度善悪について問いかけたいという思いを、この作品に込めたように思う。
最後に、
アメリカでは68人に一人が自閉症という診断がなされるというナレーションが流れた。
人と違うことで「病名」というレッテルが張られる現代社会
日本でもかなり多くの子供たちに、このようなレッテル付けがなされている。
人と違うことが「ダメ」なこととして考えられ、そこに病名がつけられることで「正しい」ハンディキャップが与えられることで、ようやく他人から奇異の眼で見られずに済むと考えるのが、この現代社会だろうか?
この物語の中で描かれる正義はいくつもあった。
あのリビング・ロボ社社長ラマー
株の空売りで資金を稼いで新しいナノテク技術を確立させる。
これはその通りではあるが、悪質な手口 不正を隠すためにプロの暗殺集団まで雇う。
彼は旧友のCFOと妹のリタまで殺害した。
ラマーの誤算は、CFOとリタが応援に呼んだウルフだったのだろう。
この物語は財務省や過去の事件、大企業のマネーロンダリングなどスケールの大きさを見せてはいるものの、単にラマーによる不正とそれがバレそうになったから裏社会の暗殺集団を雇ったことで派手なドンパチが繰り広げられるだけとも言える。
そこに掛け合わせた自閉症の兄弟
生い立ちとレッテルとスパルタ教育
単純な不正発覚から始まったラマーの行動
兄弟たち
成長したジャスティーン 凄腕ハッカー
彼女からの電話によってキング局長が動いていたことが明かされる。
この構図こそ古き良きアメリカ時代の善悪 うまい言葉が出てこないが、そんな感じなのだろう。
守られるべきという言葉が良いかどうかわからないが、ハンディキャップとレッテル
これに対する正しい認識の再確認
幼い頃からたたき込まれた技術そして数学 これは努力だろうか。
「世界は優しくなんかない」
家を出ていった母 幼い自閉症のウルフ ソロモングランディの童謡で抱きしめる父
母の葬儀と父の死
このことが兄ブラクストンが裏社会へと入るきっかけになったのだろうか?
まさかの再会
妹が電話の声の主だと思っていたが、まさかブラクストンがそこに登場するとは思わなかった。
この物語を読み解くのは難しくはないが、ブラクストンやジャスティーンの現在に至る背景が奇抜だった。
そこに掛け合わされたキング局長とメディナ分析官
正義というものの再定義
ウルフはこの中心人物として描かれている。
凄腕会計士 × プロの暗殺者
まるで鼠小僧ハリウッド版だ。
最後にディナ宛に届いた絵画
一人トレーラーハウスを牽引して去るウルフ
この辺がいかにもアメリカ的だった。
特典映像には製作者の想いが語られてた。
それを見れば答えがわかる。
謎解きものとウルフの人生 二面性
「被害者」というレッテルを逆手に取ったことなどが語られていた。
そこにあった新しさには、やはり正義というものの再定義があったように思った。
「古き良きアメリカ」とは、単なるノスタルジーではなく、正義・努力・家族・誠実さといった価値観の再確認。
それは、
現代社会の複雑さや分断の中で、もう一度「何が正しいのか」を問い直す姿勢でもある。
ラマーは「技術革新のための資金調達」という大義を掲げながらも、手段として不正と殺人を選んだ。
ウルフは「法の外」で動きながらも、自分なりの倫理とルールを持って行動する。
この対比が、まさに「正義の再定義」につながっていると感じた。
スリリングで面白い作品だった。
たぐいまれなる能力
途中で寝てもうたよ
餞別にポロック
ベンアフレックは監督としても成功したが役者として味があるひとだ。と思う。
美男でタフガイだがフェロモンは希薄。デカいのに威圧感はなく、優しそうで、すこし間抜けな印象もある。案外いそうで、全然いない。
グッドウィルハンティング(1997)の鷹揚なアニキの気配をけっこう明瞭に覚えているし、酷評されたジーリ(2003)でのスカした感じも似合っていた。
(ちなみにアフレックとロペスはジーリからの交際だそうだ。20年間お互いに色んな人を試して今年(2022)ようやく結婚に至った。とのこと。)
192cmの長身だが、颯爽とはしていない。バットマンも似合っていたが軽快or俊敏なムードはなく“どっこらしょ”という感じ。柔和、温厚、ジェームズスチュアートっぽい。
Pros側にHollywoodlandやGONE GIRLがあるかと思えば、Cons側にJersey Girlやgigliがあって毀誉褒貶だが、俳優ベンアフレックが記憶に残っている映画は少なくない。
この映画The Accountant(邦題はなぜか「ザ・コンサルタント」)のアフレックも、記憶に残っている。
自閉症の過去がある癖っぽいヒーロー。感情をあらわさない会計士にして殺し屋。一般人な経理係(ケンドリック)と帳簿について話すときだけ素地が出る。
長身から繰り出されるアクションはすごい迫力。だけど激さない。あくまで静かに、会計監査をしているときと同じ大人しさで、敵をぱたぱたやっつけちまう。痛快。
脚本もよく練られている。
ストーリーのなかで弟と妹が巧妙に配置され、感心した。
ケンドリックは華奢な才媛だけれど、ちょっとモテ過ぎかな、とは思う。
音楽もよかった。
開けてびっくりの餞別(ポロック)と、キャンピングトレーラーが走り去るラストで流れるヴァンモリソンみたいな声の曲、深い余韻があった。(Sean Rowe - "To Leave Something Behind")
ところで昔ジャクソンポロックを描いたことがある。学生時代に一人暮らしのアパートに壁絵が欲しくて自分で描いた。じぶんにはアートの才能も造詣もないがポロックなら、それ風のものが描ける(ような気がした)。
ポーカーする犬だってクーリッジの真作なら破けるようなもんじゃないが、ポロックにはかなわない。
なんか好きな映画だな。すごくいいと思う。
様々な伏線をラストで回収していくメッセージ性のある映画です。
会計士&凄腕のスナイパーが、謎の助手と一緒に事件を解決していくというストーリーです。
ストーリーとしては地味ですが、いろいろなメッセージ性が詰まっています。
自閉症の子を持つ家族事情や兄弟間の関係がリアルに描かれていて、さらに、そこからの自立、そして、活躍っぷりが見事に表現されています。
一般的に、何かしらの病気を持っていると、「ハンデ」だと感じる方が多いかもしれませんが、そこからの創意工夫と努力で、世界トップレベルの技術を身に付けて活躍ができるということに凄く実感が湧きました。
今の世の中でいう、いわゆる、SDGsに対する取り組みとしても素晴らしい映画だと思います。
ジェンダー平等の実現
人や国の不平等をなくす
etc.
様々なメッセージが込められているように思います。
そして・・・
ラストは、ちょっとだけ、びっくりします。
お楽しみに!
全317件中、21~40件目を表示