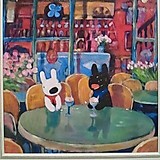スポットライト 世紀のスクープのレビュー・感想・評価
全55件中、21~40件目を表示
真実を知るのが怖いのではない。信じたことを疑うことが怖いのだ。
つい忘れるが、我々は闇の中を手探りで歩いている。
そこに急に光りが射すと、ようやく間違った道に来たことに気付く。
2001年アメリカ・マサチューセッツ州ボストンの日刊新聞「ボストン・グローブ」のチーム「スポット・ライト」がある事件を調査し、記事にして公表するまでを丁寧に描いています。実話です。
事件というのは、カソリック神父による子供への性的虐待です。
カソリック教会は、事件を知っていながら、問題の神父(複数)を異動させたり、お金で被害者側を黙らせるなどしていた為、この事実が発覚するまで、かなりの年数が経っていました。
結果、とんでもない被害者数になっています。
この事件が発覚しなかった理由は、概ね下記の通りかと思われます。
1)カソリック教会が組織ぐるみで隠蔽していた。
2)殆どの被害者が貧しくお金で黙らせることができた。
そして本作を理解する上で、最も重要なこと。
3)キリスト教徒においての"神"の意味。アメリカ、そしてボストンの地域性(ほぼカソリック)。
が、理由に挙げられると思います。
アメリカの紙幣には「In God We Trust」と印刷されていますよね。
「我々は神を信じる」
これはアメリカ国家の公式なモットーですよね?
この事件が長らく発覚しなかったのは、勿論カソリック教会の腐った体質もありますが、もう一つは「聖職者がそんなことをする筈がない」という、いえ、そんなことを考えることすらできないほどの深い、深い、信仰心を持った人たちが住む国、そして街であったということだと思います。
この"深い信仰心""神"を理解しないと、本作の本当のテーマは汲み取れないように思われます。
例えば、マイケル・キートン演じる"スポット・ライト"チーフのロビーは、一度、この神父による性的虐待を記事にしています。
さらっと、軽く。
しかし、ボストンの地域性に縛られず、カソリック教徒でもない新編集長がマイアミから来て言うんです。
「この事件、もっと掘り下げるべきじゃないか?」
カソリック教徒のロビーは「とんでもなく重大な事件である」という、認識さえなかったんです。これ、上記した3)の理由を証明するエピソードだと思います。
光が、差した瞬間です。
当然こんな地域性ですから、記者達は色んな妨害にあい、事件を取材していくんです。
記者達がノートにメモをとっている姿が、新鮮でした。一つ、一つ、起こった事実を丁寧に書き取っていく。
大人になった被害者が数名、加害者もちらっとしか出て来ません。そして一番印象的なのは、起こった事件の"再現シーン"がないこと。
大人になった被害者への、聞き取り取材シーンのみです。
何故なら再現シーンは"想像"だから。
本作に好感を持ったのは、この点です。
ドラマティックな展開はありません。記者達を過剰にヒロイックに描いてません。寧ろ、ロビーのエピソードから、事件の一端はメディアにも責任があるという主張。
あ、なんだったら善悪とか、正義とかについて、何一つ言及していません。
ただ"事実"をありのままに伝えようとする、記者達の姿を淡々と描いています。
その判断をするのは、記事を読んだ読者。映画を観た、観客。
しかし逆に言うなら、私達は記者を通してしか、事件の全容を知ることができないということですね。
ここは言及せずに、含んでおきます。
ジャーナリズムの意味を、考えさせられる内容でした。
そして個人的に思うのは、本作は邦題のように"世紀のスクープ"を描いた作品でも、記者達の正義感を描いた作品でも、また、おぞましい事件を描いた作品でもないということです。
本作で描かれたのは、"恐怖"です。
聖職者から受けた性的な虐待は、「魂への虐待」と表現されています。
なぜなら、子供達は「神を失った」からです。信仰を失ったからです。
貧しい家の子供達にとって、教会へ行く意味、また"神"に縋る意味は、裕福な家の子より大きい筈です。
彼等は、生きる大きな"支え"を失いました。
その為、被害者達は薬に依存したり、中には自殺された方もいます。
記者達も、神を失いました。
もしかしたら、この事件の記事を読んだ人達も神を失ったかもしれません。
失わなくても、とてつもない"恐怖"を感じた筈です。
「おぞましい事件だ!やべ、こえー!」
でしょうか?
そうじゃないと思います。
本作で描かれてたのは、「世にもおぞましい事件を知る恐怖ではなく、"信じた何かを疑う恐怖"」です。
記者達の戸惑いと恐怖の向こう側に、自分のアイデンティティを根底から叩き壊され跪く人達の姿が見えました。
本当に、怖い映画でした。
やっぱ、映画館で観れば良かった!
アカデミー作品賞の中では、一番好きかもです。
あ、でも。
敢えて苦言を呈すれば、レイチェルの金髪ってあんまり好きじゃない。
あ、本作もマーク・ラファロは良いですが、私の中のベスト・ラファロは日本劇場未公開(DVDは出てるよ)の"それでも、やっぱりパパが好き!"だということを付け加えて、終了します。
※Catholic 日本では公式には「カトリック」と表記します。
見事に「見せない」
性的虐待の場面が1秒も無い。それでいて、どんな大変な行いであるかが、こちらにはまじまじ分かる。この凄さと怖さ。劇中で、「標的は教会そのもの」という台詞があったが、この事実も描かれた物語も「その個人」でなく「システムそのもの」を見ている。双方のリンクが素晴らしい。
辛かった
これが実話ということが信じたくないというレベルでした。
推定1000人を超えたと言われる被害者、200人にも及ぶ加害者である神父。
信じている宗教というのをいいように利用し、12、3歳の子供を標的にしていく。
もう本当に新聞社の社員たちがすごいと思います。様々な圧力にも打ち勝ち、合っていることを突き通す。
最後に新聞が世に出た時、被害者からの電話が絶えないのが、私的には辛かった。
こんなに言えない人がいたということ、それを言えるようにした新聞を出せて良かったと思う反面、それが現実だということがとんでもなく重いなぁ、と思いました。
すごく重かったし辛かったけど、やり切った達成感も伝わってきて、それが救いでした。
冒頭から集中して観るべき
マネー・ショートの時もそうでしたが、
この手の実話の映画化は思うことがありすぎて内容が上手くまとまらない。
まとめきれない。
事件が報道されたのは2002年の年明け。
911の翌年。14年前の自分は何を考えてだろう。
映画を観て衝撃を受けるということは、
当時の報道されたこのニュースを知らなかったという証明にもなります。
思い返してみると、あの頃ちょっと記事で見かけただけで、
興味ないからと大して内容を追いかけていなかった自分としては、
色々と考えさせられることがあります。
それぐらいエグい事件でしたし、そう思えるように描かれていました。
映画化されることで更に広く知れ渡ることにもなりますが、
これだけの事件が娯楽に繋がらなければ思い返すこともない。
如何ともし難いですね。
小難しい部分もあるので、
思考が追いつかないこともありましたが、
時間が制限される中でも非常に巧みに構成されていて、
後半になるにつれ食い入ると思います。
ただこの後まだ観てない人に薦めることがあれば自分がこう言います。
事件は既に始まっている。冒頭から集中して観るように、と。
淡々として丁寧
絶対的なヒーローも悪者もいなかったのが好き。
ジャーナリスト側の命題は"スクープをあげる""新聞を売る"ことだから、打算がちらつくし、被害者の心情に寄り添えない場面もある。もちろんそれだけではなく、悪事を放置したくない情熱も本物なんだけど。
教会は教会で、組織としては完全にブラックなんだけど、一個人に目を向けていくと、そもそも神父が性的虐待を受けていたり、立場上教会を庇わざるを得なかったり、「コテコテの悪人っぽさ」がない。
映画化する時に、もっとエンタメっぽく「正義に燃えるジャーナリストvs巨悪のカトリック教会」とはしなかったところに、丁寧さを感じた。
マイケルキートンは、バードマンが凄く良くて印象的だったけど、今回も良かった。過去の汚点を前に疲れ切って立ち尽くすおじさんの顔が最高。
「教会の恐ろしさ」って実質的な権力ももちろんなんだけど、人の心の拠り所で原点だという点なのかなと思った。主人公が泣きそうな顔で「年をとったらまた教会に戻るものだと思ってたのに」って言ってるシーンが印象的だった。親の汚点を直視するような辛さかなぁ。
誠実に徹して地味になり過ぎたかもだけど。
地味、なんでしょうね。何かが起きるわけでもなく、事実を時系列でなぞっただけ。
そういわれたら、違うとは言えない。
でも、この事実の重みと、地元紙の記者が、自分の文化の悪しき点を明らかにする苦しみ、被害者の苦しみがよく伝わり、とてもドラマチックだったと思います。
性犯罪の何が辛いって、被害者を責める風潮があることです。誘ったんだろうとかいう声なき声が被害者をさらに責める。
特にこの場合、地域の信仰の拠り所である神父が、尊敬されるべき存在である神父が犯した卑劣な行為なわけです。それを、ノーと言いにくい事情のある子供を選んで、自分の行いが露呈しないように相手を選んで、ことに及んでいたわけです。
被害者は、培った良心から加害者を憎むことさえできなくて、自分で自分を責めて、生きていけなくなった被害者も多い。
生き残った被害者も、未だに、その過去に苛まれている。
そういったことが、強く胸に迫り、怒りと憤りを噛み締めながら見ていました。
教会の過ち、それから黙殺してきた地域の過ちを悔い、正そうとする記者たちの真摯な姿が丹念に描かれています。
無関心でいることや、権威や既存の価値観の見たいところだけを見ていては、自分も誰かの悪魔になり得る。その警鐘として受け取りました。
信仰と教会は別
今も多分この問題でバチカンは揺れているらしい。
教師の性虐待とよく似た構造があるが、生死、魂、生き方、価値観、社会化などのかだいでは、信者と家庭ぐるみでより深く関わる聖職者が加害者であり、教会が組織的に隠蔽していた事が重大だ。
時々報道されていたが、映画で見るとリアルさがあり、特にカソリックの伝統の中で育った記者たちが、自分の中の何かが壊れたように感じてしまう所が、しっかりと描かれていた。
現代社会で宗教の果たす役割は、変化してきた。しかし、宗教にしか扱えない大切な問題はたくさんある。
私自身の生活と直接関わる問題というわけではないし、どこまで理解できたのかは心もとないが、何か人の心の深い部分に響く映画だった。
ペンは剣よりも強し
まさにこの言葉を表した映画。
ドキュメンタリーということだが、
現代の日本のマスコミで、
これだけ情熱を持って記事を書いてる人が
どれだけいるのかなぁなんて考えた。
あまり宗教宗教言わない日本人でも、
カトリック教徒たちが教会に刃向かうなんて、
それこそ「正義」の心を持ち、
何が何でも暴いてやる!
という気持ちがないと無理だと思う。
いよいよ記事に、というタイミングで、
9.11が起こり、掲載に「待った」がかかる。
この辺りもリアル。
何年も放っとかれた記事より、
世界を震撼させたテロ事件。
しかし、外からやってきた新編集局長が、
なぜあんなにもこの記事にこだわったのか?
その辺りがもう少し詳しく
描かれてもよかったかも。
なんにせよ、終わり方がすごく好き。
新聞を読んだ被害者からの
鳴り止まない電話。
大人になると、暗黙の了解や
権力なんかがわかってくるけど、
それに歯向いたくなった。
●現代版ダビデとゴリアテ。
カトリック教会というゴリアテをボストン・グローブ誌が撃つ。
まさにパンドラの箱。究極のタブー。
719年ぶりとなる、ベネディクト16世の自由意思によるローマ教皇の
生前退位は本件と無関係ではあるまい。
神父による性的虐待。
概要がわかった今となっては、教会の構造的な問題だろうと思う。
禁欲と独身性。
伝統という名の世間知らずさ。
教会の権威と厳格さ。
神父の性的虐待を追う記者。
やがて、それが氷山の一角にすぎないことがわかる。
確率論からすると、想像を絶する数字だ。
一方、グローブ誌は53%をカトリック信者の読者が占める。
それでも信念を貫き、真実を追う。
ターゲットも本丸に定める。
かつて、そのことを訴えていた人たちともう一度、接触する。
変わり者だと思っていたが、それは色眼鏡で見ていたから。
変わり者でなければ、噛みつけない相手だ。
信念を持って戦い続けた彼らと、
多岐にわたる詳細な取材で真実を世に問うた記者たち。
蛇足だが、その取材姿勢がリアルだった。
動揺して泣き出す被害者。
それでも口調は変わらない。
傾聴するが、同情しない。
冷静に、客観的に真実を追い求める。
それだけに、現場記者が感情を爆発させるシーンは刺さった。
スクープが他社に取られるかもってのもあっただろうけど、
いまも続く被害を1日でも早く止めたいという社会正義からだろう。
スクープ当日から電話が鳴り止まない。
電話の主は意外にも。
さらに蛇足だが、若い頃に新聞記者になろうと思ったことを思い出した。
こういう仕事がしてみたかった。
現実はそんなに甘くはないのだろうけど。
秩序がもたらす混沌
神の御使を糾弾した愚かな人間の話。
…と、書いても違和感がないほど「教会」は浸透しキリストの威光は絶大なのである。
驚いた。
2002年の話しである。
もっと昔の話かと思ってた。
携帯もインターネットも普及している。
で、その時の責任者はさらなる強大で強固な城へ匿われたと本作品は告げる。
目からウロコなのは、絶大なカリスマ性を維持していること。
神に従事している人間、または組織に間違いがあってはならない。もしくは、間違ってるはずがない。
そんな体裁を保つために隠蔽され続けてきた。
どうやら個人は糾弾できたものの、その組織ぐるみの隠蔽工作にまでは及んでいないようだ。つまりは…現在もまだ進行中の話しなのである。
作品は、終わりに近づく程ヒートアップしていった。取材者それぞれに異なる正義…いや、信念かな?そんなものがあり必ずしも同じ価値観ではない。だけれども、目標は一つ、そして揺るがない。どちらに神の意志が作用していたのかと思うほどだ。
センセーショナルな作品だった。
取材している記者達でさえ、盲目的に教会を崇めてた。だからこそ、裏切られたと思うのであろう…。
「教会はなんでもできる」
このシーンの後に911を引き合いに出したのは、やり過ぎかとも思うが…どうやら、その案件のために足止めをくらったのは確かなようだった。
ノンフィクション
期待して見に行ったら期待をうわまった!淡々とストーリーが流れていくんだけど、どんどん引き込まれていく。記者たちの色々な葛藤が描かれていて感情移入できる。ただ特ダネをスクープしたいだけじゃなくこの誰もが目を瞑ってきた事実を世の中に伝えたいとう気持ちが伝わる!最後の電話が鳴っているシーンはすごく良い。あと終わったあとの字幕がズシーンと心にくる。レイチェルマクアダムスは恋愛映画でしか見たことなかったけどこの人なんでも演じれるんだな!ますます好きになった。マークラファロは天才
飽くまでも実話を基にした社会派映画
特段、派手なシーンとかはありませんが、
真実に向き合って、正しい側へ進むのは
難しいけど、信念を持って貫き通した記者達の
努力は報われたんだと思う。
隠蔽した枢機卿が昇格して異動したという
最後の一文に衝撃を受けたものの…
パンフレット購入してみたら、カトリックの神父の職を剥奪等の処分をしたり、色々と改革したあとローマ法王が辞職(7年も経ってからだけど)したりと波紋は広がっていっているようで、少し安心した。
緊迫感は無かったが
予想外に露骨な取材妨害がなく、拍子抜けはした。地道な取材、これまで培ってきた信頼、信念、生まれ育った街への愛情など、淡々としたドラマだった。
事件を追いかけるよう指示したユダヤ人の新任編集局長、スポットライトの4人、それぞれの立場で関わる弁護士たち、どこにも悪役はおらず正義の味方もいない。
ラスト近く、これまで誰もこの事件に注目して大きく記事として取り上げた記者はおらず、主人公さえもかつて埋め草的記事として扱ったこと、それを主人公が認識した時の表情が印象的であった。
深い内容でした
上映中セルフ一つも漏らさず集中して鑑賞しました。後半の記事の裏どりも終わりチームでミーティングしてる最中から最後まで涙が止まりませんでした。チームのリーダーの気持ち、そして被害者の気持ちや家族の気持ち映画に出ていたすべての役の方の気持ちなどが私の魂を揺さぶりました。最高の脚本、作品だと思います。
いいドキュメンタリー
2001年、もう大学生だったはずなのに、全くこのニュースを知らなかった。
エンドロールで流れる都市の多さに驚きつつも、淡々とこの映画を観れてしまうのは、やはり私がカトリック信者ではなく、また無関心な日本人だからだ。
このニュースだけではなく、もっと知っているはずのニュースがあるはずなのに、ニュースになり、知る機会があるものも、ほとんどしらないまはま、無関心で生きている
当時のニュース、調べてみよう
タイトルなし(ネタバレ)
テーマソングが一曲だったのがかなりの衝撃。 字幕で見たが大満足 さすがアカデミー賞だと思った。エンディングの都市の名前が上がったときはゾッとした。実話に基づく映画という反響はかなり大きいと思う。
カトリック教会の異常性に吐き気がした!
正直、アカデミー賞の作品賞と脚本賞のW受賞の前評判は期待外れだった。ありふれたドキュメンタリー映画を観ているようで退屈だった。息もつかせぬ展開を期待する人にはお勧めできない。
「ボストン・グローブ社」の新任局長が、同紙の特集記事「スポットライト」に過去、取り上げたことがある「神父による児童性的虐待」を深堀するよう、「スポットライトチーム」のボスに指示するところから映像が展開する。取材は、被害者家族が相談した弁護士のヒアリングから始まるが、弁護士が何人も登場し、しばらくは名前と顔が一致しない。そんな観客を置き去りに、記者と弁護士との意味不明な展開が延々と続く。
児童性的虐待がテーマの映画にも関わらず、性的虐待シーンがない。被害者による状況説明だけでは観客の感情を揺さぶれない。被害者の取材映像は多い一方、加害者神父の取材映像は、元神父を訪ねたときの1,2分のシーンだけ。元神父は何か言いたそうだが、家族が記者を追い払い、そこで取材は終わってしまう。加害者神父の名前は、セリフの中には繰り返し登場するが、映像はおろか写真も見せない。なぜだ?カトリック教会は治外法権か。事件を隠匿したとされる司教は、事件について何も語らず。事件公表後、司教はバチカンに異動し、位が上がったと言う。
最後、「スポットライト」欄が取材記事で埋め尽くされた新聞が市民に配達される。「ボストン・グローブ社」の幹部が苦情電話と抗議デモを心配する中、「スポットライト」担当室の電話が次々に鳴り始める。電話の主は、今まで口を閉ざしていた被害者家族だった。「ボストン・グローブ社」は加害者神父を80人と発表したが、その後の取材で143人に訂正、被害者は1,000人を超えた。こればボストンだけの数字。この取り組みは全米各地に広がり、その地名を紹介して映画は終わるが、その後のカトリック教会については何も語らない。消化不良のまま、映画館を後にした。
記者として
事実を伝えることが仕事。
だけどそれは、この世界ではとてもとても
難しいことかもしれない。
その中で、信念を持って、自分の仕事をやり抜く
チームに感動。
完璧にできるわけがない。
日々暗闇の中手探り状態。
そこから生まれる、世界を変える記事。
素晴らしい映画でした!
考えさせられる事実
見せつけられた途方もない事実に
ただただ節句した。
エンドロールの被害地区が、なんと多いことか。
日本は海外ほど宗教が生活と密接ではないが、
自分や身近な人達が、もしその立場おかれて
いたとしたら…、
もしこの記事が世に出なかったら…
考えただけで、末恐ろしい。
作品は、取材を進めるにあたり
次々と闇が明らかになっていく様子が
丹念に描かれていて、引き込まれた。
教会の圧力がさほどなかったと感じたが、
内容からそこは強く描かなかっただけなのか。
キャストの演技もリアリティがあった。
アカデミー作品、脚本賞に納得。
勇気
勇気や熱意が新聞社にありました。
人間とは本当にもろい。
神父の価値観と被害者の意識が相違している
その部分でいま一度宗教の在り方や
組織の在り方を考えさせられました。
要は、一人一人の意識レベルが
向上しない限り、問題は消えない事実もあるかと。。。
全55件中、21~40件目を表示