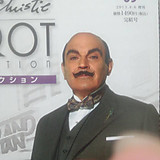映画 聲の形のレビュー・感想・評価
全578件中、281~300件目を表示
立川で見てきた
前回2016/9/23に新宿で見て痛く感銘を受け、原作買って、更に感動し、身内に読ませ、会社の夜勤用推薦図書として常設したり、嫌な人のあだ名に「川井さん」などが定着した頃に丁度、立川からメールがきて、スタッフ監修の極音上映と聞いて見てきた。
正直思ったほどではないというか思ったとおりというかうんなんかそんな感じ。
ヤマカンも言ってたけど二回目見ると荒削りな荒の部分に目がいっちゃって初回に見た時の感動より目減りしちゃうかなとか、原作読んでからだとイヤリングの件とか強調しすぎ?とか思ったり。うんまぁ原作読んだのがでかいと思う。原作の方が良い。
で、音響の話なんだけど。
これも、これも初回見た時の衝撃の方がでかくて、記憶の中の音響と大差ないというか、まぁ俺そこまで耳よくねぇしなというのが正直な感想。
ですが、花火と最後の世界が開けるシーンは良かった。花火見に行った時の胸に音が響く感じを思い出した。
まだ見てない人なら絶対に立川に行くべきだし、
耳の聞こえない人も絶対に立川に行くべきだし、
最近立川以外で見て記憶が増長してない内の人も行くべき
書いてて思ったけどあくまで初回と立川の対比であって
映画自体はいいよ思い出すだにうるっとくるもん
泣かないでよ西宮
聲の形が心の聲に…。
今年、最初の映画鑑賞。前々から観たいと思っていた作品。「君の名は」がエンタメ作品なら、こちらはグッと思春期の心にスポットを当てたヒューマンドラマ。
心の聲が形となって、それぞれの登場人物の痛みとなって、すれ違っていく。と同時に温かさを運ぶ。
年をとって考えれば、そんな事と思える事もこの時期には、あまりにも大きなシコリとなって、トラウマに…。
主人公は、そんな苦しみと向き合い方を、もがき、模索する。現在、イジメや学級崩壊をしている今の子供達が観て欲しい作品。
但し、学校や先生を安易に悪く描くのはやめて‼︎今の殆どな先生や学校は一生懸命、子供のために取り組んでいる。それでも、こうした事はいつの時代も起こるんだってこと。
気になっていた映画
浮世離れ
大衆向けアニメとオタクアニメの決裂を表象するかのようなものでした。
新海作品や「この世界の片隅に」などと比べると背景世界の描写やキャラクターの動機、心情の奥深さに欠けてます。
アニメ調にデフォルメするならするで、デフォルメして欲しかったが、中途半端にリアルさとアニメ感が混在して気持ち悪かったです。
キャラクターを製作者の意のままに操っているかのような「製作者の見えざる手」が丸見えでした。
主人公の葛藤や変化は納得できますが、
なぜ西宮さんが主人公を好きになったのか?
あれだけいじめられながら、心が捻くれず、なぜ最後泣き崩れ、崩れたと思ったらいとも簡単にけろっとしているのか?
西宮さんを理解せずに都合よく扱っているのは製作者の方なのではないでしょうか?
登場人物のキャラ付けも、あのひょうきんなキャラクターならば、友達全くいないわけないでしょうに。
ツンデレの女の子もいくらなんでも初恋を引きずりすぎです。
正直言って背景がボロボロ過ぎて、作者の伝えたい内容が全く伝わりませんでした。
リアリスティック三部作
「シンゴジラ」
「君の名は。」
「この世界の片隅に」
に対して、大変お粗末な映画を日本が誇るアニメ制作会社京都アニメーションが作ってしまったことに愕然とします。
高校生までは面白く楽しめるものでしょうが、おおよそ大人まで楽しめるものではありません。
第三者からしたら不自然で、主人公にとって都合のいい展開の仕方をしますから。
もはや主義主張のない監督が作る製作会社主導のアニメでは、本当に面白いものが作れないということがよくわかった映画でした。
スクールカーストや主人公の心情描写は丁寧であっただけに残念です。
これもあざとい?
原作未読、予備知識なしでの鑑賞。
聲…石板の楽器の簡略字に耳を加えてできた文字だそうです。つまり、口から発する音というよりは、空気の振動、響きを耳で拾う、というのがこの字の成り立ちなのですね。
伝えたい、分かって欲しい、上手く言葉に出来ない、
だけどそもそも何を分かって欲しいのか自分でもよく分からない。
自分のことばかり分かって欲しいって訴えているようだけど、こちらのことを理解しようとしているのか?
ごめんなさいと言うけど、どう反応して欲しいんだ?
イジメが良くないことくらい分かってる、だけど止める勇気がない、第一そんなことしたら自分だってイジメられる。
分かってるのに口にしない自分は卑怯だ、このままだとますます自己嫌悪に陥る、もう居場所がない、逃げるしかない。
よほど生まれついての強靱な精神力を持った方以外、誰でも感じるようなもどかしさがとても丁寧に、しかも多くの人が思いあたるような友人関係の中で描かれていると思いました。
少女は聴覚に障害があるので、コミュニケーションの手段がたまたま手話や表情が主体となっているだけで、伝えたいという気持ちや相手のことを理解しようとする気持ち(響きを拾う力)は、障害の有無とはあまり関係が無いのだと気付かされました。むしろ、生半可な言語表現や態度の方が、本質を見誤らせることの方が多いのかも知れません。鑑賞後、もしかして自分がその生半可な奴じゃないのか、と若干の後ろめたさも覚えさせられる、ちょっとほろ苦い映画でもあります。
障害をお持ちの方、そのご家族や関係者の方のご苦労は想像することしかできませんが、障害の有無に関わらず、何かを伝えよう、理解しようとする行動が何かを響かせ、何かの形を渡すことができるのだということを教えてくれた素晴らしい作品です。
君の名は。やこの世界の片隅に、など今年多くの人が繰り返し観ている映画はどの作品も、制作した側(伝える側)の意図をはるかに超える様々な形に響いているのだと思います。きっと3回観た方は3回とも違う形で作品世界を捉えているはずです。
どこかのヒット作品のレビューで、万人受けを狙った、とか、あざとい(小利口、露骨で抜け目ない)という表現をネガティヴな意味で使っているのを見た記憶があるのですが、製作者に何かを伝えたいという熱意があるのなら、構わないのではないでしょうか。どういう形で受け取るのかは、受け手側次第なのだと思います。伝えたいことはどんな形なのだろう、と何度も考えさせられるような深みや厚みや共感性やいら立ちや知的刺戟がなかったら、繰り返し観る人はいないと思います。
現実世界の争いやいじめについて、改めて深く考えたくなる。
初めて『君の名は。』を見てしばらく経った頃、『聲の形』や『この世界の片隅に』も凄い映画らしいという噂をネット上で見かけ、『聲の形』と『この世界の片隅に』を同じ日に見に行った。
2つとも噂に違わぬ大傑作で、私が今までに見た映画のベスト10を塗り替え、
『聲の形』は7位に、『この世界の片隅に』は6位に、新たに入った。
『聲の形』は「障害者に対する接し方」と「いじめ」をテーマとした映画。
あらすじを知った時、同様に障害者とそれを取り巻く人々をテーマとした
昔の作品『どんぐりの家』(原作:山本おさむ)を連想した。
私の親族にはダウン症児がおり、その子とその家族が陥った状況が『どんぐりの家』での描写そっくりだった。
『聲の形』に『どんぐりの家』と似た気配を感じ、
「見なければ」という義務感めいたものを持ちつつ、映画館に足を運んだ。
私見では、『どんぐりの家』がどちらかと言えば「障害者に対する接し方」を描く方にベクトルが向いているのに対して
『聲の形』はどちらかと言えば「いじめ」を描く方にベクトルが向いている様に感じられる。
『聲の形』が訴えている事の1つは、
「いじめはごく普通の子供の間でも実に些細なきっかけで起こるものであり、子供の中に障害児(※)が加わった場合はさらに起こりやすく、陰惨さの度合いが強くなり易い」
といった事だろうか。
(※障害児に限らず、何らかの意味で「弱点を抱える」者あるいは「周囲と比べて相対的に立場が弱い」者に置き換えても、この図式は成立する)
主人公の西宮硝子と石田将也そしてその周囲の子供や大人達が陥ったのと似た状況に陥った観客は、私も含め、かなり多いのではないかと思う。
この映画には「絵に描いた様に分かりやすい悪人」は殆ど存在しない。
強いて言えば、将也の教室の担当教諭・竹内ぐらいだろうか。
小学校での竹内の仕事ぶりはいかにも「お役所的」で冷淡に見えた。
だが、あの程度なら(あるいは「残念ながら」と言うべきか)どこの学校にもいるだろう。
あとは植野直花の言動に色々と疑念を持ったが、
それとて彼女を「悪人」と断ずるには酷に過ぎる。
彼女の様な「ちょっと勝気(あるいはナマイキ)な女の子」は
どこの学校でもごく普通に見られるはずだ。
劇中で描かれた将也の罪を要約するなら、
それは「無知と未熟ゆえの想像力や配慮の欠如」という事であろう。
その罪ゆえに将也は硝子の心を傷つけてしまい、
後に激しい自己嫌悪に陥る事となった。
仮に将也と級友達そして担当教諭にもう少し想像力と配慮が有れば、硝子に対するいじめは起こらなかっただろう。
先程「いじめはごく些細なきっかけで起こる」という旨の事を書いたが、
この映画は「ごく些細なきっかけで、事態はいくらでも悪化する」という事をも訴えているかの様に、私は感じる。
将也と硝子は劇中でそれぞれ別々の時期に自殺を図るが、
二人とも死を免れ(硝子の場合は正に間一髪だった)、
辛うじて最悪の事態は避けられた。
劇中の状況がもう少し悪ければ、二人のうち少なくとも一人は死に、遺族やその周囲の人間にも大きな禍根を残しただろう事は想像に難くない。
本作を「御都合主義の感動ポルノ」などと評する人間を見かけたが、その種の人種は「現実主義()の悲劇ポルノ」の中毒者なのだろう。
そんなに悲劇が見たければ、溢れんばかりに存在する現実世界の陰惨なニュースを、寝食を惜しんで「消費」するがよい。
私が思うに、現実世界の理不尽は、天災などのように人間に由来しないものと、戦争や確執などのように人間に由来するものに、大別される。
いじめは、大人の世界での戦争や抗争や確執の、子供の世界への投影である。
大人の世界で戦争や抗争や確執が絶えたためしが無いように、いじめも絶える事は無いだろう。
大人の世界での争いごとを根絶するのが不可能でも、起こった争いごとによる惨禍を少なくする試みは常に行われてきた。
いじめも、根絶するのが不可能でも、惨禍を少なくする試みは常に行われて然るべきだ。
『聲の形』を知る数年前から、私はゲーム理論に興味を持って糊口をしのぐ合間に関連書籍を読み漁ってきた。極めて個人的な意見だが、ゲーム理論が戦争の構図を理解するのに役立つのと同様、いじめの構図を理解するのにも役立つかも知れない。
(ゲーム理論から導かれる重要な結論は「敵に決して弱みを見せるな」「敵にはこちらにとって都合良い情報のみをつかませろ」であると、私は思う)
話が脱線してしまったが、この映画のラストは、安堵感を覚えると共に、
現実世界の争いやいじめについて、改めて深く考えたくなるものであった。
名作です!!
名作だと思います。我が家では中学から大学の子供たちも全員が二回観ました。こんなことになるとは思ってもみませんでした。一回目、それなりに感動して近くの「聖地」に「巡礼」までした「君の名は。」の予告がキッカケで本作を観ましたが、それとは比べものにならないくらい何度も涙があふれ、衝撃を受け、それが後に尾を引きました。どういうことだったのか原作を買って家族で読み、考えさせられました。ネットでの見解もたくさん検索しました。知れば知るほど深く「生きる意味(人は希望や意味無しに生きられない)」とか「命の重さ(それでも生きているだけで価値がある)」とかを思わされ、改めて映画でどう描かれていたのか確認したくなりました。映画は本当に良くできています。聴覚障害を持つヒロインの硝子の気持ちに私自身も気付けなかったことがショックだったのですが、主人公の将也が感じていることを追体験しているのだと理解しました。ラストは映画のほうが好きです。アニメでこんなに心をつかまれるのは個人的には三十年程前に観た「銀河鉄道の夜」以来です。学校に通う子供たちの話で、いじめが描かれていたり、どちらも文科省が後押ししてたり、サントラが素晴らしいことや、どちらも原作が何度も書きなおされていて、物語がまだ未完のような余韻が残るところも似ています。またどちらにもクライマックスで主人公が神に自分のささやかな切なる思いを述べる独白の場面がありますが、その中身はエゴではなく他人の幸せのために自分の命を使いたいという若者らしい純粋で切羽詰まった誓いの発露です。その願いが聞き届けられて奇跡が起き、主人公は最後に再出発できるのだなと思われる展開があります。そのファンタジー的な要素も心揺さぶられる重要な要因かもしれません。世の中がわかったような気になっていた若い時よりも歳を重ねる程に「今、見えているものだけが全てではない。むしろ見えないものや未来にどのような意識を向けるかのほうが大事だ」と感じているだけに、とても説得力を覚え、感動しました。
一言で衝撃的な作品でした。
ちょうど山田尚子監督が舞台挨拶にいらっしゃった日に鑑賞しました。
観に行くきっかけは『君の名は。』を鑑賞してから2ヵ月ほどの間にTwitterで『聲の形』の評価の高さを感じ、気になり始めたからです。
因みに前情報は『聲の形』公式サイトにあるPVのみで、原作のコミックなどは全く見ていません。
作品の内容に関してですが一通り見てみて“リアル感”と“場面場面の衝撃”を感じました。小学生時代ではよく見られる場面が過去を思い返せば妙に納得してしまったり、ただ今の目線で見るとどうしても許せない感情が沸き上がってしまったりしてしまいますね。そういったリアル感は非常に伝わりました。
あとリアルならではで起きること、不測の事態、人間関係のいざこざ、過去と現実など様々な場面で衝撃的で、結構心に来ました。ストレートなリアルさが描けていると思います。
けど一番は硝子の聴覚障害が肝で、“伝えよう”という気持ちと将也の“変わろう”とする姿がとくに心に残りました。
初鑑賞が山田尚子監督の舞台挨拶の日ともあり、本当に素晴らしい作品だな~と感じ、素直に拍手しました。
監督の貴重な話も聞けましたし、その後原作が気になりコミック全巻を読みましたが、映画で全て収まりきらないほどのボリュームで映画で語られなかった話も多くあり、驚いたことを覚えています。
総評ですが、観て良かった作品でした。それは間違いないです。
また、この作品は2回観に行きましたが、内容がちょっと濃い(重たい)ので2回目は1回目ほどのめり込みはしませんでしたので4.5という評価にさせていただきました。
重たいけれど、大事なテーマ。傷ついた者達の確かな絆。
【賛否両論チェック】
賛:傷つき、生きる意味を見失っていた主人公が、かつて傷つけた相手と再会し、次第に惹かれていく様子が、切ない雰囲気の中で描かれるのが印象的。その過程で少しずつ他人の声を聴こうと、必死で心を開いていこうとする姿にも、またグッとくるものがある。
否:イジメや自殺未遂等、重たいテーマが続くので、軽い気持ちでは観られない。
軽い気持ちでイジめていたことが、全て自分に返ってきて、初めて他人の痛みに気がついた将也。彼が死ぬ前の身辺整理のつもりで再会したイジメの相手・聴覚障害を持つ硝子と打ち解け、次第に心惹かれていく姿が、切なくも温かな雰囲気の中で描かれていきます。
イジメや自殺未遂等、重たいテーマではありますが、思春期の主人公達が葛藤し、ぶつかり合いながらも彼らなりの答えを探そうと模索していく様子に、胸が熱くなるようです。心を開けない相手の顔に「×」がかかって見える演出も意味深ですし、
「君に、生きるのを手伝ってほしい。」
というセリフは、本当に心に残る名言だと思います。
なかなか気軽に観られる作品ではないかも知れませんが、生きることを改めて考えさせられる、そんな1本です。
私の映画
聴覚障害、いじめ、自殺、恋愛…
いろんなテーマが折り重なっている作品だから、観た人それぞれの経験や興味によってどこをクローズアップするのかは変わってくるだろう。
私にとっては完全に、ディスコミュニケーションの映画だった。
主人公の将也が校内すべての人間の顔に×を付けたあたりで号泣。
その後はずっとダラダラ泣き続けた。
泣きすぎて吐きそうだった。
これは私の映画だ。
だから、客観的に、冷静に評価することなんてできない。
映画を観て泣いてたのは今の私じゃなくて、
学校内の全ての人間の顔に×を付けて、俯いて、見下して、
でも誰かに手を差し伸べてほしくてしょうがなかった、17歳の私だ。
あの頃の自分が見たら…、多分受け入れられないだろうな。
そんなにうまくいかねえよ、って言うと思う。
でも彼女に言いたい。
今いる世界が、世界のすべてじゃないってことを。
いろんな経験をして、自信をつけることで、世界はどんどん広がるってことを。
ポスターのキャッチコピーにもなっている「君に生きるのを手伝ってほしい」の台詞が素晴らしい。
本当に生きるのがギリギリな将也だからこそ、嘘くさくない重さが生まれる。
それにしても、将也のお母さんの髪型はあれでいいのか…?
現実は
自分の体験ではいじめるような子は逆の立場にはならなかった。自らぐれたりしてドロップアウトはするが…。
最後に気がついたが大人の男は全く深く関わるかたちででなかったな…父親は0。
登場人物の中の誰かには重なるはず
さすが京アニ!
表現力が飛び抜けてる!
人の顔を見られない✖︎の表現だったり、
手話の完成度だったり、
わかりやすくも共感しやすいものでした。
でもやっぱり、観ててツラかったですね。
いじめて、いじめられる中で、
親、教師、クラスメートの言動や行動は
「ああ、こういうの見たことある」って。
クラスで犯人探しするみたいなシーンは特に。
クラスメートは自分以外の誰かに
責任を押し付けて、自分のことは棚にあげる。
教師も面倒事が嫌いだから
都合の良いように誰か1人だけに
全部を負わせて、それで済まそうとする。
日本の学校を忠実に描いてると思う。
自分が行ってた学校が異常だったのかもしれないけど、
本当に、こういうのが普通にありました。
だから、こういうの本当にムカつく。
特にあのメガネの女みたいなの、本当に嫌いだった!
被害者ぶって、人の同情を誘って、周りを味方につけて、
自分に都合の悪い人を貶める。
自覚がないとしても、やってることはそういうことだから。
それにホイホイ釣られる
赤髪男みたいなヤツもどうかと思うけどね。
たぶん、自分は
主人公とツンデレ女の間くらいな
性格してるんだろうなって思う。
きっと他の人も
登場人物のうちの誰かに
共感するものがあるんじゃないかな。
高校生の硬質ヒューマンドラマ
全578件中、281~300件目を表示