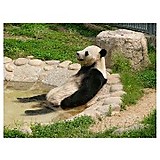リリーのすべてのレビュー・感想・評価
全184件中、101~120件目を表示
誰にも渡したくない、この余韻を
2016年春、早くも今年ナンバーワン!、と思える作品に出会えました。
「リリーのすべて」
私はとても良い作品だと思いました。
エンドロールでは不覚にも涙してしまいました。
世界で初めて「性別適合手術」を行った人の話です。
物語の舞台はデンマークの首都ロッテルダムです。
1,926年。第一次大戦の傷も癒え、束の間の平和が訪れたヨーロッパ。
人々は平和な時代を、おおいに楽しみました。
さて本作の主人公アイナー・ヴェイナーは、芸術家です。
主に風景画を描いている絵描きさん。
奥さんゲルダも画家です。彼女は肖像画を描いている。
ただ、画商さんからは
「奥さんの絵は……ちょっとねぇ」と渋い顔をされています。
なかなか売れそうもない。
でも奥さんゲルダは、肖像画家として、なんとしても成功したいと願っています。
今、手がけているのは、大きなバレリーナの絵。
ぼくは絵画の知識、まるでないんけど、たぶんサイズは150号近いんじゃないですかね。
2m×1,8mはラクにありそうな超大作です。
モデルさんが、たまたまいなかったので、ゲルダは旦那さんに
「ちょっとアンタ、手伝って」
といきなり、バレエのチュチュとタイツ、トゥシューズを押し付けます。
ご主人のアイナーは、やせ形で、いわゆる草食系男子。かなりイケメンです。
美男子は、女装させると、本物の女には出せない”怪しいまでの”「女子力」がある事は、結構知られていますね。
「しょうがないなぁ」とご主人、しぶしぶ靴を脱ぎ、ズボンを下ろして、白いバレエタイツに脚を通してみました。そのときです。
「えっ……」
なんだろう、この感覚は?
彼はドキリとします。
-どういうこと?-
自分でも分かりません。
なぜか胸が苦しい。でもちょっと嬉しい。
この白いタイツの心地良い肌触り。
「まさかこれが自分の脚?」
彼が見つめるその先には、白いタイツに覆われた、均整のとれた、無駄のない脚がありました。
それは、まさしくバレリーナの脚そのもの。
続いてバレエのチュチュも体に当ててみる。
「オッケー! ハイ、そのまま、じっとしててね」
奥さん、旦那にポーズを取らせ、描き始めます。
全てはここから始まってしまいました。
女装させると「うちの旦那、結構いけるじゃない!」
と奥さんゲルダも、ゲームを楽しむように、旦那を着せ替え人形みたいに取り扱います。
ついでに「メイクもやっちゃえ!」
その勢いで奥さんは、女装した旦那を伴ってパーティーへ繰り出します。
会場に着くなり
「まぁ~、素敵なお友達ねぇ~、どちらのお嬢さん?」
と、女友達からも尋ねられます。
フフフ。
こんなに「綺麗な女」に変身させたのは、自分のアイデアとメイクの実力。
奥さんの思惑は大成功。アーティストとしての面目躍如、といったところでしょうか。
パーティーは盛り上がります。
やがて旦那のアイナーは、あることに気づきます。
パーティー会場の男性の視線です。男たちは自分に向かって微笑みかけてきます。その快感。
ちょっとの間だけ「女の子ごっこ」をするつもりだったご主人。
しかし、これが、ご主人アイナーの中に眠っていた「女である私」を目覚めさせてしまったのです。
やがて彼は、普段から女性の姿で生活を始めます。
もう後戻りできない。
「やっぱり自分はどこかおかしいのか?」
夫婦は病院に行きました。
このお話、今から90年ほど前のことですよ。
当時、男が女の格好するのは「ホモ」「変態」「異常者」扱いされていた時代です。
21世紀の今でさえ、いわゆる「LGBT」への偏見の目が、根強く残っている現実があります。
それが90年前の世の中では、それこそ、もう、人間としての市民権さえ剥奪されかねない。
当初、夫婦は精神科へ通いますが、やがてドイツに「性」に関する名医がいるとの噂を聞きつけます。そこで夫婦はドイツのドレスデンへ直行。
そこで医師から提案されたのは外科的な治療でした。
「手術は二度に分けて行います。まず、ご主人の男性器を切除し……」
名医は偏見の目を持たず、丁寧に丁寧に説明してくれました。
ついにアイナーは、本当の女となるために決意します。
「私は、もうアイナーじゃない。リリーです。女性として生きていきます」
本作は、たいへん格調高い、気品溢れる作品です。
変なエロさや、いやらしさはなどは全く感じないんですね。
これはきっと原作の良さ(ちなみに本作は実話です)そして丁寧な脚本の仕上げ。
作品を作る視線、主人公たちを温かく見守るスタッフたち。
更には、映画全てをまとめあげた、アカデミー賞監督トム・フーパーさんの手腕。人格者としての品性の良さ。
それら全てが相まって、こんな素晴らしい作品にしあがったのでしょうね。
時折、風景画のように挟まれる、デンマークの街並み。
朝の日差しの清々しさ、あるいは夕暮れ時、セピア色に染まるロッテルダムの風景。
ただ、もう、ずっと、鑑賞していたくなるような味わい。
まさしく絵画そのものです。
また、画家のアトリエの中での「ほんのり」「ふぅわり」とした明るさ。
照明スタッフがこういうところ、実にいい仕事してますねぇ~!
かつて伊丹十三監督が、ため息まじりにこう言いました。
「ヨーロッパの監督はいいよな。街を映すだけで映画になっちゃうんだからね」
ほんとにその通り。
街並み、それ自体が、ひとつの美術館とさえ言えるほどです。
歴史とその土地の文化を雄弁に物語っていますね。
さて本作では、衣装にも注目です。
1920年代の女性たちが身にまとう、当時最先端のファッション。
そのバリエーション、センスの良さは特筆すべきものです。
シックで気品があってお洒落なんですね。とっても素敵です。
20世紀に入って最初の世界大戦。
それは、人類が初めて体験した大量殺戮戦争でした。
そのあまりの凄まじさ、悲惨さ故に
「もう二度と世界は、あのような愚かな戦争は起こさないだろう」
当時を生きた人々は、皆そう思ったのでした。
「もう二度と、あんな馬鹿な戦争は無い」
その安堵感は、敗戦国ドイツ以外の国、特にフランスなどで、顕著だったように思われますね。
芸術家にとっては、まさに天国のような時代が訪れました。
パリでは芸術家たちが、生き生きと活動を始めます。
ちなみに、日本の「FOUJITA」藤田嗣治が脚光を浴びたのもこの頃。
狂乱の1,920年代と呼ばれた「エコール・ド・パリ」が花開いたのです。
文化、芸術の都「パリ」
その影響は、本作の舞台である、デンマークにも大きな影響を与えていたことが伺えます。
そういった意味で、本作は、アート系映画としての資質さえも兼ね備えております。
また、さりげない音楽も大変趣味がいいですね。
本作はこのように「欠点を探すことが難しい」ほどに、よく出来た作品なのです。
主人公リリーを演じた、エディ・レッドメイン
本当によく演じました。
才能ある画家でもあり、良き夫だった男性を演じます。
さらには、我が身の奥深くに閉じ込められていた「女性である自分」に気づく。
その控えめな演技。
これは監督の演出力と、役者の波長が共鳴した奇跡なのでしょうね。
いやぁ~、もっともっと語り尽くしたい。
そんなことよりも、早く本作を劇場で、ご覧になってみてください。
なお、私が見た劇場では、男性は私を含め、二、三人ほど。
あとは、全て女性でした。
私の前の席に、若い女の子たちが四人、連れ立って来ていました。
その娘たちは、エンドロールが終わり、劇場の照明がほのかに灯るまで、誰も席を立とうとはしませんでした。
ずっとこの作品の余韻に浸っていたようでした。
私も、この静かな余韻を誰にも渡したくない、とさえ思いました。
そして、ハンカチを取り出し、こっそり瞼を拭いました。
誰にも見つかりませんように、と願いながら。
ジェンダーを真正面から
愛と美の美しくさ
俳優の動きに注目
ゲルダはそして母になる
綺麗な男性、エディ(リリー)
『リリーのすべて』を観る。世界で初めて性適合手術を受けたリリーのお話。エディ・レッドメイン、カッコイイし綺麗だなぁ。最初は男性の格好をしているにも関わらず、メイクや持ち前の中性的な甘いマスクで既に女性っぽい。イチャついててもほんわかした雰囲気を醸し出している。その後は自分の性について悩んだり奥様も混乱したりするも、壮絶なパニックに陥ることがないので観ていられる。あれが喚き散らしたりしているとまた印象が変わってきているのかもしれない。個人的にはこのままの方が安心してみていられる。衣装がとにかく綺麗で見惚れてしまう。リリーのデンマークでのお友達で同性愛者のヘンリク。演じるはベン・ウィショー。彼が出てくるとテンションが上がる。そんな彼も実生活で同性愛ということを公表している。難点がちょっと。同一性障害というよりも多重人格のような印象を受けてしまった。途中で“役割”という言葉が出てくるが、それ以外は人格が出てくる、といった2つの人格があるような演出がなされている。
トランスジェンダー
邦題もちょっとあれだし原題もうーん。とは思う。けれど内容自体はよかった。
トランスジェンダーというトピックは最近ますます社会に出てきていると思う。この映画は初めてトランスジェンダーした男性の物語。いろんな葛藤があって自分自信もすごく辛かったと思う。けれど同じくらい辛かったのは妻。私はリリーよりも妻の方に焦点を当てて観た。愛する夫が急に異変を感じ始めリリーとして生きたいと決心する。夫を愛してるし妻のことも夫は愛してる。でもリリーとして女性として生きたい。複雑だったと思う。ましてやその時代では前例がほとんどなかったんだと思う。そんな中いろんな思いはあったけれども、どんな時も一緒にいた妻。どんなに投げ出したくても一緒にいた妻。私は夫の葛藤より妻の葛藤に感動した。
エディーが出てるからもあって凄く話題になって周りでもたくさんの人が観たと言っていた。感じたことは人それぞれだけれども、何かの役に立って欲しいと思う。
笑顔が切ない
エディ・レッドメインが…
愛だけが理由ではない
1920年代というまだまだトランスジェンダーの概念がない世の中で、男性(アイナー)から女性(リリー)に性転換した夫と、それを支えた妻の物語。
妻の側からすると、愛する夫が殺され、かつて夫だったものから「あなたは私の世話をしてくれて感謝してるけど、もう夫はいません、女としての人生を生きています」と残酷な通告を受けて、それでも夫だった人が死ぬまでその側にい続けた物語。
彼女がそうした理由はなぜだったのだろうか、と考えながら映画を見ました。
愛だけでは説明が足りないと感じる。友人としての愛に変わったというのも足りない。ショッピングに行くとか、いわゆる友人とすることを2人はしてないからです。
妻がリリーの側にい続けたのは、リリーが妻の芸術上のミューズだったからなのだと思います。リリーをモデルにした絵は高く評価されました。妻は妻であるのと同時に画家であり、夫を失った悲しみを超えて、画家であることを選択した。
ただ、メリットを理解して納得しての選択ではない。妻の中にはずっと葛藤があり、葛藤の正体を彼女自身、わかってはいなかったと思います。自分がどうしたいのか、どうするべきなのか、わかってはおらず、いわば状況や感情に流されて、リリーの最期にたどりついた。
(なお、ひとりの女であることは、友人ハンスが埋めてくれた。ハンスはいわば当て馬ですが、強面なのにおとなしく当て馬役をこなしているところが、個人的には好みでした。)
リリーはトランスジェンダーの歴史的シンボルだけれども、それを実現させた背景に、深い葛藤と曖昧な意思を持った強くも弱くもある人がいたことが、この作品の美しいところのように思いました。
美しい。
性同一性障害。
もちろん詳しいことは知らないし、認識としては、「3年B組金八先生」で採り上げられ、上戸彩が熱演したもの、という程度である。
世の中には多くの性同一性障害の人がいて、差別や偏見にさらされているとしたら、胸が痛い事態である。
ただ、僕の知り合いにはいない。
そんな僕が観ても、リリー(エディ・レッドメイン)の苦悩には胸がしめつけられる。
リリーのそばにいたゲルダ(アリシア・ビカンダー)の苦しみも察するにあまりある。
ときにあかるく振る舞う両者には、ただただ頭が下がる思いである。
トム・フーパーの演出のキーは美しさである。リリーの美しさ、ゲルダの美しさ。
コペンハーゲン、パリなどのヨーロッパの美しさ。
そして、男だったリリーが描き続けた故郷の美しさ。
絵画がモチーフのひとつであったが、カットのひとつひとつが絵画のようであった。
まさに名画の名にふさわしい。
エディ・レッドメインが素晴らしい。もし「博士と彼女のセオリー」がなければ、オスカーは彼に渡っていたはずで、レオナルド・ディカプリオの戴冠はまたもやお預けになっていたであろう。
それくらい、彼は素晴らしかった。
山無し落ち無し意味無し。
見所はエディ・レッドメイン、それが全ての一本。
物語が進むにつれ、しぐさ・表情までが女性にしか見えなくなってくる、これぞ役者魂を感じた。
映像・色彩も静かな中にも情熱を感じさせる画面作り。
何よりも評価したいのは日本公開に当たって「ぼかしで逃げなかった」事だろう。
本当に大事な場面を、そのまま映したことは作品にとって本当に幸せなことだと思う。
(「ぼくのエリ」をもう一度やり直せ!)
ただ、物語としては驚くほどに平板で全てがあっさりと流され進んでいってしまう。
主人公とその奥さんの心の葛藤も、演出上は非常にあっさり流され。
乱暴に言ったら「わがまま(元)男に、周りが振り回されるだけ」になってしまっている。
当の本人はやりたいことやりきって、好きにおっ死ぬっていうオチ。
コレなら映画に別にしなくても…と思ってしまった。
事実ベースの話を過剰にドラマッチクにしろとは言わないが、もう少し映画的演出は欲しかったのではなかろうか。
淡々としすぎて、自分としてはごくまれな恐ろしく眠くなった作品。
全184件中、101~120件目を表示