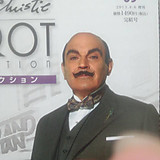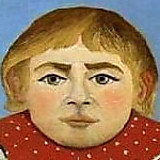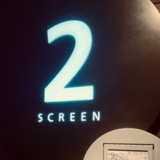ハッピーアワーのレビュー・感想・評価
全37件中、21~37件目を表示
大河ドラマのようでした。要所で大笑いしました。
早寝早起きの自分が、何年かぶりに夜更かししてしまいました。ときどき、顔が暗くて見えないまま話しつづけるショットがあり、それが妙にミステリアスで最初に引き込まれました。これはもう数回みて考察してみようと思います。心理学でいう「ペルソナ」のことかな?そりゃ考えすぎかな。
主人公4人でもあり、1人1時間は必要であるとして、決して飽きずに、大河ドラマ5-6話分を一気に見終わった気分でした。4人とも女性だが、若くして成熟しているともいえるし、しかし実はまだまだ若く、成長の余白と希望がある。その一方、さくら子の義母は生き抜いた老人の知恵がある。彼女は常に論理を超えた存在にも見えた。そんな対比でみていました。また主人公らは決して回避せずにもがいており、逞しく、その振る舞いはむしろ羨ましいと映った。その点、男どもは何とも脆弱で、女性の手のひらの上で泳がされているだけかいな、と何度も大笑いしました。
キャスティングは最大の演出
なんだか凄いの観ちゃいました。3部構成5時間超。
全く飽きない。眠気もない。引き込まれて引き込まれて。
まさかね、まさか、こんな展開になるとは?の始まりのシーンから一気です。
一部、二部、三部 全てスキ無し、無駄無し、息つく暇なしです。
休憩時間中の続きが待ち遠しい気持ち、こんな気持ちいつぶり?
人間関係や、人間同士のコミュニケーション(友人、夫婦などなど)の根幹となる人間の気持ち、価値観、考え方、そこから導かれる生き方・・・こんなこと永遠に解き明かせないんじゃない?・・・なことに真正面から向き合って、ほんの一部ではあるけども、人間そのものを切り取る・・4人分。
そりゃ、5時間でも足りないですよね(笑)
まず、演出のキーであるキャスティングが素晴らしい。演技経験がほぼ無い方々を起用されたことが、作品にリアリティと説得力を生んでいると思います。テイク数も少なかったんじゃないのかなー?なんて勝手に推測。生々しく、体温を感じるんですよね、映像から。
演者のみなさん、最初はセリフ棒読み気味ですが、どんどん演じることに慣れてきた感じになり気にならなくなります。棒読み気味でも朴訥な感じが場面によっては緊張感、緩和を生み出してますし、あのなんとも形容し難い「間」。あれは演出なのか?いやいや、長回ししてるので演者たちが作った、いや経験がないからこそ生まれた「間」なのでしょう。
演技としては稚拙と言われるのかもしれませんが、僕はとてもよかった絶妙なのです。その存在が。
また、カメラワークは単調のようで、顔のアップ、切り替え多用で動きがうまれ、会話劇をより深く描いていると思います。なぜなら女優陣含め皆演者の表情が良いんです。
役柄と同じ生活されてるのでは?なんておもっちゃいます。全員。
あぁ、ここまででかなり書いてしまいましたが、もう少し。
さてさてお話。よくもまぁこんなお話つくれましたね!と驚嘆です。日本映画すごいじゃん!
4人の37歳の女性がそれぞれ異なる生活基盤のもと問題(問題の種)を抱えつつ生活していく。
それぞれの繊細な心の動き、微妙な違和感、心の中の揺れ動きを映像としてを丁寧に丁寧に、そうですねぇ例えるならひと針ひと針刺繍を作っていくかのように描いていきます。
若干、「ん?」と思うようなイベント出来事はあるものの、あまり気になりません。出来事で成り立つストーリーではなく、出来事によって変わる心情がメインだからかな?
本作は自分を知るとは?他者を知るとは?。
他者の中の自分。他者と対する自分。(色んな)社会の中における自分。それらを通じて「自分」を見出し、「自分に素直に」次の扉を開くまでのお話だと思います。もちろん他者も知る中で。
自分を理解し、認めて受け入れることはできているようでできていない。・・・自分自身と向き合う勇気がないからなのか?自分をわかっていると勘違いしているから?
いや、何かから(ひとそれぞれの手枷足枷)解き放たれていないからかもしれないです。
自分を理解し、受け入れ自分に素直になる。。。。素直に行動する。。。素直に求める。。。
その結果はもしかしたら一般的に言われる幸福ではないかもしれないし、一般邸に言われる苦労しかないかもしれません。自身の置かれている立場や環境によって変わるのでしょう。
しかし自分に素直になるとは揺るがない強さを手に入れることだとも思います。
でも、人間としてはもっとも幸せ(ハッピー)なのかもしれません。それが。
そして、わかったと思っても、また新たなことも発見したり調整が必要になったりするのでしょう。
そんなに単純じゃないですからね、人間なんて。何度も繰り返すのでしょう。他者と自分の「解り合い」を。
他者と自分の「解り合い」
それこそが、自身を前に進めるためのものであり、他者を前に進めるためかもしれません。
その時間こそが「ハッピー(を作る)アワー」なのかも?
それを実現してくれるであろう他者との時間は友人との時間。
短いながらも「ハッピー(な)アワー」。
ナイスな題名だと思いました。
こーいうドラマ、地上波で多くの方に見てもらいたいと心から思いました。
人間関係がやたら殺伐感が増し、コミュニケーション不足が言われている昨今だからこそ。
最後にこれからご覧になる方々へ。
一部で描かれるワークショップはしっかりと観てください。本作のテーマがぎゅっと詰まっています。
濃密な時間
平凡の大功徳
夏目漱石は「文学論」の中で、J.オースティンの小説を「平凡の大功徳」と評したそうだ。
この映画では、普通では考えられない長時間にわたって、J.オースティンさながらの“卑近”な話が、「寸毫の粉飾」を用いずに描かれる。
どこかで聞いたような愚痴や口げんか、「こういう奴、居るな~」という登場人物。
さらに、第1部の「ワークショップ」や第3部の「朗読会」のシーンは延々と続き、少し居眠りした後に目覚めても、まだやっているほどの長さであった。
その結果、自分の中の“日常感覚”が生々しく反応する。映画を観ているのに、実生活の中で聞いているような感覚に陥るのだ。
あたかも自分も参加しているような、あるいは、“盗み聞き”しているような感覚だ。
そのことで、漱石の言葉を借りれば「奇なきの天地を眼前に放出して」、「客観裏に其機微の光景を楽しむ」効果が生まれる。
“劇的”な演出とは、真逆の手法だ。
時間感覚も、マヒしてくる。
頭と目をフル動員して、激しい展開を期待する映画なら、次第に疲れてくるだろう。しかし本作品の、実生活のひとコマのような“まったりした”時空の中では、317分でも長く感じない。
上記と関連して、この作品には「謎」がある。
「打ち上げ会」のシーンなどで、役者の台詞が、しばしば“棒読み”になるのに、なぜ面白いのか?である。
台詞のあいだ、役者の身体の動きが止まっていることも多い。
現実には、人間は考えながら、そして身体を動かしながら喋る。他人の話に割り込むことも、しばしばである。
だから、あれほど抑揚の乏しい、言語明瞭かつ理路整然とした会話は、現実にはあり得ないし、映画の台詞としてさえ異常である。
身体の動きを止めた“棒読み”は、役者が“素人”だからというだけではなく、監督が積極的に求めた演技だろう。
この場合、演技の要素は、すべて台詞の中身に存在する。
だから観客は、もはや映画でありながら映画を観ているのではない。複数人による“朗読による演劇”を観ているのだと思う。
一方、“棒読み”とは逆に、ハッとさせるほどに、自然な発声による会話も出てくる。
冒頭の「お弁当」のシーンや、「朗読会におけるQ&A」のシーンなどは、現実世界の何かのトークを、そのまま脚本にねじこんだと思われる。
脚本家が、頭で書いたのではないはずだ。
映画館の客席には、女性も目立った。
しかし驚いたことに、脚本家は3人全員、男らしい。その男たちが、女性の“生活”を描く。
この作品が本当に成功しているかどうかは、女性がどう感じたかで決まると思う。
自分としては、ビターな家族関係や性愛をテーマにした“だけ”の本作品は、非生産的で面白くはなかった。
ただ、各々の登場人物が、ズレながらも絡み合い、複雑な経路を辿りながら、伏線を回収しつつ、それぞれのカタルシスへと向かっていく“織物”のようなストーリーは、とても狡猾に吟味されていると思う。
自分としては、結末よりもそこに至るプロセスが面白い。“あけすけな”独特の会話劇は、間違いなく一見に値する。
丸1日費やしたが、良いものを観た。
【自分と向き合うことと、解放感と】
自分自身と、自分の奥底に潜むものと向き合うのは大変だ。
だが、そうしないことには、自分のことを好きになれなかったりする。
この長い長い作品を観ながら、僕達は自分自身を理解しようと試みることになるのではないのかと思う。
女性は女性としてシンパシーやエンパシーを感じるだろう。
また、男性は、女性4人が主人公だけれども、その視点で男性としての自分に共通する部分を見つけたり、当然、彼女たちを取り囲む存在としての男性を通じて感じるものもあるだろう。
この作品を観た、その日の夜、Eテレの100分で名著「ディスタンクシオン」の最終回で、著者である社会学者ブルデューの随分古いインタビュー映像が流れた。
移民労働者に関する著作に収められた移民との対話を読んで、自分自身を見出したという人達の反響が多かったこと、中には、自分を理解することが出来たという女性もいたことが語られていた。
大袈裟な言い方かもしれないが、この「ハッピーアワー」は、登場人物を通して、僕達を自分自身に向き合わせる、そんなエネルギーを秘めている気がするのだ。
僕は、ジェンダレスな社会を志向する方だ。
ただ、この作品を観ながら、「批判的な意味ではなく」、ジェンダーから逃れることは、改めて難しいなと感じるし、そして、この事実と折り合いをつけながら生きていかなくてはならないのだろうなとも思う。
話は変わるが、鵜飼がボランティアをしていたと言っていた東日本大震災の被災地、神戸、そして、有馬は、もしかしたら、象徴的に使われたのではないか。
神戸は阪神淡路大震災で被害の大きかった場所だし、有馬は、こずえの朗読でも出てきた通り、有馬高槻断層帯でも知られる場所だ。
この作品は15年の公開だが、18年の大阪北部地震は、この断層の一部が動いたものだ。
僕達は、生きていく中で、悩みなど様々な歪(ひず)みを抱えて過ごしている。
純の起こした離婚裁判は、長いこと蓄積された断層の歪みの反動のエネルギーのようなもので、更に、これに突き動かされたように、桜子、芙美、あかりの人生も揺り動かされる。
活断層が動いた後の余震のようだ。
何事もないように立っていたビルや住宅、道路や、畑や田んぼにも亀裂が入り、元に戻すのは容易ではない。
だが、そこに折り合いをつけて、また、僕達は生きていかなくてはならないのだ。
前段で、ジェンダーと折り合いをつけながら生きなくてはならないと書いたが、そもそも、僕達の存在そのものが微妙なバランスを保ちながら生きている。
あの、鵜飼がワークショップで見せた、一点立ちの椅子のようだ。
あっと言う間に、倒れてしまう。
丹田に耳を当て、耳を澄まし身体の音を聞いてみたり、背中を合わせて呼吸を合わせて立ち上がることが出来て、楽しくても、何かを感じても、それは、何かを理解したことにはならない。
やはり、言葉は重要だ。
だが、時として、言葉は耐えられないほど軽く、心の奥底を表現するのが難しかったりする。
こずえの小説の中に出てくる拓也を模したのではないかと思われる人物。
こずえの気持ちを窺い知ることが出来ても、こずえが拓也に直接好きだと言う方が、本当はより伝わりやすかったり。
だからといって、更に踏み込んで、誰かと肌を擦り合わせ、肉体を合わせても、本当に欲しい回答を得られるわけではない。
有馬で4人の写真を撮ってくれた滝好きの女性。
父親が祖父の死を隠していたことを話す。
父親はよく嘘をつくのだと。
純は、それを聞いて何を感じていたのだろうか。
僕は嘘ではなかったのでないかと思う。
父親は、祖父が生きていると信じたかったのではないかと。
純が、公平に対して起こした離婚裁判には、真実じゃないものもあるのかもしれない。
しかし、溜まりに溜まった歪(ひず)みから生まれた公平に対する感情は真実だ。
何かを掴みかけていると言って、身重で一人旅立つ純。
事故を起こした拓也にざまみろと言ってやると話す芙美。
家を出ていかないし、良彦に謝ることはないと言い放つ桜子。
怪我をしながら、複数の男と寝て、桜子に詫びてやり直したいと、純の帰りを待って、また、旅行に行きたいと言うあかり。
自分に向き合って、何か吹っ切れたような4人は、前よりも、もう少し、いや、もっと自分を好きになっているに違いない。
※ 年末で過去放送のドラマの再放送オンパレードだったりするが、この作品は夜中にでもテレビ放送してあげたら良いのにと、日本中の人に見て欲しいと思うくらい、素敵な作品でした。
あっという間の317分
引き算が凄かったな
気持ちを見せ合う難しさ
静かな映画、なのに監督さん、描きにくいもの、言葉になりにくいものをたくさん詰め込んで、5時間の時間量で描ききってやろうと、力技です。
友人、親子、夫婦といえども、心を素っ裸でさらけ出せるほど鈍くない。さらけたところで理解しあえる保証もない。トランプ♣︎の「神経衰弱」みたいに、気持ちのカードをめくって、答え合わせ。違うとみんな揺らぎます。淡々としてますが、ほんとは怒濤の嵐が吹き荒れている。でも決して表には出さず。静けさ、緊張感。
本音を探り合い、答え合わせするのは疲れる。ガッカリすることに怯えて一人、じっと耐えています。男たちは、自分とすら向き合わない。自分の気持ちを理解する、という発想すら封印。向き合うと、淡々と進めていけなくなるからね。万が一にも弱さに気付いたら、大変だ。キャパオーバーで、精神が壊れ、日常が壊れかねないものね。
見ざる・言わざる・聞かざる、というのが日本では先人の教え。器が小さいなら、最初から入れるな。先人は、厳しいですね。登場人物の一人の妹が「兄貴は、空っぽ、というのがバレないようにしてるんじゃないですかね」と評していた。リアリティあります。でも空っぽだから出来る役割を果たしているようです。
時に限界超えて、マグマが噴き出します。
ドロドロと空っぽ、どちらがマシか。私もわかりません。
どう生きていけばよいか、正解は簡単にはわからない。わかった人がいても、その人の正解が、自分の正解かわからない。
やっと見つけたと思っても、永遠の正解でもない。一瞬ですね、ハッピーアワーは。
ですが、みんな、意外とそれぞれに根は強い。
そして冷たい訳でもない。お互い心配。気にしてる、良くも悪くも。で、それがお節介や押し付けになっていないか、またチェックし合うのですが。気遣いは、「気にしぃ」となり、もう無限ループ。サジ加減はそう上手くはできない。近付いたり、離れたりしながら、流れていく。
コウヘイさんという、じゅんさんの夫、この人だけは私、本当に怖い。何が怖いって、離婚を望むじゅんさんに対し、冷静に悪意なく、「理解出来るまでは諦めない」精神で追いかけ回し、そこに研究者魂を発揮するところです。初めて恋したのですかね...
一生をかける気ですね、おい、それ愛じゃないよ。
完全なストーカー行為、相手の自由を侵害してるぞ。
頭良くて、小説の読解力も高いのに、コウヘイさん何故わからぬ。
執念。飽くなき探究心。理解できれば、対象を手中にできるという達成意欲と向上心か。
「こうしかできない。」
とコウヘイさん。
まあ人間ってそういうものかもしれませんね。
その方が楽で、ハッピー。一人よがりですが。
他の登場人物も「こうしかできない」症候群。
一人のハッピーアワーを、誰かとのハッピーアワーにしようと、実は健気に努力して。そして上手くいかず、もがいた挙句、諦めて。でもまた信じようとして。
愚かかもしれませんが、絶望しないことだけが、生きるには必要。
ハッピーアワーの夕焼けは、一人で見ても充分美しい。なのに誰かと見れたらもっと美しいかも、とつい想像して自分で寂しさの種を蒔く。でもまたやがて、そこも抜けて、もう一度夕焼けの美しさに気付く。幸せにも正解がないのでしょうね。
演じることの彼方へ
上映時間5時間17分、やはり映画館へ行くのに少し怯んだのは事実。しかし冒頭からの素晴らしいシーンに引き込まれてしまい、ただただこの映画を観ている時間がこのままずっと続いてほしいと思うようになりました。でもプロの俳優さんではなくほぼ素人さんらしい。演技経験不問でワークショップに応募された人たちから選考を経て17名の方たちからスタートしたとの事。しかし演者と役がぴったりと重なっているかの様なこのリアリティー感は何なんだろうと感ぜずにはいられません。
映画の「演技」って何なんだろうと、改めて考えた時、役者はその役に恰もすっぽりと入り込み、観る人に如何にリアリティーを感じさせるか、という事になるのかも知れません。プロの俳優は磨き抜かれた演技で様々な役柄をその役に成りきり、役作りをします。種々雑多な役を私達の前にその人に成りきったかのように演じます。その演じることの集積の結果として映画はフィクションであるにもかかわらず、私達に恰も「本当」のことであるかの様に説得性を持ちます。役者が「役者であること」の必然性がここにあるかと思われますが、その演じることの方法を、ラジカルに覆してしまったのが「ハッピーアワー」では、と思ってしまいます。ほとんど演技経験のない人を集め、プロの役者とは次元の異なった演技の付け方《一例:シナリオの読み合わせの際、抑揚も付けず感情移入もせず棒読みを繰返しながら台詞を覚えていく》によって次元の異なったリアリティーを私達の前に差し出されたこの映画は、奇蹟としかいいようのない衝撃でした。
冒頭三十才代後半の女性四名がケーブルカーに揃って横並びに座り摩耶山へと登って行くシーン。観客である私達も彼女らと共に誘われるかのように、山上の映画という名の異空間の世界へと運ばれる。晴れわたっていたのに、頂上は白い霧雨に包まれ、期待していた眺望は望むべくも無い。彼女らは雨を凌ぐ東や風の休憩所で手作り弁当を前にたわいのない話に耽っている。しかし周りは濃霧に閉ざされ、この世から何か孤絶されたような不安な不穏なものに纏わり憑かれたかのように予感させられる。そしてケーブルカーで降りて行く彼女らを待っているのはどのような世界なのだろう。
四名の主人公の各々の人生が語られ始め、徐々に日常から非日常への転変を、「省略」という映画技法を敢えて駆使ぜず、たゆたゆ如くゆっくりと一人ひとり追っていく。
ということで5時間17分になっているのでしょう。
最後にお願い! 長尺ものですがどうかもっと上映して下さい。関西では神戸元町映画館で昨年12月と今年4月、京都の立誠シネマで2月に上映されただけです。それ以外の館主さん、宜しくお願いします。
夕暮れと朝焼けの物語
私の家族は映画を観ながらよく寝る。8割は寝る。(最近では『シビル・ウォー』で寝てて、すごく面白いのに睡眠障害ではないかと心配になった。)
本作上映時間、5時間27分。
プロの俳優さんではない方々が主演。
冒頭、公園のシーンがあまりにも棒読みで心配になる。これで5時間持つの?と。
朗読会のシーンなど眠気さそってんのか?と思わせる場面も延々と続く。
確実に寝るだろうなと思いながら家族と一緒に観た。が、一睡もしなかった。映画に釘付けだった。凄い映画だった。
—
「ハッピーアワー」。
居酒屋などで「ハッピーアワー」と称してビール半額などのサービスをやってたりする。たいていは開店まもない夕暮れ、17〜19時くらいだろうか。
本作は、30代後半、人生の夕暮れにさしかかった女性たちの物語。
夕暮れ…昼とも夜ともつかない。変わり目であり分岐点の時間帯にさしかかった人たちの物語。
—
親友で何でも分かり合っていると思っていた、あかり、桜子、芙美、純の4人。だが、互いに知らない素顔が少しずつ見えてくる。
最初は、アマチュアの方々の、こなれてない硬い演技が気になってしょうがなかった。だが所々、彼女らの真情が垣間見えるような、生々しい表情が映し出され、そのギャップにドキっとさせられる。彼女らの硬い皮を剥いで素顔を掘り出すような臨場感がある。登場人物たちが役の設定上被っている「硬い皮」であり、演者本人の皮でもある。「素顔を晒した」とこちらが感じても、それが本当の「素顔」かは判らない、判ったつもりは許さないスリリングさがある。
桜子、純が連れ立って街中を歩くシーンがあって、その姿があまりにも街並になじんでいて(有名は俳優さんだとどこかしらオーラがあって群衆の中で目立ってしまう)、ああリアルだなあと思う。観続けるうちに,私の知人もこういう表情するなあとか、前にどこかで会ったことあるような人たちだなあという親近感・既視感も湧いてくる。そういう意味でもリアルである。リアルな存在感が増していくのだが、その一方、麻雀のシーン(「はじめまして純です」)やクラブのシーン(担ぎ上げられるあかり)など、普段の生活ではこんなことしないだろうというシーンもあって、彼女らがリアルな人物ではなく、映画というフィクションの世界の住人であるという当たり前のことに気付かされたりもする。どこにでも居そうで、どこにも居ない人たち。
彼女たちを捉えるアングルは、突発的なハプニング的なものではなく周到に考え抜かれたものであり、構図も極めて映画的な企みに満ちている。リアルさとフィクショナルな映画的企みが混然一体となって迫ってくる。
—
終盤、芙美が朝焼けをバックに歩くシーンが印象的だった。
人生の分岐点にさしかかった彼女たちは「選択」する。
分岐点で惑って立ち止まっていた彼女らの時間が再び動き出したような気がした。ああ、これは人生の夕暮れの物語ではなく、何かが動きだし始まる物語だったのだと思った。朝焼けの物語だったのだと。彼女らの選択が「良かったのか・悪かったのか」が重要なのではなく(この映画は「判ったつもり」で断を下さない謙虚さに満ちている)、始まる事が重要だったのだと。
女性たちが毅然と歩き始めるなか、対する夫たちは分岐点で立ち止まったままだ。その対比もまた、残酷さと隣り合わせの映画的な面白さに満ちている。
5時間越えの長編とは思えないスピード感。
演技とは何か
もともとコミュニケーションというのはぎこちないもの
この映画が女優賞を獲得したことは衝撃というほかない。というのも、ひとりひとりの演技は非常にぎこちなくて、はっきりって上手くない。決して下手ではない。内面というものを巧みに表現できているような印象をもつから、むしろ素晴らしい表現をしているといえる。ただ、その台詞回しは非常にぎこちない。でも、それが不思議なリアリティーを生み出しているように感じてしまう。何せ、この世の中のコミュニケーションというのは、実はぎこちなかったりするわけで、上手い役者のようにはなかなか振る舞えないものであるのだから。
この映画の最大の難点はなんといってもその長さ。すべてを見ようとすると5時間以上もかかってしまうわけで、気軽にというわけにはいかない。正直あんなに長い必要があったのかどうか大いに疑問に思うところもある。しかし、その脚本はその長さの分だけ濃いものがあり、手を抜いていたずらに長くしているのではなく、詰め込みたい内容があるから長尺になってしまったという意気込みは感じる。ただ、さすがに削れる部分はあったように思ってしまう。
導入部分、正直睡魔に襲われた。しかし、語られるセリフの量が増えるに従って徐々に魅せられていく。人々の会話の面白さ、会話の中で巧みに捉えられるひとりひとりの表情、それらが見事に融合して、人間関係の面白さがどんどん伝わってくる。
話の内容は、現実世界に起こりうるものばかりで、突飛な展開というのもそれほどない。しかし、どこにでもあるような展開されているはずなのに、人々が織りなす人生模様が非常に面白い。そう感じてしまうのは、見事な脚本があったからなのかなーと感じた。
後半もやや退屈感を感じてしまう。それまで、会話や表情などで丁寧に描かれていたものが、それこそ特殊な出来事や展開に頼ろうとした意図が見え隠れしていて、それがかえって自分の興味を削いでいったように思う。展開を動かしたこと自体に不満はないけれど、丁寧な描写が徐々に薄れていったように感じてしまったことが、後半の退屈感につながっているように思う。
それにしても、この映画がどのように構築されていったのか、その演出とか撮影風景なんかが全くイメージできない。まるで、そこら辺で起こったことをそのまま編集したような印象を持ってしまう。それくらいリアリティーがあったし、それゆえの女優賞なのだろう。自分としては、勝手ながら、監督賞が最適かなー、と感じた作品。
昔、日本語ペラペラのイスラエル人に 「真っ白なカーペットに赤いイン...
昔、日本語ペラペラのイスラエル人に
「真っ白なカーペットに赤いインクを落すようなものだ!」
と非難された事があります。
本作もそんな感じ。
仲良し30代後半の女性4人組にある事が明かされ次第に波紋が広がっていく。
ホラーでもサスペンスでもなく、
今の時代、この世代に起こり得る人間模様が描かれている。
冒頭、4人がピクニックに来て土砂降りの中お弁当を食べるシーン。
それは彼女達の波乱の始まり。
バツイチで看護師で姉御肌のあかり、
主婦で中3の息子のいる桜子、
キュレーターで編集者の夫を持つ芙美、
そして既婚の純。
舞台は神戸。
神戸を知る人は知っている場所が映るし、何より言葉やイントネーションが心地よく感じるだろう。
濱口作品は『親密さ』しか観ていないけど独特な作風で
『親密さ』でも芝居が丸々映されていたように
本作もワークショップやある女流作家の朗読会が丸々映されている。
自分も参加している体験ができるけど、逆に興味があって参加したワークショップや朗読会ではないから少し退屈に感じたり。。。
でも必要。
あとは別れのシーンや乗り物に乗ってのシーンが好きだな。
彼女達4人の着火剤的存在の脇役のセリフが棒読みで感情が見えにくいのも特徴。
ドラマチックな展開になりえるだろうシーンも冷静な気持ちになって新鮮に感じる。
317分の時間の中で彼女達の“ハッピーアワー”を探してみる。
街の居酒屋の“ハッピーアワー”の短い時間なのかもしれない。
真っ白なカーペットに着いた赤いシミをどのように落とすのか想像してみるのも悪くないと思う。
観る価値なし
俳優さんの演技は素人にしては見応えあり。特に女性陣はプロには出せない素人ならではの良さが引き立ち、映画の内容に合っていた。その分が星ひとつ。
映画そのものは駄作、5時間と3900円かけて観たのに残念、腹が立って仕方がなくて一晩眠れなかった。
普通の人の日常生活を単にトレースしただけの内容にエンターテイメントとしての映画の価値は見出せない。登場人物は自分の枠組みと思い込みの中だけで生活して、出来事は色々と起こるがそこに発見も気づきも変化もなく話が進んでいく。30代後半の女性仲良し4人組(独身、既婚子供あり、既婚子供なし、既婚離婚訴訟中)が織りなす学園ドラマ版のような映画。現実の方がもっと厳しく、あたたかく、複雑ですよ。人物の描き方にも深みがない。
観る側の立場に全く立たず作られた作品。浅い。
全37件中、21~37件目を表示