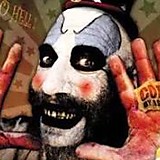この世界の片隅にのレビュー・感想・評価
全1071件中、841~860件目を表示
反戦映画としては秀作だが、うーん…
戦時下で暮らす人々の日常を丁寧に描いているのは素晴らしかったが、どうにもこうにも女性としてすずさんに全く共感できず。好きになった人ではなく見初められた顔も見たことのない人のところへ嫁に行き、ハゲができるまで義姉にいじめられても実家に帰らず我慢。夫との初夜のシーンなどは辛くて見ていられませんでした。女性は主体的に生きるな、というメッセージでもあるのか?と疑心暗鬼になるほど。
観てどんよりしました。
言葉にできない凄さ
22歳男ですが。
重い、思ってたより重いよ…
各種レビューで絶賛されていたので鑑賞。「ただの戦争映画じゃない、笑えて泣ける」というような紹介のされ方だったので、そこまでヘビーな内容じゃないのかな?と思っていましたが。
思ってたよりずっと重いよ…。確かに笑えるシーンもありましたが、やはり戦争を扱った映画。主人公に起きる出来事も、柔らかい絵柄にしては悲惨で。見ていて辛くなってしまいました。
映画の出来としては、登場人物に魅力があまり感じられなくて、特に感情移入も出来ず。ストーリー面も特段良かったとは感じられなかったので、絶賛されている割には…?というのが正直なところです。
とはいえ、戦争とはどんなものなのか伝えるために、終戦記念日の前あたりにテレビでやると良さそうな映画でした。
ごく普通
周りが過大評価し過ぎ。星5なんて付けれない。
主人公が嫁に行き、時限付き爆弾で右手と姪を無くし、故郷にも原爆落ちて、身寄りのない子供引き取る話。
戦争映画としては、ごくごく平凡。
すず役の声担当するのんがはまり役、コトリンゴの音楽も・・・
のんびり屋さんのすずが、開戦、節約、毎日続く空襲、そんな中で力強く前向きに、それでも楽しく生きていこうという物語。空襲や焼夷弾、ピカドンの閃光…戦争の怖さも描かれています。が、すずが絵を描くシーン、特に海のうさぎが跳ねてる絵のシーンが印象的でした。すず役の声担当するのんがはまり役、コトリンゴの音楽も・・・
銃後の戦争
2016.11.26 第1回鑑賞(1日数回あるうちの最終の上映で、やや多めな観客数)
その後、原作および絵コンテ集を購入
2016.12.29 第2回鑑賞(昼間1回のみで、ほぼ満員)
なんとか、パンフレットも入手。
ほぼ、情報がない状態で観た第1回と、原作を読んだ後の第2回では、少々印象が異なる。
第1回目でも、特に先入観もなく、りんと周作の関係性は読めた(おそらく、エンディングの部分で勝手に補完していたのかも)。
第2回目を見ると、逆に、ほぼカットで、すずも何も知らないままに描写されている感じ。エンディングの補足説明が本編を補完した好例だったのか。
1回目を見て原作を初めて読むと、ほぼ原作通りに感じていたが、2回目で確認すると、なるほど、随所がカットされている印象になる。ほんと、完全版を製作するなら、出資したいところ。
最悪、DVDだけでも・・・完全版を作れないものか。
本編は庶民の生活が淡々と描かれるだけの展開で、現在の3.11ならぬ、8.06あるいは8.15に向かう。
B29が飛んでくるまでは、のほほんとした雰囲気が続く。
空襲シーンはなかなかのもの。グラマン戦闘機による地上襲撃(航続距離がB29に比べれば短いので日本近海に航空母艦が出没していたのであろう)は、各地で行われていたので、祖母から話は聞いている。呉だけの話ではないはずだ。
この辺の、爆音、エンジン音、砲撃音は下手な戦争映画(邦画全般?)より、迫力、臨場感、恐怖を覚える。ここは映画館で見るべき。
本作の場合、その恐怖の後にも笑えたりするシーンがあるのだが・・・
S40~50年代、戦記ブームの洗礼を受けた世代なら、ほぼ何の解説もなく理解できる内容?ただし、庶民の生活にフォーカスしたような文献は少なかったような・・・
祖母からコーリャンを食べたと聞いたが、いまだ、どんなものか分からない・・・
物々交換で農家から作物をもらうような話は、よく聞いた。
惜しむらくは、上映館が(上映回数も)少ないのが悔しい。
昼間1回こっきりは、ない。せめて夜の回を追加してほしい。
「創作を現実に昇華」
いくらかの映画評論家・評価・レビューなども読んだ上で
落ち着いたので感想を書こうと思う。
基本的にこの作品は「創作を現実に昇華」した。
勿論、人によりそうと思わない場合もあるのだろうけど。
当たり前だがフィクションをノンフィクションと大多数が
錯覚するまでの作品などそうはない。
そういう意味で「創作」として「傑作」であろう。
原作は漫画であるためそのレベルにまでは達し得ない。
漫画というメディアは「ページをめくる」という
能動的動作により創作の枠から抜け出ることが
できないからである。
さらにこの映像作品は、映画のスクリーンの
大きさによる没入性(contextual visual cues)により、
「世界」として完成しうるのである。
DVDやBDでも面白いことは面白いだろう。
でもそれは完成品ではないのである。
強制はしない。
ただ、ぜひ映画館であの世界を体験していただきたい。
その経験は、きっとあなたの心の一部になるであろうから。
# https://twitter.com/connneko_kraken
# でつぶやいた内容と同じです。
2016年映画館で観た作品では最高の作品!!
この作品は単館上映作品なので、上映映画館はホームページでチェックしましょう。
ハッキリ言って素晴らしい作品です。
戦争映画は、ほとんどは静かな作品が多いものだと思っておりましたが、この作品の主人公すずちゃん(のん)はこの厳しい戦争時代の広島市・呉市で前向きに生きようとすることで、周りの人達も笑顔になれて生き生きと頑張ろうとする日常を描かれているストーリーが良くて、失うものはあるけども、負けずに頑張ろうとする主人公にちょっと泣いてしまいました。
主人公のすずちゃんのシャイで天然なところや1つのことを考えたら、周りのことを考えずちょっとしたハプニングが起こってしまうシーンは面白かったし、とくにどの登場人物もそうですが、目の表情が好きでした。そこをぜひ注目していただきたい。
お熱い恋のシーンもありますが、途中での水彩画や絵の具で描いた画像での演出シーンもぐっときたものもあれば、ホロッときたシーンもありました。(ネタバレになるのでこれ以上は言えませんが、要チェックですぞ。)家族とかとの共演シーンとかもいろいろいいのですが言えないのがくやしい。
劇中に流れる音楽も良くコトリンゴさんの曲もホンワカしていい曲です。サントラ買う予定。
この主人公の声を担当したのがのんさん。旧芸名はNHK朝ドラマ「あまちゃん」でおなじみ能年玲奈さん。方言を使っての声の演技は大変だろうなとは思いますが、リアルガチにすばらしくて、すずちゃんの役どころにドはまりですごくこの作品にいい味を出しておりました。
共演者は有名な声優さんだらけでございますが、負けず劣らず素晴らしいといっていいでしょう。
ラストシーンもぐっと来て考えさせられるシーンではありました。アニメーションだからこそ表現できるシーンでもありますし忘れてはいけないことだと思います。
戦争に入る前の日常からあの悲劇が起こりそして終戦後までのすずちゃんと周りの人の日常を描いている戦争映画ではありますが、暗いことがあってもこの世界の片隅で生きていこうとする人たちの頑張っているところは今でも語り継がなければいけないといけないし、単館上映作品ではありますが、私が行った映画館でも老若男女ほぼ満席で観ておりました。
ぜったい観ておくべき作品だし、多くの映画館で上映するべき作品だと思います。私も時間があれば、もう一度観ておきたいです。
ありゃあ
原作を既に読んでいたからこそ
この作品の評価、感じ方は人それぞれだと思う。
とりあえず私は原作を既に読んでいるから、その立場で感想を書くと
①原作者は何を伝えたかったのか
②映画として監督がやりたかったことは
この2点で述べたい。(ネタバレは無しで)
①まず前提として、こうの先生はこの作品の前に「夕凪の街 桜の国」という漫画を描いている。この作品はとても感動したのだけど、なぜ感動したのかというと「原爆を描いているのに、それを直接描かず、戦後を描くことで、原爆の本当の悲惨さと、それに立ち向かい、幸せになるために前向きに生きてゆく」ことを描いた類稀な作品だったからだ。だからこそ、「じゃあ次は戦時中においても健気に生きる主人公を描こう」と先生が思われて描かれたのがこの作品なのだ。別にこの作品が「昔の日本人は今と違って奥ゆかしくて真面目で質素倹約で…」と今の我々に説教したい訳じゃない。事実として日本は戦争を体験した。多くの人が苦しんだり死んだりした。でもみんな必死に生きていて、ささやかな幸せを送ろうと頑張ってた。悲しいことがあっても小さな希望を見つけて生きていた。それをただ提示しただけのことなのだ。別に劇的なドラマがある訳じゃない。それでも私達にとってはかけがえのない作品になるのだということ。私達が生きる上でこの作品は必ず「心の栄養」となり得るだろう。
②当然だが、片淵監督こそ主人公「すず」を最も愛した人に違いない。この作品はジブリなんて目じゃないくらいにリアリティを追求している。「この世界の片隅に、ウチを見つけてくれてありがとう」だからこそ片淵監督は、「すず」の存在を確固たるものにするために、徹底した時代考証や、アニメ演技をこだわり抜いたのだと思う。激しい空襲に遭い、焼け野原となった呉において、それでもこの子は生きていたんだというメッセージを私は感じ取った。
まあいずれにせよこれは映画であり、どのような感じ方があってもいいと思うが、とにかく今は、この作品が海外でどのような反応を受けるのかが楽しみで仕方ない。
あと「夕凪の街~」のアニメ映画化もついでにお祈りする笑
奇跡のような映画、と言ってもいいですか?
思い過ごしかもしれませんが、他のどの映画のレビューよりも、『語らずにはいられなく』て投稿されている方が多いように感じます。
他の作品の場合、あの感動を分かって欲しい、とか、共有して欲しい、みたいなものがベースになっているのかな、と思いますが、本作の場合、観た方それぞれが、自分の中に生じた感情が一体何なのだろう、自分の中のどんな要素に響いたのだろう、と考察するために、『取り敢えず書いてみないと整理できないから書いてみた』ようなコメントが多いように感じました(少なくとも私はそうです)。
最近、世の中が妙に短絡的で攻撃的になっている気がします。やたらと嫌◯◯、反△△と煽る一部メディアや気に食わないからと駅員さんを殴ってしまうこととかです。格差問題のように、個人の力だけではなかなか現状が打開出来にくい閉塞的な状況が続くと、鬱屈したフラストレーションを発散する手段として、単純明解で勢いのある威勢のいい言動が一定の支持を得て、何となくそこに乗ってしまったほうが居心地がいい、という“空気”が生まれることがあります。
もしかしたら、間違った方向である種の空気が醸成されてやしないか、という漠然とした不安。先の戦争が愚かな選択の積み重ねだという結論はすでにでていて、まさか同じことを繰り返す筈がない、と何となく思い込んでいますが、本当に大丈夫だろうか、という不安。
空気を“読まない”すずさんを通して、そんなことを教条的な押し付けがましさを全く感じさせずに、それでいて重く問いかけてくる奇跡のような映画だと思いました。
〝空気〟を作るのは他の誰でもない自分なのだという責任感が深く刻まれました。
日本の戦争映画
見終わって、これほど余韻に浸れる作品もなかなかないでしょう。 広島...
見終わって、これほど余韻に浸れる作品もなかなかないでしょう。
広島市の江波で生まれ、嫁いで呉市に移り住んだ女性 すず。すず の両親、兄、妹。嫁ぎ先の夫、両親、義姉と姪っ子。前半はどこにでもある家族の幸せな日常、後半は戦時下に移り防空頭巾を被り防空壕に逃げ込む日常が丁寧に描かれています。呉は軍港なので空爆も日常茶飯事だったようですね。戦艦大和や武蔵も出て来ます。
この映画の印象的なところは、苦しい戦時下の日常を、人間らしさを失わず、笑いと優しさとペーソス溢れる人間ドラマにしているところ。そして、劇中頻繁に出てくるすずの絵描きシーンも上手い。
昭和20年8月6日、広島に原爆が投下され、何もかも失われた被爆地(故郷)。そこから這い上がり希望に満ちたエンディングに感無量となりました。
主演の のん(能年玲奈) のおっとりして時に力強い声色が、素晴らしい。この映画がターニングポイントになって、また引っ張りだこになるんじゃないですかね(*⁰▿⁰*)大ヒット中の『君の名は。』も本当に素晴らしかったですが、自分は本作に軍配。年齢層が高いのも納得ですが。今後、日本映画史で語り継がれる作品、日本人 皆が見るに値する秀作かと思います。
不特定多数の方から製作資金を集めるクラウドファンディングも使って、素晴らしい映画が誕生しましたね(^^)最後の最後まで席は立たないように。
全1071件中、841~860件目を表示