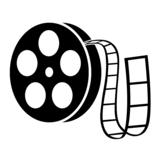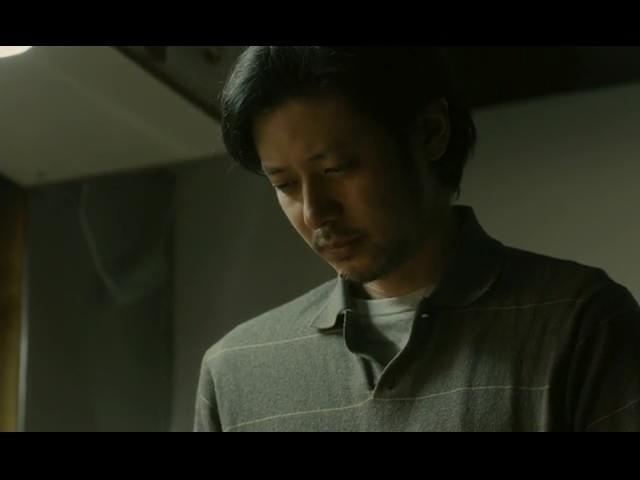オーバー・フェンスのレビュー・感想・評価
全94件中、41~60件目を表示
繊細で壊れそうな大人たち
函館にて大工を目指し職業訓練校に通う白石と鳥を愛する女性さとしが惹かれ合う様子を描いた作品。
オダジョーに蒼井優に松田翔太と好みの人からしたらいい雰囲気の役者を集めた俳優陣。
原作未読のためよくわからないがあまり登場人物の過去とか内面とかの描写が少ないため、結構な雰囲気映画感も漂っていた。
また職業訓練校が舞台なのにどこか金銭的に余裕がありそうな松田翔太の様子にも少し違和感。これは自分の偏見かもしれないが笑。
また蒼井優がかなりの電波かつヒス女を演じる。オダジョー演じる白石と良い感じになったのちの癇癪ぶりは中々恐ろしい笑。
満島真之介はビックリするくらいの暗い役。帽子を目深に被りすぎて最初誰だかわからなかった笑。
全体的にセンチメンタルな空気漂う壊れてしまいそうな作品。
動物園で鳥の羽が舞い落ちてくるシーンがよくわからないがその後の自転車2人乗りしながら羽を舞い散らすシーンの美しさがとても良かった。
なんといっても蒼井優の怪演ぶり見事!
職業訓練校は再就職の為、技術支援してくれる所。
色々な理由で来ているメンバー。個性揃い。
こんなに連むかな?くらい仲が良い。
職業訓練の他に野球もやるの?とは思う。(平々凡々と会社へ行ってる私みたいな人間には分からない。)
そんな中で、主人公 白岩(オダギリジョー)が飛び抜けてカッコイイ。
荒んでいる人生を送っている人への格言たっぷり。
詩人になれそう。
そんな彼は前半当初は淡々としていて、表立っても話さない。
しかし聡という女性に興味を持ち始め、淡々としていた白岩に心の変化が生まれる。
白岩に出会う聡(蒼井優)
頭のネジ一本抜けてんだか、普通の人より感受性強過ぎるんだか、自分をコントロール出来ない女性を怪演している。
普通ならばイタイだけの女性。しかし聡は白岩の「普通」を改めて考えさせてくれる女性であり、また新しい自分に気づかせてくれる女性でもある。
彼女の演技が無ければ、つまらない淡々とした映画。
オーバーフェンスという題名、良くつけたと思う。
徐々にフェンスを乗り越えてゆく姿を魅せてくれる、楽しませてくれた映画だった。
残念なのは舞台の函館が古い場所しか映し出してなかったところ。
綺麗に描写出来なかったんかな〜。坂道は青空の下で、とか。
舗装されてない誰も歩かなそうな汚い海岸沿いを自転車で走られても違和感しかない。(普通あんな所自転車で走らない)
オダギリ
いい間の映画
落ちぶれた人間の集まる技術学校における、人それぞれが周りに持つ壁、フェンスをうまく表現していてとてもリアルだし、心が温まる映画。
内容は重いが、それを受け止めようと奮闘する登場人物達の生活をうまく表現しており、その間が素晴らしいと感じた。
単調にワンシーンで映すのではなく、そこにまるで意味の無いような間を持たせることで印象づけ、映画に入り込ませていた。
最後のソフトボールの試合は、こっちが応援したくなる気持ちになった。
気になったのはBGM。
なんだろう、不協和音的なものでシーンの重さを表現したのかと思ったけど、何だか好きになれませんでした。
蒼井優は本当にこういう演技が上手い。
発狂する演技に挟む無の表情が美しくもあり、引き込まれる。
離婚経験があるから
何の柵を越えるのか
●やるせなさの向こう側。
佐藤泰志の作品は、なんだかやるせなくなる。けど、引き込まれるのだ。その独特な世界に。静かに、ひとり葛藤しているというか、いつまでも小さな傷が治らないというか。そんな小さな傷を持った者たちが出会い、交錯する。
ぶっ壊れてる女。ぶっ壊す男。森くんの不器用さ。
ハクトウワシの求愛ダンス。キレイだ。危ういとわかっていながら、好奇心が勝って、オレなら聡にのめり込んでしまうかもしれない。何も考えず、ただ生きているだけにならないように。
白岩の感情が溢れ出す「怒り」と「悲しみ」のシーンが好きだ。そして自転車二人乗りのシーンも。「悲しみ」を乗り越えた白岩が、吹っ切れたようにバットを振り抜くラストに救われる。結局、人はどこかで折り合いをつけていまの環境を生きていくしかない。その積み重ねの先に未来がある。まさに、オーバーフェンス。
北の街感、北のリアル
佐藤泰志の函館三部作のトリ
鳥の求愛ダンスを踊ってみせる女が普通なわけはないと、わかってはいても・・・しかし病んでる女は迫真。
「お前は自分がぶっ壊れてるって言ってたけど、俺はぶっ壊すほうだから、お前よりひどいよな」
ホームランで〆るところがしっくりこない。
優香もしっくりこない。
ギリギリの光量できれいに撮れているところ。
オダギリジョーが失うものが何もないと自暴自棄になっている普通の男をさらっと好演。
かつまたさんのおかげで。
心にしみわたる作品
ズレてるのは誰なのか
精々いまのうちに笑っておけよ
函館の職業訓練校建築科に通う白岩(オダギリジョー)。
妻と別れて、故郷に戻ってきた次第だ。
訓練校に通う面々も、何かしら生きづらさを抱えている。
ある日、クラスメイトの代島(松田翔太)に連れて行かれたキャバクラで、ホステスをしている聡という名の女性(蒼井優)と出逢う。
彼女は、いつかの昼間に道で連れの男に向かって、鳥の動きを真似て踊っていた女だった・・・
といったところから始まる物語は、何かしらの生きづらさを抱えた人々の物語であるが、前2作と比べて、閉塞感を少し打ち破るような希望を持った物語である。
が、どうも観ていて、しっくりこない。
よくわからないのだけれど、脚本が狙うところと、演出が狙うところが少しズレているような感じなのだ。
高田亮が書いた脚本は、先に書いたように「生きづらさを抱えた人々が、互いに信頼しあって、最後に少しだけ希望を持つ」物語なのだが、山下敦弘監督の演出は、あくまでも「生きづらさ」にこだわっているようにみえる。
全体的に、ロングショットの長廻しで、俳優たちが醸し出す「生きづらさ」の雰囲気をつかみ取ろうとしている。
そんな中、たまたま誘われた酒席で、若い女性を前にして、突然、くすぶっていた怒りを噴出する白岩のシーンが、静かな口ぶりで怒りをあらわにする白岩の顔をアップで撮っている。
そのときの白岩のセリフは、こうだ。
「何が面白いんだ・・・まぁ、精々いまのうちに笑っておけよ・・・なにも笑えなくなる日がくるんだから・・・」
ありゃりゃ、ここなのか、監督がいちばん力を入れているシーンは。
なので、本来、力を入れるべき「フェンス」(生きづらさの象徴)が、妙に取っ散らかってしまう。
動物園の檻。
開けても飛び立たないハクトウワシ。
聡が、発信していた叫びの象徴であるダチョウ・・・
職業訓練校のフェンス・・・
これらのメタファーが、どうにもうまく、心の中で一つになっていかなかった。
期待が大きかった作品なので、失望度も大きかった。
その壁の向こう側
全94件中、41~60件目を表示