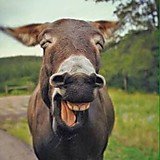わたしに会うまでの1600キロのレビュー・感想・評価
全103件中、1~20件目を表示
俳優、監督、脚本の才能が相まって生まれた秀作
C.ストレイドによる自伝的物語を、売れっ子作家ニック・ホーンビィが脚色した人間ドラマ。ホーンビィといえば、キャリアの原点において自身のスポーツ・エッセイを自らの手で映画用に脚色したことでも知られているが、本作もこれに似たかなり大胆な脚色を行っている。その結果、核となるエッセンスを極上のユーモアとエモーションが巧みに支えた、思わず胸の熱くなるような重厚なストーリーラインが誕生した。そこに主演のリース・ウィザースプーンによって体当たりで演じられる等身大の人間像が加わり、「自分を変えたい」「人生を変えたい」「自分の中の母の記憶と向き合いたい」という感情が少しずつ天高くに向けて昇華されていく。ジャン=マルク・バレ監督ならではのヒリヒリする内面描写も素晴らしく、特にフラッシュバックを多用したイメージの連鎖は観る者の心をえぐってやまない。かくも俳優、監督、脚本の才能が絶妙に相まって生まれた秀作である。
リース・ウィザースプーンという傑物
リース・ウィザースプーンって求められた役柄を過不足なくきっちりこなすよね。
主役なら主役、脇役なら脇役をきっちり。
おバカな可愛い子ちゃんでも、微妙にムカ付くタイプの優等生でも、献身的な奥様でも、隙のないキャリアウーマンでも、だめんずにハマるOLでも、金持ちでも、お金持ってない階層の人でもきっちり。
そりゃもう、きっちりと作品のムードに調和してる。
で、下品な振る舞いを演じても演技に品があって、愛嬌があるから悲壮感を漂わせても見てる方はイヤな気持ちにならなくて、お顔がそれほど美形じゃないからパフォーマンスにコクがあるっていうか、良い加減で印象に残っちゃう。
そんなリース・ウィザースプーン(1976年生、公開時38歳)が、プロデューサーとして製作し、自ら主演した本作、すごく複雑な役どころだと思うけど、どのシーンでもすごく本物っぽく見える演技だし、お母さん役のローラ・ダーン(1967年生、公開時47歳)とは9歳しか年齢差がないのに、確かに親子に見えるのが恐ろしい。
この人、どれだけ自分を客観視して自己分析、自己演出して、どれだけ自分をコントロールしてるの!?
この作品、凄い作品ではあるんだけど、人生の苦境に陥った主人公が旅に出て生まれ変わるって話で、要するにお遍路さんの物語。お遍路行路の過程で自分と対話したり、贖罪したり、自然の雄大さを思い知ったり、他人の優しさに触れたり、本作では要するに「親離れ」(と、私は解釈しました)をしたり、そういう映画や小説はゴマンとあるでしょ?でも本作では宗教性とかスピリチュアルなアプローチは一切なくて、非常に理性的で清々しい印象。
プロデューサーとしてこの原作をセレクトして、主演俳優として過酷な役柄をやり遂げて、えらく真っ正直な作品を作り上げちゃった。
すごく地味だけど、かなりの力技を必要とする作品だと思うんですよ、こういう作品って。なのにプロデューサーと主演俳優を両方務めるなんて、何気に途方もない荒技なんじゃないの?
だって俳優としての演技だけ見ても、アカデミー賞を獲得した『ウォーク・ザ・ライン 君につづく道』(2005)に決して劣らないパフォーマンスだと思います。これやりながらプロデューサー業までこなしてたとか、ちょっと信じられないレベル。ホント恐ろしい。
実際、凄い人なんだろうなぁ…リース・ウィザースプーンって。
お母さんへの想い
評価が高いが自分にはあまり響かなかった
実話に基づいて、
何度でも立ち上がって前へ進むこと、、、
他の方も指摘されている通り邦題の相変わらずの悪さを象徴した作品w
いらんこというなw
まあそれは他の作品でもよくあること。
今作はまあ自分探しの旅にフラッとでかけたニュアンスで観たら結構違ったw
主人公のシェリルの事がわかるまでに結構時間がかかる。
冒頭からいろいろなシーンが回想されて、まあ一人で歩き続け、一人で眠り、色々な場面で思い出すこともあるだろうが、本当にシーンが多くてつなぎ合わせていくのが一苦労w
母の死が原因なのはわかるが、トレイルを始めようとして専用の一式を揃えているのに、コンロの燃料の種類を間違えるかね?ww
しかもコンロに切れて蹴っ飛ばすw
インターネットが無いとはいえ、いや、あんたが悪いよw
でも自暴自棄になったのも、突然旅に出たのも、少なくとも理解はできる。
ドラッグやセックス依存になるのは少し「?」だが、人を無くした悼みはその人しかわからないし、彼女の回想シーンで出てくる母親は素敵な女性そのもの。
そしてよくできた母だ。辛くないわけがない。
シェリルは神を信じているのかはわからないが、弟と奇跡が起きるように心から祈っていた。
旅の中でいろいろな人と出会うが、いまいちパッとしない人ばっかりw
女性のハイカーと出会ってもテンション上がって、終わりw
そんなものなのか?
PCTがどんな感じなのか、日本人には検討もつかないが過酷なのはある程度伝わってきたが保養所みたいなところもあり、極地ではなさそうなので比較的ドロップアウトも容易そうな感じもした。
しかしなら最後までやり抜く強さは大したものだが、途中までは死んでもいいのかもと言う投げやりな気持ちもあったのかもしれない。
主演のリース・ウィザースプーンの演技はかなりの入り込みようだし、口も態度も非常に悪いw
これがどこまで脚色されているのかは不明だが、最後まで彼女に寄り添っていた夫は本当に愛していたのであろう。
長い距離や過酷な旅路なのは理解できたが、そんなに大きな出来事が起こることもなく、回想シーンで途切れていくので少し飛ばし気味な感じもしたが、徐々にトレイルに慣れてきたのか、自分への自信なのか一歩一歩に力強さや誇り等を感じられた。
ラストの少年とのやり取りには熱いものがあった。
見る時期やタイミングが合えば非常に素晴らしい作品になったのかもしれない。
また自分を見つめ直す時や、自分を赦す時に観てもいいのかもしれない。
大自然は好きですが1600㎞は歩けないな~(笑)
WILD
わたしはとても好きな映画の一つになりました。
母親と過ごしていた日々の自分と母親を失ってからの自分。
失ってからなにもかもだめになり、
それが心底嫌になった。そんな時にみつけたPCT。
(変わりたい!という気持ちで始めたというよりも、半分罰を与えたようにも感じました。)
そしてその中で色んな人に出会うけれど、子どもに会うところで彼女は自分にも言えることを男の子にもいう。
みんな問題があるけど、ずっと問題ではなくて、変わると。
PCTを歩き終える頃には自分を許してあげる、自分にごめんねという。そういう考えに変わり。
自分の母親はこんな人に私を育てたんじゃない、
現実と理想の自分との差、
それを許せるようになる。
だめだめでも自分が自分を許せたら。
前を向ける。前に進める。
こんな映画だったのね!
ひたすら歩く、ひたすら生きる
何のために自分は生きているのか。
生きていることに何の意味があるのか。
途中で生きることをやめたい。
でも、立ち止まらずに生き続けなきゃいけない。
生きる を 歩く に、
重い荷物 を 様々な苦難 に、
置き換えればいい。
彼女がひたすら歩いてわかったことは、
これからも歩き続けて行かなきゃならない。
生きる目的は、生きることにある ということ。
過去に色々あって、未来にも色々あるだろうけど、
生きたい意欲は、食べたい、眠りたいということに等しい。
生きることの意味は考える必要なく、生まれた時から備わっているもの。
目に見えない未来こそが希望。それが耐えられない未来だとわかってしまったら、それこそ"死に至る病"だ。でも未来はわからない。わからないことは素晴らしいことだ。
ゴチャゴチャ考えず、
"時間を味方に、時々出会う苦しみも悲しみも楽しみも嬉しさも全てを受け入れ、ひたすら歩むことが人生の目的だ"
それを知る旅の物語。
どこまでいくの
1600キロ歩いたからって何なのだ?
母の死、夫との離婚を機に人生を一からやり直す為、1600キロのトレイルを3ヶ月程で踏破した女性:シェリーの実話を元にした映画。
覚悟はある様ですが、1人キャンプもした事無い様な女性ではトレイル困難の各オチが分かり、盛り上がらず。
主人公:シェリルの回想も入り、悲しい過去と自分を見つめ直す旅内容になっておりますが、語りすぎ。
これが本編トレイルの内容や面白さを邪魔していると感じてしまった。内容がありきたりで余り面白く無いし、シーンも多過ぎる。中途半端に入れてくる。
各地様々な人達の出会いは良いのだが、シェリルには余り活かされてもいない様な気もします。活かされているのは序盤のトレイルについて教えてくれる男性と最後の少年ぐらいか?。
なんだかんだでいつの間にか終点らしく、いつの間にか彼女が自分に納得して映画は終わってた。。。
彼女まともに歩いてない様な🤔
ちなみに制作はTSGエンターテイメント。ああ、あのサーカス映画を作った映画か。語り過ぎるんだよなこの会社。私には合わない訳だw
孤独にはなれない
モンタージュ
今日の作品はフレンチカナダ人監督ジャン=マルク・ヴァレ監督の作品をご紹介。
リース・ウィザースプーンがアカデミー賞主演女優賞でローラ・ダーンが助演女優賞でノミネートされたことでも話題になりました。
ジャン=マルク・ヴァレ監督はダラス・バイヤーズクラブ (Dallas Buyers Club)で一躍有名になった監督です。彼はマーティン・ペンサと共に自分の作品を編集まで行います。
そこで今日は、映画編集の基礎となっているモンタージュについてご紹介しましょう。
モンタージュ (Montage) はもともとフランス語で、映画編集におけるモンタージュとは、実際にみなさんが映画館で見ている映画そのもののことを言います。
具体的にいうと、別のカメラアングルや別の時間軸の2つのショットをつなぎ合わせることをモンタージュと言います。つまりは、現代の映画そのものがモンタージュで出来上がっています。
実際に我々が現実世界で見るときには、視点を切り替えたり、別の場所にジャンプすることはないですよね?映画の世界ではそれが当たり前ですが、それが映画たる最初の所以でもあります。
この映画では、そのモンタージュで遊びまくっていました。
この映画の構成自体がそうなのですが、パシフィック・クレスト・トレイルを歩きながら、それまでに彼女が経験した出来事を回想するというような形式で映画は進んでいきます。
あえて時間軸を一方向に進ませず、PCTを歩いていく中で、実際に主人公が見たもの、感じたことをモンタージュでつなげていくことで、彼女のそれまでの人生を視聴者が主観的に見ることができるようになっています。
このモンタージュを使うことによって、映画は現実よりも一つ次元の高い超現実的なものになっているのです。
たとえば、写真を見たときに、その思い出に浸る瞬間は誰にでもあると思います。しかし、それは実際にその時の映像が見えるのではなく、頭の中で回想し想像しているだけです。
映画ではそれを実際にスクリーンに映します。つまりは、視聴者はキャラクターの頭の中を疑似体験できるということです。それによって、自分の体験と重ね合わせて、ときにはそのキャラクター自身に自分を照らし合わせたり、ときには映画の世界からそのキャラクターを見つめることもあります。
毎回言っていますが、映画はキャラクター。
モンタージュはキャラクターアーク以外の役割もありますが、映画のキャラクターに命を宿す一番大事な手段だと思います。
だから編集はすごい。編集があってこその映画です。
ふたたびサイモン&ガーファンクルが沁みる
よかった
全103件中、1~20件目を表示