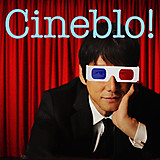この国の空のレビュー・感想・評価
全42件中、21~40件目を表示
ここまで昭和の女性が合うとは
この映画はいつもの戦争映画とは違います。戦時中の日常が描かれてます、まずは二階堂ふみの昭和の女性をしっかりと演じれています。長谷川博己さんはエロさをしっかりと表現されてます。あと二階堂ふみのモンペが紐やゴムではなくジッパーつきのだったので何気におしゃれだなと感じました。
古さが新鮮な作品
ここにも戦争が終わることを望まない人物が
先日TV放映されていた「火垂るの墓」を観て、主人公が戦争の終結を望まなかったことについて考えた。
本作で二階堂ふみ演じる主人公の女性も、愛する隣家の男の妻子が疎開先から還ってくるために、終戦の日を喜びや解放感とは無縁の心境で迎えたのだった。
この作品の中では、戦地へ赴くことのない人々の心情が率直に語られており、終戦を自らの戦いの始まりととらえる二階堂の心情の吐露もこの延長線上にあると言える。
東京に残っている人々の語る言葉には、天皇への忠誠や軍人への敬意などよりも、日々の食料の心配と空襲への恐怖が先に立っている。空襲への恐怖は、自分の街が攻撃目標から外れ、遠くの街が炎に包まれるのを見ることで安心に変わるのである。
これはまるで景気の動向を心配し、台風や地震など災害への恐怖、しかも台風や地震が自分の住む場所に被害をもたらさなければ他所がどうなろうとひとまずは安心していられるという、現代の人々の心情とほとんど変わりないのである。
遠い戦地を慮って禁欲的な生活をしている者は皆無であり、人々は日々のささやかな喜びを求めている。それは、久方ぶりの甘いお菓子であり、田舎の河川敷での水浴びであり、密やかな恋である。
この作品では買い出しや防火活動など、戦時下の最も生活じみた部分を丹念に描いている。戦争映画と言えば、戦闘を題材にしてその勇ましさや凄惨さを伝えようとするものだった気がする。
小津安二郎の戦後の映画は、まさに戦後の家庭が描かれているが、そのパースペクティブにはあの戦争というものがはっきりと映っている。いままた、こうした市井の人々の生活を描く中から、戦争についての人々の思いを描く映画の潮流が始まったのだろうか。それとも戦後70年の一過性のものに終わるのだろうか。
頼むから、蛇足はやめて、監督さん
高井有一さんの、谷崎潤一郎賞を受賞した同名小説(1983年)の映画化。
戦争映画は、人類の記憶として重要だとは思うけれど
自分的にはすでに一生分観た気がするので食傷気味。
でも予告編を見て二階堂ふみさんが出るのを知り、
ああそれなら観てみようか、と思った次第。
「ドクトル・ジバゴ」や「小さいお家」などと同様、
戦争は背景としては重要だが、
軸はあくまで人の――ここでは二階堂さん演ずる里子の――生き方にある。
そして、
茨木のり子さんの詩「私がいちばんきれいだったとき」が
見事に重なる。
少女から女になりつつあるとき、
戦争も末期で、東京はすでに大空襲に見舞われ、
若い成人男性はほとんど応召して周囲にいない、という状況で、
妻子が疎開中の隣家の38歳の男性に心を惹かれてゆく・・・
その情念が、丹念に描かれてゆく。
原節子さんもかくやという
二階堂さんの古風な演技が素晴らしい。
最後の最後(エンドロールの直前)、
痛恨の蛇足がなければ、満点だったのに。
頼むから、世の中の監督さんたち(あるいは製作の方々)、
原作にない余計な説明を付け足して
作品を台無しにするのは、やめてくれ。
市井の人々
悲惨をみせずに写しだす、戦争の悲しさ。
先日観た「日本のいちばん長い日」
と見事にシンメトリーになっていた。
皇室や政治家や軍人が、
混乱の中で戦争を終わらせる話に対して、
こちらは
なかなか終わらない戦争に翻弄される、
平凡な少女の話。
太平洋戦争末期の、東京杉並。
毎日のように空襲警報が鳴り響き、
B29の焼夷弾に怯え、
食料給付も少なくなる。
原子爆弾や本土決戦の恐怖から、
死への覚悟を受け入れる。
そんな絶望的な焦燥感のなかで生きた
母娘のスライスオブライフが、
淡々と描かれていく。
食事のシーンが多いのも、
彼女たちの生命力を、
浮彫りにしている。
悲惨な現場をみせなくても、
戦争の悲しさが、
親子の毎日を通して、
しんしんと伝わってきた。
主人公の里子は、
とにかく戦争に苛ついている。
娯楽なんて何もない。
自分がいちばんきれいな時だろう
結婚適齢期に、
男たちは戦場に行ってしまい、
恋をしたこともない。
そんな里子が
虚弱体質で兵役を免れた
妻子ある男に惹かれていく。
欲望を満たすことで、
不安から逃れようとする二人が、
あまりにも切なすぎる。
全体に静かなトーンが、
映画を上質なものに仕立て上げている。
二階堂ふみさんと長谷川博己さんの台詞回しが、
とにかく美しい。
抑えられながらも情緒を感じる、
会話の内容と声、表情、心情などの、
繊細な描写がうまい。
まるで
小津作品のオマージュのような佇まいに、
思わず息を飲んでしまった。
工藤夕貴さんの母親も、良かった。
自分の過去を娘にさらけ出すシーンは、
女になった娘への愛情にあふれていた。
エンドロールで、
女性詩人・茨木のり子さんの
「わたしが一番きれいだったとき」
という詩の朗読には、
不覚にもぐっときてしまった。
安全保障関連法案を
成立させようとしている時代に、
何も不自由のない現代の女子を見ていると、
戦争の不幸を二度と繰り返さぬようにと、
祈るばかりだ。
日本の黒歴史
綺麗な映画でした
戦争映画とは全く異なる映画
はじめに感じたのは劇中の人々の言葉遣いがとても美しいな、ということです。
男女ともに一つ一つの言葉が丁寧というか堅実?というかで、台詞にひきこまれました。
あとで原作を読んだら、出てくる台詞はほとんど原作のままです。
ただ、現代人にとっては言葉がかなりかしこまっているので演技を意識してしまうというか、違和感を大きく感じる方もいると思いました。
内容は、ありきたりになってしまいますが、二階堂ふみさん演じる里子が女になっていく姿は圧巻の演技だと思います。
戦時中という特殊な環境ゆえか、普通の19歳ではなかなか得ることのできないであろう里子の、神秘的な雰囲気や滲み出てくるような美しさを、とても魅力的に演じられています。
戦時中の話だからこそ、さまざまな面の美しさにとても目がいきます。
この映画には、内容に関係なく、とにかく美しいという印象を持ちました。
私が一番綺麗だったときを思い出した
色んな映画を観てきたが、こんなにも初めて結ばれたときを思い出し、淡い気持ちになった作品は始めてだ。
一線を越えるときの戸惑い、愛しさ、激しさは男女の普遍的なものであるから、私の一番綺麗だったときと重ねて、里子に感情移入できた。
今なら里子は、母と同じように河原で水浴びができるだろうな、と思う。
終戦間際でなければ里子の物語はなかった。
しかし、戦争があろうがなかろうが男女の物語はいつでも、誰にでもあるだろう。
戦争に関係なく、その激しさは圧倒的だ。
陳腐な男のセリフや、どこかで見たようなメロドラマのようなシーン、そして全体的に暗めの画面が逆にそれを炙り出していた。
淡い物語だった。
ただ、食事や服装が知り得るかぎり、今までで一番贅沢で、ちょっとモヤモヤした。
もうひとつの戦時中。
高井有一の原作を荒井晴彦が脚色監督した作品。
終戦間近の東京杉並。母と娘の2人暮らしのところへ母の姉が転がり込んでくる。
彼女たちの隣に銀行員の男が住んでおり、彼は妻と子を疎開させていて一人暮らし。
この2軒の家のまわりで物語は進む。
といっても物語は、戦局悪化のなか、市井の人々がどのように生活していたかを丁寧に描く。
里子(二階堂ふみ)と隣の市毛(長谷川博己)が惹かれあっていくのが中心に据えられていたわけではなく、あの時代の人々、を描いていた。
晩年の黒木和雄のタッチに近い。
深い映像と演技陣の頑張りで、同時代を生きた気に少しなった。
二階堂ふみ、長谷川博己はもちろんいいのだが、里子の母の工藤夕貴、叔母の富田靖子もよかった。
わたしが一番綺麗だった時
女性が一番綺麗だった時は戦後の直前だった
原作と空気が違ってた。どっちがいいとも言えない。
工藤夕貴と富田靖子の姉妹役にこころ踊らせる
この角度も
全42件中、21~40件目を表示