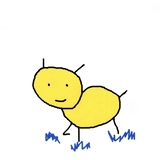勝手にしやがれのレビュー・感想・評価
全77件中、21~40件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
根無し草青年のミシェル(ジャン・ポール・ベルモンド)。
自動車泥棒の常習で、女性から金をくすねての生活。
今日もマルセイユで盗んだ車でパリに向っていたところ、スピード違反で白バイの警官に追いかけられる羽目に。
が、いつもと違ったのは、車のダッシュボードに拳銃が入っていたこと。
ひょんなことで警官を射殺。
追われる立場になってしまう・・・
といったところからはじまる物語で、その後・・・
パリへ戻ったミシェルは女のもとを転々とし、貸した金の取り立てをするも渡されたのはヤミ小切手で、現金化するには別の男の下へ行かねばならなくなる。
途中、数週前に南仏で知り合ったキュートな米国娘パトリシア(ジーン・セバーグ)と再会。
ベタベタと付きまとうが、パトリシアは束縛されるのがイヤ。
ついには、警察にミシェルの居場所を密告し、ミシェルは射殺されてしまう・・・
と展開する物語はあらすじだけ抜き出すとバカみたいだ。
まぁ、チンピラを主人公にした犯罪映画のハナシなんて、バカみたいなものが多いんだけれど。
撃たれたミシェルはパリの街路をフラフラと逃げ歩いた挙句、「最低だ・・・」と呟き、自らの手で瞼をおろして死んでしまうが、「バカだな・・・」と読み替えてもいいでしょう。
で、この映画を物語を語っても仕方がない。
やはり、強烈な音楽と映像のスタイルで語るべき映画だろうし、また、そう語られてきた。
ビートとパンチの効いた音楽、ギクシャクとしたカッティングと編集。
特に映像については、製作された1959年の時点では、相当強烈な印象を残したはず。
鑑賞後、中条省平の新書『フランス映画史の誘惑』で確認したところ、ジャンプカットと呼ばれる、間を縮めた編集つなぎは、長回しで撮っていたがゆえに尺が長くなりすぎ、尺を縮めるための編集だったそうな。
そういわれれば、「ヘラルド・トリビューン紙」を売り歩くパトリシアと再会したミシェルが彼女と話しながらが歩くシーンや、ホテルの一室でミシェルと交わす男女の駆け引きのシーン、最後のフラフラ逃げるミシェルのシーンなど随所で長回しが登場する。
これらのシーンは、切るに切れなかったということだろう。
逆に、ヘラルド・トリビューン紙のパトリシアの上司が彼女に著名作家の取材に行けというシーン(取材後の話を聞くシーンだったけ?)は、あまりに冗漫なので、セリフの間まで詰めている。
自動車での移動シーンも長く撮ったが、繋げると冗漫だったので、短く繋げたのかもしれませんし、冒頭の警官殺しのシーンは、逆に、全然撮っておらず、ショットが足りない感じがします。
ということで、ヌーヴェルバーグ的カッティングと編集は、尺との闘いから生まれたのですね。
で、この映画以降、ヌーヴェルバーグ的手法が他の映画でも頻繁に用いられるようになるわけですが、それはまた別のハナシ。
この映画を観て、「なんだか、前にどこか別の映画で観たような感じが・・・」と感じたならば、それはこの映画の模倣ですから。
名作だが映画史の文脈の中での評価から免れない
自由で奔放!
Blu-rayで鑑賞(字幕)。
即興演出や手持ちカメラの撮影は、今や一般的な手法だと思いますが、本作がパイオニアと考えるとすごいな、と…
パイオニアなのにすでにして洗練されていると云うか、カメラの揺れさえも物語の一部になっている感覚でした。
奔放なミシェルと自由が欲しいパトリシアを象徴するかのように、編集もカメラワークも勝手気儘に編まれているのはかなりおしゃれな感じがして、刺激的だなと思いました。
お洒落でかっこいいベルモンド💕
今見ても、クールでかっこよくて知的で面白い場面が沢山散りばめられている映画だから、公開当時のヨーロッパなり映画界はびっくりしたんだろうなあと想像できる。ゴダールもトリフォーも凄いんだろうが、凄いのはベルモンドが主役だからだ!ゴダールが人間国宝ならベルモンドはもっと凄い人間国宝です。ベルモンドだから車がピッタリ、背も高く足も長くお洒落なフランス男で愛嬌あって可愛いいたずらっ子。彼だからパトリシアは好きになるし、パトリシアに惚れちゃったんだよと言う彼の言葉も分かってあげられる。
抽象的・哲学的な言葉のやりとりやモノローグは大島渚の映画「絞死刑」(1968)を思い出した。いきなり撃つとか撃たれるはタランティーノ。
パトリシアが膝から足までをビデで洗うシーンが好き。ビデは便利で大袈裟なシャワーもバスタブも不要で小回りが効くからとてもいい。パトリシアが映画館のトイレの小窓からパンプス脱いで逃げて刑事をまくところは小鹿みたいでよかった。ピカソとかルノアールの絵がピンナップみたいに壁に貼ってあったりモーツァルトを聞いたりディオールの服がいいな、などアメリカ人の女の子がヨーロッパに憧れて学んでる感じが面白かった。
ベルモンドはサングラスも帽子も煙草も運転姿も親指で唇をなぞるのも全部が素敵だった。でも孤独と絶望が溢れ出ていた。江戸木さん企画・セレクトのベルモンド映画大会、今年で3回目(で最後?悲しい)。その中で見た「オー!」(1968)は他の作品と色合いが異なるなあと思ったことを思いだした。若いベルモンド。美しい恋人がいて彼女には自分の仕事を隠している。お洒落でネクタイたくさん持っていて元カーレーサーだから運転素晴らしく、孤独で認められない辛さが滲んでいた。このベルモンドはゴダールの映画に出たからできた役なんじゃないかなあ、と勝手に今日から思うことにした。
おまけ
よく聞く話に、高倉健の映画を見ると映画館から出る時に男性は高倉健になってしまって歩き方まで変わるとか。今までそういう経験なかったけれど、今日は、映画の人物(ベルモンドとジーン・セバーグ)が混ざりあった人になって映画館を後にした。視線とか首の傾げ具合。ハッと気がつき恥ずかしかった。
なんで日本語字幕が「最低だ」なのか
すごく昔の作品なのに、この点に触れられているコメントはほとんど見ないので、今更だけど書きます。
ベルモンドの最期のセリフは「デギュラス」degueulasseなんだけど、これは直訳なら「吐き気を催すほどのもの」という意味で、状況がそれほどひどいということ。
忌避すべき、くらいの強いニュアンスで使うけど、容姿形容で使われることが多い。
本編なかほどでベルモンドはセバーグにこの言葉を使っている。そこでの訳は「醜い」になっている。
ベ「本心とは逆のことを言うもんだ」ベ「君は醜い(デギュラス)」セ「デギュラスって?(フランス語がつたないアメリカ人なので意味がわからない」
ここでベルモンドは変顔してみせる。
このやりとりが、まんまベルモンド最期のシーンに繋がる。ベルモンドはまず変顔し、そしてデギュラスと言って息絶える。
セバーグが何て言ったのか刑事に聞いて、デギュラスと言ったと彼は答える。
それはシチュエーションからしたら「(裏切って)お前は最低だ」と理解すべきなのかもしれないが、彼女は変顔とセリフから、あの時のやりとりだとわかる。
そして彼を理解して、彼の癖だった唇を拭うしぐさをする。
そういうシーン。でもこれが、邦訳の「最低だ」だけだとさっぱりわからない。
台詞上「Tu es ~(君は)」と「C'est ~(こんなの)」の違いはあれど、デギュラスは重要なキーワード。そこはしっかりわかるように翻訳してほしい。
あと、日本語字幕では「車」としか書いてないけど、セリフでは2CV(シトロエン)や403(プジョー)等と車種を言ってたり、彼女のことを聞かれて「アメリカ人」と言ってることになってるけど実際には「ニューヨーカー」と言ってたり。
ゴダールは台詞にもかなり気を配っているので、もう一度しっかり訳して欲しいなあ。
ジャン=リュック・ゴダール監督を偲んで
ジャン=リュック・ゴダール
9月13日死去
享年91
持病に苦しみスイスで薬物による安楽死を選択
U-NEXTで鑑賞
ヌーベルバーグ
ニュースで久々に耳にした
脚本より映像か
ゴダール監督作品初鑑賞
昔のフランス映画は野暮天にはハードルが高い
1960年だから日本の年号では昭和35年
既に日本でもカラーが主流だからこの作品がモノクロなのはゴダール監督の拘りだろう
あらすじ
自動車泥棒の常習犯ミシェル・ポワカールはマルセイユ郊外で追跡中の警察官を射殺してしまう
パリに逃亡したミシェルはアメリカ人留学生パトリシア・フランキーニと再会しやがて男女の関係になる
ミシェルとの逃亡を断念したパトリシアは警察に密告してしまう
映画の原題は『A bout de souffle』
「息ができない」か
ミシェル
「もしあんたが海が嫌いで山も嫌いならそして街も嫌いなら勝手にしやがれ!」
邦題のタイトルはこの台詞から取られたんだろう
むかし公開された洋画の日本だけのタイトルはかっこいいものが多い印象
『勝手にしやがれ』といえばまず思いつくのが阿久悠が作詞した沢田研二の代表曲だがこの映画のタイトルから拝借したらしい
この映画がなければジュリーが帽子を飛ばすことは無かったし『プレイバックPart2』も『勝手にシンドバット』も生まれてなかったかもしれない
その点だけでもこの作品は日本に絶大な影響を与えた黒船といえる
語尾にやがれといえば「待ちやがれ」「一昨日きやがれ」だが時代劇っぽくもありなんだか古めかしい
「一昨日きやがれ」に至っては全く無理な話でドクにデロリアンを改造してもらわないといけない
最近では大島優子の写真集『脱ぎやがれ!』だが目立つのは半ケツ程度で中西里菜に比べたら然程脱いでいるわけではない
半ケツは腰が曲がり切った片田舎の婆さんが誰に頼まれたわけでないのに野外露出するのであまり好きじゃない
話を映画の内容に戻す
パトリシアのこの台詞も良い
「あなたを愛したくないの。だから警察に電話したの。これが愛なのかを知りたくて一緒にいたわ。自分の気持ちを確かめるために。私はひどい仕打ちをした。つまりこれは愛じゃないわ」
白昼の街中だというのに丸腰のミシェルの背中にいきなり発砲するパリ警察
無茶苦茶だ
ミシェル
「君は本当に最低だ」
パトリシア
「最低って何?」
不自然な映像が多い気がする
トイレで警察を巻いたパトリシアがミシェルに会うシーンはいきなりすぎた
いらないシーンをカットして強引にくっつけたせいだろう
初のヌーベルバーグだがそれ以前のフランス映画を詳しく知らないのでその違いがよくわからない
自分は幸いなことに鑑賞中に眠ったりはしなかったが王道のハリウッド映画こそ本当の映画だと断言するようなタイプは爆睡する可能性大
都会的でインテリなセレブならこのくらいの映画の良さは十分理解できるだろうし一流の嗜みといえよう
僕は一回観ただけではこれだけ高く評価されている理由がよくわからなかった
ただなんとなくだがカッコ良さは伝わった
ショートカットのジーン・セバーグがとてもキュート
『悲しみよこんにちわ』のセシルカットだ
ジーン・シバーグが可愛かった
ミシェルはマルセイユで自動車を盗み、追ってきた警察官を射殺し、パリに逃げた。パリに着いたものの、金もなく、警察から追われているため、アメリカ人留学生のガールフレンド、パトリシアと行動を共にしていた。しかし、ミシェルが警察に追われる身であることを知ったパトリシアは、一緒に逃げることを断念し警察に通報した。そしてミシェルは・・・という話。
ひっきりなしにタバコ吸うジャンポール・ベルモンドが印象に残る。
昔は自動車泥棒って簡単に出来たのかな?
最後の、「あなたは本当に最低だと彼は申していました」と伝えられたパトリシアが「最低ってなに?」と訊き返すシーンはどういう意味なんだろう?
全体通してよくわからなかったが、60年前は斬新だったのかも。
ショートへヤーのジーン・シバーグが可愛かった、
タイトルなし(ネタバレ)
ミシェルの「まったく最低だ」は「愛してる」と同義に解釈できるように思う。
「まったく最低だ」を最後に死んでしまうミシェル。フランス語がそこまで堪能じゃないアメリカ人のパトリシアにはうまく意味が飲み込めない。「なんて言ったの?」と刑事に問いかけるけれど、刑事は「あなたはまったく最低だと」と答える。
ミシェルとパトリシア、ふたりのあいだでのみ共有される可能性のあった言葉が、第三者を介して「正しい言葉」で「翻訳」された瞬間に、「愛してる」という意味を失う。
映画の最後は、パトリシアの「最低ってなんのこと?」という言葉とパトリシアによって再現されるミシェルの癖だった仕草。
パトリシアがミシェルの「最低」という言葉を理解できなかったのは、フランス語がわからなかったせいなのか、それとも、彼の感情も自分の感情もわからなかったせいなのか、また、それとも、別の何かなのか、
言葉による、ふたりの永遠のすれ違いが描かれる。しかし、死んだミシェルが、パトリシアによって、仕草として再現されることで、彼女の中に彼がまた現れる。失われると同時にまたなにかが生まれる、
ミシェルにとって、言葉や言葉の意味なんてどうでもよかったのかもしれないと思うことがある。美しいも醜いも、どちらも同じ。そこにあるのはパトリシアに向けた、君を抱きたい、愛してる、という真っ直ぐな感情だけ。もはや意味は、意味を、持たない。もちろん、まったく最低だ、も。
言葉メモ
「星占いって?」「未来のことさ」
「フランス人は5分を1秒と言うのね」
メモ
人殺しのミシェルと、ミシェルを密告して死に追いやるパトリシア。パトリシアのミシェルに対する複雑な感情はミシェルと同じ人殺しになる、という同一化願望のようなものもあるのかもしれない。ミシェルが死んだあと、パトリシアがミシェルの仕草を模倣するのも、同一化の象徴なのかもしれない。
やっぱり最高!
う〜ん。やっぱり超カッコイイ…
どうしても久々にスクリーンで観たくなって、キネマ旬報シアターまで遥々と電車を乗り継ぎ辿り着き、タップリ堪能してきた。
もう本当に最高。
オープニングの唐突なスピード感。
マーシャル・ソラールの粋な音楽。
あまりにもモノクロ映えのするフォトジェニックなジーン・セバーグ。
ボギーに憧れる若気の至りココに極まりなベルモンド。
ナボコフをイメージして、すっかり大物作家になりきってたジャン=ピエール・メルヴィル(人生最大の野心は?→不老不死になって死ぬこと!)
ラウル・クタールの本当にヌーヴェル・ヴァーグとしか言いようのない鮮烈軽快なカメラワーク。
そして、あのラストシーン!
最後に“FIN”の文字が出た瞬間、思わず久々に「おおお…」と唸ってしまった。
こんな映画、もう二度と誰にも作れないだろう。
1959年の製作で、こんなことをやってしまうなんて…
今さら言うまでもないが、これが無かったら、アメリカン・ニューシネマだってタランティーノだって、その他の数多の諸々の映画だって存在しなかったに違いない。
そして邦題『勝手にしやがれ』が兎にも角にもズバ抜けてる!冒頭のベルモンドの台詞なのだが、原題からの翻訳などでなく、この言葉をチョイスしたセンスが本当に素晴らしい。
もう本当に最高だ。
何度でも言う「本当に最高だ!」
睡眠導入剤
大むかしに大阪の某劇場で、オールナイトのゴダール特集を観たが、それはある種の拷問のような、あるいは修行のような体験であった。
そのときに上映された作品名も内容もまったく憶えていない。憶えているのは、ただただ眠かったこと。そして、退屈な作品の連続に、「早く終わってほしい、朝になってほしい」と思ったことだけだ。このときにもしかすると本作を観たのかもしれないが、何しろ作品のことはなんにも憶えていないのだからどうしようもない。
で、あれから幾多の歳月が流れ、何故かまたゴダールの映画を観にいってしまった。やっぱりつまらないし、眠かった。眠気とのたたかいであった(僕は映画鑑賞という行為を大切にしているので、どんなにつまらない映画や気に入らない作品でも眠ったりしないのだ)。
当時のパリの風物、ブレッソンやドアノーの写真を思わせるような映像、スタイリッシュなファッション、ジャズによる軽快なBGM……。それらのおかげでなんとか最後まで観ることができたが、映画じたいはほんとうに退屈だった。
ヌーヴェル・ヴァーグの傑作かなんか知らんけど、ゴダールの映画は、僕の頭でストップし、こころや魂には届かないのであった。
よっぽどインテリジェンス溢れる人でないと、こういう作品の価値はわからないのでしょうね。
寝つきが悪い方にはオススメです。
フィルム・ノワールの「分流」としてのヌーヴェル・ヴァーグ。その起点を成すゴダール流「ファム・ファタル」映画
ジャン・ポール・ベルモンドの『リオの男』で、ベルモンドがさんざん車を後ろから走って追っかけてったり、最初から最後まで無賃乗車を繰り返しながらパリからリオまで行ってまた帰ってきたりするのって、思い切り『勝手にしやがれ』のパロディだったんだな(笑)。
今回およそ30年ぶりに観て、初めて気づいたよ。
あまりに仕事が忙しすぎて、有楽町で観られず、横浜でも観られず。
ようやく柏のキネマ旬報シアターでのリヴァイヴァルで観ることができました。
大学生の時以来だから、筋から何からさっぱり忘れてた。
ゴダールといえばやはり「難解」という印象がどうしても強いが、長編第一作である本作は、必ずしもそれは当てはまらない。
たしかに、技術や演出技法において当時真に革新的だったことは確かだが、のちのゴダール映画とちがって、いちおうちゃんと筋はあるし、何が行なわれているかもだいたいわかる。
すなわち、ある程度は物語映画としての「体裁」を保っている。
むしろ、オーソドックスな「ノワール」+「恋愛映画」=「逃避行」の枠組みに、新たなるヴィヴィッドな感性と即興性、そして意識的な「作家主義」を注ぎ込んだ作品と位置付けるのが妥当ではないか。
それに、自然光の下でのロケーション主体の撮影や、手持ちカメラ、ノーメイク、即興演出、リアルなダイアローグ、ジャンプカットなどの諸々の「新手法」は、当時はそれこそ誰しもがぶっ飛ぶくらい斬新だったかもしれないが、いずれも、その後普遍化して“当たり前”になったやりくちばかりだ。つまり、われわれ今の視聴者にはむしろ「違和感がない」。
マーシャル・ソラールのジャズの小粋な使い方などは、60年代以降の気の利いたアクション映画やサスペンス映画の「お手本」みたいな感じで、ちっとも難解だったりとっつきにくかったりはしない。
全体に満ち溢れる、「動き」の気配と躍動感、切れの良い音楽、魅力的な俳優と女優のしぐさや立ち姿は、間違いなく観客を楽しませるものであり、バリバリに「エンタメ」している。
現代人からすれば、他の50年代、60年代の古臭い映画より、よっぽど「今に通ずる普通の感覚の延長で」楽しめる映画だといっていいかもしれない。
お話は比較的、単純だ。
無軌道な青年が、米国人ジャーナリストの女性に会いにいくために、いつものように車をパクってパリに向かうのだが、途中でスピード違反でポリ公に目を付けられ、職質されかかったので射殺する。
青年はパリで元カノの金をネコババして女に会いに行くが、新聞ではお尋ね者として指名手配されている。ふたりは再会し、デートするが、官憲の影は間近に迫っていた。
逃避行、一夜の情事。その末に女が下した決断は、「密告」だった……。
もともとはトリュフォーが自身のデビュー作として温めていた企画で、1952年に起きたほぼ同内容の実在の事件「ミシェル・ボルタイユ事件」を題材にとっている。トリュフォーは結局プロデューサーの同意が得られず、先に撮った『大人は判ってくれない』(59)でデビューを果たしていた。ゴダールはぜひこの企画を譲ってくれと懇願し、親友の許可を得た彼は、トリュフォーのシノプシスをもとにさっそく脚本を書き上げたのだった。
僕個人にとって、『勝手にしやがれ』が達成した最大の功績というのは、主演ふたりの魅力を最大限に引き出したことにあるのではないかという気がしている。
すなわち、従来の映画では、役がまずあって、それに合わせて俳優が演技をした。あるいはその逆で、まずスター俳優がいて、それに合った役があてがわれた。
ところが、『勝手にしやがれ』において、その「後先」は不分明だ。
本作における、ジャン・ポール・ベルモンドとジーン・セバーグは、あたかも最初からこのフィルムのなかにいたかのように自然にふるまっている。そのうえで、ちょっとしたしぐさや立ち姿、目線の動かし方や歩き方といった日常の何気ない所作から、途方もない魅力と吸引力を発している。
彼らはミシェルとパトリシアでしかないのだけれど、同時にベルモンドとセバーグでもある。
ここでのベルモンドとセバーグは、役を生きながら、同時に、本人そのものであるかのように生きているのだ。
なぜか。
それは、ゴダールが「役」に俳優を当てはめず、俳優そのものの資質や佇まいに、役を「引き寄せて」演出したからだ。その場で実際に会って感じたベルモンド個人の魅力、セバーグ個人の魅力を、貪欲に「役に取り込み、役の一部として同化させた」からこそ、本作の二人は「奇跡的なかっこよさ」を身にまとうことになったのだ。
ゴダールの用いた「即興演出」「自然光撮影」「手持ちカメラ」「ロケ」といった新手法は、「そのため」の手段として採用された技法だ。
役者独自の魅力を見逃さないこと。それをヴィヴィッドにフィルム上に切り取って見せること。フレキシブルに役者に合わせて役を改変すること。
その「対応性」を高めるための手段が、演出における即興性であり、リアリティを付与する撮影方法だった。
それから、もう一点。
われわれは、ゴダールの名前、あるいは『勝手にしやがれ』のタイトルを聞くと、つい反射的に「ヌーヴェル・ヴァーグ」と直接的に結び付けて想起しがちだ。
実際に『勝手にしやがれ』がヌーヴェル・ヴァーグ初期の輝ける結実であることは、もちろん論を俟たない。
だが、こうやって久方ぶりに観直してみると、『勝手にしやがれ』が、題材選択においても、キャラクター造形においても、撮影技法においても、「フィルム・ノワール」の延長上にある映画だということを改めて痛感させられる。
それも、フランスによって変容させられた50年代のフレンチ・ノワールではなく、その大本にあるアメリカン・ノワールからの直摸の部分が大きい(ここ数年、シネマヴェーラでフィルム・ノワールをお勉強がてら見まくって、だいぶ脳内比較ができるようになった)。
何よりまず、本作は「ファム・ファタル(運命の女)」に狂わされる男の転落人生を描いた、典型的なノワール・プロットを採る。
試みに、Wikiのフィルム・ノワールの稿を見ると、ノワールの典型的な特徴としてあげられているのは、以下の通りである。
舞台設定(現代の大都市)
視覚的スタイル(コントラストを強め陰影を強調した画面)
テーマ(犯罪、詐欺、離別、精神疾患など)
登場人物の性格(ハードボイルドな男性主人公、謎めいた女性)
物語手法(時系列を複雑に行き来する構成、説明省略の多用など)
全体的なムード(社会に対するシニシズムや憎悪、閉塞感)
いかがだろうか。まさに『勝手にしやがれ』を説明しているかのような文章ではないか。
(まあ、本作では上記「シニシズムや憎悪、閉塞感」を超えて、ある種の「ニヒリズム」の領域に達しているのが、真に「新しい」といえるのだろうが。)
自然光の採用や、ロケによる撮影といった技法も、もともとは40年代~50年代のアメリカン・フィルム・ノワールに端を発するものだ。
トリュフォーも、ゴダールも、もともとセリ・ノワール(フランスで出されていたアメリカやイギリスの犯罪小説中心の叢書)の熱烈な愛読者であり、幾度も映画の題材に採っている(とくにトリュフォーが繰りかえしアイリッシュ原作を採用していたのが印象深い)。クロード・シャブロルなんか、たぶん撮った映画の半分くらいはミステリー映画だったくらいの推理小説好きだ。要するに、ヌーヴェル・ヴァーグの担い手にとっては、大きな霊感源のひとつが、フィルム・ノワールであり、ノワール小説だったのだ。
そもそも、『勝手にしやがれ』は、冒頭の献辞において、アメリカの低予算映画専門スタジオだった、モノグラム・ピクチャーズに捧げられた映画だ。
作中で登場・引用される映画群も、ロバート・アルドリッチの『地獄への秒読み』(59)、リチャード・クワインの『殺人者はバッヂをつけていた』(54)、オットー・プレミンジャーの『疑惑の渦巻』(49)、同『歩道の終わる所』(50)、ジョン・ヒューストンの『マルタの鷹』(41)など、総じてアメリカのフィルム・ノワールのプチ映画史を形成している。
ジャン・ポール・ベルモンド演じるミシェルの葉巻を用いたキャラクター付け自体、ハンフリー・ボガードを祖型としたものだ。
すなわち、「ヌーヴェル・ヴァーグ」というのは、「フィルム・ノワール」の「分流」――あるいは、フレンチ・ノワールとは別の形での(より本質的で批評的な形での)受容から始まった「新運動」だったのではないか、というのが僕の問題提起である。
このテーマは、二週間後にもう一度柏まで行って観る予定の『気狂いピエロ』に直接的に引き継がれ、そこでは原作であるライオネル・ホワイトによる小説版との比較が、きわめて重要になってくるはずだ。
ー ー ー ー
にしても、この僕がよりによって、ゴダール特集上映なんかに足を運ぶなんてなあ、と思うと、ちょっと面はゆくなるし、なんだか気恥ずかしい。
大昔、まだ大学生だった僕にとって、ゴダールはある種の「仮想敵」だった。
より正確にいうと、「ゴダールを絶賛するような手合い」を、勝手に敵認定して猛烈にイラついていたのだった。
今から考えるとお恥ずかしいかぎりだが、当時の僕は、映画の本道は娯楽にあると信じ、客を楽しませることに腐心している映画こそ評価されるべきだと本気で考えていたから、藝大に入れなかった私立美大生あたりが「やっぱゴダールだよねぇ」みたいなことを言ってると勝手に妄想し、反吐が出るぜ、こいつら絶対いつか滅ぼしてやると過剰反応し、レオーネやペキンパーやデ・パルマを偏愛し、「秘宝」的な映画観に大きな影響を受ける一方で、オナニズムと承認欲求に毒されている(と僕が独断で決めつけた)難解な「ゲージュツ」映画を、ことごとく嫌悪していたわけだ。
振り返ってみると、あれも若さゆえの「潔癖主義」だったんだろうな、と。
なんか、柄谷やら蓮實やら浅田やらデリダやらラカンやらフーコーやら、「当世流行りの難解な言説&芸術批評」を、さもしたり顔で「わかってるか」のように語る一部のスノッブ連中が、とにかく憎くて憎くてたまらなかったのだ。その前提には「俺がまったく何言ってるのかわからないのに、なんだよそれ! わかるやつがいるなんて信じたくないよ!」というやっかみと羨望があっただろうし、恥ずかしげもなく「難しいことを読み解いてる自分」を誇示できるメンタルの強さが信じられないというのもあった。
でも、時を経て、そのうち思うようになった。
「ちょっと待て。ゴダールにせよ、ニューアカにせよ、世間でしっかりヒットしてブームになっている時点で、それはもう十分『エンタメ』としても成功してると言えるんじゃないか?」
「たとえ難解でも独善的でも意味不明でも、一定層のスノッブを刺激して集客して彼らを良い気持ちにさせているのだとすれば、それはそれで立派な『娯楽映画』であり、お金儲けの正しい『エクスプロイテーション』ではないのか?」
この視点に気づいた瞬間に、僕のなかで「ゴダール・コンプレックス」は雪解けを迎え、ゴダール映画もまた、豊穣なるエンタメ映画の海へと還っていたのだった。
逆に最近は思う。
自分が若かったときにあれだけ鼻に付き嫌悪した、「難解さへの憧憬」という若者独特の背伸びしたカルチャーが、いまや恐ろしいことに、日に日に廃れつつあるのではないか?
ネットやSNSの「わかりやすさ」にスポイルされ、「三行」「終了」「論破」といった脳停止ワードに精神を毒された連中には、歯ごたえがあって、ちょっとやそっとでは読み解けないような評論をもっと読ませたり、一見しただけでは意味すらつかめないような映画をもっと観させたりしたほうがいいんじゃないのか?
というわけで、最近の僕はゴダール容認派であるどころか、大いに推進派へと鞍替えした次第。
みんな、もっとゴダール観ようぜ!
ひさびさに拍手したくなったこのラスト W
ヌーベルバーグ=新しい波= と言うけれど、
男女の追いかけっこと すれ違いってもんは、時代を超えて国を超えて、いつもどこでもこんなものなのではないだろうか。
(それまで作られてきた)夢見心地のおとぎ話映画ではないから、せっかく金を払って映画を観にきた人間の神経を疲れさせてくれるのかもしれないが、この会話の諧謔性は、いつもの男と女を蒸留し濃縮して見せてくれるからこそ、だからツボにハマるのだよ。
いろいろと思い当たるからね。
ジャン・ポール・ベルモンドは、ふられる男の哀切を演じてはトップクラス。
東の渥美清、西のベルモンドか。
♥
仕事に遅れるのに、朝のベッドでしょ。
警察がやってくるというのにスケとの会話一択でしょ。
そして銃で撃たれてフランキーニに見せるあのふくれっ面。
「サイテーの女だよオメェ」。
で、臨終の儀式はセルフとか。
ものすごっく幸せそうなブランキーニの表情で FIN
うわー、
カッコよすぎて、おいらも眠っていた不良の血がたぎったよ
61歳。映画館を出て、何か嬉しくって、バイクをすっ飛ばして夜の街を家まで帰りました。
スケを幸せにできなくったって構わんのよ。追いかけること、そして逃げること、それが幸せ。
破戒も、幸せ。
「あなたの野望は?」
「不老不死を手に入れて死ぬ」。
これ、ヤラレタ。
助演者も、ちょい役出演のゴダールも 粋だわ
・・・・・・・・・・
東座の支配人さん、
いい映画をありがとう。
今夜の彼女は、白の小紋を散らした濃紺にほそい縦縞のワンピース。ペチコートも?フレアのワンピースのスカートが広がっていて素敵だった。
(マスクは同じ濃紺にベージュのレース)。
薄暗いロビーでよく見えなかったけれど、気合いの入った東座は切符を買う時から映画が始まっています。
ぜひ。
·
これも映画
アフリカンもアジアンもいないパリ。ところ構わず煙草ぷかぷか(当時は当たり前か)。
とてもじゃないが、感情移入なんかできっこないチンピラ(知らない女のスカート捲ったり、カネもクルマも盗み放題、ピストルぶっぱなして警官射殺)が主人公。でも好きな女には裏切られても恨みもしないんだ、この男は。
世間の常識から映画造りの常識まで既成概念をとび超えた映画。
「どぶねずみみたいに美しくなりたい」なんて思える非・常識な感覚。「今まで覚えた全部デタラメだったら面白い」なんて思える非・常識。そんなことを考えながら面白がって観てました。
原題 "A bout de souffle"「息も絶え絶え(もうダメだって感じ?)」だってさ。
同調圧力って嫌いだから、今日はマスクをポケットに入れて外出だね。
最初にこの映画を観たのは小学生の時。それ以来ショートカットの女の子がずーっと好きです。
初めて大画面でジーン・セバーグに会えたよ。
パリに恋する
ヌーベルバーグの金字塔
4Kレストア版を劇場鑑賞。
本作は細かくストーリーを追うような映画ではなく、哲学と感性とエモーションで疾走感とオシャレと粋を表現したことで当時の批評家達にその革新性を評価され、即興的な演出やセリフ、手持ちカメラでのゲリラ的な街中のロケ撮影など当時としては斬新な撮影手法がその後の世界中の映画関係者へ多大な影響を与えている。
今回30数年ぶりに鑑賞し思ったことは、言い方は悪いかもしれないが、その時代では世に強烈なインパクトを残した最先端の映画ではあったが、決して時代を経ても色褪せない普及の名作の類ではないということ。
言い換えるとナマモノなので採れたては最高に美味しいが賞味期限がある、そんな映画ではなかろうか。
特にミシェルがホテルで一生懸命パトリシアを口説くシーンはさながら詩集や哲学書を読み合っているようなセリフの応酬が延々と続き退屈ささえ感じてしまう。
ただ、今見ると少し幼さを感じる拗ね顔のジャン=ポール・ベルモンドのさながらパリ中にあるもの全てが自分のものであるかのような自由気ままな振る舞いと愛に生きる姿は当時のパリジャン達の理想の格好良さであったのではないかと思うし、現代においてもそのファッションやクルマなどおしゃれで粋な雰囲気は永遠で憧れる。
おじさん世代にしかわからないと思うが、無様でカッコ悪いがどこかカッコ良さを感じるラストシーンは「太陽にほえろ」のマカロニ刑事が殉職するシーンとダブってしまうのだが、ショーケンもきっとミシェルの生き方に憧れてたんだろうななどと勝手に想像している。
見おろすのいいな
全77件中、21~40件目を表示