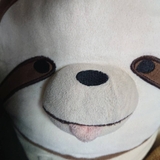チョコレートドーナツのレビュー・感想・評価
全93件中、1~20件目を表示
愛と理不尽と怒り
実際にあった話をベースに、フィクションを多分に含んだ今作。こんなにも愛しくも悲しい話が完全な実話じゃなくて良かったと心の底から思います(男の子は実際は死んでないらしい)
法と差別の間で葛藤するゲイカップル二人と犠牲になったダウン症の男の子が本当にやり切れなくて、怒りがふつふつと込み上げてきて終わったあともなんとも言えない気持ちになります。
時代的にゲイ差別が一番激しかった事を考えればこういった悲しい話も実際あったのだろうなと思います。大好きだけどもう2度見たくない話の代表格ですが最初のシーンの伏線が回収されるのでぜひ2回目を見て欲しい。
他人の愛は理解しがたい
同性愛者への理解に乏しい時代が、愛し合う家族の絆を引き裂く悲劇。として観たものの、自分にも反省する所のある話だと思いました。
例えば美女と冴えない男のカップル、大きく年の離れた夫婦、子どものいない家。世の中は、自分には理解できない愛であふれています。口に出さずとも「何か事情があるんだろうか?」と邪推してしまうこともしばしばで、その上同調が得られれば、即席の正義感で関係を壊すかもしれません。
あの時代の「同性愛」は公然と邪推し、攻撃して打ちのめすことを許された、大衆にとって不可解な関係の1つだったのでしょう。上司がわざわざ薬物依存の母親を解放してまで主人公を妨害したのもそのためではないでしょうか?
見返りのない愛は自分事しか信じられない。
人は身勝手な生き物です。
アラン・カミングの微笑は、何かこっちまで安心するくらい温かくて優しくてよかった。
邦題が秀逸。
この手の題材は苦手だが観て良かった。実に実話がベースとのことだが、1970年代と今では状況が一変しているので今ではこのような作品は今では逆にリアリティがないかも?チョコレートドーナツという邦題は秀逸で、オリジナルのタイトルよりもずっと良いと思う。何度もチョコレートドーナツを食べる場面が出てくるものと勝手に想像していたが見事に裏切られた。
本当の意味で殺したのは誰か
この物語はマルコが好んだハッピーエンドではない。正義が勝つ話でもない。結局差別がなくなる訳でもなく、どうしようもない世界は続いていく
ここで重要なのはマルコを殺したのは誰か?という話だ
この映画を観たら、「母親」だと答える人もいるだろうし、差別主義者の「判事」や「裁判に関わった人」だと答えるかも知れない。母親と司法取引をした男かも分からない
でも俺はマルコを殺したのは他でもなく、ルディとポールではないかと思った
月曜から夜ふかしで、独り身の女性が出演した時、誰かとご飯を食べたいと言ってスタッフが招かれて料理を作り振舞った。女性は誰かとご飯を食べれた事が嬉しく、美談のような形で終わった
けれどマツコは女性に「人とご飯を食べる喜び」を教えたのは本当に正しいことだったのか、と言った。スタッフの行動は本当に善だったのか、と。女性に笑顔を与えたのは確かだが、その女性の孤独をより濃くしたのもまた事実だ
マルコはルディとポールという暖かい存在を知らなければ、愛のない冷たい部屋で生きていけたかもしれない。それはただ息をするだけの「生きてるフリ」に他ならなかったかもしれないが、それでも死ぬことはなかっただろう。家庭丁の保護下にあるか、出所した母親のネグレクトに近い形でかろうじて生きていくことは出来たはずだ
最後マルコは「家に戻ろう」として死んだ。家とはまさに母親の家ではなく、ルディとポールの家だ
ルディとポールがマルコに愛を与えなければ、その存在を知られなければ、マルコは生きていけたかもしれない
愛を知ってその温かさを求め死ぬか、愛を知らずにただ息をするだけで長く生きるか。そのどちらがいいかは分からない。マルコはそのどちらがいいかを考える知能もなかっただろう
ルディとポールはただ善意と愛でマルコに愛を与えた。その結果がマルコの死だとして、その二人の行動が間違っていたとは言えない。差別がなければマルコは二人の元で笑顔で暮らす未来を掴めていたはずだ。だから悪いのは差別そのものなのかも知れない
けれどこれはポールの言葉の「解」になっている。ポールは理想を捨て現実に生きていた。そしてルディに触発され、正義と理想に立ち向かった
ポールはこれは差別ではなく事実だ、と言った。差別される世界を消すことはできないし、その「構造」の中でどう生きるかという問題でしかない。これはある種で諦念のように思えるかもしれないが、差別のある世界での生き方への解として結果的に正しかったものなのかもしれない
それが間違いだと思い、ポールは立ち向かった。その結果としてマルコを死なせたのだとしたら、やはりこの世界に正義はないのかもしれない
それでも、そのただの幻想に過ぎない理想の為に命を削ること。それを人は「生きる」と呼ぶのではないのだろうか
やるせない・・・
なんだか心がすさんでしまってどーしていいかわからなくなってしまっていた今日この頃、無性にこの映画がまた観たくなった。
偏見と人のエゴに満ち溢れたこの世界に翻弄されながら時折くったくのない笑顔を見せながら生き抜いているダウン症の少年マルコ。その健気な姿に心打たれ、同じく偏見に苛まれながらそれぞれの人生を歩むゲイのカップルが家族に迎え入れる決心をして無機質な法や偏見やエゴと闘う。
結末があまりにも切なくて気持ちの持って行き場がなくなるが実話をベースにした作品であり、これが現実の世界と思うとさらにやるせない。それでも人のやさしさのパワーを感じさせてくれる作品です。
ゲイカップルの話かと思いきや
ゲイバーで歌と踊りを披露しているルディ、ゲイを隠しながら検察官をしているポール。
2人が仲良くなり、恋愛模様が描かれるストーリーかと思ったら違っていた。
ルディの隣部屋に住む親子は母親が育児放棄でクスリにのめり込み、子どもであるマルコは自閉症。
ある日その母親が逮捕されて、ルディがマルコの面倒を見ることにした。
ルディの聖母の様な愛情深さとダイナミックな行動力が素敵だった。
ポールはルディとの関係や自分の性癖を隠したがっているのも、今でこそオープンマインドな時代だけれど差別や偏見まだまだ強く根付いている1980年代が舞台だそうなので仕方ない。
マルコが母親の元ではなく、ルディとポールの元に戻られたならどんなに幸せだっただろうと心が傷んだ。
他者を認める
アラン•カミングさんを初めて観たのは、
ドラマ『グッド•ワイフ』。選挙請負人?
短髪でいつもスーツのキリッとした紳士。
ルディの外見にはちょっとビックリした。
職業はバーの歌手&ダンサー。
女装してドラァグクイーンだが見た目ムサい。
もっと歌手として活躍したいと希望を持つ。
パートナーのポールは弁護士。
離婚歴がある。
ルディと付き合う時点でカミングアウトはしていない。
国が違うからか鈍いからか、
男性2人が連んでいても友人だな、ぐらいにしか。
だが、作品中では2人をゲイカップルと決めつけた
言葉や態度が何度も見受けられた。
さらに蔑みの視線。
🇺🇸では同性愛者の権利が州法により様々らしいし、
人々の意識なんて想像できない。
数年前に教育用として
お父さんと多分10歳前後の息子が出かけボートに乗る。
そこへお父さんの恋人❤️として男性が一緒に乗る。
3人が楽しく談笑する様子のストーリーが表された
絵本を見た。
どこの国だったか?欧米だった。
ポールはルディから何度も認めろ、カミングアウトしろ、
と促されていたが、なかなか。
職業柄、言いにくいのもあるのだろうか。
この事もいろいろ考えさせられる。
同性愛は、私の理解の範疇を超えているのだが。
愛情というのは、本人の気持ちによるモノで、
他者が愛せ、嫌え、と言ってもできるモノでは
無いとはわかっている。
だから、異性ではなく同性しか愛せないのなら
仕方ないことだと思う。
この考えからだと偏見や差別が生じない筈だが、
現実は違う。
子孫繁栄から考えただけでも間違っていると
捉えられるのかもしれないが。
そして多分、人間だけだろう。
ルディたちがマルコに執着する気持ちがわかりにくい。
法廷でポールが、
「太って背の低い知的障害児を誰が養子にする?
俺たちしかいない。」 と言ってた。
この言葉では理解しにくい。
マルコの純粋無垢な心❤️が好きだったのか⁉️
法廷で裁判長がいろいろな証人の話のもとに、
2人が愛情豊かにマルコに接し、
マルコも2人が好きでいろんな面の成長もある、
と認めているのに‥‥。
検察の差し金か、マルコの母を異例の措置で
釈放して、マルコを引き取らせる。
実の母子が一緒になるのだから、ルディたちには、
手も足も出ない。
子を思う普通の親子なら幸せだったかもしれないが、
そうなら以前にマルコがひとりぼっちには
なったりしていない筈で普通の親子じゃなかったからだ。
なぜ裁判所とかはこの事実に目を向けようとしないのだ。
母親が急に子供思いになったと思っているのか。
マルコの人権を無視したな、みすみす‥‥と私は理解。
ルディの前向きな性格に勇気をもらえる
色んなところでおすすめされて気になってた作品。障害者とLGBTの話とかどうせお涙頂戴でしょ?と期待してなかったけど、今作は最初からグイグイ引き込まれた。
ルディの前向きな性格に勇気をもらえた。ただでさえ自分がゲイで生きづらいのに、他人の子でしかも自閉症の子を育てようとする覚悟がすごい。
アラン・カミングの演技力も抜群で、見た目はおっさんなのに立ち振る舞いとか仕草で女性にしか見えなくなってくる。
ハッピーエンドじゃないのに驚いた。マルコの「ハッピーエンドが好き」発言は死亡フラグだったのか...。
ただ個人的にハッピーエンドは好きじゃないので、バッドな終わり方で好きだな。こっちの方が現実は上手くいかない感が出ててリアルに感じたし、難しく重いテーマの雰囲気と合ってたと思う。
マルコかわいい。
ラストが読めてしまったのが残念。
事実はどうなのか知らないけど、
でもそれが一番ましな終わり方なのかもしれないと思った。
あのまま二人を待ち続けて生きながらえると思ったらやり切れない。
途中あれやこれやと考えてしまって消化不良。
でも何度観てもそうなのかもしれない。
アラン・カミングが好きで観たけどやっぱり大好きなアラン・カミングだった。
とりあえずマルコが素晴らしくかわいかった。マルコかわいい。
人々が寛容でない時代の歪み
................................................................................................
主人公のオカマの隣人がドラッグで逮捕、子供が施設に預かられる。
この子供はダウン症で、施設がイヤで自宅に戻って来た。
オカマは哀れに思い、自分が親代わりになろうとする。
オカマの恋人は弁護士で、手続きを踏んで里親になる。
ところが当時はまだオカマが受け入れられない時代だった。
オカマの恋人の上司が2人の関係に気付き、恋人はクビ。
さらに裁判所に裏から手を回され、この子供も2人から取り上げられた。
そして本当の母親が子供を引き取る約束のもと出所を許された。
その母親は、この子供を毛嫌いするろくでもない男と交際した。
愛情に飢えた子供は冬空のもと、昔の家に戻ろうとして凍死。
................................................................................................
実話をもとにつくられた作品らしい。
性に寛容なアメリカでも、少し前までオカマに厳しかったのな。
オカマにせよダウン症にせよ、理解され出したのはほんの最近なんやなあ。
もう少し実話に寄せても良かったのでは
ラストが残酷すぎる。。現実のルディさんは美容師だったようだし、マルコの母親がジャンキーなのと、近所に住んでたルディさんがマルコを育てたのは事実らしいけど。その他は全くの創作だから、現実はあんな悲しい最期ではないと知ってホッとはしたけど。実際はどうだったのだろう?他人の子どもを、ましてや障がいのある子を育てるなんて、なかなか出来ることではないし、苦労もしただろうし、ルディさんは本当にすごい人だったんだなぁと尊敬する。
そしてこの映画は配役が良い。アランカミングさんは表情も演技も、本当に魅力的な人だなぁ、とファンになった。マルコ役の子もすごく可愛かったし。ヒガシの舞台も良かった。
人に優しくなれる作品
テーマが重そうで敬遠していたが…評判通りこれは間違いなく名作だ。
やはり重いテーマだったが、できるだけポップに描かれているので救われる。
そして主演2人の表情がとて印象的で、目が離せない。思い出の8ミリビデオシーンはよくある系だが、本作では特に効果的でグッとくる。
「過ぎた望みですか?」「子供のためを考えてください」「一人の人生の話だぞ」このシンプルな想いが、なぜ届かない?
「小さく埋もれた記事」「あんたらが気にも留めない人生だ」本当に残念で怒りも湧かないほどに落胆してしまった。
なかなか差別が無くならない人間社会、本作品の時代設定から40年ほど経った現在において、果たして同じ過ちを繰り返してはいないと本当に言えるだろうか。
忘れてはいけない
ハッピーエンドが大好きな魔法少年 マルコは、ハッピーエンドにはならなかった。
時代のせいにしてはならない。
我々の心の中に幾分ばかりかある偏見が、こういう悲劇を起こしてしまうことを、忘れてはいけない。
同性愛に関する意識は変わりつつあっても、日本の法律は・・・
実の親でも子供の前で教育上よろしくない言動は日常的にあるのに、
愛情持って環境整えて、愛情持って接して、ちゃんと栄養考えてご飯食べさせて、教育支援もして、すごくよくがんばっても、同性愛は親として相応しくないという理屈がよく分からない。
今も子供の前で女装や同性愛カップルがキスをするのは教育上よろしくないとされているのかな。
この映画では、彼らが同性愛カップルだから、という偏見のせいで、
実の母親を無理矢理釈放してまで、引き取らせて悲しい結末になった。
昔の映画らしい、悲しさを強調する為の嫌味な終わり方だな、と思ったけど、
昔じゃなくて今でも日本では、実の親という理由で、とんでもない親に戻して子供が命を落とすニュースがある。
親としての素質を見ず、実の親の元に返すのが一番、という日本人の頑な偏見で、日本の法律や法に関わる人達の判断はこの映画の1970年代から進歩していない事実に恐ろしさを感じる。
というわけで、多様性よりそちらの方に意識がもっていかれてしまいました。
マルコが戻りたかった場所
嘘がなくストレートに愛を表現するルディ( アラン・カミング )の慈しみに満ちた表情、切々と情感豊かに歌う姿に魅了された。
ダウン症のマルコ( アイザック・レイヴァ )の無垢な笑顔が切ない。
子供は親を選ぶ事が出来ない。その事実は、時に残酷だと改めて感じた。
ー恥を知る事ね
NHKを録画にて鑑賞 (字幕版)
不必要なセンセーショナル
本作では知的障害を持つ少年をゲイカップルが保護し、家族として暮らす…という物語からいわゆるLGBT差別的な展開を見せます。
広告でも「1970年代アメリカであった実話を映画化」などとしていますが、その実態は「ゲイが同じアパートのネグレクト男児を保護していた」程度のもので、本作の大部分は創作のようです。
本作が何をテーマにしているのかは正直わかりません。
LGBT差別を問題にしているのであればもっと正しい描き方はあったと感じます。
ひたすらに邪悪に描いた母親や社会と比較してゲイカップルが優れているなんてそれこそ差別意識全開だと私は感じます。
ゲイへの偏見に塗れて悪意のある質問を繰り返す検察。
子供のことを顧みない薬物中毒の母親。
育ててくれているゲイカップルを慕い、施設から脱走する少年。
悲痛な訴えも聞き入れてもらえずに少年と家族になれなかったゲイカップル。
ありとあらゆる悪意と悲劇を作中にこれでもかと投入します。
脚色と演出からは「酷いでしょう?悲しいでしょう?憤りを感じるでしょう?」という作り手側の意思を感じました。
正しいはいつも間違える
悔しかった。何も誰も悪くないのに、なんでっつらくて悔しかった。正しいのかもしれないけど、その正しさで誰かの人生が蔑ろにされてしまう可能性を、ちゃんと考えないといけない。正しいは全てでも、正義でもなんでもない。
私も、ハッピーエンドが好きです
多くの映画レビュアーさんたちが口をそろえて「素晴らしい映画だ」と言っている本作。日本公開時に1館のみでの上映しかなかったところ、映画コメンテーターのLiLiCoさんが積極的に働きかけて全国140館規模にまで拡大したそうです(LiLiCoさんご本人が語っています)。
作品のざっくりとしたあらすじだけ知っている状態での鑑賞でした。
結論ですが、非常に素晴らしい映画でした。
今以上に性的マイノリティ(LGBTQ)に対して差別的であった1970年代のアメリカで、ゲイのカップルとダウン症の男の子が疑似的な家族として一緒に暮らす物語。血のつながりや戸籍上の関係は無くても、そこには何者にも断ち切れない強い絆があります。ラストの展開は思わず涙がこみ上げてくるほどに悲しく美しい終わり方でした。ラストの展開に対しては「胸糞」と言っている人もいらっしゃるみたいですが、私は「胸糞」というより、とにかく「悲しい」という印象でしたね。
・・・・・・・・
同性愛に対しての偏見が強かった1970年代のアメリカ。歌手を夢見ながらショーパブでパフォーマーとして働いていたルディ(アラン・カミング)は、客として来店していたゲイであることを隠して検事局で働くポール(ギャレット・ディラハント)と恋仲になった。ある日、ルディはアパートの隣室に住んでいたダウン症のマルコ(アイザック・レイバ)が母親から育児放棄されている現場を目撃。そしてその母親が薬物で逮捕されてマルコが独りぼっちになってしまったのを知り、自分が親代わりとして彼を守ることを心に決めたのだった。
・・・・・・・・
この映画を観て真っ先に思い浮かべたのは、2020年に公開された草なぎ剛主演の名作映画『ミッドナイトスワン』でした。「トランスジェンダーの主人公」「育児放棄された子供」「疑似家族として絆を深める」「トランスジェンダーであるが故の社会からの偏見」などなど、共通する部分が数多くありました。公開順で言えば『チョコレートドーナツ』の方が6年も早いので、『ミッドナイトスワン』は本作の影響を色濃く受けてるのかもしれません。冒頭は「展開が似ているからストーリーも同じ感じかな」と思っていましたが、ストーリーが展開していくにつれて『ミッドナイトスワン』とは全く違う展開になっていったので、新鮮味を感じながら鑑賞することができました。
前半はルディ・ポール・マルコの三人が、社会の偏見がありながらも家族として絆を深めていく非常に美しい展開です。私はこういう「疑似家族モノ」に弱いので、ほっこりしながら鑑賞していきました。マルコを演じるアイザック・レイバの表情の演技が素晴らしく、彼の笑顔を観るとこちらまで笑顔になってしまいますね。
しかし後半、彼らの絆を引き裂くような重く悲しい展開が待ち受けています。社会制度や偏見によって、幸せに思えた関係が唐突に終わりを告げます。マルコはルディとポールから引き離され、釈放された母親に預けられ、母親は相変わらずクスリと男遊びばかりの育児放棄。マルコは自分の家を求めて町を彷徨い、最後には橋の下で……。前半の幸せが嘘のような、あまりにも悲劇的な展開です。
ルディとポールが迎えに来てくれるのを楽しみにして、荷物をまとめて待っていたマルコ。母親に引き取られた後に「おうちじゃない」とずっと言っているマルコ。思い出すだけでも涙が出てくるようなシーンですね。
最後にポールが裁判官や検事局の元同僚に対して手紙と新聞の切り抜きを送るシーンも観ていてキツかったですね。手紙を受け取った彼らも自分のやったことに多少の罪悪感を抱くことになったでしょうが、「こんな悲しい復讐劇があるか」と、なんとも言えない悔しい気持ちになりました。
前半の幸せな展開から後半の悲しい陰鬱な展開への落差があまりにも大きくて、これが「胸糞映画」と言われる所以なんでしょうね。『セブン』みたいな胸糞映画とは違うタイプの胸糞。個人的にはどちらかと言えば「儚く美しい」って感じの印象を抱いたので、あんまり「胸糞」には思えなかったですけど、元気な時に観ないと数日引きずるタイプの映画でした。
もしかしたら観ていて辛く感じる人もいるかもしれませんが、絶対観て損しない素晴らしい映画でした。私が今年観た映画の中で間違いなくベスト3に入ります。オススメです。
ハッピーエンド
あまりにも切ない物語。
ずっと胸が苦しくて、ハッピーエンドを迎えるための準備だと思いながら鑑賞。
予想外に悲しい終わり方をした。
愛には人それぞれ形がある。
この映画を観て、愛に対する偏見が無い、本当の愛について考えられる人が増えればいいと思う。
全93件中、1~20件目を表示