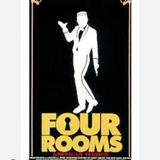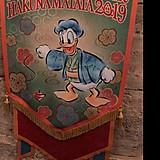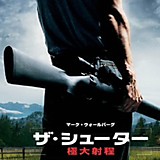大統領の執事の涙のレビュー・感想・評価
全119件中、21~40件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
教科書やニュースで知ってはいたハズだけど・・・
こんなにも近年まで(いや、今もだよね)強く激しい差別が続いていることに
改めて気付かされた。
「息子は犯罪者ではなく、アメリカの良心のために闘ったヒーローだった。」
それに気付き、長男と和解したシーンは胸が熱くなった。
奴隷から自分達で権利を勝ち取り、大統領まで出した黒人の勇姿
自分の無知さを思い知り、恥ずかしくなりました。
もちろん事実としては知っていたことですが、改めて黒人の方の視点にしてみると想像以上に辛いものです。
今では大方当たり前になっている人種差別撤廃の考え方も、本当に少し前までは当たり前ではなかったんだということがよくわかる作品でした。
とにかく、主演のフォレスト・ウィテカーさんと妻グロリア役のオペラ・ウィンフリーさんが良かった。
もちろん夫婦間の愛みたいなものも良かったのですが、子供が小さい頃から最後に老いていくまで同じ人とは思えないほどでした。
主人公のセシルを中心に時代が動き、彼の身の回りもどんどん変化していく。
父親は大統領に支え、2つの顔を使い分ける一方、長男は何度逮捕されても自分達の権利のためには何度でも立ち上がる。
次男はアメリカの国のために戦う。
そしてそれを見守る母親。
同じ家族といえども立場が違うとこうも意見が変わってくる。
KKKのシーンは本当に怖かったです。
教科書では写真としてしか載っていませんが、映像(勿論実際のものではありませんが)で見ると本当の恐ろしさが見えてきました。
ケネディ大統領が理解を示した矢先、暗殺されてしまったシーンとオバマ大統領が見事当選を果たし、Yes,we canと言い、終わるラストが印象的です。
ラストは遂に報われ、バラクオバマという救世主が現れたかのようでした。
綿花畑で父親を目の前で撃たれたところからオバマ大統領の当選で締め括るという非常に物語性のある締め方だと思いました。
途中でかなり下ネタを挟むのですが、これがなかなか良いスパイスになっていました。
下ネタなんかを挟むと何気ない会話といった感じになりますね。
理解しあうということが難しいことだと感じました。
執事として使えること、人権活動をすること。
やりたいことを親に認めてもらうこと。
心の奥底が見えないほうがいいこともある。
人権を獲得することの大切さがわかりました。
理解しあうということが難しいことだと感じました。
題名から想像していたのと違った…邦題が悪すぎる。
断片的なエピソード・・
物語はワシントン・ポスト紙に載った実際のホワイトハウスに34年務めた執事ユージン・アレンの記事に触発された脚本家ダニー・ストロングによって書かれたが話を劇的にするため、綿花畑での惨事や息子の戦死ほかフィクションが多く含まれる。奴隷もどきからオバマ大統領誕生までの主人公や黒人たちの苦難の歴史は感慨深いが執事の物語として観るとエピソードも少なく「日の名残り」の老執事と主人の関係ほどの深みが描かれていないのが残念に思えた。
考えてみれば職を辞したとはいえ執事の守秘義務、忠誠心は堅いのだから「家政婦は見た」のようなスキャンダラスな話が表に出てくるわけもなく家庭問題で尺を埋めざるを得なかったのだろう、タイトルに騙された気もする。
本題の人種差別について考えてみた。アメリカの人種差別の根はいわば白人至上主義だからインディアン狩りに始まり黒人奴隷、ヒスパニック系、アジア系移民まで広く及ぶのである。差別撤廃は人道主義的見地からと信じたいが政治家特有の計算も見え隠れする。産業構造の変化や人種構成も変わってきており能力評価主義に動いているがプア・ホワイト層の不満を扇動したトランプ政権の台頭により雲行きも怪しく見える。人種差別を扱った映画は多いがいまや新たな格差社会が台頭してきておりAIに仕事を奪われるといった話が実しやかに語られる時代になってしまった。映画で定番の近未来は悲観的なディストピアが多いがそこではどんな人間の黒歴史が上映されているのだろうか・・。
【黒人米大統領執事は自らの感情を表に出さず、7人の大統領に仕えた・・。2時間でアメリカの正当な近代史を学べます。】
セシル・ゲインズ(フォレスト・ウィテカー)が仕えた7人の大統領。
1.ドワイト・アイゼンハワー(ロビン・ウィリアムズ)
2.ジョン・F・ケネディ(ジェームズ・マースデン)
3.リンドン・B・ジョンソン(リーヴ・シュレイバー)
4.リチャード・ニクソン(ジョン・キューザック)
5.ジェラルド・R・フォード(・・・)
6.ジミー・カーター(・・・)
7.ロナルド・レーガン(アラン・リックマン)
ナンシー・レーガン(ジェーン・フォンダ)
と、劇中では各年代の重大な出来事 ”キューバ危機” ”ケネディ暗殺” ”ベトナム戦争” 及び数々の ”黒人問題” が描かれる。
激動の時代でも、セシルは黙々と執事を務める。
”世の中を良くするために、父さんは白人に仕えている・・” という彼の言葉に息子ルイス(デヴィッド・オイェロウォ)は反発する・・。
<近代、アメリカ史を黒人の視点から描いた作品。親子の物語でもある。
ラストは涙が溢れます。>
<2014年2月15日 劇場にて鑑賞>
静かに胸にせまる歴史絵巻
尤も、本当に理解するには、USAの文化面も含んだ知識が必要。
「俺は絶対やめないぞ」だけで表されるウォーターゲート事件。
突然画面に現れる兵士の映像。ベトナム戦争。
そして、差し込まれる当時のバラエティ番組。
ひょっとしたら、バックミュージックも、当時を知る人ならその意味合いも一緒に感じ取れるのか?
”ニガー”と呼ばれた方々が経験してきた話を、政策とともに描く。
端的に要点だけを映像化して、全体の流れを見せてくれる手腕は見事。
でも、自分の勉強不足もあって、置いていかれている感が半端ない。
見ているだけでも心が凍り付いたKKKの襲撃、
実際の当時の映像も混ぜて描かれる斬撃等
激しい差別が行われている一方で、
ホワイトハウスで、要人の生活を支える役職に就く黒人たち。
芸能分野で、時代を作り、世界を魅了している黒人たち。
それでもの、制度としての差別を表現したいのか。
”あの”時代、否、USAの現実を肌で知らないことを思い知らされ、映画の中に入り込めない。壁一つ隔たれたところから絵巻を見せられているようで、もどかしい。
知識不足を感じたのは、時代観・生活感だけではない。
ホワイトハウス内でのセシルの位置にピンとこないのだ。
”執事”。
日本では、室町時代では、将軍を補佐する最高職のことである。
また、映画や漫画・アニメ、小説でのイメージだと、その家の家事や使用人を束ねる役目。使用人の中では、ハウス・スチュワードに次いでNo.2と認識していた。
だから、映画の中で「黒人は出世できない」と言われてもピンとこない。「黒人は白人の給料の4割」とか言われても、JFKに挨拶していた職員は皆黒人で、出てきた白人職員は人事部長のような人だけだったし。
上流・下流、勝ち組・負け組という言葉はピンと来ても、欧米での支配者層と被支配者層と、日本での感覚が違うからか、今ひとつピンとこない。
と、もどかしさがこみあげてくる。
それでも、短いエピソードの中にも、各大統領の人となりを描き出していて興味深い。
自分の打ち出した政策がなかなか浸透しないことにいら立つアイゼンハワーをロビン・ウィリアムズ氏が端的に表現する。こんな表情のロビン氏は初めて見たような気がする。
理想主義のお坊ちゃんを演じさせたら右に出るものがいないマースデン氏はJFK。ジャッキーの慟哭に胸が引き裂かれる。
ジョンソンとニクソンは狂言回しか。
セシルを重用したとされるレーガンとレーガン夫人の、一見相手を大切にしているように見せつつ、人を利用してはばからない様子に唖然とする。そりゃ、レーガンの時代に辞めたくなるよ。
ただ、セシルと彼らの心の交流が台詞だけで語られるので、今一つ腑に落ちない。
「君は国のために尽くしてくれた」レーガンが言う。寿命が縮むと言われる激務をこなす大統領が、その人なりの明晰な頭脳と心で、決断できるように、生活を整える。彼らがいたがからこそなしえられることであろうということはわかるが、そのなかでもセシルが特別なのはどういう点でなのか?
もどかしい。
ルイスを狂言回しとして、ホワイトハウスの外で起こっていることを並走して描き出すのだが、これもまた、上記のことも絡んで、記録映画のようになってしまった。
そんな絵巻の中で、翻弄される一つの典型として描かれる家族。
”あいつらの国”に間借りして、”あいつら”を恐れ、期待した父、
”あいつらの国”に自分たちの居場所を作ろうとした息子たち。
権利を主張し行使する長男。
”あいつらの国”のやり方に組する(”あいつら”が始めた戦争に参加する)次男。
その間に挟まれた母。
そしていつしか…。
そんなセシルを演じたウィテカー氏。セシルが一歩踏み出す様と『ケープタウン』を思い重ねると、感慨深い。
そして次男を演じたケリー氏。『ヘアスプレー』を思い出す。
グッディング・Jr.氏は、この重苦しい物語の中で、『ザ・エージェント』で見せた軽いノリと落ち着きとを見せて、おかしみと安定を与えてくれる。
ハワード氏は『クラッシュ』で見せたインテリとは真逆の役。幅広い役者だ。
レッドグレーヴさんは、『MI』や『ジュリエットからの手紙』とは全く違う、田舎の女地主主人を見せてくれる。
駆け足で巡る絵巻。
走馬灯のよう。
映画館で観た方が映画に集中できたのかもしれない。
家で見ると、ググりながら見たくなってしまう。
そんな風に、その奥に隠れている本当に大切なものを共有しきれないもどかしさが尾を引く。
浅学な私が悪いんだけどさ。
歴史授業で見せたい映画
歴史の授業にピッタリ
映画の総括としては、普通かなと思った
映画館で見ても、損はない映画だと思うけど
「映画」として見たときに物足りなさを感じる
しかし、歴史コンテンツとして見たときにとても分かりやすく
まとめられていて、いいと思う
フォレストガンプの対にはなっているが対抗は出来ていない作品
気にはなっていたが視聴しそびれていた一作。町山智浩さんの評にてフォレストガンプへのアンチテーゼとして作られたと聞き、興味が湧いて鑑賞。
なるほどフォレストガンプが“見なかったこと”にしていた負の歴史を描いており、対になる一作だった。
しかし、人間性はよろしく無いが才能だけは抜群のロバートゼメキスのフォレストガンプと比べると描いている時間も舞台も似通っているのに何か物足りない。それは画の力だと思う。
この作品は基本的に主人公の家、ホワイトハウス、長男の目線という3つから構成されているのだが、あともう一つ必要なものがある。それは一般人の目線である。
ゼメキスはスタジアムの観客、抗議デモの観衆といった具合にその時代に生きていた当事者以外の人々を挟んでいるが、本作はそれが無い。そのためアメリカの負の歴史を描いているのに、とても規模が小さいように感じるのだ。戦争映画で司令室とその側近の家庭ばかりで肝心の戦闘シーンが無いというか。
例えば長男がセルマの行進に参加したり、ブラックパワー最中のナイトクラブといった、その歴史の中で流された群衆を入れていれば世界感を広げて描けたと思う。
また本作は50〜80年代のアメリカを生きたある黒人一家を通じて描かれるが、この一家にいる三人の黒人男性は、
・体制に従属した黒人=父
・体制に挑んだ黒人=長男
・体制に使い潰された黒人=次男
の3つの状態を表している。
ラスト体制に従属した者も挑んだ者も融和しオバマが生まれる、という流れだ。
しかし、この映画の肝というべき家族の誕生が描かれない。
1シーンづつでいい、嫁との出会い、長男の誕生を3〜5分でいいから入れるだけでこの物語の出発点を示すことが出来る。
が、それをしないが為に主人公にとっての嫁、子供といった家族の慈しみに乗れないのだ。家族を失った主人公が自分の家族を得る為に生きた軌跡を描くべきだった。
また次男の死が無駄になってしまっているとも感じた。父と長男が対の存在であるのならば、その融和は次男の死がキッカケになるべきではないかと思う。
次男が死んだ時点で父がホワイトハウスを、辞め息子と寄り添うという感じに。
フォレストガンプの対にはなっているが対抗は出来ていない作品だと感じた。
面白くはない
・無駄にキスシーンが多くて不快感を感じた
・ストーリー自体は史実に基づいていて
勉強になると思うが、
流れの中でどんなことを学びどう受け止め身につけ
それを行動に反映していったのかなどの
感情の動きなどに関しては演者の演技力任せで、
しっかり描かれているとは言えず、
あまり良かったとは思わない
・ほかのバトラーが、
どんな経緯でホワイトハウスで
雇われるようになったのかも見たかった
・日本と外国では恐らくデモ参加への意識が
また違うだろうからかもしれないが、
離職後にデモに参加し留置所に入ることに
かなりの違和感を感じた
・息子をはじめとする有色人種の行動によって
結果的に現代の法としては
差別の緩和・解消に繋がっただけの話で、
これを見て「気に入らないことがあったら
断固反対の姿勢で挑めばいいんだ!」となる人が
出てしまわないといいな、と思った
固い決意を持って田舎を出たかと思ったのに
窓ガラスを割って商品盗んで
謝罪もなしに仕事くれとか、驚いた。
まともな家族の中で
まともな教育を受けることができないから
そうなってしまうのもあるだろうし、
それが元で野蛮だから
近寄りたくない関わりたくないと
なったのもあるだろうし、
こうした負の連鎖は
現代でも起こりうることだな、と思った。
二つの顔を持て
人権という大きな障害とは。
トランプ前・トランプ後
ざっくりとしか知らない、アフリカン・アメリカンの暗黒時代を、
大統領執事となった男の人生を通して、生々しく垣間見ることが
できました。
この執事ひとりの存在が、いかにこれまでのアメリカ大統領の
政策に影響を与えたか。やはり大統領とはいえ、人間だもの、
身近で従順に仕える人間に対して情を感じないわけにはいかない。
ラストは…
トランプ次期大統領確定後に初めてこの映画を観た自分的には、
ああ時代はめぐるのだな…という、軽い絶望感。
前だったら、希望に満ち溢れてキラキラ輝くエンディングシーンと
なっていたことでしょう…むう。
ホワイトハウスのニガー
総合80点 ( ストーリー:80点|キャスト:80点|演出:80点|ビジュアル:70点|音楽:70点 )
黒人の人権を求めての戦いの歴史を、執事になった一人の男を通して描く。苦難の少年時代を送り、差別されることを受け入れ政治をあえて無視することによりかろうじて生活が出来る居場所を確保した黒人は、それを守るためにそれ以上の進歩を否定し戦おうとはしない。
一方で息子はそんな父親と正反対に、差別を認めず危険を犯して黒人の地位向上のために戦い続ける。もう一人の息子はそんな米国のために戦い命を懸ける。その対比が時代の変遷を物語っていた。
やはり一朝一夕に社会は変われない。黒人差別の撤廃だっていきなりそのようなことが出来るわけではなく、まず白人の支配から逃れて生活の場を確保し、そこから徐々に黒人の権利を主張する。そのためには数十年の時間が必要なのだ。
20世紀前半は勿論のこと、戦後でもまだまだ差別は根強く続く。70年代ですらホワイトハウスでニガーという言葉が普通に使われ、80年代のホワイトハウスですら黒人というだけで給与と昇進に差がつくというのは驚くと同時にがっかりする。オバマが出るまで長かったが、それでも少しずつ時代は変わっていく。その変遷が主人公の一生を通じて上手く描かれていた。
全119件中、21~40件目を表示