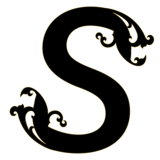インターステラーのレビュー・感想・評価
全986件中、181~200件目を表示
総合芸術としての映画の力
観る前は、どうせノーランでしょ?とか思ってて申し訳ないです。
不整合なんてどーでも良くなる程のテーマ、設定、プロット、脚本、外部参照、内部参照、キャスティング、演出、演技、撮影、美術、音楽、そして腕力。
総合芸術である映画の醍醐味を堪能できます。
テーマや設定に主眼を置く人、SFに拘りがあり過ぎる人の中には不整合をスルーできずに微妙な評価を下す方も居そうなきがするけど、映画の本質ってそれだけではないという事を強く再認識させてくれる作品です。
ノーランらしく、分かり易い外部参照が片手じゃ数え切れないくらいあってその話だけで朝まで飲めそうな勢いなんだけど、本作は特に内部参照が素晴らしい。
何気ない会話でさえ後々効いてくるし、それが一々気が利いてる。そう、良い『再帰性』。
美術もヤバくて謎事象の表現は現時点では200点だと思います。
アレ見て触発されたり悔しがったりしてる人多いだろうなー。
クリストファー・ノーランって、設定・画づくり(美術、撮影、空気感)とかはサイコーなのに、脚本とアクションシーンの撮り方がアレで勿体ないってイメージだったけど(ダークナイト・ライジングとかメメントとかプレステージとか)、既往作品のバランスの悪さも好きになってしまうかもしれません。
今作で巨匠の域に到達したと言っても過言ではありません。
映画が終わってしまうのが寂しくて何だかよくわかんない涙が出て来たのは久しぶりでした。
個人的にはノーラン作品の最高傑作
もう少しだけ現実味があれば…
大作ぢゃん!
カメ止めのような読後感
友人が一番好きな映画と聞いてみてみました。
しかし、私にはあわなかったようで、何度か挑戦したものの毎度途中(他の惑星行ったところ)で飽きてしまうんですが、やっと見れたので記録として残します。
2時間50分のうち、2時間20分で起承転結の転がおこる。2時間35分から結。
ながい…。そこにいたるまでがながい……。
・この世界はこうです
・登場人物はこういうことで悩んでいます
・解決方法を見つけました
・その解決方法は犠牲が伴います
・解決方法を試します
・少しづつ犠牲の範囲が広がってきました
・解決方法だと思っていたものに問題があります
・絶対絶命
からの転(2時間20分)。
つまり、2時間20分までずっとこの世界と登場人物の説明。そして、わりとセリフ映画。
丁寧といっていいのか、説明が長いというのか。
本当に、中途半端に雑多な知識があるせいで「え?ワームホールってこんなんだっけ?」とか「ブラックホールって、粒子が分解するのでは?」とか。「星は明るいけど、光源どこ?」とか、めちゃくちゃどうでもいいところで思考が止まってしまったのも残念。
多分、映画館でみたら「こういうもの」って思うんだろうけど、家だと雑念が多すぎる〜〜〜。
ただ、転からの回収があまりにも綺麗。
たたみかけが美しい。もう一回みたくなる作品!
「ハァハァ…ながい…ながい…」って思っていたところで、急激な音楽の変化。テンポの変化。彩度・色味・暗い展開からのハッピーエンドへの助走。キャラクターへの愛。
いや〜〜〜〜〜すごかった。
カメラワークも面白かった〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
私にとってカメラを止めるなみたいな感じでした。
{??」で始まり「??」で終わった。
1回で理解ができる人は頭の回転が速いんだと思う。
もしくはもともと宇宙に興味があったのかなあ。
1回見たけど、「え、これは何?何してるシーン?」という疑問が多すぎて、「???」のまま見進め、そのうち見せ場があるんだろうと見続けるんだけど、「???」のまま変わらず。
アクションというよりはヒューマンドラマなのかな?
3時間という長い時間で、途中気がそれてしまう。
何も考えずボーっと映画見るタイプの人には向かないのかもしれない。
考察サイトを読んでからもう一回見ないと自分には理解できないなと思った。
面白いと聞いていたので、理解できたらうれしいと思うんだけど、3時間をまた見るのか~と思うと腰が重く感じてしまう作品だった。
崇高と卑屈を内包する人間の行動原理のような何か
異常な気候変動によって全世界的な食糧危機にある近未来、人類の存亡を賭けて、他の惑星への移住計画が秘密裏に進行していた。メガホンを取ったのはCGを排した映画製作を手がけるクリストファー・ノーラン。
科学的裏付けを持った“創造性”、極限までIMAX撮影にこだわった息を飲む“映像美”、ロボットの声優にまで演技派を配した“俳優陣”、大学で相対性理論を学びながら執筆された“脚本”、至るところに貼られた伏線を次々と回収しながら、複層的なストーリーを見事にクライマックスまで導く。
世界トップクラスの頭脳を結集してもなお、解明されていることのほうが少ない宇宙。人類の救済という崇高な理想を抱く物理学者やエンジニアが、一瞬で死を迎え得る漆黒の闇に囲まれ、圧倒的な孤独に苛まれた時、感情、卑屈さ、生存本能、恐怖が渾然一体となった先に、人類代表としての“自分”の行動原理に何を見るのか。プランAとプランBが生々しく物語る。
このレビュー執筆時点(2020年4月上旬)、全世界は新型ウイルスの侵食を許し、多数の感染者と死者を出し、震撼している。医療体制は崩壊寸前で、経済は戦後最も停滞し、外出禁止を余儀なくされた影響で世界からネオンが消え、個々人のちょっとした距離すら離れるようにと指導が入る。マスクと消毒液を買い求めドラッグストアには朝から長蛇の列ができ、ニュース番組は朝から晩までウイルスの感染者数を報じ続け、未曾有の局面でもなお、政策ではなく政局論争が跋扈する。
場面設定は全く異なるがしかし、何かが、崇高と卑屈を内包する人間の行動原理のような何かが、どうにもだぶって見える気がしてならない。
好みは分かれる?
親は子供の記憶の中で生きる
1秒も目を離せない
私たちはアイを知ることが出来るだろうか
日本語吹替版にて3回目の鑑賞。
アイを知る存在は、超えられ、アイを知らない存在は穏やかな夜を知る。アメリアの台詞/アイには、もっと何か、意味があるのよ/には、私たちが銀河を越え、滅びを免れる叡知(Hint,Hope)が含まれていると思う。オイラーの等式に用いられるi、電流を表すi、親友となるAI、底見えぬ深淵を持つeye、私という存在についての情報を1文字に含んでいるI、意図されたものか、偶然か、何処からかふと湧くアイ・デアr、父と子の、断ち得ぬ絆としての愛。観測出来ないアイを、私たちは信じることが出来るだろうか。それはさて置いて、マーフの/パパは必ず帰って来るって云った/のシーンで毎回泪が出るのは何故だろう。ロミリィの/あれ、あッ、あれ、あれだ、ワームホール(興奮)/クーパーの/分ァかってる、唾飛ばすな/がイイのは、何故だろう。TARSとクーパーのやり取りに、この上ない親しみと楽しみが感じ取れるのは、何故だろう。きっと、この映画がアイを教えてくれているからだろう。素晴らしい映像、音楽、脚本。この宇宙での”169分”という時間を感動で満たしてくれて、ありがとう。クリストファー・ノーラン監督、キャストの皆さん、制作スタッフの皆さん、最高!。
主人公補正
鑑賞後の気持ち
感動
鑑賞後の心の変化
特になし
鑑賞後の行動の変化
ポルターガイストは観察することにする
好きなシーン
ワームホールを通過するシーン
嫌いなシーン
5次元の世界のシーン
今までリアルSFっぽかった映画が一気にファンタジーになった気がした
スケールがでかすぎて理解が追いつかない
世界的な飢饉や地球環境の変化によって人類の滅亡が迫る近未来を舞台に、家族や人類の未来を守るため、未知の宇宙へと旅立っていく元エンジニアの男の姿を描く(解説より)
単純なSF映画でなく、宇宙理論を科学的な根拠に基づいて制作されたとあるが、そもそも当方の予備知識が一切ないため、宇宙理論?どこ辺が科学的根拠なの?という感じであった。
冒頭は主人公と家族の時間
中盤は宇宙の冒険(地球を守るための使命)
後半で伏線回収、その後の世界
といったような構成だったかなと
約3時間にも及ぶ壮大なストーリーで、なかなか集中力がもたないところもあった。
名作といわれるだけのことはあり、ストーリー構成がとても丁寧に作られている印象を受けた。
しかしながら当方の理解度によるところが大きいが、個人的にはそこまで刺さる作品ではなかった。
ラスト50分の急展開
話が壮大
話が難しいから理解できないところも多いけど、理解できなくても十分楽しめる。ちょっとご都合主義。
前半からめちゃくちゃ泣けるシーンあった。
マット・デイモンがどんな役かを知ってたから驚きは少なかった。
アン・ハサウェイは良い風に映ってたけどだいぶ自己中なこと言ってた。
ティモシーが大人になったらケイシーになる。息子の扱い悪くて可哀想。別れの時も一言だけだったし、ケイシーになってから悪者っぽく描かれていたし、最後なんて話にも出てこない。新しい家族を捨ててまで、父の農園を守るという健気さが泣ける。
これが噂のコーン畑。ノーランが1から栽培したらしい。
TARSが「2001年宇宙の旅」のHALLに似ている。
『未知』は怖い
人類移住計画のため未知の空間『宇宙』へと旅立つ精鋭達……この映画を観終わり、人類の為に日夜研究している方々に思いを馳せる。まじで自分なんもしてないと自己嫌悪になる…
自分の命欲しさに嘘を吐くのは本当に人間だよ。こんな広い宇宙へ旅立っても人は争うのか……人間恐ろしい。
でも人間にそう言った感情があるからこそ、生き延びることが出来るってのも皮肉なんものですね。
しかしまさかのブラックホールの中!!!未知の領域だから妄想し放題!!!重量=愛!!なるほど!!!
素晴らしい映画でした…観てよかったです。
ただ一つだけ気になったことが。
マーフの兄は明らかに親の愛情不足?最後までぞんざいな扱いだったので可哀想に思う……。「父さんのことは諦めるよ」と言われたとは言え、娘の事しか想ってない…何故
そのせいか知らないがやさぐれてしまった兄……息子にあまり愛情を注いでないように見えた。
家族3人でドイツ軍のドローン?を追いかけてた頃が一番幸せだったね……。
全986件中、181~200件目を表示