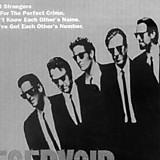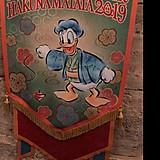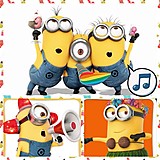舟を編むのレビュー・感想・評価
全260件中、181~200件目を表示
地道な月日の積み重ねで辞書は出来る
総合70点 ( ストーリー:70点|キャスト:70点|演出:70点|ビジュアル:70点|音楽:65点 )
地道に続ける地味な作業を、地味だけど真面目に描く。音楽も演出も控え気味。辞書作りをこんなに小さな部署でこんなに時間をかけて行っているとは思わなかった。少しずつ少しずつ月日を積み重ねないと出来ない仕事があった。その間に製作に関わっている人々も、結婚や病気といった人生の転機を迎えるほどの時間が経過する。長い割には淡白な展開だけど退屈するとまではいかず、彼らとともにゆったりと流れる時間をのんびりと眺められた。
辞書の魅力を伝える事に専念した映画
松田龍平が素敵だ
この映画の監督、石井監督があの「川の底からこんにちは」の人だと知らなかった。
じわじわと来るいい映画でした…やっぱ、松田龍平がいい。ほんと、いいな彼は。
原作は読んでないので、勝手なことを言うが、まじめ君が恋によって、もっと壊れたとこが見れたら、もっと面白かったな。
あー、「用例採取」しちゃいそ(笑)
全体的に薄味で物足りない作品。
全く面白くなかった訳ではないが。
全体的に薄味で物足りなかった。
まず俳優陣が非常に豪華。
私が好きな俳優さんが沢山出ており彼等が動いているだけで胸躍るものがあるのは確か。
ただ全編通して薄味。
本作は辞書編纂に苦慮する仕事の話と、主人公と女板前の香具矢(カグヤ)との私生活の話、大きく二つに分かれますが。
…両方とも中途半端。
辞書編纂の作業は作業工程を見せることで途方も無い作業の道程を見せようとしていますが作業の説明自体は興味深いものの、10余年の期間がブツ切りで描かれるため苦労感が伝わり難い。
終盤、大きなアクシデントが起こっているような雰囲気有りますが盛り上がりを作り出すための、話のための話感が強かった。
プライベート側も序盤は主人公の不器用感やピントのズレをコミカルに描いていたものの中盤以降はすっかりと影を潜めて面白さの要素が減っていました。
また本来は話の一つの軸になり得る、宮崎あおいが演じる香具矢(カグヤ)の女板前としての苦悩も摘み食いはしたものの尻切れ蜻蛉の感が否めない。
結果、大した波乱も無く何か分からないけど上手くいっちゃった感が。
主人公も含めた周りの人物の成長した感じが薄かったような気がします。
ただ、薄味ですが安心して観れる作品なのは確か。
他人と観に行く上では安牌かと。
オススメです。
編むという事
"マジメ"が送るとっても静かで熱い物語
【あらすじ】
ひょんなことから辞書編集部に異動となった真締(まじめ)は、膨大な言葉の波をも悠々自在に渡る辞書「大渡航」の編集に携わることとなる。その名の通りマジメな彼は多くの支えと言葉への情熱で、辞書編集に奮闘。ついに「大渡航」の発刊を実現させるのだった。
【感想】
"物作りって、人の絆があるから出来る"ー。そんな当たり前のことに気付かされ、自身を囲む物にちょっぴり感謝したくなるのが「舟を編む」だ。
言葉を愛しているけれど、ものすごく無口な真締。まるで辞書を引くかの様に紡ぎ出される嘘のない彼の言葉は、次第に「大渡航」に関わる者のハートに火を付けて行く。真締を支え続ける妻・香具矢、口達者で実はお人好しの同僚・西岡、将来の真締夫妻を思わせる松本とその妻…。一冊の辞書の制作過程を軸に描かれる個性豊かな登場人物達の姿に、時にはぷっと吹き出し、観終る頃にはほっこり心が温まる。
出演者達のあまりにナチュラルな演技にも注目しながら、一度観て損はない作品だ。
キャスティングの勝利
地味だけど、良い
なんとなくいい映画
個人的には言語が好きなので、辞書編集の苦労を少しでも知ることができ面白かったです。
ただ、単調なので母はちょっと飽きているようでした。
また、辞書編集の仕事の部分がメインになっているので、恋愛パートの描き方はちょっと雑(という表現が正しいかはわかりませんが、見る方の「どうせお約束で上手くいくんでしょ」という空気に頼り、丁寧に描けていない感)だなと思いました。
でも、悪い映画じゃないです。
地味な映画ですけど、興味があったら観てみるといいと思います。
うーむ。まずまず。
地味な良作
全体的な雰囲気がとても落ち着いていて、ノンビリ平和な気持ちで見るのに適した良作。派手なアクションもなく、人がバタバタ死んだりせず、うるさい音楽が鳴らず、季節の音や本の静けさ、「言葉」の応酬などによって、落ち着いているけれど飽きさせない、素敵な雰囲気を作っていました。俳優陣も派手さがなくて良い!
後半足早なところ、あおいちゃんの描き方にちょっと不満が残るところがやや残念だったけど、ただ辞書を編集するだけの映画で、よくここまで引きつけたなと思います。
松田龍平はミズタクでした。あの雰囲気いいですね。
人の地道な努力
全260件中、181~200件目を表示