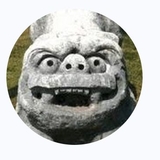わが母の記のレビュー・感想・評価
全59件中、41~59件目を表示
不器用な親子愛
井上靖の後期の自伝的作品の映画化である。だから井上靖の作品を読んでいなかったり、’60年代の日本の雰囲気を知らなかったりすると厳しいかもしれない。だが私にはこの映画は素晴らしいと思えた。
小説「しろばんば」などでも描かれているとおり、洪作は両親に対して複雑な感情を描いており、初老となったころでもそれを引きずっていることが序盤から判明する。雨がしとしとと降る中雨宿りをする母親と子供時代の洪作。反対側にいる母親が洪作の元に来てあるものを渡す。子供の頃の話自体は描かれないが、このシーンはとても重要だ。屈折した親子の愛情がここに込められている。
しかしその後のシーンからは一転して、初老の伊上洪作とその家族の生活が繰り広げられる。これらの場面を支えているのは間違いなく主演である役所広司と母親役の樹木希林であろう。認知症の老人を演じさせたら樹木希林の右に出るものはいない。確信犯なのか本当にぼけているのか、相手をいらつかせる寸前の笑いだ。このスレスレのユーモアが作品の全体を担っていると言っても過言ではない。そしてなんといっても役所広司。微妙に家父長制の残る家で厳しくもありながら、家族を思う優しさは誰よりも強い父親に成り切っている。特に娘達や女兄弟、母親といった家族との掛け合いは見物だ。言葉の端々にあるささくれだった感情で時には互いを傷つけるが、それでも親子の愛情は消えない。
問題点がないわけではない。井上靖という文豪が書いたものを原作としているためか、一つの台詞に色々と詰め込みすぎている。それが顕著に表れるのはラストシーンだ。もっとも泣けるシーンのはずなのに、洪作が自らの内面を語ってしまうことで感動が逆に薄れてしまった。映画はあくまで映画であることを意識するべきだった。
しかし感動できないかというと、そんなことは全くない。一つは洪作が昔書いた詩を、記憶を失いつつある母親が読む場面。目の焦点も定まらず無心に読んでいる母親に対して、当の洪作は思わず涙を流す。母親が息子を愛していたことの何よりの証拠だからだ。そして洪作が母を背負う海辺のシーン。親子が完全に和解し、洪作が心の底から母親を愛することが出来た。これほどまでに感動的な親子愛のシーンはなかなか無い。久々に映画で泣いてしまった。
素晴らしい映像、セット、役者、そして脚本に恵まれたことでまれに見る名作が完成した。記憶を失っても愛情は消えないのだ。
(2012年5月12日鑑賞)
押しが強くないからウルってしてしまう。
む~ん、
皆さん、こんにちは(いま5月7日pm2:15頃です)
自分でチケットを買って見に行こうとは思わなかった。
ある人にもらったからみたんだけど・・・
見に行く前日、日経の映画評を見たら満点だった。
小津安二郎の世界にも似て、すばらしいって。
よくは知らないけど、小津作品はストーリーは淡々としているけど、
その画面づくり、絵づくり、構図には聖なるものが宿っていると
いったひとがいる(ヴェン・ヴェンダーズ監督だったと思う)
①ストーリー
②配役、演技
③映像、音楽
これが映画の3大要素だと思っているんだけど、
僕は初めて「構図」というものに着目してみようと思ったのだ。
でも、初めのうちは「画面の構図」を見ていたのだが、
(確かにおもしろい画面構成があったのも確か)
だんだん、その意識も薄れていってしまった。
やっぱり、物語に目がいっちゃうんだよね。
この映画、ストーリーに大きな変化はないんだけど、
ごくありふれた日常的な世界が淡々と描かれている。
みんないい人。だけど、機嫌の悪いときは誰にもある。
機嫌が悪い同士が接触すれば、ちょっとした火は起きるみたいな。
まして、その日常性を失って、非論理的な世界へ行ってしまいそうな
母を相手にすればなおさらだ。
役所さんも、希林さんもうまいと思ったけど、ほんとに存在感がある
と思ったのは宮崎あおいでしたね。
それも、うちに帰って自動車のCMを見たときそう感じたのだった。
それでなにがいいたいのか?
結論を出そう。
①ストーリー 8
②配役・演技 9
③映像・構図 9
小津監督のように特出すべきものはなかったように思うが、
すべて平均点以上といったところのような気がする。
泣けたけど
映像はキレイで、シナリオも演出も創りも悪くなかったけど……。
役所さんの「昭和っぽい」父親像、樹木希林さんの「そのまんま」のボケ老人像が、僕はウソ臭くてダメでした。
昭和の父親はもっともっと家族を顧みないことを「正当化」していたはず。妙に優しいところが作品を矮小化していた。「昭和の厳格な父」を演じているはずが「よくあるただの中年俳優」に見えてしまった。
仕事中心の考えは当たり前だと「家族を顧みない父」でいなければ、この話はドラマが小さくなってしまう。確かにエピソードでは描写されている、つまりそのシーンはあるのだが「佇まい自体」が全然厳格でなかった。
役所さんはいまは空回りする「ダイワマン」のキャラが一番合っている。
樹木希林さんは、リアルにやればやるほどフジフィルムの「綾小路さん」に見えてしまう。ボケる前までは楽しく見れたのだが、ボケてからはただのギャグ。40年近く前の「寺内貫太郎一家」から一貫して演じているキャラをやっているだけ。
この役、草笛光子さんとかがされたら、どんなに素敵な作品になったろうかと思う。樹木希林さんにはもう「ボケ老人」はやってほしくない。本人がそうであるように「スーパーおばあちゃん」を演じて欲しい。
一時の中井貴一さんもどんなシリアスな映画に出ても「ミキプルーンの人」、または「JCBのたぬきとカッパの友達」に見えて作品をぶちこわしていたように、役者がCMで「固定キャラ」を演じるのは、特にコミカルな場合、自殺行為だと思う。
ハリウッド俳優は本国では絶対にやらないからね。その分、日本とかでCMでて稼いでいるけど。
他の役者さんと、「昭和の世界」の作り込みはすごく良かった。
日本でこういう作品を成立させるには、やはりキャスティングに凝らないとダメでしょうね。でも「人気優先」でないとやはり客入らないだろうけど。
長塚京三さんとか斉藤洋介さんとかと、草笛さんか吉行和子さんで観てみたかったな。
親の心子知らず 子の心親知らず
親の心、子知らず
昭和真っ只中の夫であり父親として洪作は、当時としては普通にワンマンだ。作家志望の若者をさっさと運転手として雇い、妻に「それでは車を買わなければ」と言われれば、「もう買った」と事も無げに言う。万事がそんな具合だ。
洪作には3人の娘がいて、一番下の琴子だけは横暴な父親に反発する。まず、この二人が巻き起こす波風が親子とは?という疑問にひとつの筋道を形成していく。ことごとく反目し合いながら、実はこの二人、頑固で自分の考えを貫く似た者同士なのだ。
一見、横暴にも見える洪作にも、親と子の関係で拭い切れない苦い思い出がある。幼いとき、母は二人の妹だけを連れて、自分だけ知らない女のところに置いていかれたのだ。母に捨てられたという想いが、ずっとしこりとなっている。
それでいて、母から別れ際に渡されたお守りは今も大事に身に着けたままだ。本人は自覚していないだろうが、母親に対するコンプレックスは相当に強いものがある。
母・八重は何かにつけ「あの女に預けたのは一生の不覚だった」と言い出す。洪作を預けた相手を嫌悪した言い方だが、“あの女”が憎いのではない。裏を返せば、息子を手放してしまった自分を嫌悪しているのだ。自分が知らない息子の8年を知る女への嫉妬がある。
洪作と母は、いわばコンプレックスとコンプレックスがぶつかり合ったまま人生を歩んできたことになる。
ついに洪作は「息子さんを郷里に置き去りにしたんですよね」と問いつめるのだが、このあと八重の口から出る言葉に、洪作は数十年もの時の流れを一気に遡る。堰を切ったように溢れる涙が、長く遠かった母との距離を詰める水路のようだ。
親と子とは、ちょっとしたことが深い溝になるが、その溝を埋める手立てはなかなか探り当てられないものだと、つくづく思う。探り当てられた洪作は幸せだ。
役所広司も巧いが、樹木希林の演技を超越した表情、仕草、語り、この人の右に出る役者はいないだろう。
硬派な作品が多い原田眞人監督だが、今作では女性的な視点で語られるシーンが多く、感性に豊かな幅の広さを感じる。
芦澤明子の撮影による映像は、デジタルによる上映にもかかわらず、落ち着いた色調に抑えられ、奥行きもあり、どのカットも美しい。
呆けても母は母
絶品でございます。
記憶を失っているようで、すべてを見透かしているような八重を、すごみとユーモアをもって体現した樹木の演技が圧巻です。
試写は早く半年前に見ました。
当時は「キツツキと木こり」の公開直前で役所広司主演の試写が続いた格好となったのです。だから役所広司の木こりのオヤジから大作家への変貌ぶりが驚きでした。
本作は古き良き昭和の家族の物語。井上靖の自伝的小説の映画化で、ロケ地にも井上靖の生前の書斎が使われているなど、リアルティにこだわって撮られていました。
これが松竹映画となると名匠小津安二郎の映画を連想せずにはいられません。実際に原田真人監督は随所に小津安二郎映画へオマージュがささげたシーンを盛り込んだそうです。
本作のポイントは、幼い頃に曽祖父の愛人に預けられた主人公の洪作は、母親八重に捨てられたという意識を持ち続けているところ。それを問い詰めたくとも、八重は認知症が進み、答えてくれません。その捨てられた思いは、洪作の家族を顧みない身勝手な行動に繋がり、妻や娘たちから総スカンを喰らって、孤独な日々を過ごしていたのでした。
洪作と八重の周囲に、洪作の妻と2人の妹、3人の娘という大家族。そんな大勢の家族との思いを交錯させる中に、家族の確執と真情も浮き上がります。ただその根っこにあるのは洪作が母親から捨てられた思いと同根ではなかろうか窺えました。そんな家族ものらしからぬえぐい台詞の応酬を見せる、濃い中身を原田監督は巧みに、重くならずにつないでいきます。特に妻や娘たちの女としてのしたたかさやたくましさがさりげなく描かれているところが特筆できます。そんな中で根底に見え隠れしてくるのは、深い愛情。
前半は登場人物の説明のような台詞や家族の何気ない会話の応酬が続き、いささか退屈しました。でも洪作と八重の過去が明かされていく後半は、親子の絆の深さを見せ付けられて、涙を禁じ得ない感動に包まれていったのです。
物語は、夫を亡くした八重が、息子の洪作や娘、孫たちと暮らすことになるところから始まります。高齢のため、認知症の症状が進み、とっくに送った誕生祝いを「まだ送っていない」と言い張ったり、娘をお手伝いさん呼ばわりしたり。徘徊も目立つようになり、一家は八重の言動に振り回されるようになります。でも洪作の
一家は年寄りを決してのけ者扱いすることなく、むしろ温かく見守っていこうとしているところにとても好感を持てました。
。
記憶を失っているようで、すべてを見透かしているような八重を、すごみとユーモアをもって体現した樹木の演技が圧巻です。
樹木の演技は抑制されているとはいえ、表情豊かで動作も活発。本当にボケているのかなぁ~、ボケているふりをしているだけなのかな~とどっちともとれる絶妙な演技で笑いにして誤魔化されてしまうのですね。まるでやんちゃな子どもが素知らぬふりをしているかのような表情は絶品です。小津映画の人物とは異なるキャラでもはや樹木の作り出した空気感にどっぷり作品がはまり込んでしまったといっていいくらいなんです。
終盤、記憶を失っていく八重の中にも、大事なものが残されていたことが分かります。次第に物語の核心である洪作は幼い時になぜ捨てられたのかその真相に近づいていきます。でも前途したように八重はそのことさえ、忘れてしまったようなのです。
あるきっかけで八重が行方不明になったとき、洪作はとっさの判断で、八重の母親としての思いの宿る場所へ向かいます。そしてそこに佇んでいた八重に長年聞き出そうとしたことを尋ねるのです。
このとき八重がとつとつと口にする言葉は、予期せぬ言葉でした。その一言に洪作は驚きを隠せなかったようですが、見ている方もはっとしました。
惚けてはいても、八重のこころの消すことができない母の情の表出が宿っていたのです。親とはこういうものなのだ、と感じ入るしかないシーンでした。
このシーンによって、洪作の記憶は八重の声によって蘇っていきます。それに応えるかのように、背負われた洪作の背中の感触によって、八重の母親としての感情が蘇って、一筋の涙として描かれます。
まことに親子の絆としての記憶は、長年の風雪を超えて、一度は忘却してしまったとしても、僅かなきっかけさえあれば鮮明に蘇り、深い感銘をもたらすことを思い起こさせてくれた作品でした。
また特に確執の深かった琴子と洪作が親子の絆を取り戻していくところも良かったです。琴子役は宮崎あおい。やっぱり彼女が出演していると華が出ますね。
老いるということ
母と息子の絆を通して
母親の老後をいろいろな意味で見つめていく映画
そんな母親はボケて奇行を繰り返す訳だが、、、
人は誰でも老いていく
さらに、本作品に描かれたように認知症を誘発する場合も多々ある
でも本作のそこには、老人看護によくある憂鬱感や絶望感は一切なく
家族の生活の中でみんなで看取るという姿がただただ描かれていて。。。
もちろんその家族それぞれにおかれる環境や状況は多々あるが
親の老後の面倒をみるということは「こういうことだ」と強く感じた
なにも憂うことはない、なにも心配することはない
ただただこの世に生みおとしてくれた両親に感謝しながら
最期まで看取ってあげればいいだけなのだ
この世に存在できたことで享受できた喜びや悲しみや慈しみに比べれば
と思いながら。。。
そんな辛い看護ではやはり家族の支えや助けが重要であり
核家族化が進んで著しい現代だからこそ
今一度家族の在り方を問われているような気がした
人は一人では生きていけない
だからこそ、自分が本当に困ったときに
誰かが手を差し伸べてくれるように
品性を大事にして慈しみを忘れずに生きていかなければいけないのではないだろうか
母親の臨終を伝えた妹の電話
そんな妹に主人公がかけた言葉
心からの労いと感謝の念が溢れていた
ぐっときます。
演技も映像も素晴らしい
日本映画の良心
名画と呼ぶに相応しい。
今年始まってまだ半分も経ってないが、間違いなく現時点での日本映画のベスト。
これからも多くの期待作が公開されるが(夢売るふたり、終の信託、おおかみこどもの雨と雪…等々)、年末になってもその地位は揺るぎそうにない。
他の方のレビューを見ても、大方同様の感想を述べており、僕も全くの同意見なのだが、やっぱり言わずにいられない。
まず、原田眞人監督の演出。
これまで社会派映画が多かったが、一連の作品で培ってきた細やかでリアルな演出が、初挑戦となるホームドラマでも違和感なく発揮されている。
絶妙な間や会話のテンポ等、よくあるホームドラマとは違うリアリティを出していた。
俳優たちの見事なアンサンブル。
役所広司はいつもながらさすがの名演。
宮崎あおいも少女から大人の女性への成長を、美しくナチュラルに演じていた。
豪華共演陣も、家族や親戚にこういう人いるいる、と思わせる適材適所。
そして何と言っても、樹木希林!
名演技と言うのが言葉足らずなほどの名演技。
いや、演技というものを超えている。
かと言って、素な訳がない。
どうやったらここまで成りきる事が出来るのか、言葉さえ見つからない。
老いて記憶が薄れても、盲目的に息子を探し続ける母。
母に捨てられた記憶から、何処か母に抵抗を感じる息子。
そして自分もまた、奉仕は愛情と言って、娘たちに壁を作っている。
ただ支え合って寄り添い合うだけではなく、時には衝突したり苛々したりしながら歩み寄って行く姿は、誰もが覚えがある筈。
映画は役所広司演じる息子と樹木希林演じる母がメインだが、役所広司演じる父と宮崎あおい演じる娘であったりと、各世代に通じる“家族”の話である。
そんな家族の話が、美しい日本の風景を背景に語られ、これ以上ない名画になっている。
日本と、日本映画と、日本の家族の姿に、改めて素晴らしいと賞賛したい。
納得の作品だが、「文部省選定」みたいな…
文豪というよりも、大成功を納めた流行作家、あるいは国民的作家というべき井上靖とその母親の姿を描いた作品。
井上靖と同郷で、高校(井上は旧制中学)の後輩にあたる原田真人監督は郷土の大先輩、偉人の人間味を役所広司からうまく引き出している、と思う。
ぼけた母を演じた樹木希林の名演は、まあ、日本アカデミー賞助演女優賞は間違いないんでしょうな、という感じ。
大作家の末娘を演じた宮崎あおい(こちらが助演女優賞か?)も好感度の高い演技を見せる。
さまざまな好条件が整い、よくできた映画だ。
非の打ち所がない作品といっていいだろう。
しかし、その優等生的な作品ゆえに、何か心に残らないんだなあ。というのはあまりにへそ曲がりな批評だろうか。
とても素敵な作品です
これが当たらないと日本映画界が心配。
まだ三月ですが今年の邦画暫定首位。多くの方にご覧いただきたい本当に良い日本映画で、最近では「大鹿村騒動記」以来です。三世代それぞれの鑑賞に十分応えられる国民作ではないでしょうか。原作・脚本も良いのでしょうけれど、役所さんを筆頭に演技とキャスティングにも突っ込みどころが見当たらず、特に樹木さんの老婆役は一つの到達点を観たようです。美しい日本の原風景映像、ロケ地、美術も素晴らしい。家族の会話ですから多めになる台詞にも無駄が無い。涙を禁じ得ない方も多いでしょう。僕は個人的な家族事情から終始じんわりと涙腺が緩んでいました。僕の父母は幸い健在ですが、生涯愛することはないと思っています。これは、たいへん辛いことです。おっと映画の話でした。ファミリーなんてカタカナに置き換えず、家族とは、家庭とは、現代日本が失いつつある、否、既に失ったその姿が、ここにあります。菊池亜希子さん惚れ直しました。
拝啓 両先輩、いい映画でした
原作 井上 靖 × 監督 原田 眞人(敬称略)
お二方は、俺にとって特別
母校 沼津東高校(旧沼津中学)の先輩になるのだ
そんな縁で、井上 靖の自伝小説には馴染みがあった
「敦煌」「額田女王」「天平の甍」「蒼き狼」などの歴史物もいいが
氏の作品は、自伝小説の方が活き活きして個人的には面白い
その一つ「しろばんば」では、曾祖父のお妾で洪作育ての親
戸籍上の祖母、おぬいばあさん
つまり、本作の土蔵のばあちゃんとの描写もある
監督は俳優として「ラストサムライ」で見初め
「クライマーズ・ハイ」の人間描写に魅せられ
その後、母校の先輩と知って誇らしく思った
「わが母の記」は井上 靖の自伝的な話で
舞台となるは、監督や私の故郷でもある沼津や伊豆
ここまで見る前に思い入れを感じる作品は、初めてだ
本作では、小説家と生みの親である八重との関係を描く
小説家 洪作のモデルは靖自身である
洪作は、実母八重に捨てられて育てられたとの想いを抱え
そのわだかまりの中、痴呆の兆しを見せる母と向き合う
彼の家族も交え、彼は母に何を思うのか
単純ゆえに難しく普遍的な家族の在り方を見せる話だ
そのスクリーンには、なつかしき風景や風俗が広がる
天城のわさび田、沼津御用邸前の浜、川奈ホテルとゴルフ場
旧家の古めかしさ、「~だら」という方言、バンカラな学生
特に、洪作は我がオヤジそっくりで懐かしすぎた
オレは家族を養うために稼いでいる、黙って言うことに従え
身の回りのこと、着替えの用意から母の世話まで女の役目だ
理不尽とか身勝手とか、そんなことは言える雰囲気にない
役所 広司は、そんな昭和のオヤジを連れてきた
おかげでで、幼き日がよみがえった
また、母を演じる樹木 希林には祖母を見た
同じ言動を繰り返し、お節介を焼きながらよく動く
それでいて、誰からも愛された祖母だった
その目配せから動きから、演じているとまるで感じさせない
また、宮崎あおいの生意気さと優しさ
南 果歩の奔放な妹、キムラ緑子の感情溢れる様
どの俳優も、不自然さを感じさせなかった
ある時はテンポよい会話、たとえば冒頭の洪作兄弟の会話で
またある時は沈黙と間が、饒舌にその感情を描写する
判り易く言葉で言わせる野暮はなく、BGMも最小限だ
その「行間を読ませる」描写にどんどん引き込まれていく
彼らが作った昭和の家族は
活き活きとした、生命力溢れる作家井上靖の小説と同じ匂いだった
あんたは世の中をわかっていない
その母の言葉に呆れる洪作
俺を捨てたあなたに言われたくない
母に対する想いが溢れ、変化していく洪作の様は染みた
それでも 母は母 家族は家族
表現は全く違うが「ザ・ファイター」とも似たテーマ
そんな「簡単で複雑」なことが込められていた
終盤の御用邸海岸でのシーンには胸が熱くなった
ただ、この想いは30代以上くらい
昭和の古めかしさを知り、年齢を重ねないと伝わりにくいと思う
洪作が、家族に母を任せきりで自分では何もしないのが気になる
若え衆は、そんな今風な感想を持つかもしれない
しかし、当時はごく普通の文化であり、そういうもんなのだ
不器用ながら家族を守った父、それを支えた母
ようやく彼らを客観的に見られるようなった最近のオレには、効いた
両先輩が下さった物語は、自省のきっかけにもなるだろう
あるのが当たり前であることに慣れきった単純で複雑な家族愛、ってやつを
真野恵里菜さんが素晴らしい
さりげなく、愛情を、絆を
この作品をスクリーンで観ながら、私は、原作者の井上靖の実際の顔を思い浮かべていた。それは、作者本人を演じた役所広司は、あまりに優しすぎる顔をしているからだ。井上靖本人は、目付きが厳しく、顔に人生の苦労を背負ってきたシワを刻んだ、とても気難しい顔だちをしていた。その顔を頭に浮かべていたせいか、「自分は捨てられた」というわだかまりや恩讐を母に持ち続けた作者の気持ちが、リアルに私に迫ってきた。
物語が進む中、私はひとつの疑問を作者・井上靖に投げかけていた(映画の中では、伊上と名乗っているが)。
「あなたは、母にどうしてほしいのか。抱きしめて、申し訳ないと言ってほしいのか。それとも、自分の目を見て涙の一滴でも流してほしいのか」
多くの読者を虜にした、数々の小説を残した井上靖なのだから、劇的な展開を望んでいたのではないのか。と、思いながら見ていたのだが、映画は、次第に認知症を深めていく母の姿とともに、淡々と進んでいった。私を含めて、スクリーンを観る観客の大多数は、母と井上靖との関係よりも、井上の家族が中心に描かれていたのに少し意外に感じていたと思う。
しかし、この映画の面白いところは、作者の井上とその家族との交流の中に、母と作者との絆そのものが隠されているところだ。それは、気むずかしい井上を父に持つ家族たちと、父とを繋いでいたのは、井上の母の存在があったからだ。原田監督は、セリフが多い中で、井上と母とが絡まない部分に、母と井上との絆の強さを家族たちが感じるシーンを巧みに入れて、認知症であっても母の重要さを観客に語りかけている。
そして、母と井上が理解しあう瞬間は、とてもさりげなく訪れる。それは、時おり井上と家族たちとが触れ合う一時と同じく、心地良い風から画面から流れてきたかのような爽やかさだ。肉親が、恩讐を越えて理解しあう、愛情や優しさ、絆というものは、抱きしめあったり涙を流しあったりするものでなく、本当はさりげないものであることに観客は胸をしめつけられる。疑問を持ちながら見ていた私も、そのさりげなさに目を潤ませてしまった。
私も、ある時から父と話さなくなり、互いに遠ざける関係がしばらく続いた。その間も、私は子どもの頃から父の影響を受けていただけに、父と気持ちを通じ合いたいと思ってはいた。しかし、その思いが叶う前に父はこの世から去って行った。だから、この映画の井上の気持ちは、私には痛いほど理解できる。両親とあまり会話をしていない人が、この作品を観ると、人生観が大きく変わるかもしれない。
全59件中、41~59件目を表示