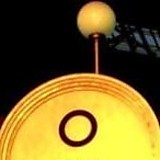ヴィヨンの妻 桜桃とタンポポのレビュー・感想・評価
全9件を表示
全ては夫婦のスパイス
松たか子の真面目な妻と、才能ある小説家なのに家庭をまるで顧みないヒモ夫の浅野忠信。
夫は生きることより死ぬことに価値を見出し、妻は妻で夫が頼りにならない分自立していく。
妻が自立すればするほど、夫は妬き、
離れ離れになる2人で、もう別れちゃえばいいじゃんと思ったりするんだけど
妻は夫を思っている。それは情なのかもしれないけど。
夫は外に女がいたり心中してみたり、でも結局は妻と離れられない。
外で散々好き放題出来るのは、地に足ついた妻のおかげか。
結局周りが横やりを入れようと、全ては夫婦のスパイスなんだなぁと。
ヤキモチを妬く夫も、妻に言いよる男たちも、結局は脇役に過ぎなくて、
松たか子の芯のある演技とか、浅野忠信の一見筋の通らないふらふらさも、うまく調和していてとても好きだった。
三鷹から武蔵小金井まで1時間歩く妻夫木聡も、なんというかリアリティがあって、
こういう夫婦のあり方みたいなものを感じた。
こうはなりたくないけど少し憧れる、みたいな、相反する気持ちをうまくバランスとっているような。
表面ではなくて心の中で繋がっている、繋がせている、夫婦の形とか愛って表現したらこんな感じなんかなぁと思わせる映画。
"死にたかった夫"と"死なせてあげられなかった妻"
太宰治の原作は未読です。
何度も映画の公開前に読もうとしたが、どうやら色々な太宰作品から断片的に引用しているらしいのを知り、読む時間がなかなか取れないのも在って断念しました。
従って、細かな部分に於いてかなりの勘違いをするかも知れません。
夫は絶えず「死にたい」と漏らしていた。
終盤で妻と愛人が対峙する場面が有る。
まるで勝ち誇ったかの様に、薄ら笑いを見せる愛人。
自分には一体何が欠けていたのだろうか?
そんな思いを確かめ様としたのかは計りかねるのだが、妻はパン助から口紅を売って貰い、自ら口に塗る。
眼の前には“本当は好きだった男”
口紅で化粧をした自分は、表に居る女達同様に男共に媚びを売る虚飾に満ちた人種と言って良い。
しかし、外へ出た妻は、そっと口紅を置いて我が家へと帰って行く。(実際は椿屋)
“死にたかった夫”と“死なせてあげられなかった妻”
それまでの偽りの夫婦生活をお互いに戒める様に振り返る。
この時に登場するのが、脚本家田中陽造が拘った《さくらんぼ》
おそらく太宰作品の中に出て来る重要な要素なのでしょう。残念ながら太宰作品を未読のこちらには、その本当の意味合いの詳しい部分は分からない。
しかし、ここで過去の田中陽造が関わった作品に似た様な場面が有ったのを思い出す。
鈴木清順監督作品の『陽炎座』
確かあの作品では《酸漿》が使われ、妄想とも現実とも区別のつかない、男女の妖気漂う世界が展開されていた。
『陽炎座』自体は泉鏡花の原作が有り、自由奔放なイメージに溢れるはいるが、それと比べると本作品に登場する夫は、その生涯で死にとり憑かれていた。(と思われている)原作者の太宰治の等身大に近い男。
監督は根岸吉太郎。
日活ロマンポルノ出身の人で、やはり全作品を観た訳では無いので、これも自信は今ひとつなのですが。この人の作品に登場する男女にもどこか共通する個所が有る様な気がする。
思えば、デビュー作となった『オリオンの殺意より 情事の方程式』の時から、出て来る男女のカップルにはどこか“死のイメージ”が見え隠れする時が有った。
出世作となった初めての一般作品である『遠雷』でさえ、ドライな男女が割り切って結婚し、最後になってやっと本物の夫婦として歩んで行く。その時に遠くで鳴り響く《雷鳴》には様々な解釈がなされたのを思い出す。個人的にもどことなく怖いイメージが有る。
『永遠の1/2』等は、全くの別人を似ていると言うだけで勘違いし、押し通す話だった様な気がする。(予習をせずに、当時観た不確かな記憶だけなので少し心配)
…と、根岸作品を全部検証した訳では無いのですが、この人の作品に登場する男女は、時に“擬似夫婦(恋愛)”をしている場合が多々見受けられる。
そう言った意味でも本作品のラストで、浅野忠信と松たか子演じるこの夫婦は、『遠雷』での永島敏行と石田えり同様に、真の夫婦として歩んで行く一歩だったのかも知れない。
しかし『遠雷』の時は雷鳴だったのだが、本作品のモデルとなった人物は太宰治本人に他ならず。彼のその後を考えると、本作品でのラストシーンは、見方によってどことなく男女の心中場面を映したモノクロ写真の様な風情も有り、単純なハッピーエンドとも言い難い。
出演者では、松たか子が絶賛されている様ですが、個人的には浅野忠信が良かった。シラフの時はなかなか死ねずにいて、自分の居場所を絶えず探して居るかの様にオドオドしているかと思えば。酒を飲み酔っ払った時になると、気が大きくなる典型的な駄目人間を巧みに演じている。初めてと言って良い位にこの人の演技力を素晴らしいと思った。
素晴らしいセット美術を始めとして、日本映画の面白さを堪能出来る作品です。
がしかし、お薦めするのは少し気が引けます。それは、この作品の表向きが、本当に馬鹿な夫婦の物語でしか過ぎないからなんですが…。
(2009年10月11日TOHOシネマズ西新井/スクリーン8)
曇った日に凛と咲いている花を見ているよう
言わずと知れた太宰治の名作。
売れない作家の大谷を支え続けた妻、佐知の話。
したたかで美しい女性の映画だった。
ストーリーはつまりがどうしようもないダメ男を妻が支え続けるというもので。
佐知は明るくしたたかでまっすぐで、最高の奥さんだけれどもそれゆえに大谷は苦しくなる。
浮気をするけれど佐知に思いを寄せる男のことは気になる。
一見すると、大谷の心のバランスの悪さとかばかりが目についてしまうけれど、きっとお互いに依存している夫婦の話だったように思う。
佐知はきっと大谷を待つ自分、大谷を好きな自分、大谷を支えている自分、それによって自分自身をささえていたのかなぁなんて思ったりもしました。
それは男性を妻が支える時代だったからなのかは分からないけれど、「夫婦愛」という言葉ではくくれないような二人のアンバランスな心の関係が描かれた作品のように思いました。
まーほんで何が素晴らしかというととにかく松たか子。浅野忠信も、見事にダメ男ぶりを演じきっているんだけれど、松たか子の演技が秀逸!松たか子がいかに素晴らしい女優さんかということを改めて思い知った作品。
どこまでもまっすぐに大谷を支え続ける佐知。
まっすぐな女性は時に女性の目から疎ましく見えてしまうものだけれど、一切それがなかった。
なんかこう、まっすぐすぎるとうっとーしいというか。それが無かった。
非常に印象的なシーン2つ。
1.佐知が初めてチップをもらうシーン。
チップをもらった彼女はあっけらかんと
「わたし、お金になるんですね」
という。
その言葉の嫌みのなさが凄い。
嫌みなく演じた松たか子が素晴らしい。
あ、そう思ったんだな、とだけ思うまっすぐな一言。
その一言と表情で、佐知という女性のすべてがわかるような一発だった。名演技。
2.佐知が堤真一演じる弁護士さんのもとに向かうシーン。
とある決意をして彼のもとに向かう佐知は、口紅を買う。
その口紅を塗るシーンがまー、なんとも言えない。
大谷を助けるために女性であるという武器を使う決意をし、向かう彼女。
この映画の中でいっちばん松たか子が魅力的なシーンでした。
あとで気づいたけど監督さんがサイドカーに犬の人と一緒でした。言われてみれば空気感がにている。
話の盛り上がり??はあんまりないので物足りなく感じるひともいるかもしれませんが、個々の俳優さんの名演技が光る作品です。脇役まで全員素晴らしい!
個人的には広末涼子があんまり好きじゃないけど、今回の役どころは良かったような気がする。かもしれない。
最後のね、シーンも素敵です。なんか、「うん、うん、それでいいよ、うん」ってなる感じ。
晴れても無い、雨でもない。そんな日に咲いてる花を見ているような、そんな映画でした。
真逆な夫婦の愛の形
「生きる」ことに向き合えず「死ぬ」ことばかりを願う人には、「死」=「崇高な英雄行為」である。いかに美しく、いかに理想的に死ぬか。そのことを日々考える。皮肉なことに「死」を夢見ることがその人の「生きる」糧となっている。しかし死が崇高で美しいのは、天寿を全うした人だけだ。理想の死を追い求める人に死神は微笑まない。死神が抱きとめるのは、生きることに前向きだが、一瞬の絶望で発作的に死を願ってしまった人だ。
太宰治をモデルとした小説家大谷(浅野)は、典型的な死を願う人だ。「僕は生きることが怖い」と弱音を吐き、次々に愛人を作り、呑んだくれ、泥棒まで働く。そんなどうしようもないダメな亭主を健気に支え続ける妻(松)。彼女は決して弱音を吐かない。夫のろくでもない行為を強く責めることなく許し、尻ぬぐいに回る。何故か・・・?愛しているから?これほどの仕打ちを受けたら愛などとっくに覚めてもおかしくはないのに・・・。自分は浮気をするくせに、妻の浮気が許せない夫は、ついに愛してもいない愛人と心中を図る。しかし前述のように死神は残酷だ。安らかな死ではなく、のたうちまわるみじめな姿と、スキャンダルだけ残って再び生きなければならないという辱めを彼に与える。それでも妻は夫に「どうしたらいいの?生き残って良かったというべき?それとも死ね無くて残念でしたと慰めたらいいの?」と静かに問いかけるだけ。だが彼女の心は常に血を流している。夫が残した睡眠薬を発作的に飲もうとする彼女だったが、彼女の生きる力の方が死神よりも勝っていたらしく、空を見上げて踏みとどまる。そして彼女は夫を助けるために、愛してもいない男に抱かれるのだ・・・。
松たか子の抑えた演技が良い。疲れた顔を見せず、凛とした上品な佇まい、抑揚をつけないセリフ回しが効果的だ。
だが本作で一番好演したのは、浅野忠信ではないかと思う。インテリ特有の物憂げで上品な佇まい。丁寧な口調と柔らかい物腰。こちらが責める前に謝る確信犯。寂しげな表情で「僕は弱い男です・・・」と言われたらもう許すしかない・・・。酒の飲めない浅野が『風花』で見せた絶品の酔っぱらい演技がここでも活きている。人間、やはり見た目が大切だ。彼のアンニュイな雰囲気があってこそのダメ男だろう(むさ苦しい男が「死にたい・・・」とウジウジしていたら「さっさと死ねよ!」って思っちゃう・・・笑)。
生きるエネルギーが間逆な夫婦だが、互いに引き合うことで生きていけるのだろう。それがこの夫婦の2人にしか分からない愛の形なのだ。
[ヴィヨンの妻.桜桃とタンポポ]
映画初主演(意外)にして、どこを切っても松たか子の魅力一色の、徹底大礼賛映画。
[ヤッターマン][空気人形][愛のむき出し]など、このところ男優不要の女優メイン映画の流れが目立つ。ヴィヨンの妻も明らかにその一本だが、根岸吉太郎監督は、是枝監督などと比べ、よりオーソドックスな出自(撮影所出身)であり、また作品が生誕百周年を迎える太宰治の原作であるため、ひたすら主人公の女性佐知のけなげな姿だけを描けばよいというわけには行かず、小説家大谷(浅野忠信)と愛人の秋子(広末涼子)の心中未遂には大なスペースを割かねばならないため、奇妙にウェイトの歪んだ映画となっている。
佐知が借金のカタで勝手に転がり込む闇酒屋夫婦(伊武雅刀&室井繁-どちらも芸達者)の店も、お客たちもみな静かな善人たちであって、時代背景である敗戦直後のギスギスした殺伐さはかけらもない、非リアリズムでパラダイスな酒場(種田陽平.矢内京子の美術、黒澤和子の衣装デザインなど、スタッフの仕事は言うまでもなく秀逸)。泥棒になった亭主の罪を減じてもらうため、今や弁護士に成り上がった初恋の男(堤真一)に抱かれて来ても、佐知は不潔さも淫靡さもまるで身に染みない。きっと作中の世界そのものが、アル中作家が譫妄状態で紡ぎだした、自らを慰撫するための幻想なのだろう。そもそも佐知が酒場で働き出した時点で、この男は地上に存在する理由を失っているのだから...。
とはいえ松たか子の何事もスパッと割り切って生きて行く、いかにも江戸っ娘的な潔さ、きびきびとした立ち居振る舞いの魅力と、日本映画の衰えぬセット芸術の素晴らしさを見ているだけで、充分元は取れる映画ではある。
私、お金になるんですね
映画「ヴィヨンの妻 ~桜桃とタンポポ~」(根岸吉太郎監督)から。
[原作]太宰治とあって、ちょっと迷ったが、(汗)
大好きな「松たか子さん、広末涼子さん」の共演とあって、
1度にふたりが観れるなんて最高・・とミーハー感覚で観てしまった。
気になる一言は、物語とはあまり関係ない、単なるつぶやき。
夫の借金を返すために小料理・椿屋で働き始めた佐知(松たか子役)は、
あっという間にお店の人気者になり、チップを大勢にいただく。
(たぶん、私でもチップをやりたくなるな、きっと(笑))
2歳になる子どもの病気治療代もない貧しい暮らしと比べたら、
その世界は、驚きの世界だったに違いない。
あまりのチップの多さに、思わず口にした台詞が
「私、お金になるんですね」
実は、この台詞、原作は短編ということもあって、
読み直してみたが掲載されていないが、妙に、耳に残った。
以前、働いた経験があるような人物設定だったが、
人の役に立って、お金がもらえて、人気者になった彼女の台詞は、
「労働の意義」を表しているようにも感じる。
この世の中に、自分の存在感を意識したシーンだった気がする。
出番は少なかったが、広末涼子さんの演技にも、魅了された。
「おくりびと」の妻役から、ひと回り大きくなった彼女。
これからの活躍が、目に浮かぶようだ。楽しみである。
心ある時代。
第33回モントリオール世界映画祭で監督賞を受賞。
となれば期待が高まり、皆さん観に行くんだろうな~と^^;
やはり館内は混んでいた。
特に太宰ファンでもない自分は、こういう男イヤだな(爆)
としか思えないのだが^^;でもこういう男にはこういう女が
しっかりと!付いて、支えてくれるものでもある。
夫婦って面白いと、時代的に人間の心が豊かだったと、
そういった風情を大いに楽しめる作品だったと思う。
役者たちは皆、粒揃いで芸達者。
なので彼らを観ている分にはとても安心感があったが、
この根岸吉太郎はそれぞれの女性の撮り方が巧い。
とりわけ驚いたのがヒロインを抜いて広末涼子の演技。
何に出ても浮きまくり(爆)どこまでやっても少女っぽさが
抜けない上、なぜか落ち着いた淑女役の多い彼女だが、
今回の愛人役は「アタリ」だな、と感じた。悪役昇華。。
松が演じる妻とは対照的な性格となるが、どちらも巧くて
さらには室井滋なども絡んできて、とても観応えがあった。
この才能ある大谷という作家バカ(すいません^^;)や
口先だけのエロ弁護士(堤真一)や、良く分からない工員
(妻夫木聡)らに慕われまくる、大谷の妻なのだが、
どこかあっけらかんとして女を感じさせる艶っぽさがある。
情けない男たちは、こういう女を好きになるのだろうし、
女も男を支えることが喜びなのだから相思相愛となる。
誰が何を言おうとも。の世界なのだ^^;
全体的に落ち着いたトーンの懐かしさが味わえる作品。
(今では赦しも癒しも得られぬ男女の世界。いざ昭和へ?)
物悲しい
原作未読
役者がよかった。
映画全体のなんともいえない空気感を体現する大谷の存在と、強くて、しかしは儚くてもろいさちの献身的な行動と笑顔。
つばきやの二人の普通な優しさ。
器用な不器用さを表すには浅野以外に大谷は考えられないと観た後思った
非常に物悲しい気分になった
素晴らしく文学的
とても知的な大人の映画でした。文学作品らしい様々な暗喩的行為が出てきます。原作は読んでおりますがこのような描写はなく、映画独自のものだと思います。それらの行為の意味を一々考えるのも楽しいでしょう。
まず画面の絵が素晴らしく美しいです。ありがちなストーリーですが、センスの良い絵でグッと映画に引き込まれます。
妻・さちが夫にささげる献身的な愛が見どころです。
ささげる相手である夫・大谷が妻に愛を感じていないことは無く、一等上等な愛を抱いているようです。
大谷は様々な女性で自らの寂しさを紛らわせていても、劇中、妻に「私が知らないことがたくさんあるのね」となじられた時「あなたが知らない私など、どうでもいい部分なのです」と言い、妻に見せている面が一番重要だと考えていて、他の女性たちとは一線を引いています。
生活面でお金を渡さない夫であったり、妻に着物をあつらえない大谷ですが、
他の場では大盤振る舞いをよくしています。
金の使い方が間違っているのではないか、と疑問に思うところですが、おそらく俗なものを妻に触れさせないようにしたかったのでは?と想像します。
妻に神聖や純真を感じていることと「大事にしているつもりなんだけどな」という台詞から合わせて考えると、かなり独特に大切にしているのではないでしょうか。
自分の一番大切なものを変えないように大切にしていきたいと思っていても、妻は自分を思うがために穢れていってしまう。
妻に神性を見た夫は自分のために妻をただの女に引き下ろしてしまったのです。
夫婦をめぐる恋模様は発展していきますが、二人の間に絶対的な愛があるせいかドロドロせずまるで純愛映画のように見れます。さらっとした見心地でした
しかし、文学的な描写にこだわりすぎて、
「分かる人が見なければ意味がわからない」という映画になっていると思います。
そこが私は好きなのですが・・・
全9件を表示