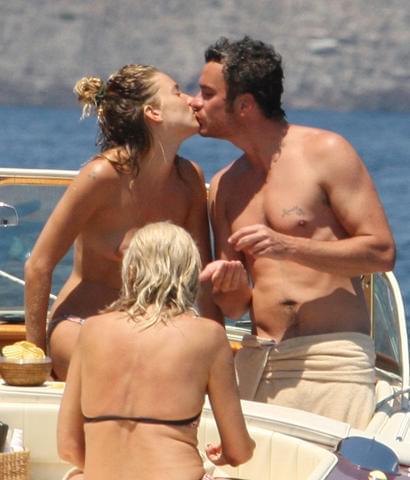ファクトリー・ガール : 映画評論・批評
2008年4月15日更新
2008年4月19日よりシネマライズにてロードショー
ウォーホルの思想を体現したイーディという名の光を映し出す

(c) 2006 Factory Girl, LLC
アンディ・ウォーホルの女神、ボブ・ディランの恋人、ボストン上流階級の娘、「ヴォーグ」の人気モデル、28歳で死んだドラッグ中毒者——そのどれもがイーディだ。が、イーディの真髄は、ウォーホルの「作品の表層が全て。裏側には何もない」という思想を実践し、自分自身が作品となったことにあるのではあるまいか。イーディの意味は、彼女を被写体にした写真と映像が表現する。イーディの本質は、彼女自身の言葉よりも第三者が彼女について語った言葉が捕らえているので、彼女の言葉は忘れられたが、カポーティの言葉やディランの曲は残っている。イーディという現象の中心は空洞で、それが反射する一瞬の激しい光こそがイーディなのだ。映画という突き詰めれば形を映し出す反射光である表現様式にとって、これほど魅惑的な題材はないだろう。
監督はデビュー作がポップ音楽界の有名人のドキュメンタリー映画だった人物。まずは、イーディとウォーホルとディランの三角関係という思いっきりゴシップ誌なネタを主軸に据える。そのうえで監督が試みたのは、65〜66年のニューヨーク限定の、アートとファッションとスキャンダルが渾然一体となって放った一瞬の燦めきを、ドキュメンタリー的に再現することだったと思われる。22歳のイーディがウォーホルと出会った65年、16歳のツイッギーがマリー・クアントと出会ってスウィンギング・ロンドンが花開いてゆく。あの時代だけの輝きはこうだったのかもしれない、そう思わせる瞬間がある。
(平沢薫)