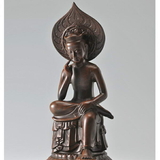愛を読むひとのレビュー・感想・評価
全99件中、1~20件目を表示
【91.6】愛を読むひと 映画レビュー
作品完成度
本作の完成度は、一貫して抑制されたトーンと、細部にまで行き届いた演出によって、原作が内包する複雑なテーマを深く掘り下げている点にある。一見すると、これは単なる恋愛映画のように見えるが、その実、物語の核にあるのは、戦後ドイツの加害者世代と、その罪と向き合わねばならない次の世代との葛藤である。ハンナの抱える「読み書きができない」という秘密は、彼女の戦時中の行動、そして裁判での証言を左右する決定的な要素となり、物語全体の展開に不可逆的な影響を与える。この秘密を軸に、彼女の自己欺瞞、そしてマイケルの無力感と後悔が重層的に描かれ、観客は個人の愛と社会的な罪の境界線を問い直される。監督スティーヴン・ダルドリーは、この繊細なテーマをセンセーショナルに描くことなく、静謐なタッチで描き切っている。特に、ハンナがマイケルの朗読テープを聴きながら文字を練習するシーンは、彼女の贖罪と成長、そしてマイケルとの精神的なつながりを象徴的に表現し、強い感動を呼び起こす。
監督・演出・編集
監督スティーヴン・ダルドリーの手腕は、原作の持つ重厚なテーマを崩すことなく、映画的な視覚言語で再構築した点にある。彼は、登場人物の感情の機微を、雄弁な台詞ではなく、表情や仕草、そして空間の演出によって表現する。編集のクレア・シンプソンは、過去と現在を行き来する物語を滑らかにつなぎ、ハンナとマイケルの関係性の変遷を効果的に見せる。特に、法廷でのハンナと、傍聴席から彼女を見つめるマイケルの視線が交錯するシーンは、二人の関係性の断絶と、それでもなお消えない絆を暗示し、観客の胸に深く刺さる。抑制された演出は、物語の核心にある悲劇性を一層際立たせ、観客の感情を揺さぶる。
キャスティング・役者の演技
本作の成功は、そのキャスティングの妙に大きく左右される。特に、主演女優ケイト・ウィンスレットの鬼気迫る演技は、本作に計り知れない深みを与えている。
ケイト・ウィンスレット(ハンナ・シュミッツ役)
ハンナという難役を演じきったケイト・ウィンスレットの演技は、驚くほど多層的である。彼女は、マイケルとの愛に溺れる奔放な女性、職務に忠実な看守、そして裁判で己の罪と向き合う被告人という、異なる顔を持つハンナを見事に演じ分ける。特に、読み書きができないという秘密を抱えるがゆえに、法廷で屈辱的な選択を迫られるシーンでの、彼女の表情は観客の心を打ち砕く。プライドと羞恥心、後悔と諦念が入り混じった複雑な感情を、一瞬の目の動きや口元の震えだけで表現するその演技は、まさに圧巻。彼女の演技は、ハンナという人物の持つ人間的な弱さと、それでもなお保とうとする尊厳を鮮やかに描き出し、観客は彼女の行動を単純に断罪することができなくなる。この演技で彼女は、第81回アカデミー賞主演女優賞を受賞。
デヴィッド・クロス(若い頃のマイケル・ベルク役)
15歳の少年マイケルを演じたデヴィッド・クロスは、ケイト・ウィンスレットという大女優を相手に、堂々たる演技を見せる。彼が演じるマイケルは、ハンナとの出会いによって性的な目覚めを経験し、純粋な愛と官能に揺れ動く思春期の少年を瑞々しく表現する。ハンナが姿を消した後の喪失感、そして法廷で再会した際の困惑と苦悩を、その繊細な表情で的確に伝える。彼の演技は、マイケルの成長と内面の変化を丁寧に描き出し、物語に説得力を持たせている。
ラルフ・ファインズ(大人になったマイケル・ベルク役)
大人になったマイケルを演じるラルフ・ファインズは、過去のハンナとの関係から未だに解放されず、苦悩を抱える男の静かなる葛藤を表現。彼の存在は、物語の語り部として、観客にハンナとマイケルの物語の結末を暗示する役割を担う。ハンナの死後、彼女の遺産を巡って娘と話すシーンでの、過去の自分を振り返る彼の憂いを帯びた表情は、この物語が単なる悲恋物語ではない、より深い人間ドラマであることを示唆している。
ブルーノ・ガンツ(ロール教授役)
クレジットの最後に出てくるブルーノ・ガンツは、法学部の教授として、マイケルに戦犯裁判の傍聴を促す重要な役割を担う。彼は、過去のナチスドイツの罪と向き合い、それを次の世代に伝えようとする知的な指導者を、落ち着いた演技で表現。彼の存在は、マイケルが個人的な関係性から一歩踏み出し、社会的な罪という大きなテーマに向き合うきっかけとなり、物語のテーマ性を補強している。
脚本・ストーリー
デヴィッド・ヘアーによる脚本は、ベルンハルト・シュリンクの原作小説『朗読者』の複雑な構成を巧みに再構築。物語は大きく三つのパートに分かれる。少年時代のマイケルとハンナの恋愛、大学生になったマイケルが法廷でハンナと再会するパート、そして大人になったマイケルがハンナの死と向き合うパート。それぞれのパートが独立していながらも、ハンナの「読み書きができない」という秘密によって結びつけられている。このストーリーテリングは、個人の愛と、ホロコーストという歴史的な罪という、二つの異なるテーマをシームレスに融合させている。
映像・美術衣装
クリス・メンゲスとロジャー・ディーキンスによる撮影は、1950年代のドイツの空気感を見事に捉える。少年時代のマイケルとハンナの情事を描くシーンでは、光と影を巧みに使い、官能的でありながらもどこか純粋な雰囲気を醸し出す。一方、法廷や刑務所のシーンでは、無機質で冷たいトーンが、物語の重苦しさを際立たせる。衣装はアン・ロスが担当し、時代背景を正確に反映した衣装が、登場人物の社会的地位や心理状態を巧みに表現。特に、ハンナが看守として着る制服は、彼女の厳格さと同時に、彼女が自らのアイデンティティを形成しようとする様を象徴する。
音楽
ニコ・マーリーによる音楽は、物語の情感を静かに、しかし深く彩る。派手なオーケストラではなく、ピアノを主体としたミニマルなスコアは、登場人物たちの内面の葛藤や悲しみを繊細に表現。特に、ハンナが朗読テープを聴くシーンで流れる音楽は、彼女の孤独と、マイケルへの想いを静かに描き出し、観客の心に強く響く。主題歌はないが、このスコア全体が、作品のトーンを決定づけている。
受賞歴
本作は、第81回アカデミー賞において5部門にノミネートされ、ケイト・ウィンスレットが主演女優賞を受賞。スティーヴン・ダルドリーは監督賞にノミネートされ、長編デビュー作から3作連続での監督賞ノミネートという快挙を成し遂げた。この受賞歴は、本作が批評家からも高く評価された傑作であることを裏付けるもの。
作品
監督 スティーブン・ダルドリー
129×0.715 91.6
編集
主演 ケイト・ウィンスレットS10×3
助演 レイフ・ファインズ A9
脚本・ストーリー 原作
ベルンハルト・シュリンク
脚本
デビッド・ヘア A9×7
撮影・映像 クリス・メンゲス
ロジャー・ディーキンス
A9
美術・衣装 ブリジット・ブロシュ A9
音楽 ニコ・ムーリー A9
結末のそのケイトウェンスレットが刑務所に入った後もそのケイトウェン...
結末のそのケイトウェンスレットが刑務所に入った後もそのケイトウェンスレットの彼氏が本を読んで、それを声を上げて朗読したそれをカセットテープに録音して、もう刑務所の中に居るその文盲のそのケイトウェンスレットに幾度も送り続けたでしたが、その原作をまだ読んでませんが、それが信じられませんが、その小説なりにその映画なりにそれがないと話が続いていきませんが、そのケイトウェンスレットが美人だが、戦前にナチスの女子刑務所の官吏で、またロマ人でさらに文盲だったが、戦後にその罪を問われ、一人責任を負ったが、法廷での法廷言語に黙秘権を行使しますがありますが、知的障害者や身体障害者だと自分の意見を自分の判断として自己責任として語れないですが
原罪
巧妙に組み立てられたスリラー。
ハンナが頑なに守ってていた事に、価値がなかったとしたら?
文盲(もんもう)という秘密。
このハンディをハンナが恥じて頑なに言えなかった事に、
ハンナの人生は狂わせられ、結果的には最後には
自殺を選ばねばならなかった。
非常に巧妙に仕組まれた原作とその映画化作品。
ハンナは文盲の電車の車掌でした。
15歳のマイケルはハンナの家に行きハンナから
愛の手解きをうける。
夢中になるマイケルだったが、ハンナは
マイケルに本を読むことを頼んでくる。
しかしハンナは急に居なくなってマイケルの前から姿を消す。
次に再会した時ハンナはナチスの看守として、
ユダヤ人300人の死に関わった罪で
裁かれる被告になっていた。
15歳でハンナに本を詠み聞かせしていたマイケルは、
その時は法科大学の学生で弁護士を目指していた。
授業の一環です裁判を傍聴したのだ。
ハンナは看守としてユダヤ人が収監されている講堂が爆撃されて
炎に包まれているのに、鍵を開けずに閉じ込めて死なせた容疑。
看守は5人居たのに、頑なに過失を認めず、
書類にサインすることを拒絶する。
その時マイケルは気づいたのだ。
ハンナが字を書けないことを、それでサインが出来ないことに。
しかしマイケルは知らんふりを決め込んだ。
ハンナを擁護しなかった。
保身に回ったのだった。
ハンナは他の賢い看守たち4人の罪を被り終身刑になる。
本を読むこと、
物事の真理を考えること、
思考すること、
正しい道を自分なりに選ぶこと、
ハンナは何年も刑務所に服役して、自分の侵した罪を理解しただろうか?
なぜユダヤ人が焼け死ぬのを見殺しにしたことが罪なのか?
分かったのだろうか?
分からなかったのではないだろうか?
ユダヤ人は動物以下と教えられ、素直に信じた。
ハンナは変われなかったのでは?
ユダヤ人差別から抜け出せなかったのではないか?
無知の悲しさ。
頑なさの沼。
マイクにしたって、死んだハンナの墓にお参りしても、
知らん顔を決め込んだ罪は償えない。
やり直しはきかないのが人生。
重い余韻が残った。
いきなり違う映画が始まってびっくりした
運命というものの重み
人と人が出会ってしまうことの重さを感じた。原作も読みたい。
ハンナに対する同情、生き残ったユダヤ人の怒りの両方が伝わる。
マイケルの中の、相反する感情がどんどん濃くなっていき、心に染み付いていく様子。ハンナへの愛と罪の意識。許しを乞う人間の姿は辛い。
頭の固いおっさんと、意味不明な行動。
................................................................................................................................................
主人公の少年が病気で、道で倒れた時、女性が助けてくれた。
それがきっかけで、少年は女性を好きになり、2人は同棲生活を始める。
少年は性の手ほどきを受けたが、逆に本を読んで聞かせる事を求められた。
女性は文字を読めず、またそれがコンプレックスなのだった。
法学部に入った主人公は、この女性が容疑者の1人である裁判を傍聴する。
看守だった主人公達が、火事の際に囚人達を見殺しにした事件だった。
この女性はハメられて首謀者に祭り上げられ、懲役を食らう。
裁判は、女性の筆跡鑑定により判断しようと言う流れになったのだが、
文字を書けない事を知られたくないため嘘の自白をしたのだった。
主人公はそれに気付いたが、黙っていた。
刑期はかなりの長期で少年もおっさんになったが、
その間中おっさんはテープに物語の朗読を録音し、送り続ける。
女性は刑務所の図書館で原作を借り、照らし合わせる事で文字を学ぶ。
刑期も終了間近となり、おっさんは女性の身元引受人になる。
そして刑務所内で一度会い、少しの会話をする。
ところが女性は出所の日を前に自殺してしまった。
................................................................................................................................................
うーん、理解不能な点が多かったなあ。
このおっさんは一体何を考え、何故そのような行動を取ったのか?
まあ裁判で彼女の濡れ衣を晴らさなかった件については、
彼女の意志を尊重したのだとも取れる。
でも、だとしたら彼女はまさに被害者ということである。
一応罪にはなるかも知れない、でも本来は微罪なのである。
なのにこのおっさんは女性を犯罪者扱いして上から目線で扱っている。
例えば、テープは送り続けたが、彼女からの手紙に一切返信しない。
何これ?読み書きすら出来ない哀れな女に対して、
テープを読んで送って上げてるって態度にしか見えなかった。
そして最後に会った時、過去の事をどう思うかを聞いた。
女性は自分達の恋愛の思い出話の事と思って笑顔で話し始めるが、
すぐに遮り、自分の罪を反省したのかの話だと言った。
お前はどんだけ上から目線やねん、アホかっての。
女性は長い孤独の末に出会えたこのおっさんに甘えたかった。
それとなく手を机の上に差し出すが、男は軽く触れるだけでスルー。
お前は女心ってものがわからんのか?だから離婚されるんやって。
ホンマに頭のかたーい、自分の考えを押し付けがちな、
学校に子供を通わせずに自宅で家庭教師をつけたりしがちな、
欧米の古くさーい、カトリックの親父っぽさ満開やった。
日本人にはこのおっさんの意図は理解できないのではないだろうか。
それともこのおっさんでなく、女性側に感情移入せよって事?
いやそういう描かれ方もしてなかったし、全く意味不明。
気持ちの潔さが哀しい 死んだ人は戻らない
何とも前後半のギャップが激しく、考えさせらる映画だった。「青い体験」のような年上の女性との恋愛、時を経て驚愕の事実を知らされる。主人公だけでなく、下準備なしの観客も。いろんな思いが錯綜し、後でじわじわ蘇る感動。
軍事裁判で責められる彼女から、ようやく原題の事実を知る。現代では「文盲」も「無学」もやる気と機会があれば取り返しができるだろう。当時のドイツだけでなく、日本もソ連もヒステリックなまでの全体主義的統制社会で、自分の弱みを正直に話せたか? おそらく破滅的行為で、彼女自身が劣等市民として収容所に入らなくてはいけなかったかも。そんな葛藤が自分だけの秘密となり、忠実な党員として身を守るしかなかった。「あなたならどうしましたか?」 単純だけど厳しく辛辣な一言だった。
一方で、向学心の灯を消さなかったのだと思う。だから、ラスト近くの再会シーンの違和感もわかるような気がする。彼女は昔のように、物語を聞きながら仲睦まじく勉強したかったかな? 一方、彼は、虐殺に加担した彼女の行為を許しきれなかったか? 経済的援助も生活支援もするが一歩踏み出せない彼の印象が、出所後の生活不安や社会復帰の困難さを解消できなった? 残された部屋で呆然と立つ彼女の視線も、頭を抱える彼の姿も、なんとも哀しい。彼女が、勉強した本を足台にする気持ちは思い出しても辛い。
二人とも、気持ちの根底は、「死んだ人は戻らない」だったのか?
ケイト・ウィンスレットの女優賞は文句なしでした。
相似形の魂
見過ごしてきた作品のゲオ旧作鑑賞です。
何故マイケルは、あのとき踵を返してしまったのか。何故手紙に返事をしなかったのか。原作を読んだことはありませんが、最初は自身の恥ずかしい秘密が白日のもとに晒されるのを恐れたからという印象が強くて「最低野郎」だなと思いましたが、色々解釈の余地を残しているようにも思えました。(以下ネタバレありです)
もし踵を返さず、真実を語っていたらどうなったのか。
ハンナは多分無期懲役を免れたかもしれませんが、彼女があえて罰と引き換えに守った秘密を白日のもとに晒すことになります。映画「砂の器」の指揮者が自分の出生の秘密を守るために罪を犯したように、その秘密はロマである彼女にとっては、自分のいのちより大切なものだったのかもしれません。指導教授が促したような真実や正義の回復ではなく、一度は愛した彼女の意思と希望を最大の利益と考えて行動した結果だったのかもしれない・・今はそう思います。助けたいけど助けられない・・矛盾に引き裂かれた彼の心の苦しさを思うと胸が痛みます。
何故手紙に返事をしなかったのか。
それは多分彼女が犯した罪をマイケル自身が整理仕切れていない面もあったのだと思いました。最初で最後の面会のとき、マイケルはそのことをはじめて尋ねていましたから。多分法廷での彼女の証言を聞いて、彼女自身の心の中で自分がしたことの意味の整理がつくまでは、時間がかかる。それができるまでに手紙のやりとりをしても破綻に終わることが彼には目に見えていたのだと思います。だから彼は本を読むことに徹したのではないか。そう思いました。
「あなたならどうしましたか?」ハンナが法廷で語った言葉に裁判長は答えられませんでした。同じように私はマイケルの罪を糾弾できるようには思えません。つまり、法的な罪と道義的な罪の違いはありますが、糾弾しきれない罪を負ったという点で、二人は相似形だったように思います。その根っこには多分歴史の矛盾があったのでしょう。切ないです。
自責の念にとらわれて生きざるを得なくなった二つの孤独な魂は、ある意味夏目漱石の「こころ」の「先生」や、シドニールメットの名作「質屋」の主人公に通じるものを感じましたが、最後彼女に向き合うことができた彼の方は、これらの主人公とは若干異なり、ほのかに明るい希望のもてるものになっていたように思います。それがまたしみじみ良いなと思いました。
いろいろな解釈を許す作品は、観る者の経験や性格と化学反応をおこして
見る人一人一人の心に深い余韻を残す場合があるように思います。本作もまさにそういう映画で、見逃した作品にもやはりとびきりよいものがあるな。改めてそう思いました。
抱えてるもの
観る前のイメージでは、
また年上女性とのひと夏の恋ですかと。
また若者の性はとまらんが年取ってから懐かしく思い出すわよ、かいなと。
ですが中盤からガラリと変わり、
涙なしでは見れない展開になります。
そこまでが微妙に見ててキッツイなあって気分にもなるのですが。
とにかくケイト演じるハンナが、まあどこがどう魅力的なのかは
つかみにくいが
何か悲しい秘密をもってるんだろうなってのは
匂っていてそこがひきつけられる。
抱えるにはあまりにも重く、
とても他人に打ち明けたり分かち合えるようなものでもない。
孤独だ。
これは被害者にあたる彼女の方も同じで、
あまりにも重い悲しみはむしろ分かり合えないし
分かち合えない。
少しは物がわかったかと思った主人公マイケルが二度、三度と
打ちのめされていく姿は観ていて
自身の思いもなんとも生ぬるいのだろうかと
突きつけられる思いである。
当初はニコール・キッドマンを予定していた役だが、
実際に見るとケイト・ウインスレット以外に考えられない。
ケイトはすごかった。
そこに座って、歩いて、それだけでハンナを表現してた。
さすがアカデミー主演女優賞。
すばらしかった。
「チャタレイ夫人」がわいせつ?お前が言うな
高校時代の授業で西欧文学の特徴である“秘密性”が講義される。主人公の秘密を読者に知らせないで想像力をかき立てる手法らしいが、この作品自体もハンナの非識字者であることを秘密に・・・ではあるけど、かなり序盤に予測できてしまうストーリーの弱さはあった。法科学生の実習でマイケルが気づいたように描かれるものの、二人で旅した時に気づかなければおかしい。しかし、恋は盲目。気づきながらマイケルは心の奥に閉まったままにしておいたのだと想像してしまいます。
マイケルとハンナの蜜月時に電車に乗ったことを怒ったハンナだったが「誰にも謝る必要なんてない」などと言ったことも興味深い。とにかく秘密の多い女性というイメージを持ったままハンナはいなくなってしまう。そして再会したのはマイケルが法科学生となった8年後のこと。
公判でも罪を認めたが謝罪はなかったハンナ。爆撃により火災が起きた教会の鍵を開かなかった罪が問われたのだ。「社会を動かしているのは“道徳”じゃなく“法”だ」と講義する法科のロール教授(ブルーノ・ガンツ)。道徳的にはユダヤ人を助けるべきだが、SSに所属し看守を務めていたハンナにとっては鍵を開けないことが秩序を守る唯一の道だったのだ。
6人の女性看守の内、ハンナには責任者だったとして唯一人重い無期懲役の判決が下され、仮釈放されるまで20年服役。刑務所内では学ぶことなどない!と主張する生き残りのユダヤ人マーター。ではハンナは何を為したのか・・・マイケルが送っていた朗読テープによって独学で読み書きを学んだ。それが贖罪になるのかどうかはハンナにとってもマイケルにとっても判断に迷うところ。マイケルの人生を変えてしまった事実についてもマーターは問う。
ホロコースト、特にアウシュビッツにおける大量虐殺については触れないが、法を教えるブルーノ・ガンツが『ヒトラー~最期の12日間』(2004)でヒトラー役を演じていたことも興味深い。最近の戦争犯罪を扱う映画なんて、上からの命令には逆らえないというテーマ一辺倒であるため、文盲であることを隠すプライドにより刑罰を受けるというユニーク性もあった。その事実に気づきながら公判に対して何もできなかったマイケルには賛否両論あろうけど、美しき初恋・初体験の思い出を引き出しに閉じたかっただけなのかもしれません。
もう一つ興味深いのは何度も繰り返し朗読されたホメロスの「オデュッセイア」。テーマは帰郷homecomingだ。故郷を夢見て旅する物語の一節が何度も登場するが、緋識字者であることも併せてハンナが故郷を持たないロマ人だったことが窺える。ユダヤ人と同じように差別を受けていた民族。被差別の側として生き残るためにはSSに入隊するしか道がなかったのとも読み取れる。そんな故郷を持たない彼女はマイケルが迎えに来てくれても自分の居場所がないことを悟ったのだろうか。自殺の真の理由は色々と想像できますが、それよりもマイケルへの感謝の気持ちに溢れていたことが泣ける。3回目の鑑賞となりましたが、やっぱり泣ける。
初体験の相手の思い出
ダフィットクロス扮する15歳のマイケルは、学校帰りに病気になり動けなくなっていたところケイトウィンスレット扮するハンナシュミッツに助けてもらった。
思春期の僕が年上の女性に裸で迫られれば、そりゃあ抵抗の余地が無くなってずっぽりはまってしまうだろうね。男性にとっては夢の様な話だろうが、ハンナからするとただ持て遊んでいただけかもしれない。しかし15歳の僕には一生拭えない出来事になってしまった。
ハンナは常に本を読んでもらう事を好んでいたが、その後ハンナはマイケルの前から突然消えてしまい、マイケルが法科の学生としてゼミで裁判所の裁判を傍聴した時、偶然ハンナが出廷していた事で再会した。実はハンナはアウシュビッツで看守をしていて裁判にかけられていたと言う重い話。ハンナには秘密があった。
初体験の相手にず~と引きずられてしまうが、男にとってはやむを得ないだろうね。そういうもんだからな。ケイトウィンスレットの体当たり演技は官能的で素晴らしかった。マイケルじゃないけど、引きずられてしまうね。だけど、ラストシーンで娘に父親のこの手の青春の思い出を語るのはちょっと考え物だと思うな。
願いのような作品
二次世界大戦後のドイツを舞台にした悲哀の物語。
スティーブンダルドリー作品でしたが、いまいちピンとこなくてスルーしてました。
が、プライムで見かけたのでふと観てみることに。
ケイトウィンスレットの佇まいが良く、その芝居もとんでもなく惹かれるものがありました。
そして若きマイケルを演じたダフィットクロスも、その肢体が若さに満ち溢れていて別の魅力に溢れてましたね。
二人のロマンチックな逢瀬は、その時代背景に大きくその運命を歪めていく。
…といった話でしたが違いました。
いや、あくまで個人的にですが、違うように見えてきました。
裁判から急激にシリアスになり、それぞれの葛藤を描かれていきます。
その辺りからいくつもの小さな「なぜ?」があったのですが、二人を通じもっと広く描いたものに見えてきました。
裁判自体アウシュビッツ裁判でしょうし、ここを主軸のようにじっくり描いていきます。
そんな中教授の言葉は、むしろ我々に投げかけてくるようでした。
文盲とそれを隠すのはロマ族(ホロコーストと同じ虐殺対象)だとは薄々分かるのですが、それをはっきり示さないのも"あえて”なのでしょう。
後悔の念と何処か目を背けたい過去。
手紙に目を通さなかったりと、ちゃんと向き合えないやり取りの末の別れ。
そうして迎えたラスト。娘に話し始めるその姿は、まるで希望を託しているようでした。
そしてこのラストで、はっきりと自分の中で腑に落ちたのだと思います。
これはドイツそのものを描いたものではないだろうかと。
できればなかった事としたい恥ずべき歴史ナチスドイツ(ハンナ)、それを未だどう向き合えば良いのかわからないままでいる現ドイツ(マイケル)、そしてそれらを踏まえ乗り越えてほしい未来への希望(ジュリアン)。
歴史を受け継ぎ、過去に目を背けず、これからの未来へと繋ぐ。
ドイツという国への問いかけと、願いのような作品と感じました。
甘美な物語にこもる戦争悲劇
バスの車掌をしている疲れ果てた女性が、
ふとした切っ掛けで15歳の少年をくわえ込んだ物語の端緒は、
デボラ・カーの『お茶と同情』を思わせました。
親と子ほども離れた不実な恋物語の始まりを感じさせましたが、
謎の女の正体を求めて、
上級なシナリオはサスペンス豊かにグイグイ引っ張って行きます。
声がいいから、と少年に本の朗読をせがむ
家族の気配がない不思議な女は、
職場の勤務状態が良いから、事務職に昇進を告げられた日に失踪する。
8年後、
少年が女を見たのはユダヤ人収容所の看守だった女を裁く法廷。
不思議な女を演じるケイト・ウィンスレットが秀逸です。
目の演技が、他に比較できない印象を残しました。
彼女の出生の秘密は明かされなかったかも知れませんが、
少年の経験は、彼の一生に大きな影をもたらす、
甘美な初恋だったことは間違いありません。
ちょっとよくわからない
前半は魅力不足の男女のダラダラ恋愛劇が続いて1.5倍速しましたが、後半結構サスペンスフルになってそこそこ面白い。
ただ、話のキーになる彼女の「文盲」が最後まで全く分からず、わかったとしても、だとしたら何なのか?そもそも彼女は冤罪だったのか?
更に、最後にNYで会った女性は誰なのか?彼女との会話にどういう意味があるのか?
娘に何を話したかったのか?話されたって困ると思うけど?
てなわけでよくわからないので3点です。映画としては4点ですけど。
テーマ性の強い作品なので、もう少しわかり易く描いた方がいいですね。
あなたならどうするか
プライドとは命懸けで守るもの。
朗読を通じて育む神秘的な愛...
全99件中、1~20件目を表示