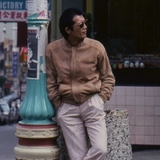ヒトラー 最期の12日間のレビュー・感想・評価
全53件中、1~20件目を表示
悪夢のような大戦禍と、悲哀に満ちた「最期」。
○作品全体
ヒトラーの描き方が独特な作品だ。
ナチスドイツの終わりの時期に焦点を当てることで、快進撃の根幹にいたヒトラーの姿は一抹も感じさせない。「カリスマ性」とか「煽動力」といった、ヒトラーを語るうえでよく出る単語からはほど遠い姿が印象的だ。
構成やセリフから「悪夢」という単語が浮かんだ。
ドイツという国そのものが「悪夢」の真っ只中である12日間だが、ファーストシーンが真夜中で、ラストシーンが夜明けである本作の構成そのものも「悪夢」を想起させる。ユンゲが地下へと潜って行くのも悪夢という眠りの淵へと向かって行くかのようだ。そしてラストシーンでユンゲが語る「目を見開いていれば…」という言葉が、瞳を閉じて見続けている悪夢の世界を印象付ける。
そして悪夢だと感じているのはドイツ国民だけではない。親愛なる国土を蹂躙され、なすすべもなく喚くも状況が変わらないヒトラーも悪夢の中を過ごしている。「偉大な総統」だった頃こそが夢であったかのようなヒトラーの姿は、作中では癇癪持ちの疲れ切った老人でしかない。時折ユンゲたちに見せる優しい表情が、むしろその悲哀を助長させる。
夢破れ、夢から醒めた老人という部分にスポットをあてていることが、「最期」の無情さを最大限に感じさせていた。ヒトラーが総統でなく、ただの老人になってしまったことがナチスドイツの「最期」で、その描き方はベルリンの大戦禍とは裏腹に、穏やかな老衰死のような、なだらかな死のように描いていたのがまた印象的であった。
○カメラワークとか
・地下施設の映し方が上手だった。狭苦しい環境のはずだけど、ヒトラーからすると心許せる人物が少ない場所。時折ガランとした空間を映すことでヒトラーの空虚に接近する。
・最初のヒトラー激怒シーン。怒る直前、メガネをゆっくりと外すのはシンプルにカッコよかった。怒ってからヒトラーの背中をなめて、奥に立つ将軍たちを映す。意見の決定的な乖離が際立つカメラ位置だった。
タイトルなし
ヒトラー 〜最期の12日間〜
2004年公開 ドイツ、オーストリア、イタリア合作
名作です
長く映画の歴史に残る作品だと思います
600万人のユダヤ人が収容所で殺害され、死者5000万人以上の第二次世界大戦を引き起こした張本人ヒトラーの最期はどういうものであったかを描いています
日本人としては、どのような立場で観たらよいものか少々悩みます
主人公のひとり秘書のユンゲはドイツ人として映画の最後にこう語ります「若かったというのは、言い訳にならない、目を見開いていれば、気づけたのだと」
第二次世界大戦を引き起こしユダヤ人を大量殺戮した人物のそばにいたことで、自分にも責任の一端があると感じていると
戦勝国のアメリカ人やロシア人なら?
ざまみろ!溜飲がさがった!自殺しやがって!責任から逃げやがった!
でしょうか?
俺達がナチを粉砕した!
二度とファシズムが復活しないようにする責任がある!
とか?
ユダヤ人や、ヨーロッパのドイツ被占領国の方なら?
言葉にもできない怒りだけでしょうか?
ドイツ人は全員死ぬべきだ!とか?
同じ敗戦国のイタリア人なら?
ムッソリーニと同じように吊されるべきだ!でしょうか?
では日本人は?
ヒトラーのように国民を見捨てない天皇陛下がおられたことの幸せをまず感じます
「日本の一番長い1日」と本作との大きな隔たりを感じます
もし、降伏せず、本土決戦になっていたなら、本作のような展開が、東京か、疎開先の松代かどこかであったことでしょう
戦争をほぼ日本人全員が支持していたのですから、国民に責任は無いというのは左翼の人々でなくても、さすがに無理があると思います
終盤、ユンゲのこぐ自転車に一緒に乗っていたドイツの軍国少年にも戦争責任はあったのでしょうか?
ゲッペルスの母親に毒殺される六人の幼女達にも戦争責任はあったのでしょうか?
しかし、大人であっても日本は都市をことごとく焼け野原にされ、原爆まで落とされて十分に罰は受けたと思います
東京裁判で戦犯とされたものは処刑もされました
戦後に生まれた私達にこれ以上責任をとろうにもとりようがありません
そうではない!
日本人は永久に戦犯国民で謝り続けないとならないのだという人もいるようです
二度と戦争を起こさないという責任の取り方もあります
しかし、それでも一方的に攻めて来られたならそれはその限りではないと思います
今日は2025年9月2日です
80年前、日本が正式に降伏文書に署名した日です
明日9月3日北京では軍事パレードがあるそうです
中国とロシアと北朝鮮などの首脳がそれを貴賓席から誇らしげに閲兵するのでしょう
日本が本作のような滅亡にいたることは、一方的な侵略を受けて日本が滅亡する時でしょう
ウクライナ戦争は3年半を過ぎて、ロシア軍は行き詰まり、戦局は逆転してウクライナがプーチンを追い詰める事が起こりそうな展開になってきました
本作のヒトラーがプーチンと被って仕方ありません
クレムリンの地下壕で本作のように、将軍達に癇癪をぶちまけているように思えてなりません
ロシアが負けてプーチンに最後の日々が訪れるように希望する
それが戦後生まれの日本人の本作への立場だと思いました
そういう展開ではなく、ウクライナが敗戦してロシアに占領されたなら?
次はヨーロッパ諸国へのロシアの侵攻がはじまるでしょう
ドイツは日本と同じ敗戦国でしたが、国軍を再建しただけでなく、ウクライナ戦争の行方を見て徴兵制まで復活させようとしています
これはファシズムの復活なのでしょうか?
台湾有事の時、日本はどうなるのでしょうか?
当時のヴィジュアルをうまく再現できている歴史映画だなと思う一方、映画的な物語の面白みはさほどなく、歴史を眺めるのみの作品だった印象。
私にとって価値ある作品〜戦記好きは必見だが、万人向けではない。
2004(日本は2005)年公開、ドイツ・イタリア・オーストリア映画。
【監督】:オリヴァー・ヒルシュビーゲル
【脚本】:ベルント・アイヒンガー
【原作】:
①ヨアヒム・フェスト〜『ヒトラー 最期の12日間』、②トラウドゥル・ユンゲ、メリッサ・ミュラー〜『私はヒトラーの秘書だった』
主な配役
【ヒトラー】:ブルーノ・ガンツ
【トラウドゥル・ユンゲ】:アレクサンドラ・マリア・ララ
【エヴァ・ブラウン】:ユリアーネ・ケーラー
1.ヒトラーの最期を描く伝記映画として一級品
様々な映画やドラマに「ヒトラー役」が現れる。
喜劇王チャプリンの『独裁者』は代表的なひとつだろう。
だが、本作でヒトラーを演じたブルーノ・ガンツはまさに憑依の域に達している。
もちろん、私はナマのヒトラーを見たわけではないが、記録映画やニュースに残されたヒトラー像に完全に符合する。
2.私にとって価値ある作品
◆ヒトラー
◆その愛人エヴァ・ブラウン
そして、ヒトラーを取り巻く重鎮たち、つまり、
◆ゲーリング元帥
◆カイテル元帥
◆ヨードル大将
◆ゲッペルス宣伝相とその家族
◆シュペーア軍需相
◆ヒムラーSS指導者
◆エヴァの義弟でもあるへーゲラインSS中将
などなど、
大物たちが、ナチスドイツ臨終の間際にどのような行動をとっていたのかを活写している。
ヒトラーとエヴァ・ブラウンのやりとり(会話)についても、かなり具体的に描写していて興味深い。
もちろん、
映画ゆえの割愛やデフォルメ、一面的な描写もあるだろう。
だが、ナチスドイツ、アドルフ・ヒトラーの落日を描いた映画で、本作を超える作品に出会ったことはない。
(知らないだけかもしれないが笑)
3.まとめ
本作が公開されて20年がたつ。
まったく色褪せない。
陰気な地下室にこもり、
怒鳴り散らしたり、
気弱になったりした独裁者の最期。
実話だということが、まだ信じられないような気さえする。
戦記好きは必見だが、万人向けではない。
☆4.5
生々しく痛切な、実録ドラマの傑作だ。
ドイツの歴史家ヨアヒム・フェストによる同名の著作、および、本作では狂言回し的な女性秘書、トラウドゥル・ユンゲの回想録と証言をもとに、ベルリンの地下壕で過ごしたヒトラーの最期を描く。
ヒトラー役はドイツの国民的俳優、ブルーノ・ガンツ(本人はスイス出身)。人種差別や誇大妄想に取りつかれ、最後まで狂気じみていた独裁者を、見事な存在感で演じ切っている。
物語の舞台は地下壕という閉鎖的な空間だが、非常によく練られた脚本で、実に手堅い室内劇としての魅力もある。また、戦火に巻き込まれたベルリン市民にも光を当てている。
第三帝国の終焉が迫る中、ヒトラーをはじめ、子どもたちを毒殺した上で夫婦で自害した宣伝大臣ゲッベルスや、国防軍の軍人やSS(親衛隊)の幹部がそれぞれ選んだ終末の姿を、生々しく痛切なタッチで描き出した、実録ドラマの傑作だ。
ベルリンの惨状とヒトラーに対する盲信
スターリングラードの戦いで敗北した時点で、ドイツの敗戦は目に見えていたにもかかわらず、ヒトラーは降伏を決して許さず徹底抗戦を命じた。その結果、遂にベルリンにまで度重なる空襲が始まり、砲弾が打ち込まれ続けるという地獄の様相を呈することになる。そのためドイツの将兵の士気は明らかに低いことだろうと思いきや、一概にそうとは言えないようだ。ヒトラーを盲信する多数の将兵達は、彼に忠誠を誓ったという理由から、そして第一次世界大戦で敗北した屈辱から、降伏など頭に無いのは驚いた。また、逆に状況を冷静に認識している人々もいた。ドイツ国内でも、現状の認識は様々だったことが窺える。このように、ベルリンの惨状や当時の人々の様子を描いた点で、今作は貴重な映画だと思う。
戦争の現実、厳しさ、辛さを知る作品
CSで録画視聴。
色々、考えさせられた作品。戦争の現実、厳しさ、辛さを知る事ができる作品。
もし、自分がこの場にいたらどうするかを考えて観た。
ただ、時間は作品の性格上、仕方なしにしても長すぎる印象が強い。
悪人をただ在るとしない。
ヒトラーが自決するまでの最後の12日間を描いた作品。
ナチスドイツの中枢で働く人々が戦況の劣勢によって焦燥や盲信、未来への展望が絶望によって染まっていく様子が見て取れる。
ナチスドイツは非道な行いをしたが、「ただ悪として存在した」としてはいけないと私は思う。
独裁者。
差別主義者。
優生思想。
戦勝国が作り上げた「正しさ」によって単純化してしまうことに危機感を覚える。
彼らも同じ血の通った人間であり、大切なもののために考え決断をした人々。
そして、それを支持した人々もいる。
彼らの決断を現代を安穏と生きる私が現代の価値観で論じることにはとても抵抗を覚える。
敗軍の幹部の妻子がどのように扱われるのか。
自分の命一つの覚悟ならできる。
しかし、愛する人の苦渋に満ちた人生を憂えばこそ。
そして薬を飲ませ、食卓で手榴弾のピンを抜く。
ナチスドイツを、ヒトラーを悪と断じて単純化しがちだが、同じ血の通った人間であることを思い出させてくれた。
リアルなヒトラー。
戦争の現実をリアルタイムでみることになるとは
【”時は来た、終わりだ・・”忌むべきナチスドイツを率いた男の狂気の最期を演じた故、ブルーノ・ガンツの姿と、ヒトラーの個人秘書ユンゲの回想シーンが忘れ難き作品。】
ー 1945年4月20日、ベルリン。
第二次大戦は佳境を迎え、迫りくるソ連軍の砲火を避けるためヒトラーは身内や側近とともに首相官邸の地下要塞に潜っていた。
誰もが敗戦を覚悟する中、冷静さを失い狂人と化していたヒトラーは、ある重大な決断を下す。
◆感想
・ナチスドイツの蛮行を描いた作品は、数多ある。
だが、今作はナチスドイツの崩壊の瞬間を”ドイツ人監督”である、オリヴァー・ヒルシュビーゲルがメガホンを取った事に大きな意義があると思う。
・自分に忠誠を誓っていた、ヒムラー、ゲーリングが敗戦を悟り、自らの元を去っていく中、ヒトラーが下した決断。
それは、連合国に降伏する前に自らの命を断て、と渡した毒薬である。
- ”責任を感じて、死ぬのであれば、自分一人で命を断てよ!”
だが、ヒトラーは愛人であり、直前に妻となったエヴァと自殺する。-
・物凄く嫌いなシーンは、ヒトラーのプロパガンダ政策を牽引したゲッペルスの妻が、6人の子供たちを眠り薬を飲ませた後に服毒させるシーンである。
- 子供に、罪は無い。何故に嫌がる長女に薬を飲ませたのか・・。-
<後年、「ゲッペルスと私」を見た際にも思ったのであるが、ゲルマン民族と大和民族は似ている部分が多いと思う。
それは、知的に優れながらも、プロパガンダにたやすく翻弄される所と、自らの民族性を神聖化し、他民族に対する残虐性を持つ所である。
再後半に、ヒトラーの最期の秘書になったトラウドゥル・ユンゲ自身の、「若いころの自分を諫めたい。」という言葉が重く響く作品であり、この作品をドイツが中心になって制作した事に意義があると思う作品でもある。>
「アンネの日記」とか。「戦場のピアニスト」とか「素晴らしきかな人生...
ただただ、圧倒されました。
帝国の末路
異常が健常になっていく瞬間
全53件中、1~20件目を表示