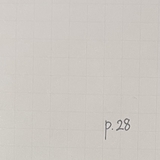ライフ・イズ・ビューティフルのレビュー・感想・評価
全212件中、21~40件目を表示
アレッツォに行ってしまいました
20数年前、公開当時に本作品を観て感銘を受けてロケ地のイタリア、アレッツォに行ってしまいました。
3人で自転車に乗るシーンがとても素敵で忘れられません。
これは壮大なるラブストーリー&反戦映画です。
グイドの様な男になれたらいいなと思って今日まで生きて来ました。
またスクリーンで観れた事に感謝。
わかっているラストシーンでまた涙してしまいました。
人の親として
楽天的なイタリアの雰囲気の中で進行する物語、しかし当初からファシスト的敬礼や黒シャツ隊など時代の不穏なアイテムが登場します。陽気な雰囲気のまま結婚、子供の誕生と進みますが気づけば周りはドイツ軍だらけ、主人公たちも強制収容所へ連行。ここで物語の核心となる嘘を主人公は子供につき続けるわけですが、個人的には実際のドイツ軍はここまで甘くはないだろうと思わせるシーンが多く、ちょっと作品に入り込めませんでした。
しかし、引き続き子供にうそをつくシーンで、「人を薪のように焼くなんてことはありえないだろう?」というセリフは現実に対する強烈な皮肉に聞こえました。最後まで子供に悲しい思いはさせまいとする姿は、人の親ならばそうだろうと納得です。
父親の姿に貫かれる
笑いのなかに涙が入り混じり、戦争の悲惨さも見事に描いた喜劇映画としては珠玉の名作ですね。
『ダウン・バイ・ロー』(1986)、『ナイト・オン・ザ・プラネット』(1991)などジム・ジャームッシュ監督作の常連ロベルト・ベニーニが監督・脚本・主演を務め、第51回カンヌ国際映画祭で審査員グランプリ、第71回アカデミー賞で主演、作曲、外国語映画賞を受賞した珠玉の名作『ライフ・イズ・ビューティフル』(1997)が2週間限定のリバイバル上映。
『ライフ・イズ・ビューティフル』(1997年/117分)
第二次世界大戦前夜、1937年のイタリア。
ユダヤ系イタリア人のグイド(演:ロベルト・ベニーニ)は美しい小学校教師ドーラに一目惚れし、得意のユーモアと当意即妙な猛烈アプローチで、彼女と駆け落ち同然でようやく結婚、愛息ジョズエを授かり幸せな日々を過ごす。
ジョズエに物心が付いた頃、ユダヤ人迫害の嵐がイタリアにも吹き荒れ、叔父、グイド、ジョズエ、そして彼らの後を追ったドーラも強制収容所に連行させる。
ジョズエを怖がらせまいと、グイドは得意の機転を利かせて、「これは戦車の賞品がもらえるゲーム」だと優しい嘘をつく…。
作品はドーラを結ばれるまでの前半パートと、過酷な収容所生活の後半パートに2部構成。
前半はとにかくグイドの陽気で破天荒なドタバタコメディをチャップリン映画のようにこれでもかとくどいほど徹底的に強調。
逆に前半の圧倒的な明るさが、後半の陰鬱な収容所とのより強い対比、濃淡を生み出し、本作をより印象深くさせています。数々の伏線回収も見事です。
最後まで家族を守るため、愛息の前では陽気に振る舞い、嘘を突きとおし、死期が迫る直前まで気丈に陽気に振る舞うグイドの姿は涙なしでは見られません。
笑いのなかに涙が入り混じり、戦争の悲惨さも見事に描いた喜劇映画としては珠玉の名作ですね。
イタリアと日本の共通項ーー戦争の悲劇性を伝える寓話
1998年公開のこの映画、観たことがあるような気がしていたのだけれど、今回観てみて間違いなく初見だった。
公開当時、評判になったし、その後も配信や再映などでよく目にした名画だから、どうやら観た気になってしまったらしい。
以下は映画のレビューというより、私自身の鑑賞体験とそこから考えたことのメモになってしまいそうだが書いてみたい。
監督・主演のロベルト・ベニーニはコメディアンでもあり、序盤からマシンガントークで喋りまくる。雰囲気は面白げなのだが、今一つ笑えない。
予告編などでこの雰囲気を見て、苦手なタイプのコメディだと敬遠していたのが、未見の理由だったのかもしれない。イタリアだとこの前半、爆笑となるのだろうか。
しかし、この多幸感あふれるコメディ的世界も、後半のイタリアにおけるユダヤ人迫害(ホロコーストの一部として位置づけられるのだろう)に移ると、失われた過去の幸せな記憶へと意味を変えることになる。
妻と子どもと共に収容された主人公は、ここで息子と妻に希望の物語を語る人物になる。別々に収容された妻には、収容所の放送マイクの隙を見てメッセージを伝え、またレコードで思い出の曲を大音響で流す。そして幼い息子には「これは壮大なゲームなんだ」という虚構の物語を語り続け、それを信じ通させる。
この物語は創作だそうだが、同時期に実際に収容所に入れられていた心理学者フランクルを思い出す。
彼は収容所で「希望を持つ人は生き延び、希望を失う人は死んでいく」ことを観察し、人生の意味を問うロゴセラピーを完成させた。『夜と霧』はその体験記録であり古典的名著だ。私自身もこの本の視点に何度も救われたと思っている。
この映画の主人公はまさにロゴセラピーの実践者のように、妻と息子に「意味ある生の物語」を伝え続け、同時にその献身的な態度によって自らの生に強い意味を与えていた。
この映画は公開当時、ホロコースト描写が軽すぎるなど賛否両論だったという。確かに寓話的な世界観で、ホロコーストは悪夢の中の壁画のような表現でマイルドに描かれる。
ここでリアルを徹底すれば、同じイタリア人の中に加害者と被害者を描かざるを得なくなり、それを避けたかったのかもしれないと感じた。
そして考えてしまうのは、日本との比較だ。日本もまた敗戦国として、戦争の物語を主に「悲劇の物語(原爆や大空襲、特攻)」として語ってきた。
戦争全体を見れば加害も被害も入り混じるのに、それでは意味ある物語になりにくい。勝者は偉大な達成の物語を語れるが、敗者はそうはいかない。だからこそ、戦後80年を経た今も日本もイタリアも「悲劇の物語」として戦争を語り続けるのではないか。
そして他国から加害責任を問われるたびに、さらに悲劇の物語で自らを支えざるを得なくなる。悲観的で皮肉な見方かもしれないが、戦後生まれとして当事者でないという思いが僕の中にあるからか、そんな風に感じられた。
とても美しく、悲劇的で、だからこそ強い印象を残す映画だった。寓話としての力と、歴史的現実の複雑さ、その両方を考えさせられる鑑賞体験となった。
僕らがチャンピオンだ!
こないだ鑑賞してきました🎬
これは確かに名作ですね😀
主役のグイドにはロベルト・ベニーニ🙂
本当に陽気な男で、大変な目に遭う後半でもそれは崩さない。
妻のドーラと息子ジョズエへの愛は本物で、特にジョズエには優しい嘘をつき続ける。
困難に遭っても信念を失わない男を、ベニーニは体現していました。
ドーラにはニコレッタ・ブラスキ🙂
グイドの陽気さに徐々に惹かれ、ついには駆け落ちに近い形で結婚。
ジョズエも生まれますが、2人が強制収容所行きの汽車に乗せられる事態に😔
このときの彼女の行動は、本物の勇気なくしては出来ないでしょう。
この場面のブラスキの演技は、一見の価値ありです👍
ホロコーストを扱っているので、後半は重たいシーンが続きます。
かといって暗さに振り切れることなく、軽く扱いすぎてもいない、絶妙なバランスは見事でした。
グイドは破茶滅茶な部分もありますが、とにかくユーモアを忘れない男で、なんだかんだ許せてしまう。
ベニーニの演技力があってこそでしょうか🤔
ヒューマンドラマの傑作として、映画ファンなら抑えておきたい一本です🫡
【90.1】ライフ・イズ・ビューティフル 映画レビュー
ロベルト・ベニーニ監督の『ライフ・イズ・ビューティフル』(1997) は、ホロコーストという悲劇を扱いながらも、ユーモアと愛に満ちた独自の視点で描いた異色の傑作。単なる悲劇の物語に留まらず、人間の尊厳と愛の力を讃える普遍的なテーマを提示した点に、この作品の真価がある。批評家として、その多角的な側面を深く掘り下げる。
作品の完成度
本作の完成度は、単なる技術的な巧みさだけでなく、そのテーマ性とメッセージの深さにおいて極めて高い。前半のロマンティック・コメディと、後半のホロコーストという対照的な要素を見事に融合させ、観客を笑いから涙へと自然に導く構成は、ベニーニの卓越した才能の賜物。この構成は、単に物語を二部に分けるのではなく、前半で描かれるグイドの楽天的な性格と家族への深い愛が、後半の絶望的な状況下での行動原理となることで、物語全体に一貫した説得力をもたらしている。
グイドが息子ジョズエを守るために作り出した「ゲーム」という嘘は、単なるごまかしではなく、父親の無償の愛が生み出した究極のファンタジー。このファンタジーは、収容所の現実を覆い隠す一方で、恐怖に打ちひしがれることなく、希望を失わないようにするための唯一の手段であり、観客に深い感動を与える。このような独特なアプローチは、ホロコースト映画の新たな地平を切り拓いたと言える。
しかし、その完成度の高さゆえに、一部で「悲劇の美化」という批判も招いた。だが、それは表面的な解釈に過ぎない。この映画は悲劇を美化しているのではなく、悲劇的な状況下でなお、人間が持ちうる美しさ、愛の力、そして希望を強調している。ベニーニ自身が「これは私の人生哲学の反映である」と語るように、絶望の淵でも光を見出す人間の強さを描くことで、観客に生きる勇気を与える。これは、芸術が持つべき最も重要な役割の一つであり、その点において本作は紛れもなく完成された芸術作品と言えよう。
監督・演出・編集
監督を務めたロベルト・ベニーニは、本作で自身の才能を余すところなく発揮。コメディアンとしての経験を活かした軽妙な演出は、物語の前半にロマンティックな魅力を加え、後半の悲劇とのコントラストを際立たせる効果を生んでいる。特に、グイドが息子に語りかける「ゲーム」のルール説明や、収容所内でのユーモラスな行動は、ベニーニの独特な間合いと演技指導の賜物。
編集もまた、この緩急のついた演出を支えている。前半の軽快なテンポから、後半の重厚な描写へとシームレスに移行し、観客の感情を巧みにコントロール。例えば、収容所での悲惨な出来事を直接的に描写するのではなく、グイドの視点を通して間接的に見せることで、物語のトーンを保ちつつも、その恐怖を強く感じさせることに成功。これは、観客に想像の余地を与えることで、より深い感情移入を促す優れた編集テクニックと言える。
キャスティング・役者の演技
ロベルト・ベニーニ(グイド・オレフィチェ)
監督、脚本、そして主演という多岐にわたる役割を担い、この作品の魂そのもの。グイドという楽天家で愛に溢れたキャラクターを、自身の個性と見事に一体化させ、比類なき魅力を放っている。前半のチャーミングな求愛から、後半の絶望的な状況下での献身的な愛情表現まで、演技の幅は驚くほど広い。特に、息子を守るために必死にユーモアを保とうとする姿は、観客の心を深く揺さぶる。彼の表情一つ、仕草一つに、父親としての深い愛と悲しみがにじみ出ており、言葉を超えた感動を与える。アカデミー賞主演男優賞を受賞したことは、彼の演技がいかに高く評価されたかを物語っている。この役は彼以外には演じられない、まさに「ハマり役」と言える。
ニコレッタ・ブラスキ(ドーラ)
ロベルト・ベニーニの実生活での妻でもあるニコレッタ・ブラスキは、グイドが恋焦がれる女性ドーラを演じ、気品と強さを兼ね備えた魅力を発揮。前半では、グイドの突飛な求愛に戸惑いながらも、次第に心惹かれていく様子を繊細に演じ、物語のロマンティックな雰囲気を高める。後半、グイドと息子を追って自ら収容所に入る決断をする場面は、彼女の強い意志と家族への深い愛を象徴しており、観客に強い印象を残す。ドーラは単なる「守られる存在」ではなく、自ら行動する自立した女性として描かれ、物語に深みを与えている。
ジョルジオ・カンタリーニ(ジョズエ・オレフィチェ)
主人公グイドの息子ジョズエを演じたジョルジオ・カンタリーニは、無邪気で愛らしい演技で物語に温かさをもたらす。父親の「ゲーム」を信じ、時に疑問を抱きながらも、その言葉に従う姿は、観客の共感を呼ぶ。特に、収容所で父親のユーモアに満ちた行動に驚きながらも、純粋に楽しむ姿は、物語の悲劇性をより一層際立たせる効果を生んでいる。彼の存在は、グイドの行動原理の説得力を高めるとともに、観客に希望の象徴として映る。
ホルスト・ブッフホルツ(レッシング医師)
レッシング医師を演じたホルスト・ブッフホルツは、ドイツ人医師であり、グイドが収容所で再会する人物。グイドとの再会を喜び、彼に便宜を図るかに見えたが、最終的にはナチスという体制の中で無力な傍観者に過ぎなかった。ブッフホルツは、この複雑なキャラクターを抑えた演技で見事に表現。善意を持っていながらも、行動に移せない人間の弱さや、ホロコーストという状況下でのモラルの崩壊を静かに描き出す。彼の存在は、グイドのユーモアが通用しない現実の厳しさを象徴する。
マリット・アンスティーン(先生)
マリット・アンスティーンは、グイドの家族の友人であり、ホロコースト収容所でグイドと再会する先生役を演じている。彼女の演技は、グイドのユーモアとは対照的に、収容所の現実を体現する存在として、物語に重厚感を与える。彼女の悲壮な表情や言葉は、グイドが息子に語る「ゲーム」がいかに切ない嘘であるかを観客に再認識させる。
脚本・ストーリー
ロベルト・ベニーニとヴィンチェンツォ・チェラミによる脚本は、独創性と普遍性を両立させた傑作。前半の軽妙で詩的なセリフ回しは、ベニーニの個性と見事に調和し、後半の悲劇を際立たせるための巧みな仕掛けとなっている。ストーリーは、グイドが愛する女性と結婚し、息子をもうけ、そして収容所に送られるというシンプルなものだが、その中に「愛」と「希望」という普遍的なテーマを深く織り込んでいる。
特に、グイドが息子に語る「ゲーム」という設定は、ホロコーストという重いテーマを扱う上で、観客が感情移入しやすい独自のフィルターを作り出している。この設定は、単なるフィクションではなく、父親の無償の愛が生み出した、究極のサバイバル術であり、物語全体に感動的な説得力をもたらしている。
映像・美術衣装
ダニーロ・ドナティによる美術と衣装は、物語の二つのパートで明確な対比を表現。前半のイタリアの街並みや華やかな衣装は、ロマンティックなムードを演出し、希望に満ちたグイドの人生を象徴する。後半の収容所では、くすんだ色彩と簡素な衣装が、絶望的な現実をリアルに描き出し、その対比が物語の悲劇性を高めている。
特に、グイドが息子を背負い、笑顔で敬礼するラストシーンは、映像的な美しさと悲劇性が同居する、この映画を象徴する場面。この対比が、観客に強い印象を残す。
音楽
ニコラ・ピオヴァーニが手掛けた音楽は、作品の感情的な側面を巧みに補完。前半では軽快でロマンティックなメロディが、グイドの陽気なキャラクターと物語の雰囲気を盛り上げる。後半では、物悲しい旋律が、収容所の悲惨さとグイドの献身的な愛情を静かに描き出し、観客の涙を誘う。
特に、メインテーマである「La vita è bella」は、映画全体を通して繰り返し使われ、物語の核心である「人生は美しい」というメッセージを聴覚的に伝える役割を果たしている。アカデミー賞作曲賞を受賞したこの楽曲は、映画の感動を何倍にも増幅させる力を持っている。主題歌は「La vita è bella」であり、アーティストはニコラ・ピオヴァーニ。
受賞・ノミネート
『ライフ・イズ・ビューティフル』は、その完成度の高さから世界的に高い評価を獲得。
* 第71回アカデミー賞:作品賞、監督賞、主演男優賞(ロベルト・ベニーニ)、脚本賞、編集賞、外国語映画賞、作曲賞の7部門にノミネート。このうち、主演男優賞、外国語映画賞、作曲賞の3部門を受賞。
* カンヌ国際映画祭:審査員特別大賞を受賞。
* 第22回日本アカデミー賞:優秀外国作品賞を受賞。
これらの受賞歴は、本作が単なる感動ドラマに留まらず、芸術的にも高い評価を受けたことを証明。
作品 La vita e bella
監督 ロベルト・ベニーニ 126×0.715 90.1
編集 退屈-1 非常に退屈-2
主演 ロベルト・ベニーニA9×3
助演 ニコレッタ・ブラスキ A9
脚本・ストーリー ロベルト・ベニーニ
ビンセンツォ・セラミ
A9×7
撮影・映像 トニーノ・デリ・コリ A9
美術・衣装 美術
ダニロ・ドナティ A9
音楽 ニコラ・ピオバーニ A9
リバイバル上映にて鑑賞
25-105
きつい
ホロコースト系の作品やっぱりきつい。。
あんなに幸せで愛に満ちた家族を奪わないでくれ。。。。全員の無事をひたすら祈らながら観ていました。
収容所で命が危険に晒され、ボロボロになるまで強制労働を強いられている中で、グイドは息子と妻を1番に想った行動をしていて本当に強かった。。ボロボロ泣いてしまいました。
過酷な環境でも笑顔を絶やさず、家族を勇気づけて最後まで守り抜いたグイドは本当に愛に溢れた優しい人物でした。
収容所では、そのような個々の人物像や背景なんて剥ぎ取られて、「囚人」として均一に踏み潰しており、きつい。
信じたくなく、目を背けたくなる事実でしたが、しっかりと向き合わねばいけないことだと思いました。
音楽も素晴らし
思い出補正が入っているので評価は高くなってしまいます。仕方ないのです。
多くの映画賞で高評価な有名なイタリア映画。
コメディ感が強く、ホロコーストを和らげることで、ユーモアを成立させている微妙なさじ加減が絶妙だった。
ロベルト・ベニーニが奥様のニコレッタ・ブラスキとまたもや共演し、子役のカンタリーニは撮影に入る前に実際に2人と共に寝起きをともにしてたらしい。
史実を正しく描くのではなくて、歴史の中に美しい親子の物語を作っている。
この映画『ライフ・イズ・ビューティフル』(1997)について、ホロコーストについて「歴史的現実を過度に美化している」として、ユダヤ系団体や一部の批評家からは本作における表現手法の倫理性やバランスに疑問を呈する声もあがったらしいが、そんな声が上がるのは毎度の事で仕方がない。
『シンドラーのリスト』(1993)だって『SHOAH ショア』(1985)の監督クロード・ランズマンから「出来事を伝説化するものである」として舌鋒鋭く批判されたりしてるし。妻のエミリー・シンドラーは実際にはオスカーの活動を支え、ユダヤ人保護に貢献した重要な人物なのに映画ではあまり目立たない存在だ。
『サウルの息子』(2015)はリアルらしいが、今作品の様に "笑って泣ける" 作品では無くて全くの別物だし。
『関心領域』や『アウシュヴィッツ・レポート』、『アウシュヴィッツの生還者』、『アウシュヴィッツのチャンピオン』、『ホロコーストの罪人』、『縞模様のパジャマの少年』等あるが、全く別物のコメディ映画として楽しむべし。
なのに泣ける。
グイドのような人になりたい。笑って泣ける最高の観ておきたい映画のひとつ
人生は美しい‼️
戦争のむごさ、ユダヤ人迫害、強制収容所という過酷な状況の中で、家族を愛し、守り続けた男の姿を、上質な笑と涙で描いた「ライフ・イズ・ビューティフル」‼️しかもタイトルの "ビューティフル" に恥じない、人生の素晴らしさ、人間の命の美しさまで描いてるんですから、感動しないわけがない‼️アカデミー賞で主演男優賞獲った時のハジけっぷりが印象的なロベルト・ベニーニはホント巧いですね‼️でもそれ以上にベニーニの子供を演じたジョルジオ坊やの愛らしい笑顔‼️癒される〜ッ‼️
子供のことを1番わかっているのは父
泣きたい時にこの映画を必ずみます、子供にこれはゲームだよ、ポイントを集めるんだ!買ったら戦車がもらえるよ!と父が優しい嘘をつき子供を辛い中も楽しませている、ほんとに素晴らしい父です、そんなお父さんが銃で打たれて死んでしまうシーンはほんとに涙が止まらなかったです、子供はお父さんを待っているのに、まださよならも言ってないのに、元気な姿のママ死んでしまう父、辛すぎて涙が止まりません、最後のアメリカ兵のシーンで嗚咽が出るほど泣きました、人生で1番泣いた映画はこの映画です。
一生忘れられない
グイドの人間性に心打たれました。
彼によって幸せになった人間はこの映画に映されてない場面でも沢山いるのかなぁとか想像してみたり。
息子の元へ戦車が来たときの健気な息子とグイドの対比がでもう駄目でした。
ラストは本当に涙が止まりませんでしたが、一生忘れることの出来ない作品です。
全212件中、21~40件目を表示