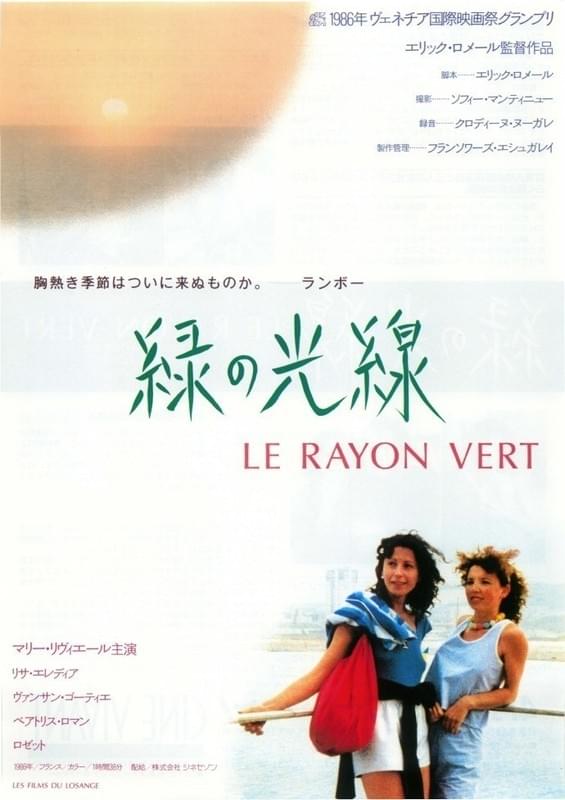緑の光線
劇場公開日:1987年4月25日
解説・あらすじ
エリック・ロメール監督による「喜劇と格言劇」シリーズの第5作。愛と幸せを求めてバカンスに出かけた孤独な女の旅を、生き生きとした会話と美しい映像で描き、ベネチア国際映画祭で金獅子賞に輝いた。秘書として働くデルフィーヌはギリシャでのバカンスを楽しみにしていたが、一緒に行くはずだった女友だちにドタキャンされてしまう。友人に誘われて南仏へ出かけたものの、周囲になじむことができずひとりでパリへ戻る。その後、ひとりでビアリッツの海を訪れたデルフィーヌは、ジュール・ベルヌの小説に書かれた、日没前に一瞬だけ見えるという「緑の光線」の話を耳にする。主演は「飛行士の妻」「恋の秋」のマリー・リビエール。
1985年製作/94分/フランス
原題または英題:Le rayon vert
配給:シネセゾン
劇場公開日:1987年4月25日
スタッフ・キャスト
- 監督
- エリック・ロメール
- 製作
- マルガレート・メネゴス
- 脚本
- エリック・ロメール
- マリー・リビエール
- 撮影
- ソフィー・マンティニュー
- 編集
- マリア・ルイサ・ガルシア
- 音楽
- ジャン=ルイ・バレロ
受賞歴
第43回 ベネチア国際映画祭(1986年)
受賞
| 金獅子賞 | エリック・ロメール |
|---|

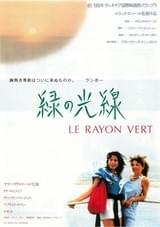

 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に
この世界の片隅に セッション
セッション ダンケルク
ダンケルク バケモノの子
バケモノの子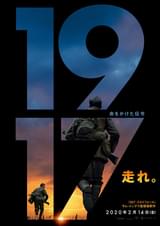 1917 命をかけた伝令
1917 命をかけた伝令