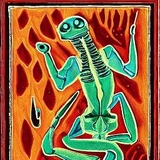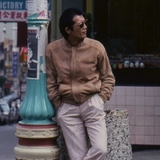フットルースのレビュー・感想・評価
全37件中、1~20件目を表示
意外と平和的な映画
アメリカ映画伝統の
田舎に行った主人公が
いろいろひどい目に遭う映画だが
本作は最後に大逆襲の快作
最初の方はバイオレンスでアナーキーな描写多かったので
主人公が尾崎豊的な反逆精神で
大人たちをギャフンと言わせる話と思っていたら
意外と理詰めで説得して平和的に解決してたのに驚いた
それにしても本作
まだネットが普及してない時代だから成立した話
今じゃここまで閉鎖的な街にするのは難しいだろうな
いやそれでもまだ閉鎖的な街はあるらしいけど
興味深いのは
何故か本作の劇中歌が
日本のドラマや音楽に大きな影響与えたこと
「Holding Out for a Hero」
麻倉未稀さんがカバーしてドラマ「スクールウォーズ」の主題歌に
「Never」
MIEさんがカバーしてドラマ「不良少女とよばれて」の主題歌に
「I'm Free」
渡辺美里さんがカバーしてドラマ「スーパーポリス」の主題歌に
ちなみにデビュー曲でもある
最後に主人公の親友役のクリス・ペンさんが
既に故人なのに驚いた
合掌
追記
参考までに
田舎に行った主人公が
いろいろひどい目に遭うアメリカ映画の見本をいくつか
「イージーライダー」
旅行中のヒッピーが田舎で排他的な扱いを散々受けた挙句
通りすがりのトラックの運転手に撃ち殺される
「悪魔のいけにえ」
旅行中の若者グループが
田舎の食人一家に惨殺される
「ランボー」
ベトナム帰還兵が田舎の戦友に会いに行った帰りに
田舎の警察に不当に逮捕されて虐待され
キレて町相手に戦争することに
この他B級のSFやホラーやアクションは
田舎で撮影されることが多いので
必然的にそういう話になりやすい
映画は時代を表す
前半の2〜30分はB級の青春ドラマのようだ。
能天気な転校生、同じく能天気な在校生、特に牧師に娘の行動は常軌を逸していた。
チャラい前半を通り抜けると、それぞれの家庭の問題点が浮かび上がって来る。個々の問題点は大きく深い傷と言える。それでもハツラツとした高校生活を送る彼らと父兄たち。終盤に向かい皆、一皮剥けた人間になっていた。
中盤から終盤にかけての人間、これが前半から有れば、もっと心打つ物語になっていたのでは、と思ってしまう。
軽薄な部分は、青春や若さで納得してしまって良いのか。映画は時代を表す。1984年はMTV全盛の時代、ある意味これで良いのだと思うのが普通か。
音楽や若い情熱の魔法や
魅力的では無い登場人物
それも要因だったのか。
※
未知の事柄を理解しようとしない姿勢に問題があると思う
青春映画の良作。テーマ曲や途中で挿入される音楽も魅力的だった。
町で起こった交通事故の原因を、公序良俗の乱れにあるとしてダンス禁止令が出されるが、事故の対策として全く本質的ではない。作中に描かれているように、若者達のダンスを禁止したところで結局大人の目につかないようにやるだけで、意味が無いだろう。この町の大人達は、単に自分達にとって未知の若者文化が気に食わないだけで、交通事故にかこつけてダンス禁止令を出しているに過ぎない。未知の事柄を理解不能なものとして頭から撥ねつけている凝り固まった思考に、最大の問題があるのだろう。その点、牧師は若者達の反発や妻の説得を受けて、徐々に理解を示すようになったのが良かった。
よそ行きの靴は脱ぎ捨てよう‼️
この作品も私にとって思い出の80年代サントラムービーの一本‼️映画以上に音楽、サントラの印象が強い作品‼️「フラッシュダンス」「ロッキー4」「トップガン」「ダーティダンシング」もそうなんですが‼️ロックもダンスも禁じられた保守的な田舎町へやってきた青年が、仲間達とともに町外れの工場を借り切ってダンスパーティーを計画、音楽を通じて若者の自由の権利を勝ち取る物語‼️軽快なオープニングから、思わず踊りだしたくなるような素晴らしき楽曲たち‼️ケニー・ロギンスの同名主題歌はもちろんなんですが、私は特にアン・ウィルソン&マイク・レノの「パラダイス〜愛のテーマ」、そしてこれまた80年代の日本の名作大映ドラマ「スクールウォーズ」主題歌の元ネタとしてが有名かもしれないボニー・タイラーの「ヒーロー」‼️この二曲が特に好きでした‼️物語としても有名な "ダンス・バトル" など、この作品がなければマーベルの「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」はなかったかも‼️
ザ・80年代
牧師さんの成長映画
演説で激高するほど、保守的で頑固だったお父さん(牧師さん)が、娘の影響も大きかったけれど、自分を変えて、ダンスパーティという自分に無かった価値観を受け入れるとは、素晴らしい成長だったと思います。あ、ケビン・ベーコンさんの映画でしたね(笑)。
思ったより真面目な青春映画
今や「世界中のどんな俳優でも共演者を最大6人たどればケヴィン・ベーコンに行き着く」と言われるケヴィン・ベーコンの出世作、気になっていたが、たまたまBSプレミアムで鑑賞できた。
若者たちが、身勝手にやりたいことをやるのではなく、真正面から議会で訴えるところが良かった。思い返すと、その一方で、図書館の本を有害図書だと決めつけて勝ってに燃やす大人が描かれていたが、面白い対比。そういう極端な人たちや、面白くないからと暴力を振るったり石を投げ込んで嫌がらせする不良高校生もいて、社会においてはそういう厄介な者が必ずいるものだとあらためて思った。
ダンスは、聖書にも記述があり、祝うために神様から許された行為だという説明は決定的で小気味良かった。レンの相棒のウィラードが、レンにダンスの特訓を受けて上手くなっていくところが面白く、微笑ましかった。調べると、ウィラードを演じたクリス・ペンは、ショーン・ペンの弟で2006年に41歳で亡くなっていたとは…。
音楽に乗せて展開していき、くどくなくテンポの良い、非常に真面目な青春映画だった。
踊れ、衝動に任せて
抑圧からの解放、社会への反抗、子の自立。
めっちゃ良い青春映画だった!
若者達の抵抗も良いが、それを見守る大人達の変化も見所。
それとOPから最高だし、作中の挿入歌も熱い!
若かかりしケビン・ベーコンの情熱ほとばしるダンスをはじめ、作中のダンスシーンが体が自然と動き出すくらい楽しい気分になる。
唯一の不満を挙げるなら
最後の最後、決めポーズで締めて欲しかったな。それとエンドロールにダンスの続きはなくても良かった。続けるならエンドロール中盤くらいまでやって欲しかったな。
けっこう序盤から思ってたことだが、自分の意思を貫く為に神やら愛やら絆みたいな目に見えない、測りようのない、耳ざわりの良いものを使うなよ。
子供だってバカじゃねーぞ?
若者は青春を思い切り楽しんだらいい!
保守的な田舎町で、 大人たちが押し付けてくる つまらない日常にダン...
【”抑圧からの解放”閉鎖的思考に捕らわれた大人達に対し、論理的にダンス禁止令廃止動議をするケヴィン・ベーコン扮する青年と、苦悩しつつもそれを認める牧師の姿も佳い。鑑賞後の爽快感が快い青春映画である。】
ー シカゴから田舎町に引っ越して来たレン(今作で、スターになったケヴィン・ベーコン)は、閉鎖的な街の雰囲気に驚く。
ダンス禁止令が出ているし、ロックンロールも禁止されており、同級生は、”ポリス”すら知らない・・。
◆感想
・今作は「フラッシュダンス」と同じパターンかなあ、と思って鑑賞したら大きく違っていた。
・レンの自由な思想に惹かれていくエリエルの厳格な父であり、町の人々の信頼熱い牧師を演じるジョン・ゴスリーと、エリエルの母を演じたダイアン・ウィーストが良い。
ダンス禁止令を”ある事件”に依り、提案した牧師。
レンに惹かれるエリエルに”初めて”手を上げてしまった夫に対し、ダイアン・ウィースト演じる妻が、あの優しい微笑みを浮かべて
”貴方は、皆の尊敬を受けているけれど、一対一では弱い人・・。”
”町中の父親になるつもり?”と諭すシーン。
- 今作では、キチンと人間が描かれている。-
・町内会で、レンがダンス禁止令を廃止する動議を出すシーンも良い。
彼は、聖書を片手に持ち、
”昔から、人は狩猟や祝いの場では躍った。聖書にも載っているよ・・。主を称えるために、飛び跳ねて踊ろう”と牧師を始め町の長老たちに語り掛けるシーン。
- ここで、レンが語った言葉は聖書に本当に記載されている。彼の知性を示しているシーンなのである。-
<抑圧された田舎町の古き慣習を、都会から来た知性的な青年が暴力を使わずに、打ち破って行く。町の牧師も悩みながらも、それを受け入れていく・・。
今作は、人間がキチンと描かれた青春映画である。>
ケビン・ベーコンがイケメン役ってだけで笑えてくる
自分の中でケビン・ベーコンとマット・デイモンとニコラス・ケイジはハリウッド業界の三大変な顔俳優なんですが、この映画ではケビン・ベーコンがイケメンでカッコいい転校生となっています。それだけで笑えますわw
この映画のサウンドトラックは日本のオリコン洋楽アルバムチャートで1984年5月7日付から通算18週1位を獲得したと書いてあります。そんなに凄い音楽がかかっていたとは思わないのですがw
この時代の10代のストレス発散はカセットテープに入れたロックをラジカセで聴いて踊ることだったようです。
悪ぶってるのに大学に行こうとしてる女とか、トラクターでチキンレースやってる不良とか、おもろいわw
良い時代ですねw
1980年代のアメリカの10代や文化を感じたい人向けです。
耳馴染みのある軽快な曲からのオープニング映像、早くもこれだけて楽し...
全37件中、1~20件目を表示