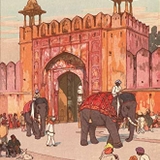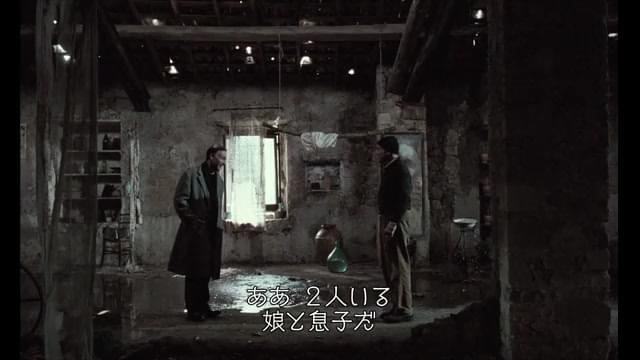ノスタルジア(1983)のレビュー・感想・評価
全51件中、1~20件目を表示
記憶の奥にある赤いノスタルジア。
思い出話で申し訳ないが、この映画は30年くらい前、友だちの四畳半のアパートで友だちが持っていた擦り切れそうなVHSテープで観た。ほとんど何が映ってるか判別できず、タルコフスキーの映画なんでストーリーを追うことも至難の業だったが、奇跡にまつわる哲学的なファンタジーと捉えてやけに感動した。ノイズだらけの画面はすっかり赤っぽく変色しているが、それもまた、霞がかっった神話的な映像美を思わせて、心に焼き付いた。
で、30年を経て、4K修復版を鑑賞することができて、まあ驚いたのなんの、あまりにも鮮明になった画面はまったく赤っぽくないし、ストーリーが明確になった以外、ほとんど別物のように見えた。自分の中での神秘性は減ってしまったが、それでもやはり名作であり、さりとて自分の中ではもっと素晴らしい名作としてあの赤っぽいVHSが残っている。そんな経験も含めて映画だと思うし、誰もが心に自分バージョンを持っていていいのではないかと思う。
タルコフスキーのこと
『ノスタルジア』が日本公開されたのは1984年の春、初鑑賞から40年の時が過ぎた。再上映や特集などで何度か観ているがその回数は定かではない。母国を離れてイタリアを旅する詩人の“郷愁”をテーマにした『ノスタルジア』は、2020年公開の『サクリファイス』と共に、我が心に深く刻まれた作品だ。今回、イタリアのライシネマに保管されていたオリジナルネガと音声を基にフィルム鮮度のクオリティにレストアされた4K版を観ることができたのは至上の喜びだ。
この作品には、一切の無駄を許さない純度の高い脚本があり、フレームに対する徹底したこだわりがあり、モノクロとカラーを使った精緻で繊細な感情表現がある。絞りによって色彩を浮き上がらせる撮影の妙、主人公の脳裏をよぎる心象風景は、完璧な配置による故郷の理想的なイメージとなって画面に映し出され、主人公の想いの深さを伝える。美術、情景、小道具、人々の動き、言葉のひとつひとつにまで、作家の強い意志が貫通している。
1 + 1 = 1
水滴になぞらえた自然に対峙する姿勢と思想の原理にも大きな影響を受けた。この呈示には、映画は、決して足し算では成立しないという、タルコフスキーの創作に対する原点が宿る。彼の講演を綴った「映像のポエジア:刻印された時間」(ちくま学芸文庫)に拠れば、映画監督には必然しかない。監督の前で、俳優はどこに立ち、何を見つめているのか。その時、心の奥底にはどんな想いがあるのか。映画の時間を生きる時、俳優はもはや彼でも彼女でもなく、映画の時間を生きる固有の存在としてフィルムに定着していく。幾重ものイメージがつなぎ合わされ、ひとつの物語に昇華されたときに映画が生まれる。
その瞬間を逃すまいとする作家の妥協なき追求によって、綿密に計算された映像が形作られている。カメラアングルはもとより、フレームの中にあるすべてのファクターが、映画監督によって既に定められている。当たり前のことを実践することの苛酷。あくなき探求と思索が、結晶体のように純化した映画となって観る者を凌駕する。素朴でありながらも芳醇、匂い立つような画面には、こうでなければならないという作家の固い決意と、心を研ぎ澄ませれば感じとれるはずだという、観客への絶大な信頼に裏打ちされている。それは決して神々しいものではなく、単純な人間の生理に基づいた感覚を共有しようとする素朴な意志である。
映画は常に開かれている。だから躊躇する必要はない。難しく考えるのもやめよう。映画館の大画面でこの類い希なる傑作『ノスタルジア』に向き合い、心が感じるがままに楽しもうではないか。
巡礼とも呼びたくなるほどの幻想的で荘厳なひととき
新たに生まれ変わった4K修復版を観た。が、本当に「観た」「理解した」と言い切れるのか。その答えに窮してしまうほど、私は相変わらず本作の空気、朝靄、魂、水の滴に包まれながら目の前を過ぎ去っていった荘厳体験についてうまく言葉にすることができずにいる。83年、祖国ソ連の土をもう二度と踏まぬと決めたタルコフスキーが放った、幻想と陶酔と狂気と寂寥の映像世界。私は初鑑賞時(学生時代、VTRにて)に灯した心の蝋燭を今なお携えながらこれからも126分の永遠と一瞬の往復を何度となく繰り返すのだろう。それはある意味、人生を賭けた巡礼であり、はたまた鏡の中の己を覗き込むような所業とさえ言える。人は誰もがアンドレイとドメニコという二つの側面を抱えながら生きている。自分が冷静かあるいは気が触れているのかなんて紙一重だ。だからこそ、ただただひたすら祈り続ける。その姿や絶えざる過程にこそ、生は色濃く迸るのかもしれない。
ノスタルジア
世界の救済への祈り
私の中で唯一、死ぬまでにもう一度観ようと決めていた映画です。
それは、当時の彼(タルコフスキー)の年齢に達したならきっと、この映画の意味が解るかもしれないとずっと思っていたからです。昔、映画館の三本立の最後に観たとき、その美しく観念的な内容に疲れも忘れ、ただそんな気持ちでスクリーンを見つめていた記憶があります。
近年、自分なりに解禁し再び観る機会に恵まれ、今回私には、彼が決してただの耽美主義ではなく祖国を捨てる覚悟でこの作品の制作に臨んだのではと感じられ、また新たな発見がありました。
常人には理解することのできない、ソビエト連邦という共産主義独裁国家に生まれた彼の人生を思い、私なりの解釈なのですがレビューを書かせていただこうと思います。
タルコフスキーはイタリアで撮ったこの映画のあと、旧ソ連に帰ることを拒み亡命してしまいます。(家族は軟禁され監視下に置かれたと聞いています)
でも、それはきっと「彼自身」というよりも、欧米に対して映像作りに後れを取っていた『彼の才能』がそうさせたのだと私は思います。(キューブリックの「2001年宇宙の旅」と彼の「惑星ソラリス」の差のように)
結果、イタリア亡命後の彼の仕事は「映像の詩人」とよばれる彼にふさわしいものになったと強く感じます。
作品中の霧に覆われたようなモノクローム的な映像が、当時の旧ソ連の状況を表しているかのようです。
そしてその映像が何度もフラッシュバックするたび、残してしまう家族への彼の自責の念を痛切に感じます。通訳の女性とのやりとりも、自分は映像の自由を求めても、精神的に自由にはなってはいけないのだと言っているようです。
そして、当時の自由を失くした圧政下の祖国に対する彼の、亡命前の絶望ともいえる気持ちが「狂人扱い」されたドメニコの言動によって(少々間の抜けた言動も、当時のソ連の権力者にわざと分からないようカモフラージュしているかのように)語られているのではと私には感じられました。
「自分が健全(正しいの)だと言う者が世を支配している…
しかし実際は、人類(国民)全てが崖っぷちにいて破滅に直面している・・・」
「神は言っている。お前たちが存在するのではない。私が存在するのだ・・・」
(特定の人間を神格化し、いいかげんなことをしている者にだまされるな・・・)
「虫の声(=神の声)をきけ、水を(自然=神を)けがすな...道を間違えたなら原点に戻るのだ・・・」
ドメニコが、賢帝と呼ばれたマルクス・アウレリウスの像の上でアジテーションをしたのも、世界のリーダー達へのタルコフスキーの命を懸けるほどのメッセージがきっと込められていると思います。
一国に限らず、人類にとって希望の灯が必要になった時、その灯が消えても消えてもあきらめず復活するように、そしてその時、分断された世界の気持ちが1と1が2のままでなく1つになる時がくるように。きっとそれが、この映画を撮って数年後に、二度と祖国の土を踏むことなくソ連邦の崩壊を見ずして亡くなった彼の気持ちなのではと私は感じました。(もしかしたら彼は死期を感じていたのかもしれません)
最後に、
彼は亡命を決意してもなお、祖国を愛していたと思います。
印象的なラストシーンは、肉体はイタリアにあろうとも、魂は雪の降るロシアの地にあるのだと暗示していると私は思います。
『ノスタルジア』というこの作品名も。
この映画は、観る人それぞれに感じ方を変えてくれる作品だと思います。
そして私自身もまた歳月とともに感じ方も変わるかもしれません。
いつかもう一度、その時が来たらスクリーンに足を運びたいと思います。
その時、世界が平和でありますように...
読んでいただきありがとうございました。
そして皆さん、良き映画ライフを!
(Amazon より移動しました)
わからなかった
・ストーカーに続いてタルコフスキーは2作目。ストーカーも何回も寝かけたけれど、ノスタルジアも寝かけた。作曲家?の取材でイタリアに来ている作家っていう状況が中盤くらいになって何となくわかってきたけれど、誰が誰でと名前などがごちゃごちゃしてしまい結局よくわからなかった。タルコフスキーのセンスと自分のセンスが一切合わない事を痛感しながらも、他の作品が映画館でかかっていたら観たいとは思う。どれもそうなのか。
・自分が40歳になってとにかく毎日が虚しい。独身だし何も成し遂げてないし成し遂げる予感もない。なので、最後にろうそくの火を温泉プールを端から端まで歩いたら(何で歩いてたのかはよくわからなかった)何かが起こるかもしれないみたいな理屈を超えた奇蹟みたいなものにすがる感じは何となくわからんでもないと思った。
知性を試される
芸術がいかに伝わらないかを、美しい映像で歌い上げる。
タルコフスキーの作品をきちんと観たのははじめて。
ロシア人の詩人アンドレイは、自殺したロシアの音楽家サナノフスキーの取材でイタリアを旅していた。
小さな温泉街で、ドメニコという奇妙な男に出会う。
アンドレイは、ドメニコからろうそくを渡される。「ろうそくに火をともし、水の中を渡りきることができたら世界は救われる」。アンドレイはその役割を受け入れる。
タルコフスキーは「世界の救済」をテーマに創作を続けていたとwikiに書いてある。本作においてもそういう話は出てくるが、描かれていたのは、「芸術がいかに理解されないか」ということだと感じた。
冒頭、イタリア語がわからなければイタリア文学は理解できない、というやりとりがある。また、ドメニコの話を聞いたアンドレイが「よくわかるよ」と答えると「よくないんだ!」と切り返される。芸術家が焼身自殺をするシーンでも、まわりの人々はぼんやりとそれを眺めている。
タルコフスキーは命がけで映画を撮っているが、人々はそれを理解しなかったり、理解した気になっているだけだ、という気持ちが反映されているのだと思う。と、これもまた、自分の勝手な推測でしかない。
それはともかく、映像はすばらしい。
特に構図が美しく、絵画的なバランスになっている。
また、カラーとモノクロの画面を使い分けている。
カラーが現在で、モノクロは過去や抽象的な風景を描くときに使っているようだ。
タイトルの「ノスタルジア」は、言葉の意味としては故郷を恋しがることのようだが、本作のモノクロ映像で登場する田舎の風景は、宗教的な意味での故郷、あの世を示しているのではないだろうか。穏やかで満ち足りた世界に人々は戻っていく。
難解で、wikiを読んだうえで自分で推測したが、こういう映画もいい。
1980年代初頭というと世界的に経済が落ち込みはじめた時期のようだが、タルコフスキーが影響を受けているかどうかはわからなかった。
美しい映像
水と蝋燭の火
タルコフスキー監督の作品はやはり映像の美しさが段違いだ。
しかし説明的な台詞がほとんどないために、何を描いているのかが予備知識なしでは皆目分からない。
小説でいう余白の多さが特徴的だが、それだけに観ている方は忍耐と集中力を要求される。
そして気がつけば心地よい睡魔に襲われる。
それすらも監督の狙いではなかろうか。
学生時代にこの作品を観た時はとてつもない傑作だと感じたが、今観返してみると難解さだけが際立つ。
当時も内容を理解していたとは全く思えないのだが、それでも感性にビビッと来るものがあったのだろう。
物語はロシアからイタリアに亡命したサスノフスキーという音楽家の軌跡を辿るアンドレイの視点で描かれる。
エウジェニアという通訳が彼に付き添うが、彼女は彼に自分のことを女として見て欲しいと願っているようだ。
しかしアンドレイは彼女には見向きもしない。
モノクロの心象風景が何度も描き出されるが、アンドレイの心はどこかに囚われているようだ。
彼はある温泉地でドメニコという風変わりな老人に出会う。
彼は世界の終末を説き続けており、そのために家族まで犠牲にしてしまったらしい。
アンドレイはこのドメニコに同調する。
ドメニコはアンドレイに蝋燭の火を灯しながら、水の中を渡りきって欲しいと頼む。
それが出来れば世界は救われると。
後にドメニコはローマの広場で世界の終末を人々に訴えかけ、ライターで火をつけて焼身自殺をする。
アンドレイはドメニコの頼みを引き受け、蝋燭の火が何度も消えてしまう中、水の中を歩き続ける。
そして最後に彼は発作なのか、疲れなのか、その場に倒れてしまう。
倒れた彼の姿は映されない。
ラストはまた雪の降りしきるアンドレイの心象風景の描写で終わる。
その余韻は長く美しい。
解説を読むとこれはアンドレイのロシアからイタリアへの亡命の物語であるらしい。
何度も描かれるモノクロの風景は彼が捨て去ってしまった故郷の記憶である。
サスノフスキーは一度は亡命したものの、祖国を忘れられずに帰国し、後に自殺をしてしまったという。
アンドレイはそんなサスノフスキーに自分を重ねたのだろう。
そして家族を捨ててまで信念を貫き通そうとしたドメニコにも自分との繋がりを感じたのだろう。
それを知った上でも理解出来ないシーンは多い。
映像の美しさと画面の構図の素晴らしさはもちろんだが、エウジェニア役のドミツィア・ジョルダーノの美しさも際立っていた。
何百回でも見たい
アンドレイ・タルコフスキーを一言で表すなら、「優しさ」だと思っている。
それは、彼の言葉からは勿論、作品からも伝わる。
どれほど滑稽に思われようと、ひたすら自己を犠牲にして世界を救おうとする。
そういう人を彼は見ていて、映画の中で表現している。
瀕死の主人公ゴルチャコフが懸命に蝋燭を運ぶクライマックスは、その意味に思いを致さなければ、ただの奇行や無駄な努力としか写らない。
しかし、彼はそのために文字通り命を賭けている。
そして、その自己犠牲は我々の生きる世に実際に存在している、と伝えている。
犬や水のシーンは前作の「ストーカー」を踏襲するが、監督の年齢の分だけより洗練されている。
主人公の独白シーンも素晴らしい。
ラストシーンでは、ロシアの「ノスタルジア」を感じられる。
自分の中で最高と言える映画であり、何百回でもこの世界に浸りたい。
武満徹、フリードリヒ、写真家・植田正治
タルコフスキーが、1983年作り上げた映像美の極致、キーワードは「水」か。
武満徹の作品に「ノスタルジアーアンドレイ・タルコフスキーの追憶に」がある。1986年、タルコフスキーがパリで客死して後の1987年に作曲された、武満がより聴きやすい音楽に移行してからの作品。武満はタルコフスキー映画の中ではノスタルジアが一番好きだと明言していた。この映画を観ると、逆に彼の音楽がよく判るような気がする。彼の1966年の出世作である「ノヴェンバー・ステップス」は冒頭ハープで始まるが、水を意味しているのだと思う。二人は、きっと同じ感性を共有していたに違いない。
映画を観ていたら、鳥取砂丘の連作で知られている植田正治の写真が思い出された。砂丘に家族をまるでオブジェのように配置して撮った「妻のいる砂丘風景」(III)(1950年)など、特に日本とフランスで評価が高いようだ。
タルコフスキーが、家族を背景のなかにとらえた、植田と全く同じような映像が、この映画の中で出てきた。タルコフスキーは、当時のソ連から初めて離れてイタリアでこの映画を撮影したが、幾つか忘れることのできない故郷ロシアの情景があり、それを「ノスタルジア」として画面に定着させた。武満と言い、植田と言い、私たちの血の中には、僅かだがタルコフスキーと相通ずるものがあるのだろう。それは、なぜだろうか。
最後に、20年くらい前まで、日本ではよく知られていなかった「ガスパー・ダヴィッド・フリードリヒ」の絵画を思わせる廃墟の情景の中で、主人公、アンドレイ・ゴルチャコフが出てきた。忘れることができない映画である。
--
この映画のポスターに使われていた情景は、最近、日本でも人気の高いデンマークの画家「ハマスホイ」を思わせる。わたしの希望としては、フリードリヒのような情景から選んで欲しかった。このポスターが極めて魅力的であることは理解する。タルコフスキーの映像の中から切り出されたことも間違いないのだが。彼を代表する映像は、より厳しいものであって欲しいと思う。
圧巻の映像美に酔いしれる作品
タルコフスキー監督の作品は観たことがなく、4Kレストア版の劇場公開を機に本作を鑑賞しました。
正直、1/3くらいは意識が飛んでいたので、感想を書けるほどではないものの
映像美は圧巻でした。
どのシーンをとっても美しいというのは、観た劇場の支配人の言ですが、まさにその通りだと思いましたし、
独特の暗い雰囲気も作品とマッチしていて、私は好きです。
それから、印象的だったのは、エウジェニアを演じたドミツィアーナ・ジョルダーノの体当たりの演技ですね。
感情表現もしぐさも素晴らしかったです。
ラストはちょっと驚いたというか、有言実行するあたり、静謐さと激しさが同居していて
なかなかこういうラストはお目にかかれないので、心にぶっ刺さった次第です。
また機会があれば、タルコフスキー監督作品にチャレンジします!!
理解不能、
なんとなく観とくと映画通みたいな?
全51件中、1~20件目を表示