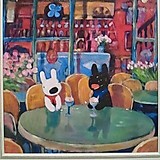知りすぎていた男のレビュー・感想・評価
全24件中、1~20件目を表示
「暗殺者の家」+母性愛+カラー+「ケ・セラ・セラ」‼️
家族でモロッコを訪れた医者のベンは、現地で知り合った謎のフランス人の殺害現場に遭遇した事から、某国首相を暗殺しようとしている一味に狙われ、息子を誘拐されてしまう・・・‼️ヒッチコック監督が最も得意とする巻き込まれ型サスペンスの快作‼️異国情緒漂うモロッコで、ジェームズ・スチュワートに近づいてきた男が倒れると、その背中にはナイフが、という導入部からしてヒッチコック監督十八番の趣向なんですが、ラストのアルバートホールでの盛り上がりが特に素晴らしく、楽譜のアップというサスペンス技巧、シンバルの響く瞬間を狙っての犯人のピストルとのフラッシュバック、そしてご存知ドリス・デイの「ケ・セラ・セラ」の効果的な使い方まで、ホントにヒッチコック監督はスゴい‼️観終わって思わず主題歌を口ずさみたくなりますね‼️
ケ・セラ・セラ
ケセラサラ
暗殺事件と誘拐事件を絡ませたヒッチコック監督の模範的サスペンス映画
名作の「裏窓」と「めまい」の丁度真ん中の時期に製作されたヒッチコック監督の模範的なサスペンス映画。フランス領モロッコ(独立は1956年)のマラケシュで某国の首相暗殺計画をフランス人ルイ・ベルナールから言付けられたアメリカ人マッケンナ医師家族が息子の誘拐事件に巻き込まれるストーリー。ベルナールが息絶える前に夫ベンが聞いたのは、要人がロンドンで暗殺されることと警告をアンブローズ・チャペルに、という言葉だけ。事情聴取を受けるためにマッケンナ夫妻は、居合わせたイギリス人ドレイトン夫人ルーシーに息子のハンクを預けて警察署に向かう。そこでベルナールがスパイと知って驚くも、尋問の仕方に怒りを覚えるベンに、何故か電話が掛かって来る。それは、ベルナールが言ったことを誰にも話してはいけない、話せば息子に危険が及ぶという脅迫だった。フランス語が話せるエドワード・ドレイトンに先に帰った夫人と息子ハンクの安否を電話でホテルに確認してもらうが、どちらも部屋にはいない。誘拐が現実味をおびて恐怖がベンを襲う。そこでエドワードにホテルに戻って事情を調べるよう依頼して自身は調書の手続きをするのだが、遅れてホテルに着いたベンが愕然とするのは、ドレイトン夫妻がチェックアウトしていたことだった。このベルナール殺害事件の発端から誘拐事件が絡んでしまう前半部分の緊張感の流れが素晴らしい。特に観光で訪れた異国の土地で知り合う見知らぬ人の素性をどう判断するのかの、人間力の視点が面白い。妻ジョーは質問ばかりで自分のことは話さないベルナールを不審に思う観察力があり、夫ベンも脅迫電話を受けて取り乱すことなく、ホテルの部屋に落ち着くまで妻に息子が誘拐されたことは話さず、医師として先ず薬で安定させようとする。そんな二人がドレイトン夫妻を信用して子供を預けたことが発端となって、二つの事件に巻き込まれるという災難のサスペンスドラマ。イギリス時代の「暗殺者の家」を20年経ってリメイクしたヒッチコック監督の愛着のこだわりが分かります。
誰にも助けを求めることも出来ず追い込まれたマッケンナ夫妻がロンドンに行かざるを得ない後半は、二つのクライマックスを構築していて見応えがあります。先ず到着と同時に公安課のブキャナン警部が接触を図るも、既に一味のスパイ(瓶底メガネの何処にでも居そうなオバサン)が偵察にきている。ジョーがかつてロンドンでも公演したことがある有名な歌手の来訪と知って詰めかけているファンの中に紛れているカットのヒッチタッチ。そこから警察にいるジョーにルーシーから電話がきてハンクの声を聴かせるのは、情報を警察に漏らさないための警告。その前に警部が暗殺阻止を優先した、情報提供しなければ共犯になると脅すのに対して、ベンが放つ言葉がいい。“ルイから話を聞いたのは私だ。妻まで脅すな”と言う。ここに主人公ベンの正義感と勇敢さの両面が良く表れています。そのハンクの声を聴くために二人が受話器を挟んでいるショットのカメラアングルもいい。斜め上から捉えたショットからのズームアップは、息子の安否に憔悴する母親ジョーに観る者が同情して観てしまう深刻さを印象付けます。更に電話が切られてしまう時のベンの叫びに重なる飛行機の轟音。ヒッチコック監督の細かく繊細な演出が分かります。そこからホテルでロンドン在住の知人の来訪を受けて、明るく振る舞う二人。最初のアンブローズ・チャペルの人探しでは、人影のない歩道にひとり謎めいた男がベンの後を歩いてくる。それだけで不気味さが演出されているし、その目的地が剥製の制作所という気味悪さ。ここでの押し問答のシークエンスは、ヒッチコック監督がスラップスティックコメディのタッチで遊んでいるような可笑しさ。このフェイントは、チャペルとチャーチの勘違いと、人ではなく礼拝堂と気付くジョーの機転の良さと行動力を表し、後を追うベンとホテルに取り残される来客のドタバタ劇はシチュエーションコメディのようです。そしてこれがラストカットのために意図されたシーンであるのが、最後に分かると言う仕組み。全てが計算されて構築されています。
アンブローズ・チャペルの室内シーンは、それまでの謎解きを説明する役割であり、クライマックスへの音楽で言えば緩徐楽章。ハンクは個室に軟禁されていても空港にいた女性とボードゲームをしていて、拘束まではされていない。ルーシーが別室に入ると、視線の先に見知らぬ男が正装に着替えている。よく見るとマラケシュのホテルで偶然を装い部屋を覗いた男で、銃を装着している。エドワードは聖職者の服を纏い、アルバート・ホールのチケット2枚を殺し屋に手渡す。そして、楽曲のクライマックスであるシンバルが叩かれる個所を確認する。これは既に映画のプロローグで丁寧に説明されています。この殺し屋が裏口から車に乗るショットの、表通りに佇むジョーが右奥に見える構図の見事さ。「めまい」でも落下したマデリンと教会から逃げるようにいなくなるスコティを一つの構図に収めたショットがあったが、どちらも物語性を持った絵画のような趣があります。そして漸くベンがジョーの元へ到着、一緒に礼拝堂に入って身を隠すもルーシーと対面する。この時の驚き怖れるルーシーの顔と、祭壇に立つエドワードに無言で報せる顔の怖さ。だがジョーがブキャナン警部に連絡を入れている間にベンは頭を打たれて気を失う。警部不在で話が進展せず警察が来ても教会内に侵入できない苛立ちから、警護のためアルバート・ホールにいるブキャナン警部を探すジョーは、ホールロビーでマラケシュで会った暗殺者から声を掛けられる。これが暗殺者にとって大きな痛手、出過ぎた真似になる皮肉。大ホールでは高名な指揮者バーナード・ハーマンによるオラトリオのような大規模な楽曲が演奏され、クライマックスに向って高揚していく。教会に閉じ込められていたベンは鐘のロープを伝い鐘楼の塔に上り詰め脱出してジョーの元へ急ぐ。暗殺者の居場所を知り得たジョーは、ベンと再会して伝え、そのボックス席のカーテン越しに光る銃身に気付き絶叫してしまう。子供を誘拐された母親の追い詰められた心境と音楽の願いが複雑に絡み合ってのシンバルの響き。運よく某国首相はかすり傷で済み、突入したベンと暗殺者が揉み合うも、逃げ切れず暗殺者は足を取られ落下して絶命。普通の作品ならここで終わるくらいの練られた盛り上がりです。
ブキャナン警部とマッケンナ夫妻の作戦会議では、ドレイトン夫妻が某国の大使館にいることが確認される。この為の伏線を、先ずハンクを連れたドレイトン夫妻が大使館の厨房から侵入するシーンで、厨房の外に追い立てられる料理人と大使館員が不満を述べるところ。そして、ドレイトン夫妻を大使の部屋に案内するシーンのドアを閉めてから画面に向かって歩いて来る大使館員。彼がイギリス警察側のスパイであるのを二回匂わせている。この曖昧さと丁寧さの映画的表現力が素晴らしい。脚本の良さ、演出の巧さは、このような細部に見つけることが出来ます。だがハンクが大使館にいるだろうと分かっていても、治外法権の縛りで突入は無理。外務省から大使に申し入れできるとブキャナン警部は言うが、首相暗殺のラスボスはその大使というのを観ている者が知っている。これが映画の話術というもの。そこで暗殺未遂に貢献したジョーを招待させるよう首相に直接電話するベンの機転の良さ。大使館には、息子と一緒に歌いなれた『ケ・セラ・セラ』が響き渡り、曲に合わせてハンクの指笛が応える。ハンクに情が移ったルーシーの改心に救われる展開もいい。エドワードが自業自得の最期を迎えるのも階段を使ったオーソドックスなもので、もっと激しく立ち回っても良いのではと思うも、既にアルバート・ホールでのクライマックスで頂点に達している為、このくらいの緊迫感で充分と言えるでしょう。
ひとつ不自然なのが、マラケシュを舞台にしたシーンで背景を合成にしたカットが多く、編集で上手く切り抜けているのですが、どうしても気になってしまう事です。ロバート・バークスが進んでそうしたのか、ヒッチコック監督の意図なのか判断に迷うところです。ロンドンでの撮影は完璧ゆえ、勿体ないと思いました。この作品で際立つのは、ヒッチ作品の音楽で映画史に遺るバーナード・ハーマンの指揮振りが見られることと、そのクラシック音楽の充実度で、オーケストラに合唱と独唱が付くとても豪華なもの。オーケストラもロンドンで最高レベルのロンドン交響楽団という贅沢さです。俳優では、主演のジェームズ・スチュワートは安定の巧さ、意外なのは歌手が本業と思っていたドリス・デイが見事な演技を披露している事。口喧嘩が絶えない夫婦の職業夫人の誇りと自信でベンと対等な妻ジョーを好演しています。助演では役柄の良さもあって、ルーシーを演じたブレンダ・デ・バンジーに好印象を持ちました。全体を通して言えるのは、これぞサスペンス映画の模範、スリラーの楽しみ方を分かり易く教えてくれる教科書的作品です。カラー化のリメイクに収まらない、脚本の密度と隙のなさが見事でした。
Veryヒッチコック
【”ケ・セラ・セラ”神に仕えし者の企み。ラストの銃口と音楽を交錯させたシーンは、興奮と緊張感を高める秀逸な演出である。】
■ベン(ジェームズ・スチュワート)とジョー(ドリス・デイ)のマッケンナ夫妻は、息子・ハンクと共に休暇でアメリカからモロッコを訪れていた。
ところが、知りあったばかりのフランス人スパイ、ルイ・ベルナールがベンの腕の中で謎の言葉”ロンドンで重要な人物が殺される・・”を残して背中を刺されて死亡する。
夫妻は息子が誘拐され、イギリスへ連れ去られたことを知り…。
◆感想<Caution! 内容に触れています。>
・モロッコのどこか長閑なシーンから、ロンドンのアルバート・ホールで行われようとした、緊迫感溢れるコンサートシーンとの対比が見事。
・首相を”叫び声”で銃弾から救った歌手のジョーが、皆の前で歌う”ケ・セラ・セラ”がハンクの耳に届くシーンも秀逸である。
<今作は、某国大使館が企んだ演奏会のシンバルの音に合わせての首相暗殺シーンの緊迫感を抱いた演出が見事な作品である。>
ヒッチコックらしいこだわり
なんか、意味不明(細かいことは気にするな?笑)
知りすぎたって何を?自分のことを知られすぎた男が、スパイの死ぬ間際に犯人のいる場所を伝えられて、子供を知らない人に預けちゃって、ピンチを自ら切り抜けようとする。うーん。イギリス警察が自国のことは自国でやれよ的にアメリカ(?)を揶揄していたのは笑えた&ケセラセラの歌はよかったです。
巻き込まれていく、その先。
一言「あー、もうどうなるん?!」
最近ヒッチコック監督の映画感想が多いのは。
NHKーBSで連日放送されているからなんです。
全然見てないしね。
最初は話の筋がよくわからす。脳内に?の嵐。
その割には飽きない。わからないのが、謎解き風なので興味深し。
夫(医師)と妻(歌手)と、息子(5歳位)。
呑気に乗合バスに乗っていたら、小さいトラブルに遭い。
それを機に次々、事件に巻き込まれていくのが「えらいこっちゃ」状態。
誰が黒幕?云々より、主人公が家族の危機を乗り越えていく、タフさや機転。
応援しちゃいました。先が見えないだけに。
時々ちょいコミカルな描写も、いいアクセント。
クライマックスのオーケストラシーン。
音にかき消されて、セリフが聞こえず。夫婦の身振り手振りのところは。
観客の想像力をかき立てて、余計盛り上がる。
“アカデミー賞歌曲賞を受賞した「ケ・セラ・セラ」はあまりに有名“。
「なぜ有名なのか」は、物語のキーポイントだったからかしら?。
全体を通して、その後の作品に影響を与えたところも感じられました。
⭐️今日のマーカーワード⭐️
「大使館は治外法権」
知らない人を信頼してはいけない
タイトルが最高だよね
前半の異国情緒漂う感じもストーリーをより霧に巻いているようで素敵だし
あのラストのほっこりする感じもすき。
ジェームススチュアートはやはり最高だよな~
あの渋さと、今作ではスタイルの良さにもびっくりした!
ドリスデイもどんどん素敵に見えてくるんだよね~
ケセラセラ~も素晴らしい歌のように聞こえましたな
ケスェラ~スェラ~~
この連休(自粛期間)でヒッチコックの代表作を観てきました。
せっかくなので、マイベストヒッチコックを。
1.鳥
2.ダイヤルMを廻せ!
3.サイコ
4.ロープ
5.見知らぬ乗客
やっぱり鳥はナンバーワン。"鳥"要素だけを使ってあれだけ恐怖心を煽るのは天才としか言いようがない。そして、ダイヤルMを廻せは最初の方に観たのですが、これも衝撃が忘れられない。この構成で作られた物語がラストまで緊迫感を保ち続けるのが凄い。(死に方も凄い)
あとヒッチコックを語るに欠かせないサイコ。
そして、ワンカットに魅了されたロープと、テニスの試合のワンシーンで衝撃が走った見知らぬ乗客。
本来なら、「めまい」や「裏窓」も欠かせないのだろうけど、この二作は"何度も観てさらに作品の良さが深まる作品"かなと。ベストは衝撃度で選んでしまった部分があるけど、この二作は心理にもっと深く踏み込んでいる。何度も観て大事な一作になるイメージが強いです。
しかし、英国時代の作品は全然手をつけれていないし、
ファミリープロットやら海外特派員といったやや埋もれた作品は観れていないので
楽しみとしてとっておきます。
ヒッチコックが最も油の乗っていた時期の最高峰の傑作だ
ヒッチコック映画の最高峰のひとつ
正に何から何まで映画作りの名人の技
最高の娯楽映画だ
本作はもともと1934年の暗殺者の家のセルフリメイク、原題はThe Man Who Knew Too Muchで同名
だから彼の中で特に熟成された作品だといえる
音楽が中心になる作品だから、そこに歌手のドリス・デイを起用する配役も素晴らしい
そして彼女に歌わせる主題歌ケセラセラもまた素晴らしい!
あの世界的な有名曲で映画音楽の枠を超えて永遠のオーディーズポップスだ
また二度登場するその使い方も感嘆するばかり
特に二度目の歌唱シーンは息子の無事を知る為に声を張り上げ、息子ごそれに指笛の歌で応えるシーンは感動を呼び涙がこぼれる
ドリス・デイは歌ばかりか演技も見事で、息子の誘拐を知って錯乱するシーンでの演技力はどんな大女優にも負けない完璧さだ
ジェームズ・ステュアートとヒッチコックの相性はもちろん最高で言うこと無し
安心して観ていられる
圧巻なのはロイヤルアルバートホールでのロンドンフィルオーケストラの公演シーンだ
冒頭と後半の二度登場する
指揮者は音楽担当のバーナード・ハーマンその人
曲は1934年のオリジナル曲を彼が編曲し直したもの
弦楽器、ソリスト、コーラスと展開し
ティパニーの連打、そしてシンバルの一撃!
気持ちよさそうに指揮棒をふるバーナード・ハーマン
彼はなんと本人役となっており、本編のロイヤルアルバートホールの入口のポスターに曲名と共に彼の名前がデカデカと大書きされているシーンがある
無数の映画の歴史の中でも最高の音楽の使い方ではないだろうか
ユーモアやウイットも見事な配分で、全てが解決して最後の最後のユーモアなラストシーンで終わらせるのは見事というしかない
ヒッチコックが最も油の乗っていた時期の最高峰の傑作だ
マッケンナ一家vs巨大な陰謀
「知りすぎていた男」DVD 字幕版で鑑賞。
*概要*
モロッコで観光してたマッケンナ夫婦と息子がある謎のフランス人と出会ったことがきっかけに暗殺と巨大な陰謀に巻き込まれていくサスペンス。
*主演*
ジェームズ・スチュワート
*感想*
ヒッチコック作品巡り第六弾!これまたジェームズ・スチュワート主演!
今回は、ある一家が誘拐、暗殺、巨大な陰謀に巻き込まれていくというシリアスな内容。
アクションシーンが多くて、割りと面白かったと思います。老夫婦、暗殺者、ダイイング・メッセージなど、伏線がちょいちょいあって、話のテンポも丁度良かった。(^^)
ただ、最後の終わり方は、あれ?これでもうおしまい?!って感じだったので、個人的にちょっと物足りなかったな。。。
さすがはヒッチコック。 いやーこれは面白い。ドリスデイの勘の良さで...
全24件中、1~20件目を表示