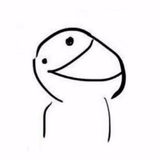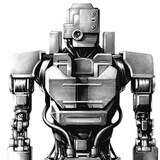白雪姫(1937)のレビュー・感想・評価
全6件を表示
ディズニーアニメの原点
ディズニープラスで鑑賞。
ディズニー長編アニメ第1作にして、世界初の長編カラーアニメーションです。
昔の映像とは思えない程作画が美しく、印象に残る曲が多かったです。ホラー要素もうまく組み込まれており、特に女王が薬で魔女に変身するシーンはいつ見ても鳥肌が立ちます。
また、個性的なキャラクターも多く、特に小人の一人であるドーピーは全く喋らないのにも関わらず、感情豊かで彼の行動を見ているだけでも癒されました。
歴史に残るような伝説級のアニメ映画になっていると思いました。
ハイホー!ハイホー!仕事が好き
このディズニーアニメ映画マラソンでは、ディズニー・アニメーション・スタジオの長編アニメニメ映画全64作品をレビューしていく。まずは「すべてを始めた作品」から。
レビューはあらすじ→良い点→悪い点→総評→評価の順番でいく。
あらすじ (ディズニー公式参照):
美しく心優しい白雪姫。その美しさを妬む継母の女王から命を脅かされ、森の奥深くに逃れた白雪姫は、7人のこびとたち――おとぼけ、ねぼすけ、くしゃみ、てれすけ、ごきげん、先生、おこりんぼ――と出会い、一緒に暮らし始めます。ある日、老婆に姿を変えた女王が訪ねて来て、毒リンゴを口にしてしまった白雪姫。横たわる白雪姫の傍らで悲しむこびとたちの元に王子様が現れて…。
良い点:
1.白雪姫はまあまあな主人公だ。
2.先生, おこりんぼ, おとぼけ, ごきげん, くしゃみ, てれすけ, ねぼすけは皆、素晴らしい準主人公だ。
3.女王はかなり良いヴィランだ。
4.狩人と鏡はどちらも非常に印象的な脇役だ。
5.非常によく扱われたコメディ。
6.数多くの暗く・強烈な場面があり、それらはよく扱われている。
7.優れた声の演技。
8.非常に優れたスコアを含んだ素晴らしい音楽と 「私の願い」、「ワン・ソング」、「口笛ふいて働こう」、「ブラドル・アドル・アム・ダム」、「小人たちのヨーデル」、「いつか王子様が」、もちろん「ハイホー」のような印象的な曲がある。
9.アニメーションは1930年代半ばから後半の作品としては驚くほどよく、優れたキャラクターデザイン、素晴らしい特殊効果、非常にきめ細かい背景を含んでいる。
10.ストーリーはかなりきちんと書かれている。
悪い点:
1.王子の登場場面はほとんどなく、プロット装置に過ぎない。
2.よく書かれているが、ストーリーにほとんど教訓がなく、ありきたりなおとぎ話に過ぎない。
3.少し退屈な場面がある。
総評:
ディズニーのキャリアと遺産をスタートさせただけでなく、映画という全く新しいメディアをスタートさせたこの映画は、「すべてを始めた作品」という称号にふさわしい。
評価:
4/5 (Great)
白雪姫でもうディズニーのスタイルはできあがっていた
実写版の白雪姫を観たあとで
アニメ版をちゃんと見ていなかったので
今更ながら観た
ミュージカル要素とか
この映画の時点でディズニースタイルが完成されていたように思う
ストーリー自体はシンプル
時間的に動物や小人たちのやりとりは
最近の映画と比べると冗長な感じがするが
それに費やすアニメーションの演出は
今観てもかなりレベルが高いように思う
掃除のコツは〜♪、口笛明るく吹き鳴らして〜♪
3月22日(土)
昨日実写版の「白雪姫」を観たが、アニメの「白雪姫」のストーリーの細かい所は忘れていたので、購入してあったDVDでアニメ版をチェック。
「白雪姫」のリバイバルを劇場で観たのは40年も前で、今は無き地下の日比谷みゆき座であった。ここでは「ジョンとメリー」や「フォロー・ミー」も観たっけ。
みゆき座の売店で売っていたバドワイザーを買って「ビール飲みながら「白雪姫」観るのはオヤジの俺達位だな」とビール片手に映画を観た。
「白雪姫」を一緒に観た作家の松村光生ももうこの世にいない。
アダプテッド・フロム・グリム・フェアリー・テイルズと出る。
原題は「白雪姫と七人の小人」
40年前、映画が始まってすぐにビックリした。井戸のシーンである。
井戸の底から水面越しに井戸を覗き込む白雪が映るシーンで、水面に波紋が拡がって行くのである。
1937年のディズニー初の長編アニメーションで既にこの表現が実現されていたのである。
この間観た「Flow」でもこれほど見事な波紋は描かれていなかったと思う。
今回の実写版でも全く同じアングルのカットがあるが、現代ならCGで簡単に出来てしまうのだろうなぁ。
原題が「白雪姫と七人の小人」なので、手を久しく洗っていない小人たちに料理をした白雪が食事の前に小人たちに手を洗わせたり、会話をしたり、小人たちとの絡みが多い。
魔女である女王は毒を調合した林檎を老婆に姿を変え白雪に食べさせる。
白雪に林檎を食べさせた女王は、小人たちに追われて崖から落ちて呆気なく死ぬ。
林檎を食べた白雪は「死の眠り」に落ちる。女王の魔女が毒を作った時の本に「スリーピング・デス」と書いてある。
小人たちは、白雪を埋葬せずに金とガラスで作った棺に納めて側に置く。
その噂を聞きつけた王子がやって来て白雪にキスをして白雪は目覚めるのである。
そして二人は幸せに暮らしましたとさ。
アニメとしての完成度は「ファンタジア」や「101匹わんちゃん」の方が高いが、短編アニメしか製作していなかったディズニーが「白雪姫」で長編アニメの製作に挑んだ事が、その後に花開くのである。
私の娘が小さい頃は、毎日(本当に毎日!)LDで観ていた。観るのはチャプターで小人たちが留守の間に動物たちと家の掃除をする「口笛吹いて働こう」のシーンだった。ウサギとシカとリスが掃除をし、アライグマが洗濯して、小鳥たちが洗濯物を干す。
「掃除のコツは〜♪、口笛明るく吹き鳴らして〜♪、たちまちきれい〜♪」小さい子は飽きないで毎日観るよね。
「ハイ・ホー」や「口笛吹いて働こう」のような楽しい曲は子供にも受ける。
DVDには特典でバーバラ・ストライサンドが歌う「いつか王子様が」が入っていた。
ディズニーの要素がこの時点で完成している
滑らかなアニメーションやミュージカル。アニメーションを活かしたユーモア。
これぞディズニーというのが第一作ですでに完成している。
敵が崖から落っこちて死ぬのも同じ。
死体を見せず主人公側の暴力性も見せずに勧善懲悪を描ける手法として、やはり第一選択。
ただ今の時代にこれを見ると白雪姫の主体のなさがついつい気になってしまう。
美人だが自分の意思が感じられない。どこぞの馬の骨かも分からない王子様をただ待っている状態。簡単に魔女に騙される。小人達の料理や掃除をする家政婦的存在。
まあ制作の時期を考慮すればそれを評価に加えるのは野暮な話。
これ以後のプリンセスの変遷を踏まえる上でむしろ重要な作品。
殺されそうになって逃げ込む形で動物達の森や小人達の小屋に行き着く展開は、アリスやオズの魔法使い的な感じで、好きな導入。
本当は怖いとかエロいとか野暮
成人になってかなり経つがディズニーアニメ『白雪姫』をしっかり観たのは初めてだ
幼少の頃に読んだグリム童話の絵本であらすじは知っている
それなのに白雪姫というとまず思いつくのが修羅雪姫の梶芽衣子だった
白雪姫は主人公だがたいして活躍していない
小人の家の掃除と料理を作ることくらい
王子様に至ってはちょこっとしか出ていない
2人とも悪と戦っていない
白雪姫と王子様のキスはそんなものかと拍子抜け
世界最古の長編アニメーション
公開は1937年昭和12年
プロ野球でいえば草生期で沢村栄治にハリスにタイガース松木景浦西村
伝説の世界だ古い古すぎる
日本では一部にありがちな幻聴ではなく実際に軍靴の音が聞こえ始めてきたきな臭い時代だ
小学生の頃その事実を知り「日本では『欲しがりません勝つまでは』『贅沢は敵だ』なのに余裕じゃんアメリカすげーよ」と思ったものだ
大東亜戦争の影響もあったか日本で公開されたのは戦後1950年昭和25年
アニメのクオリティーがかなり高い
人物の描写がリアルだ
時代を感じさせない不朽の名作
4年の歳月と当時で170万ドル費やした大作
今の日本のテレビアニメと比較したらアニメ制作会社の人たちがかわいそう
森の動物たちと7人の小人がコメディーリリーフ
彼らがこの作品のメインになっている
あのユーモラスな表情と動きで時間を稼がなければ長編にはならない
世界一の美女になりたい継母の王女は白雪姫を殺すよう家来に命令する
殺した証拠に姫の心臓を求めたがそれは不可解
普通なら生首じゃないの
西洋の文化なんだろう
魔法で醜い老婆に化ける王女
元に戻ることができるんだろうか
できなきゃ本末転倒だ
檻の中の骨が誰なのか気になる
白雪姫の父親である国王かな
悪い王女の最期は7人の小人に追い詰められ崖から転落
コンドルさんご飯ですよ
人を呪わば穴二つ
鏡のデザインが子供の頃の記憶と違う
「1番美しいのは女王です」ってこいつがお世辞言っておけば丸く収まって良かった話じゃねーか
姫は下働きのままだけど
ライオンキング以来ディズニーアニメが嫌いになった
パクリそのものより批判に対する対応が許せなかった
ディズニーはそれを今も現在進行形で続けている
著作権に厳しいくせに自分らには大甘な呆れたダブルスタンダード
B'zのパクリよりはるかに悪質で本来ならB'zより叩かれてもいいはずだがそこは世界的ブランド
日本人の多くは世界的権威に弱い
ジャングル大帝なんて知らなかったってそりゃないよ
たとえ虫プロダクションが許してもこの美少女仮面ポワトリンが許しません
愛ある限り戦いましょう命燃え尽きるまで
とはいえ天国のグリムが枕元で叫ぶ
「ディズニーアニメは嫌いになっても白雪姫は嫌いにならないでください」
子供の頃は嫌いじゃなかった
むしろ好きだった
ライオンキング以降のディズニーアニメはまだ蟠りがあるがそれ以前の作品とは和解する時がきたようだ
初心に帰って初期のディズニーアニメを観てみよう
全6件を表示