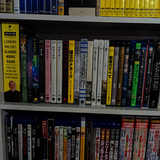ゲームの規則のレビュー・感想・評価
全18件を表示
ゲームの規則 4Kデジタルリマスター
YEBISU GARDEN CINEMAで『ゲームの規則』4Kデジタルリマスター版 鑑賞。1939年WWII勃発直前のフランス映画。ハンティングや宴会に興じる社交界の人々とメイドや勢子などの使用人たちとの騒動を描いた群像劇。その中間層に位置する狂言回しを、ジャン・ルノワール監督自身が演じているのが興味深い。#75
風前の灯
物語を要約すると、おもちゃ箱の中に密猟者と飛行士という新しいおもちゃを放り込んだら箱ごとひっくり返った。片付け終わって気がついたら、新しいおもちゃが無くなったけど、まあいっか!そんな感じか。
仏頭の脇で行われる侯爵と愛人の会話。悪趣味だが視覚的にとてもインパクトがある。ここでの会話が、物語全体を表している様に思う。現代のSNS文化同様に、言葉は自己陶酔、自己欺瞞の為の道具だ。それが暗黙の了解でありルールなのだ。
そんな館の住人たちにとっては、他人の愛や命は余興という暖の為に焚べる薪でしか無い。国民的英雄であり自分の妻に懸想する礼儀知らずな青年なんていうのは最高の薪だったのだろう。森番に目をつけられている密猟者は、火付けのための松の葉か。執事が上手く焚き付け、侯爵は自らも火の粉を浴びつつ遊興にふける。この辺りを悪意で無く当然の振る舞いとして行っているから恐ろしい。
この作品が公開されたのは1939年、まさに第二次世界大戦開戦の年。オーストリアはナチスドイツに占領され、トラップ一家は既に国外へ脱出したころあいだろう。翌年にはパリも陥落する。そう考えると館の住人たちは茹でガエルの様にも見えてくる。
そんな館に辟易して最後に立ち去るルノアール。彼には未来がどの様に見えていたのだろうか。そんな事を考えると、あの生々しい狩猟シーンがより恐ろしくなる。
…
表現力、完成度、芸術性はもちろんのこと、時代感覚の鋭さが凄い。
…
ココ・シャネルの衣装は、視線を引き付ける力が強い。
コレが
フランス社会の脆弱性を警告
原題は「遊びのルール」といった感じ。鬼ごっこやかくれんぼのような子どもの遊びの軽い決まりごとを指す。「ゲームの規則」と訳すると狩猟の獲物を指す「ゲーム」とも混同してしまうしもっと重々しい。
時代が第二次世界大戦直前なので、さすがに王朝時代や帝政時代と比べれば、上流社会を描いているといってもかなりカジュアルにはなっている。女性の衣装は簡素化、軽量化しているし、屋敷の住人やゲストと、使用人たちとの関係がそこまで隷属的だったり形式張ったりではなくなってきている。
ところで筋書きとしては狩猟とパーティーの一昼夜を通して、侯爵とその夫人、お互いの婚外パートナーを巡る四角関係?のドタバタを描く。これに使用人たちの三角関係が同時進行し、合計8人の男女が画面狭しと動きまわる。4+3の7人ではないのはジャン・ルノワール監督自身が演じるオクターヴなる人物が狂言回し的に加わっているから。コメディ映画と評する人がいるくらいでスラップスティックな動きが特徴ではあるが実に乾いている。登場人物たちの恋愛はとても刹那的で切実さが全くない。その時々の状況に応じて追いかけっこする子どもめいた恋愛ごっこである。
そもそも狩猟もウサギやキジを撃つが、その獲物を調理して食べるという次のステップがない。単に殺した数だけを競っている非生産的なものである。パーティーの演目も悪ふざけ的な演し物で芸術性は欠片もない。つまりこの侯爵の領地で行われているものごとは、恋愛も含め全てが無意味、無価値である。
映画の最後で、殺人が発生するが、これは侯爵は事故であると断じ、領地内で処理をしてしまう。
それが、この侯爵の「ゲームの規則」なのである。
もちろんある程度のカリカチュアはあると思うが、恐らくジャン・ルノワールが言いたかったのはこの非生産性や非法治性が、それは前近代性とくくっても良いのかもしれないが、当時のフランスの社会全般を覆っており社会の脆弱をもたらしているということなのだろう。
確かに、この数年後、ナチスドイツの侵攻に対しフランスは実に脆く、屈してしまうこととなる。
フランス上流階級の在り方
色恋を中心に享楽を求めるフランス上流階級のパーティーでの騒動を描いた85年前のフランス映画。色恋なんてまるでゲームという風にあっちでもこっちでもみんな軽やかに恋愛ごっこを楽しんでいる(深刻ぶって見せるときもあるけれど、それすらもゲーム?)。妻の不倫が分かっても大したことでもないというように対応し不倫相手にも接する。今の我々のモラルから判断すれば「すごいな。ホントかよ」と突っ込みを入れたくもなるが、これが名画として評価されている以上、誇張はあっても当時の上流階級を表しているのだろう(皮肉混じりだとは思うが)。最後にやらかしたのが上流階級に属していない森の門番というのがオチなのか。ゲームの規則を理解していない下々はダメでした、かな?
優しいようでドライな監督
本作はオールタイムベストなどでも毎回上位にランクされ、ジャン・ルノワール監督の最高傑作とまで呼ばれ、個人的に“宿題作品”としていていずれ見ようとは思ってはいた作品でした。
しかし先月同監督の『ピクニック』('36)を見て何となく私の好みとは合わない様な気もして先延ばしにしていたのですが、今回鑑賞してやはり予想通り一筋縄ではいかない作品であり、私にとって少し苦手というか難しい作品でしたね。
専門家筋の評価の高さについては何となく理解出来ましたが、こういう作品の感想は私が書くには荷が重く、こういう作品こそプロの評論を読むべきだと思いました。(私も読みたい)
でも、感想・分析・解析などは面倒でも、映画から受けたインスピレーションなどの話題なら色々としたくなる様な作品でもありました。
とりあえず、物凄く大雑把にこの作品を言い表すと、人間社会の大枠の種類の登場人物を配した群像劇であり、上流階級の侯爵邸で起きる数日間の出来事で人間関係の縮図の如く、人間のあらゆる普遍を描いた作品と言ったら良いのでしょうか。
それを詳細に分析すると深すぎて一冊の本にもなりそうなので書く気が起きませんので、今回はこれが私の『ゲームの規則』を見た第一印象としておきましょう。
それと、上記した私が苦手な理由も少し考えてみたのですが、特に外国映画の場合、台詞が多過ぎる作品というのも苦手である一つの要因かも知れません。
台詞が多いといっても娯楽映画特有の説明台詞ではなく、本作の場合の会話の多さは日常手的な会話の為の会話的であったり、言葉に一々その人の機微が隠れていたり、言葉の内容そのものよりも言葉自体が洋服のように裸を隠すための装飾であったりで、外国映画の場合は字幕なので自然に頭に入らず、それらの判別が非常に面倒なんですよね。
もっと近年の監督で例えれば、ウディ・アレンの初期作品や、エリック・ロメールやホン・サンスの作品を見る様な感覚に近いのかもかも知れません。
あと、悪人は登場しないが好きになれる様な人物も一人も居らず、様々な会話を聞きながら良い台詞も無茶苦茶な台詞も、それを吐く人間は総じて個人(ご都合)主義であるって事が本作の多くの台詞から感じられました。
更に本作は(純粋な)喜劇ではないのですが、基本的にユーモアやらドタバタ劇的な要素が多く、それがどうにも私の肌に合わない感じで、どうせ喜劇なら少し前に見た(同時代作品である)ルビッチ監督の『生きるべきか死ぬべきか』の方が私の好みには合っていたような気がします。
という事で本作を名作ではあるが苦手な作品と思う私は(『ピクニック』を見た時も思ったのですが)ルノワール監督よりも少しだけウエットな(若しくは甘い)人間なのかも知れません(笑)
映画講座で理解深まる
とても好きな作品なので何回も劇場で観ていますが、なぜいいのか長らく分かりませんでした。ウェルズの「市民ケーン」はダイレクトに良さが分かるのですが、この「ゲームの規則」の良さを人にうまく説明できません。しかしあらすじが分かっているのに、また観たくなる不思議な映画です。見る度に脚本がしっかり練られてる感じがします。今回、上映後に評論家の方の解説で理解が深まりました。この作品が作られたのは第二次世界大戦のさなかフランスがナチスに支配される前で、ある意味予見した感があります。
ベルトルッチ「暗殺の森」も同じ時代設定で、
ゴーストのような紳士淑女が着飾って舞踏会へ消えていくシーンが印象的でした。
ゲームの規則は4Kレストア版ができてるみたいですがフィルム上映だけ記憶にとどめたいです。できれば大きな画面でまた観たいです。
鵺(ぬえ)のような不気味さ
<映画のことば>
感じやすく徳高く
浮気心をなじる君
恨みごとは、ほどほどに。
心変わりは罪とでも?
翼あるのが恋の神。
あちらこちらに飛び移る。
<映画のことば>
社交界における愛とは、単なる幻想の交換。
皮膚の接触に過ぎない。
本作中のセリフにも時として現れる「規則」という言葉は、本来は「(規律の)明確さ」を意味する言葉なのですけれども。
しかしながら、本作では、かえって、仮面の下に隠されたような社交界の鵺的な性格を浮き彫りにするようで、それ故に、得体の知れないような、不気味さすら感じてしまい
ます。評論子は。
そのことを描き切った一本としては、良作の部類には入るんじゃあないかとは思います。
(追記)
愛憎の果てに死者まで出る騒ぎになるのは、なまじっかパーティーなんか開いたりしたからではないでしょうか。
そのことを悔いるどころか、それを「悲劇の出来事」「運命」「事故」として簡単に割り切り、「明日は喪に服する」ことで片付けてしまおうという姿勢に、違和感を超えて、何かそら恐ろしいような「非人間性」を感じてしまったのは、独り評論子だけだったでしょうか。
よくできた、馬鹿馬鹿しい映画
貴族の家でごちゃこちゃが繰り広げられ、思わぬ結末で幕を閉じる。コメディタッチの賑やかな映画。
が、見ていてうんざりしてきた。主な登場人物たちすべてが身勝手だったり気まぐれだったりで子供っぽい。先生や親のいないところでの幼稚園児のケンカを見ているような気分だ。何故わざわざそんなものを見なくちゃいけないの…。
しかし、全体にかなり上手くまとまっており、凝った作りだったとは思う。それぞれのイキイキした演技、風貌の面白さ。いろんな人が上手く組み込まれていたと思う。
クリスチーヌの夫は少しまともにみえた。誰かを責めずに騒ぎを収めたあのやり方は、洗練の極みと思えた。さいごの挨拶では、映画の観客のわたしたちにも、『皆さま、お目汚し失礼いたしました。わたくし共の実態は恥ずかしながらこのようなものでございます』と挨拶しているかのように思えた。
風刺映画ということなら、見ていてバカバカしく感じたのもしかたないか…。
誰か教えて!
完全無欠とはこの映画の事を指す!
ジャン・ルノワール監督による世紀の大傑作。
大戦前夜の上流社会をドラマチックに、しかし、その存在自体を嘲笑うかのように描いており、悲劇と喜劇がすばらしい配合で滲み出ている。
これはチャップリンの映画と少し似ており、恐らく彼の黄金期の芸術(「巴里の女性」、「街の灯」など)に唯一匹敵しうる作品である。
飛行士が思いを寄せる人妻とその夫との三角関係をベースに、夫の断ち切れぬ不倫相手、監督自ら演じる狂言回し的役柄の男、さらには猟場に忍び込んだ男と召使いの女(彼女の夫は猟場の監視である)とのロマンスを絡め、彼らを形容し難いほど無様に、滑稽に、しかし劇的に描く。
ピエロ的役割の大部分を担っているのが召使いたちだが、ラストの喜悲劇的エンディングを生み出すのもまた彼らなのである。
私が見た限りでは脚本、演出、カメラその他は全てにおいて完璧であり、この名作は映画の手本と言える。
・・・が、これに習い、この映画に近い完成度を持つ作品はあまりにも少ないように思える。
世界映画史上のベストテンに選ばれるべき、ジャン・ルノワールの傑作
私にとって、ジャン・ルノワール監督は難物である。「大いなる幻影」を初めて観た時など、何故感動出来ないのか不甲斐ない苛立ちを覚えた。素晴らしい映画であると全面的に認めながら、映画狂の愛情をもってしても、納得できる反応が生まれてこない忌まわしさは、それまで全く経験が無かったため強烈な記憶として残ってしまった。そして、今度はルノワール監督の最高傑作「ゲームの規則」である。私は、特に後半の展開にある映画の盛り上がりに、ため息交じりの感嘆を何度も反芻しながら、それは同じフランスの巨匠ルネ・クレールの畳み掛ける場面展開の見事なリズムとテンポの演出力に類似しながらも、この映画の本質に自分は深入りできないと意識した。それは「大いなる幻影」の初見の時に感じたルノワール監督の人間の器の大きさ、映画監督としての寛容さに圧倒されたことに関わる。この作品を支配するルノワール監督のこころの豊かさ(巨大な温もり)に、どっぷりと入り込めない。それは、私と言う存在がそれを享受するに相応しくないとする、自己批判を生む。また、フランソワ・トリュフォーは、ジャン・ルノワールを世界で最高の映画作家と断言している。これまでの私的な映画遍歴をもって、トリュフォー監督がルノワール監督の偉大さを尊敬することが、充分に理解できる。
どうも私という映画の僕(しもべ)は、映画は誰にでも理解できる表現で創造されなくては成らないと根底から考えているところがある。そうでなければ、チャールズ・チャップリンとジョン・フォードを映画の神様と決めつけないであろう。ルノワールの作品に対して、今満足な感想を記すことは不可能だ。ルノワールの映画は、私が狂喜し感動しても、饒舌になる世界と違っている。救いは、3年前にテレビで完全版の「大いなる幻影」を再見出来たこと。この時は感動のあまり涙を浮かべた。そして、この作品には、感動のあまり言葉を失った。
1980年 2月29日 フィルムセンター
1939年の制作年から43年経った1982年に漸く日本公開された。その2年前にあたる日本未公開時点のこの版は上映時間1時間29分で、完全版より17分短い。それでも凄い作品と感銘を受けたことは事実。世界の映画史上のベスト10に選ばれるべき傑作と思う。この年のキネマ旬報のベストテンでは、旧作ながら淀川長治氏がベストワンに選出している。
僭越ながら作家論みたいなことを言わせて貰えば、”ほとんどの芸術家は貪欲であり、そうでなければならないと思うが、ジョン・フォードとジャン・ルノワールだけは違う”と世界の様々な映画監督の作品を観てきて私が辿り着いた一つの結論があります。
コメディタッチからいきなりの悲劇、でも何もなかった様に社交パーティーは終了
貴族達がどいつもこいつも浮気していて、更にそこに、使用人たちの恋愛模様も絡んでドタバタ劇が展開。そこに、生真面目で一途な恋心抱く飛行機乗りの英雄が入ってきて、間違われたとは言え、まるで異物の様に撃ち殺されてしまう。このドタバタ劇から惨状への落差のあるストーリー展開はお見事だと思った。
貴族達によるうさぎ狩りで、何匹もあえなく撃ち殺されてしまう様が執拗に描かれていたが、その映像が後の悲劇を予見しているのも上手い。また、奥行きのある画面の手前と奥で三角や四角関係を見せつける映像も新鮮に感じた。
最後、ヒトが一人死んでいるのに関わらず、事故ということで、何でもない様に片付けられパーティは終了となるのも貴族社会なるものへの皮肉が効いている。ジャン・ルノワール監督自身が俳優として主演に近い役で出てるが、良い味を出していて驚かされた。
社会構造の変遷の予告
主にフランスはパリ郊外のコリニエールの別荘の宏大なお屋敷に野狩に集まった上流階級の人々と、そのお屋敷の使用人達のお話です
侯爵夫妻のW不倫のお話を軸に、奥様付きの侍女も色々とお騒がせで上も下も騒動が持ち上がるというもの
たいしたお話ではありません
題名のゲームの規則とは、社交界のラブゲームのお約束ごとのことです
嘘こそが社交界の規則であると監督自身が演じるオクターブが語ります
つまり監督は虚構こそが上流階級の実態であると語っているのです
終盤に英雄が、まるで野狩で撃ち殺される兎のように粗野な森番の猟銃で呆気なく撃ち倒されます
長い野狩シーンはこの殺人シーンのためにありました
英雄はご丁寧にも毛皮のコートを手にしています
将軍は侯爵が事故として事件を処理したことを肯定してこう語ります
階級を守ったのだと
このような人間は今にいなくなるだろうとも
本作は1939年の製作ですから第二次世界大戦突入の直前の作品です
本作で描かれた社会階級は戦争を経て将軍の予想した通りになったわけです
ラストシーンはそのお屋敷から去るのは、上流階級でもなく、その使用人でもない二人の人間です
オクターブとオスカー、その二人の人間は戦後の人間と社会を象徴し予告していたのです
つまり本作はドタバタコメディの娯楽作品の体裁でありながら、実はこのような社会構造の変遷を予告していたのです
本作が高く評価されている意義はそこにあるのではないでしょうか?
カメラワークが面白く独特です
長回しのパンショットで役者を追いかけます
その映像には奥行きをつけてあり、前景の役者の芝居を写していながら、背景に別の役者達が別の芝居をはじめています
カメラが切り替わって、今度はその背景の役者達が前景となり、また長回しのパンショットで歩き回るのを追いかけます
この繰り返しで、常に画面には前景と背景の二つの芝居が同時に進行してスムーズに繋がって物語が途切れなく続いて行くわけです
このようなカメラの働きで、観客の注意をそらすことなく最後まで退屈せず厭きずに観させてくれるのです
監督の力量はやはりただ者ではないと思いました
パーティーがずっと
とてもクラシカル、
たくさんの人が交錯し合い、すべてが転がるように連鎖していく。
鮮やかなその展開に見事に引き込まれてとても楽しい。
なによりも主人の紳士さに惚れ惚れ!
男の人はあああってほしい、優しく、優しく、気弱で、でも堂々と。
男女平等!と叫ぶより、ずっと自然で多様な男女の姿が麗しかった。
みんな適当で、奔放で、全ては気分次第。
それでも悩み苦しみ、泣いたり、わめいたり、だまってぐっと耐えたりする。
人間というのは、ウサギたちと同じように
撃たれてしまえば屍となる、儚い存在で、
だからこそ一瞬の人生を思うままに生きなければ、と
彼らはそんなこと考えている暇もないけど。
罵りあい、愛し合う。
同じ唇からありとあらゆる言葉が次から次へ、
現代と何ら変わらない、
人間の可愛らしさがきらきらと、
どたばたと、
ちりばめられた上品な作品に拍手!
全18件を表示