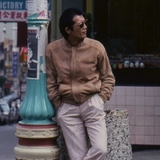クリムゾン・タイドのレビュー・感想・評価
全54件中、1~20件目を表示
嗚呼ジーン・ハックマン
アクション無いけど面白かったな 70点
前半は無能な上司の1時間で後半はデンゼル・ワシントンの活躍!これが見たかった!
潜水艦の中なのであまり物語の動きが無いけど、脚本で工夫されていたので飽きずに最後まで見れた
最後は無能な上司もまともになって早期退任されたので最後はスカッとした。
そんな上司に拍手したい
うん、
「学級会を、はじめます」(inオハイオ級潜水艦)
監督はトニー・スコット。
主演ジーン・ハックマンとデンゼル・ワシントン。
【ストーリー】
第一次チェチェン紛争(1994〜1996年)。
超国家主義をかかげたチェチェンの反乱により、ロシア強硬派が核の使用をほのめかし、アメリカをはじめとした世界に緊張がはしる。
嵐の中、あわただしく米海軍が対応、潜水艦アラバマが出航する。
アラバマの艦長、海軍たたきあげのラムジー(ジーン・ハックマン)の部下に、ハーバード大卒のエリート、ハンター(デンゼル・ワシントン)が副長に就任する。
潜航する潜水艦アラバマ。
行動3日目、キッチンで火災が発生、死者が出てしまう。艦員たちに動揺がひろがる。
6日目、司令部より第一警戒体制の指令。
ロシアの核ミサイル危機が、高まったという。
12日目、カムチャツカ沖にて潜水艦とおぼしき艦影を発見。
同時に司令部より、10基の核ミサイル発射コードを受けとる。
最終命令待ちのなか、前方の艦影はロシアのアクア級、ハンターキラー(対潜水艦戦力)と判別された。
眼前に敵、海面に浮上して通信が取れない状況の中、核攻撃を強行しようとするラムジーと、リスクを背負っても情報のアクセスを主張するハンターが衝突し、艦内が二勢力に分かれてしまう。
「世界でもっとも力のある三人、それは合衆国大統領とロシア大統領。そして、合衆国艦隊の弾道ミサイル搭載、原子力潜水艦の艦長である」
——冒頭より。
事前に知っておくべき知識として、かつてソ連には「死の手」という核反撃プログラムがありました。
これは外国、おもに西側からの攻撃には、全地球の敵基地へ無差別に反撃するっていうイカれたもの。
現ロシアもそのシステムを継承していると考えられていて、大国を核攻撃するということは、そういう結果を考えなきゃいけない。
これに関しては、アメリカや中国も近しいシステムを持っているはずで、つまり核兵器は一つでも撃ちこんだら、反撃が反撃を呼んで世界規模で猛烈なる破壊がひろがり、人類に破滅がもたらされるんです。
それが冷戦構造と呼ばれるにらみあいの根幹に横たわっていた、相互確証破壊とよばれた、「メキシカン・スタンドオフ」、つまり致死部位への銃の突きつけあい。
これが冒頭文の意味。
人類こわ。
そういった攻撃と抑制の葛藤を、潜水艦内でやっちゃうっていう人類の心の内面を、役柄わりふって撮った映画とも言えますね。
深夜番組の録画で見たんですが、やっぱデンゼル・ワシントンいいですな。
ジーン・ハックマンも、ゆうづう利かないオジイをやらせたら活きる活きる。
地上波放送だから吹き替えなんですが、二人とも専属の声優さんで安定感じゅうぶん。
ストーリーのメイン部分はこの艦長と副長の対立。
どっちつきゃいいのこの空気って焦げくさいフンイキ。
モロあれですよね、学級会で男女に分かれて紛糾するやつ。
じぶん日和見気質だから風見鶏でいたいのに、男女で対立されると否応なしにどっちか(おもに口げんか負ける方)に割りふられてしんどかった思い出。
艦の搭乗員たちも、ヒソヒソしながらどっちにつくのがいいのか、それぞれ身の振りかた考える。
『蝿の王』のような、閉鎖空間での心理劇からの衝突ストーリー。
実際のオハイオ級にはそんな能力がないので、脚本段階で海軍から協力を蹴られたそう。
しかたなしに外観は映像は自前でヘリ出して撮ったとか。
それでも専門用語は軍隊的、ダメージコントロールなどの撮り方もしっかりしていて、潜水艦ものとしてもつくりは手がたい。
艦内のセットもちゃんと潜水艦っぽいし、爆沈シーンはド迫力。
ツッコミどころもそんなにない、作りのよさが光ります。
日本版Wikipediaでは、脚本にタランティーノが記されてるんですが[要出典]で、英語版には見当たりませんでした。
ううむ…。
やっぱりアメリカは黒か白の国なのね。
結論を言うと、アメリカの原子力潜水艦、アラバマ号で、白人のシーン・ハックマン艦長と黒人のデンゼル・ワシントン副長が無線が切れて、命令が分からずおまけに水中なので何が起こっているか全く分からない中、お互いが対立し乗員が二つのグループに分かれてしまう。核ミサイルを撃つのか、撃たないのか?この点をめぐって対立する。
ロシアで政府軍と反乱軍が戦い、映画の最初では反乱軍が優勢。そこにアラバマ号が出動し第三次世界大戦に備える。ロシアの潜水艦が現れ、魚雷を先制されるが何とか「デコイ(魚雷を引き付けるおとり)」で何とか直撃は免れていたが、1発が近距離で当たり、浸水区画で作業している兵士数人が、残りの全員を助けるためハッチを閉じて犠牲になってしまう。ハッチを閉める命令を出したのはワシントンだった。
交戦中に無線を傍受するワイヤーが切れて命令書が「核ミサイルを・・・」と命令全てを確認できなかった。ハックマンは核ミサイルで攻撃すべき、と言うがワシントンは「命令書を確認するのが先決」と対立する。
他の兵士はどちらの命令に従えば良いのか戸惑う中、ワシントンは副長でありながら艦長を自室に閉じ込め、自分が指揮を執る。
しかし、厳密には艦長が潜水艦の指揮を執るので、艦長派の兵士が逆襲する。しかし、ワシントンも策をめぐらし、逆襲。
最後は艦橋で二人で対峙する。正式な命令書がハックマンが攻撃命令を出す1分前に届き、反乱軍が負けてロシアは政府軍に治められる。これによって、反乱軍が核ミサイルを撃つことはできず、ワシントンが指揮を執ることになった。
全てが終わった後、海軍本部に二人は呼び出されるが、ハックマンの証言のみによりワシントンは無実。しかも、ハックマンは引退し、アラバマ号の艦長にワシントンを推薦したのだった。
最後はハッピーエンドだが、艦長に副長が反抗するとか、普通の軍隊では起きえなかったことが起きたのが珍しい映画だった。
最後に「核ミサイルを撃つ権限があるのは、艦長では無くアメリカ合衆国大統領である」とナレーションが入り、暗にこの映画は命令違反だと言っているようだ。
ちなみに、クリムゾン・タイドとは潜水艦アラバマと同じアラバマ大学のスポーツチームの名前だそう。ハックマンが「アラバマ」と書いてある帽子を頻繁に脱いだり被ったりしているのは、アラバマ大学出身と言うことを言いたかったのかな?
潜水艦ものが好きだ。
ひっさしぶりに鑑賞。潜水艦映画大好き人間からしたら外せない作品では...
潜水艦の中はかなり広い‼️
ロシア愛国派がシベリア核ミサイル基地を占拠したことにより、アメリカは原子力潜水艦アラバマを出港させる。やがてアメリカ軍の核ミサイル発射をめぐって、たたき上げのラムジー艦長とエリート副艦長ハンターの間で対立が起きる・・・‼️自らの信念で指揮権を奪い合う艦長と副艦長、忠誠心かモラルかで真っ二つに割れる乗組員たち。常に攻撃の危機にさらされる緊張感、潜水艦の中という閉塞空間の極限状況での男と男の確執と闘い、それらが産み出すサスペンスはホントにスリリングですね‼️演技派デンゼル・ワシントンを完全にくってるベテラン、ジーン・ハックマンの貫禄がスゴい‼️まさに潜水艦映画にハズレなしの快作です‼️
面白いけど……
前提として
・トニー・スコット監督の他作品は未視聴。
・ヴァシーリイ・アルヒーポフ氏のことは未調査。
面白いけど、何かが足りない。
核ミサイルを搭載した潜水艦。このミサイルの発射はロシアとの核戦争開始を意味する。
その発射命令が出され、発射へのカウントダウンを迎えていた。しかし、そこに新たな、かつ不完全な命令文が届く。
このまま発射するべきか、その命令を待つべきか、艦長と副長の大ゲンカが始まる……!
といったストーリー。
艦長と副長のバチバチな意地のぶつけ合いや、若い船員たちの活躍、対比に次ぐ対比、アメリカ海軍への風刺、特撮シーンなどなど、見どころが沢山ある。
面会や緊迫感も良いし、好きなセリフもいくつかある。
……のだが、あと一歩何かが足りない。
"テーマ"と言える音楽が無いからなのか、描こうとするキャラクターが多すぎるのか、画になるシーンがあまり無いからなのかは、分からない。
二周三周すると新しい発見が出てくるが、あんまりワクワクはしない。
名作と呼ぶには何かが足りなかったと思う。
ちょっと変わった潜水艦サスペンスを観たい人にはオススメ。そんな作品。
もう通信機10台ぐらい積んどけよ!
核ミサイルてんやわんや映画として一番有名なのはやはり1964公開スタンリー・キューブリック監督の「博士の異常な愛情」でしょうか。
精神に異常をきたした空軍基地の司令官がB-52戦略爆撃機34機に対して、「R作戦」を実行するよう命令。「R作戦」とは敵の先制攻撃を受けて政府中枢機能が停止した場合に、下級指揮官の判断でソ連への報復核攻撃を行うことができるというもの。爆撃機は「特殊暗号無線装置」しか通信できず、その暗号は司令官しか知らない。なんとか暗号を入手し、爆撃機に攻撃中止命令を伝えるが、一機のみ「特殊暗号無線装置」が故障して中止命令が届かない…。
「博士の異常な愛情」はそんな設定の映画で、現場よりも大統領を含む司令部のてんやわんやがメインでした。
一方本作は現場がメインです。司令部の場面は一切出てきません。本作の現場は爆撃機ではなく弾道核ミサイルを積んだ潜水艦です。狭い艦内で火事は起こすわ、それで乗組員が死ぬわ、喧嘩はするわ、敵潜水艦に魚雷攻撃を受けるわ、沈没しそうになるわ、通信機は壊れるわ、艦長の犬は小便するわでもうてんやわんや。生真面目な副艦長ハンター少佐(デンゼル・ワシントン)はストレスmaxです。そんなところに司令部からロシアに対しての核攻撃命令が届きます。
命令に忠実にミサイルを撃とうとする艦長vs念には念を入れてもう一回確かめたい副艦長。二人の間には様々な対立要因が準備されています。
艦長vs副艦長
白人vs黒人
叩き上げvsエリート
じじいvs若手
実戦経験者vs未熟者
奥さんに逃げられ家族は犬だけvs妻子に囲まれるマイホームパパ
規律にこだわらないvs規律に厳しい
艦内はついに艦長派と副艦長派に分かれてお互いに武装し、内乱状態に。潜水艦という閉鎖空間で一触即発状態に陥った中で「ロシアの基地で核兵器に燃料を充填している」という情報が、さらに乗組員達の緊張を煽ります。で、すんでのところで通信機の修理が終わり「核攻撃中止命令」が届けられ予定調和的に一件落着。
「博士の異常な愛情」と本作の共通点は、「通信機」と「命令の授受」に人類存亡がかかっていること。「やっぱやめた」の命令がなかなか伝わらないこと。「通信ミスで人類が滅亡しちゃう!」というのをブラック・ユーモアで描いたのが前作、シリアスドラマで描いたのが本作です。製作費は前作180万ドルvs本作 5300万ドルと30倍ぐらいかかっていますが、面白さでは予定不調和の前作の勝ちでは?もう弾道核ミサイルを積んだ潜水艦には通信機を10台ぐらい積んでおいて欲しいものです。
本作のサブテーマである世代間の対立。単純な見方をすると艦長は「頭の固い老害」と悪者扱いされそうですが、ジーン・ハックマンの熱演のお陰で艦長は多面的で複雑な人格に描かれています。保守的な艦長もリベラルな副艦長もどちらも正しく、単純に正誤で線引きできないところが本作の怖いところでもあります。老いた艦長は若き副艦長に立場を譲り引退を決意するという健全なラストでした。
一方邦画で世代間の対立を描いた「魚影の群れ」という映画。レビューにも書きましたが若者は死に老いたものは栄えるという胸糞展開です。この映画の不健全さは誰のせいなのでしょうか。日本の若者にも明るい未来があるといいのですが。
潜水艦映画と見せかけてアメリカの縮図を描いた作品
とにかく良くできています。トニースコットの早いカットの切り替えは抑え気味ですが、テンポよく話が進み、飽きる場面がありません。アメコミのシルバーサーファーの作者はどっちが良いかなどの細かいギャグの伏線などもあり、楽しんで見れました。
白人VS黒人というわかりやすい対立はありますが、それよりも、いわゆる民主党VS共和党を描いた作品です。
ジーンハックマン扮する鷹派の白人艦長。帽子はトランプ大統領のように赤い帽子で、かつ、ジーンハックマンが権威を振りかざす場面では必ず民主党イメージの赤いライトが当たります。
対するデンゼルワシントン演ずる副長は、共和党のイメージの青いライト。
対立する場面ではグリーン。
決断を迫られるヴィゴモーテンセン演ずるウェップスは、最後、赤と青のライトに挟まれて苦悩します。
ちょっとあからさまですが、こうやって脚本に上手いこと落とし込んで、一つの作品にするのがハリウッドの良いところですね。最後の馬の話なんてウィットで本当に良いです。
日本だと踊る大捜査線みたいに、無関心な上司、無能な女性上司をコミカルに描いて、セリフで苦悩を叫ばせるみたいな演技しちゃうんですが、そういう安っぽさを嫌うハリウッド作品ならではな出来でした。
好きな作品です。
核ミサイル搭載原潜アラバマの艦長VS副艦長
多分本当に起こってそうな話
ジーンハックマン、うまいね。
潜水艦モノの傑作でありフィルム映画の名作
全54件中、1~20件目を表示