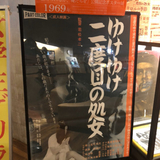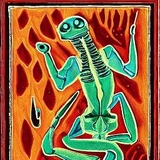カッコーの巣の上でのレビュー・感想・評価
全89件中、21~40件目を表示
インディアンウソつかない。 ”正しさ”が托卵するのは”システム”という狂気の雛か。
強制労働から逃れるため精神病院へと入院した囚人マクマーフィが、病院の抑圧と支配から自由になるために抗うアメリカン・ニューシネマ。
主人公、ランドル・パトリック・マクマーフィを演じるのは『イージー★ライダー』『チャイナタウン』の、レジェンド俳優ジャック・ニコルソン。
製作を務めるのは当時はテレビドラマなどで活躍していた、後のレジェンド俳優マイケル・ダグラス。
👑受賞歴👑
第48回 アカデミー賞…作品賞/脚色賞/監督賞/主演男優賞/主演女優賞(フレッチャー)!✨✨✨✨
第33回 ゴールデングローブ賞…脚本賞/作品賞(ドラマ部門)/主演女優賞(ドラマ部門)/主演男優賞(ドラマ部門)/監督賞!✨✨✨✨
第1回 ロサンゼルス映画批評家協会賞…作品賞!
第30回 英国アカデミー賞…作品賞/監督賞!✨
アカデミー主要5部門を制覇した、言わずと知れた名作中の名作。そして『シャイニング』(1980)と『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985)の前日譚でもある🤥
原作は1962年に発表された同名ベストセラー小説。翌年にはブロードウェイで舞台化もされており、その際マクマーフィを演じたのは名優のカーク・ダグラス。
この物語に魅了されたカークは10年にも渡り映画化に向けて奔走するも実現はならず。その後を継いだ息子のマイケルが父の夢を叶え、結果としてその作品は映画史に残る大傑作となったのであーる。
驚かされるのはそのリアリティ!
役者さんたちの演技が皆驚くほど自然で、クリストファー・ロイド(余談だが、本作は彼の映画デビュー作である)がいなければ本物の精神病患者を使って撮影したと思い込んでしまったかも知れない。
それもそのはず、本作は本物の精神病院を使ってロケ撮影をしており、ジャック・ニコルソン以外の患者を演じる役者たちは実際に10日間入院し、その流れのまま撮影を開始したらしい。
この徹底したリアリズムはキャスティングにも表れており、ロケ地となったオレゴン州立病院の院長ディーン・ブルックスはジョン・スピービー医師として映画に出演している。
本作のキャスティングで最も難航したのは巨漢のネイティブ・アメリカン、チーフ。彼を演じることが出来る役者が全く見つからず途方に暮れていたところ、ウィル・サンプソンという男の存在を人伝に知らされる。いざ初めてサンプソンという男と会したマイケル・ダグラスはその2mを越す巨体に衝撃を受け、その場で「こいつしかいない!!」とキャスティングを決めた。
面白いのはこのサンプソン、本作に出演するまで演技経験が0だったということ。彼はヤキマ市の森林警備隊員を務めているズブの素人だった。
先のディーン・ブルックスの件といい、本作は重要な人物を演技未経験者に演じさせており、それが不思議なほど絶妙にマッチしている。配役の妙ということもあるが、これは役者陣を実際に入院させることで生み出したリアリティが全体の演技バランスを上手く調節していたのだろう。
なんにしろ、役者陣の演技が非常に良かったことがこの映画の物語性を真に迫ったものにしていたのは間違いない。
そんなリアリティのあるキャラクターたちをぶち抜いて、過剰なまでの存在感を放ちまくるジャック・ニコルソン。既成の常識を粉砕しながら爆進する彼の姿はほとんどジョーカーそのものである🃏
『シャイニング』も『イーストウィックの魔女たち』(1987)も『バットマン』(1989)も、ハイテンションな狂人がジャック・ニコルソンの独壇場となったのはひとえにこの映画での彼の熱演があったからだろう。
一人だけ明らかに演技が異質だが、それは彼がこの物語上でも異質な存在だから。全てを薙ぎ払うヒーローだからこそ、彼の怪演が許されているのです。
とはいえクライマックス、彼がチーフの手にかかり自由を得る場面。あの枕をパッと取った時の顔、あれは完全に笑わせに来てるでしょ…😅ヘゲッ!というオノマトペが似合う圧巻の顔面力に爆笑してしまったのは私だけなんでしょうか…?
『シャイニング』の時もそうだったけど、ニコルソンは悲劇的だったり恐怖する場面だったりする時に過剰な顔芸によって笑わせにかかりますよね。トラジディとコメディは表裏一体だという哲学が彼の演技の根底にあるのでしょう。…いや知らんけど。
映画史にその名を残す悪役、ラチェッド看護婦長。
『ミスト』(2007)の宗教ババア、『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』(2007)のピンクババアと並ぶ、世界三大クソババアの一角をなす終身栄誉クソババアである。
「自分が悪だと気づいていない、最もドス黒い悪」とは「ジョジョの奇妙な冒険」の名言だが、ラチェッド看護婦長はまさにこれを体現している。
彼女が厄介なのは、自らの行為を「悪」だとは露ほども思っていないところ。彼女が作り上げた”完璧”なシステムこそが唯一の治療法であると信じきっており、そこに割り入る意見や価値観は全て夾雑物として取り除いてしまう。彼女の世界の中ではそのシステムは全き「善」に他ならず、それを阻むものは皆全て「悪」なのだ。独善的な ”正しさ”はシステムを生み出し、それはそこから溢れた存在を徹底的に抑圧し排除する。その正しさが行き着く先は考えを放棄し、波風を立てることを恐れる人々が列を成す狂気の管理社会である。
SNS社会となった現代にこそ、このメッセージは深く突き刺さる。世界を窮屈にしているのは悪徳ではなく行き過ぎた”正しさ”なのだ。
ラチェッド看護婦長というキャラクターはこの”正しさ”の持つ危険性のメタファーであり、だからこそ彼女は名悪役として今に至るまで語り継がれているのだろう。
また本作で描かれているのは精神外科治療に対する強烈なアンチテーゼ。
本作を観ればロボトミー手術や電気けいれん療法など、患者の人権を無視した精神外科療法に対して憤りを覚える事だろう。
脳みその一部を切除しちゃうロボトミー手術は流石に60年代を最後に行われていないようだが、電気けいれん療法は未だなお積極的に行われているという事実にはぶったまげた。頭に電気を流して鬱病とかの精神病を治療する、ってマジかっ!?そんなんほんとに効果あんの?
こういう治療法ってあまりに安直すぎる気がする。精神の病っつうのはもっと時間をかけて少しずつ回復させていくものなんじゃないんですかねぇ…。
劇伴についてはラチェッド看護婦長のかけるクラシックレコードがそのまま作品のBGMになるという演出がとられており、それ以外のところでは音楽が流れないためとにかく静かな映画である。
ただ2箇所だけ、登場人物の心が大きく動くシーンでBGMが流れるんですが、ずっーと静かな場面が続いてからの音楽だからそれが胸にドサっと迫ってくる!
その2つのシーンのうちの一つがエンディング。いや本作のエンディングは本当に素晴らしい✨
カタルシスとはまさにこの事!チーフによる水道台持ち上げは『ショーシャンクの空に』(1994)にも匹敵する最高の脱獄場面であります!!
静かな上テンポがゆったりとしているので、全体的にはとにかく地味なのだが、バスケットボールのシーンや空想野球観戦シーン、チーフのウソが明らかになるシーンなど、脳裏に焼きつく印象的な場面がところどころに配置されているため退屈することはない。アカデミー賞を総なめしたのも納得な、名作に相応しい堂々たる映画であると思います!!
…ただ本作のクライマックスは賛否が分かれるだろう。いくらロボトミーで廃人になったとはいえ、本人の意思を蔑ろにして殺しちゃうっていうのは…。
まぁチーフはネイティブ・アメリカン独自の宗教観というか価値観を持っているわけで、だからああいう行為に到ったというのはわかるんだけどやっぱりモヤモヤしちゃう。日本では2019年に「ALS患者嘱託殺人事件」なんてもんがあったから余計にねぇ…。
まぁモヤモヤするもんは仕方ない。映画はモヤモヤするために観ているようなところもあるしね。そこも混みで、鑑賞する価値は大いにある歴史的な一作であります!!
人間らしさとは
素晴らしい
怖いロボトミー手術
隔離された病棟!! 精神を病んだ人間の尊厳とは?
ジャック・ニコルソン演じるマクマーフィーは
刑務所の労働から逃れるために、精神病を
装っていました。
古い時代、1963年の精神病院に来たけれど
其処には生き甲斐を無くした患者たちがいました。
社会から隔離された、看護師たちからも自由を奪われた患者に生きる希望や自由を
与えようとして必死になるマクマーフィーの
人間らしい心を見ることができました。
刑務所みたいに厚い塀に囲まれた精神病院!
病院を脱出して患者たちをバスに乗せて走る場面は患者であっても人間として自由に
生きたい!
港から船を出す場面は、人生を謳歌したい
気持ちが伝わるシーンでした。
ラチェッド婦長を演じたルイーズ・フレッチ
ャーが光る演技でした。
患者に嫌われる役柄を体当たりに演じていました。
閉ざされた病棟にまだまだ患者に対しての
差別や偏見があった時代の古さ、理不尽さを
感じました。
病院で亡くなる患者の男性の1人。
その後の孤立したマクマーフィーの姿は
生きている屍のように見えました。
マクマーフィーと患者たちの友情、人間として
の生き方、死にいく様、尊厳を考える
ストーリーでした。
補足、昨年の9月に亡くなった女優の
ルイーズ・フレッチャーに追悼したいと思います。彼女自身、難聴でありながらアカデミー賞のスピーチは素晴らしいものでした。
【精神病を詐称した男が経験した、1960年代の精神病院の現実。人間の尊厳と社会の不合理を描いた作品。前半の明るいトーンからのラストシーンの恐ろしさに戦慄する作品でもある。】
■1963年9月のある日、オレゴン州立精神病院に1人の男ランドル・P・マクマーフィ(ジャック・ニコルソン)が連れられてきた。
彼は刑務所の強制労働を逃れるために狂人を装っていた。
マクマーフィは絶対的な権限を持つ婦長ラチェッド(ルイーズ・フレッチャー)が運営する病院に、さまざまな手段で反抗しようとする。
◆感想<Caution 内容に触れています。>
・途中までは、婦長ラチェッドが、病院内の規律を乱すマクマーフィの数々の行いを、歯ぎしりしながら観ている姿が印象的であった。
・マクマーフィが、それまで精神病患者たちが、病院の言いなりになって死んだように暮らす姿を変えて行く姿。
・それに感化されたように、精神病者たちの表情も生き生きとしてくる。口が利けないふりをしていたアメリカン・インディアンのチーフも、マクマーフィには口を聞く。
<恐ろしいのは、精神病患者たちに行きる意味を与えたマクマーフィが密かに脳の手術を受けたと思われる彼の額に刻まれたメスの後であろう。
彼はそれまでの快活な表情とは無縁の生きた屍のようになって、ベッドに横たわっている。
それを観たアメリカン・インディアンのチーフは、彼の頭に枕を押し付け、絶命させるのである。
勿論、彼を思っての行為である。
前半の明るいトーンからのラストシーンの恐ろしさに戦慄する作品でもある。>
タイトルなし(ネタバレ)
この演出家が『アマデウス』とは知らなかった。
先ずは1963年のワールドシリーズの話だから、1963年はベトナム戦争開戦前夜でそれを象徴していると思う。また、公民権法施行はまだで、国としての黒人に対する差別すら無くなっていない。従って、黒人の患者が一人もいない。しかし、主人公に施された処置はロボトミーと言う処置で、1950年代には施しが中止され、この時期には絶対に避けられていた医療処置だ。現在、この処置方法は違法である。また、考えた医学者はマッドサイエンティストと言われている。
従って、この映画公開の少し前の歴史に対する象徴的な寓話と見るべきだ。
白人の女性の婦長がアメリカの民主主義主義。
ネイティブアメリカンの逃走が、アメリカの歴史に対する贖罪。
ロボトミー手術がベトナム戦争を引き起こしてしまった国家に対してのアイロニー。アメリカと言う国家に対してこそ、ロボトミー手術を施せ!と訴えているようには見える。
だがしかし、至って難解な脚本であり、ストーリー展開が破綻している。だから、素直には評価出来ない映画だ。
アマデウスの演出家とは信じ難い。原作者が、アメリカンカウンターカルチャーの元祖見たいな方なので仕方ないとは思う。しかし、素直に共感は出来ない。
大学一年か浪人中に大森の映画館で『さらば冬のかもめ』と一緒に見たような気がする。がしかし、覚えていたのは、最後のシーンとバスケットのシーンのみだった。
物凄く残念な映画だ。
素晴らしいとしか言いようがない演技
刑務所から逃げる為に、精神異常を装って施設へと来た主人公。
しかしそこで見たのは不条理に患者達を抑制する実態だった。
嫌気がさして脱走を考えるが、不思議と共同生活をするうち「仲間」との関係が気になってくる。
そして周りも彼をきっかけに変化していく…
ジャック・ニコルソンとルイーズ・フレッチャーが凄いのはもちろんですが、他の登場人物 皆の演技がとにかく素晴らしい。
そしてストーリーも非常に考えさせられる作品。
衝撃的なラストシーン、飲み物を持つ手が止まり完全に画面に見入ってしまいました。
まさにこういう映画が自分の知らない世界を見せてくれて、日常において人との付き合い方を見直すきっかけになる。
映画史に残る不朽の名作!!
いやぁ、余韻が凄い……
映画が終わった後の拍手
生きる力を何度も権力に奪われる姿が心に響く
ここまで政治にへつらう映画があったか
この映画は精神病院が舞台で、「精神病」の患者たちが登場人物ですが、製作者側は一言注意書きを入れておくべきでした。「精神病」などはこの世界に存在しないのだ…と。それがこの映画の世界観です。
精神病を否定すれば、精神病院の患者たちへの治療は監禁や拷問にすぎません。
だから道化役マクマーフィはこうした不当な処遇を告発するような言動をつねにしている。それは身近な生活上の管理体制を素材にして、映画製作当時の東側における監視社会の不当さを訴えかけているようにも見えます。
しかし、精神病の存在を否定できなければ、精神病院の患者たちへの治療は病気から自由になるために不可欠です。マクマーフィがしていることは単なる治療妨害であり、患者を自由から遠ざけるだけの話です。むろん、これが現実なのです。
このような歪んだ世界観を、製作者側に無理やりでっち上げさせたのは、いうまでもなく「東西冷戦」でしょう。そんな世界政治の構図の中で、西側陣営の象徴たるアカデミーに、半沢直樹じゃあるまいに土下座して映画を作って、「よくできたでしょ、褒めてよ」と言っているのが本作です。
…小生はいただけませんね。
追記)
その後、ネットの情報から本作の下敷きにミシェル・フーコーの狂気論があることを知りました。
その狂気論とは、「狂気とは理性と対の知の形だが、近代的理性が権力を握るのに従い、医学的管理の下に社会から見えない場所に追いやられてしまった。しかし、時代の制約から逃げるには狂気の全面的開放が必要であり、それを実行したのがゴッホやニーチェであった」というものです。
なるほど、理性と狂気の対立という構図ならわかるかも…と思って再見しましたが、狂気の全面的開放が港のクルージングや深夜パーティで、時代を変える予兆がチーフの脱走にあるとは、小生には思えませんでした。比喩として何も意味を受け取れない。
「狂気の歴史」を読破しなければわからないのでしょうか。ならば、それは一般の娯楽映画とは言わないでしょう。
衝撃。
マクマーフィの破天荒なキャラクターのおかげで非常に
見やすかった。内容は濃厚だが、分かりやすい。
社会に馴染めないマクマーフィが仲間の希望の光となり、
元のカッコーの巣ではなかった
娯楽を強引に取り込み、婦長と対立しながら
仲間との絆を作り上げる。
病人にも分け隔てなく接するマクマーフィは現実社会では
アウトな人物でも、病院内では不思議と共感してしまう。
病院側との対立でマクマーフィの人間らしい足掻きから
だろうか。現実にこういう人がいれば、避けてしまう。
なのに映画になると共感してしまうのは不思議だ。
中盤〜終盤にかけてが素晴らしい。
カメラワークも全体像よりも表情を中心に撮る場面が
何箇所かあり、迫力のある映像に惹き込まれずには
いられない。散々楽しんだ朝、ビリーが自殺に追い込まれた
時にマクマーフィが逃げなかったのは仲間意識だろうか。
更に婦長の殺害未遂は彼の責任感からなのか。
序盤からチーフがよく映るので何かあると思っていたら
まさかクライマックスの主役を持っていくとは。
マクマーフィはロボトミー手術で人格を失った後の
チーフからマクマーフィへ愛ある殺害は衝撃だった。
チーフだけが脱出に成功したのは何とも皮肉だ。
最後に1つ、婦長の髪型どうなってるんだ笑
全89件中、21~40件目を表示