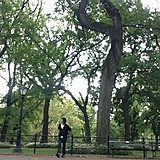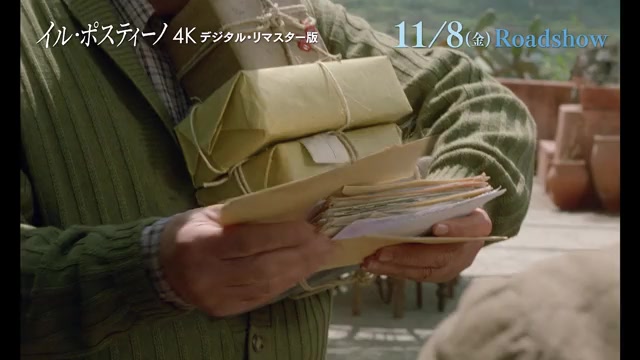イル・ポスティーノのレビュー・感想・評価
全16件を表示
言葉を紡げる幸せ、言葉を受け取れる幸せ。
⚪︎作品全体
『イル・ポスティーノ』を観て心に残るのは、単なる詩や恋の物語ではなく、「言葉」というものが持つ双方向の喜びだ。詩人ネールダと郵便配達夫マリオの交流を描いたこの映画には、派手な展開も、劇的な転換もない。ただ、島の静けさと波の音、そして二人が交わす言葉の積み重ねが、ゆっくりと人の心を動かしていく。そこにこそ、この映画の魔法がある。
マリオは最初、詩や言葉の力を知らない。ネールダに近づいたのも女性に伝える言葉を持たないから、彼のサインを求めただけだ。しかし、ネールダの語る言葉に触れ、彼が紡ぐ詩の断片を聞くうちに、マリオの中の世界が言葉によって広がっていく。海の音や風景、日常の中で見過ごしていたものが、ネールダの視線を通して詩となり、マリオの中で意味を持ちはじめる。
言葉を「受け取る」ことで、彼は世界を新しく知る。長年共にあった単なる海や山々が、言葉をもって別の景色になっていく。
だが、この映画が美しいのは、マリオがただ受け取るだけで終わらないことだ。マリオは次第に、自分自身の言葉を持ち始める。恋人ビアトリーチェへの思いを伝えるため、詩を真似るように始めた言葉は、やがて彼自身の切実な感情を伴うものへと変わっていく。ネールダから学んだ比喩や響きは、模倣のようでいて、少しずつマリオの実感を帯びたものになっていく。世界を新しく知る喜びから、自分の世界を表現する喜びへ。この変化の過程が、『イル・ポスティーノ』の最もあたたかい部分だ。
マリオにとっての言葉は、ただ恋を叶えるための道具ではなくなる。ネールダとの別れのあと、彼が自ら詩を録音し、海辺で音を拾う姿は、「世界を受け取った人間が、それを誰かに手渡そうとしている」ように見える。詩人から受け取った言葉を糧にして、今度は自分が世界を見つめ直し、言葉を紡ぐ。その過程で、彼は初めて島の風景や音を自分のものとして記録し、語り、愛する人や未来の誰かに伝えようとする。そこには、言葉を「受け取る」側から「紡ぐ」側への静かなバトンの受け渡しがある。
だからこそ、この映画は「詩の力を描いた映画」ではなく、「言葉が生きていく力を与える映画」なのだと思う。詩は特別な芸術家のものではなく、日々を生きる誰かの中に芽生えるものだと示している。マリオが感じた幸せは、ただネールダの言葉に酔いしれるだけのものではなく、自分の世界を自分の言葉で見つめ直せたことにある。それは、言葉を紡ぐ幸せであり、同時に誰かから受け取れる幸せでもある。
ラストに待ち受ける結末は、言葉の温もりとは裏腹に、社会の現実と暴力を突きつける。しかし、その余韻の中で響くのは、マリオが録音した島の音や詩の声だ。彼が受け取り、そして残した言葉や音が、時を越えて伝わっていくことで、観る者の心にも静かな灯がともる。誰かの生きた証が、言葉として、音として残る。その事実が、この映画の本当の「救い」になっているのだと思う。
『イル・ポスティーノ』は、言葉を贈ることと受け取ること、どちらの喜びも教えてくれる。人と人が出会い、互いの世界を言葉で開き合うことの尊さを、これほど穏やかで鮮やかに描いた映画はそう多くないだろう。観終わったあと、誰かに手紙を書きたくなるような、あるいは波の音に耳を澄ませて自分の中の言葉を探したくなるような、不思議な温度を持った作品だ。
⚪︎カメラワークとか
・海や空を映すときの明るさ、広さに対して屋内の狭さ、猥雑さ。マリオが世界の美しさと同居していながら、目の前のことにだけ目を向けているような、そんな序盤の物語とシンクロしているようだった。
・終盤、ネールダが再び島へやってきた時の時間経過がなにもなくて、思い切った演出だった。マリオの死を唐突に話した後、ラストでその瞬間を映すという構成も面白い。
・家の窓から父の仕事風景を見つめるマリオのカットが良かった。いつもの家からいつもと同じ風景だけれど、そこから感じる感情の表現は少し変化がある。
⚪︎その他
・劇伴が良い。素朴なマリオと美しい景色を包み込むような感覚。
・マリオが死んでしまったのは、一瞬そこまでやるか、と思ったけど、それによって言葉の力を強調させるラストになっていた。
郵便配達は二度ベルを鳴らさない‼️
素朴で心暖まってほのぼのとした微笑ましい佳作‼️チリから亡命してきた世界的詩人ネルーダが、ナポリの小さな美しい島に滞在する。ネルーダへのファンレター専用の配達人となった青年マリオは、ネルーダとの交流の中で、心を通わせ、詩を理解し、恋人も手に入れる・・・‼️「ニュー・シネマ・パラダイス」と同じく、ネルーダ役フィリップ・ノワレの存在感がホントに大きいですね‼️終盤、島を去っていくシーンも実にいい味出してる‼️素晴らしい出会いが人生を変えるというシンプルなメッセージに胸打たれまくりです‼️
ご冥福をお祈りいたします
イル・ポスティーノ(il postino)はイタリア語で「郵便配達人」、主人公の島の青年マリオ(マッシモ・トロイージ)の職業ですね。
1950年代のイタリアの小島にチリの詩人パブロ・ネルーダ夫婦が疎開、彼に多くのファンレターを届けるのがマリオです。
詩人パブロ・ネルーダは、1971年にノーベル文学賞を受賞した実在のチリの詩人で一時祖国を追われナポリ湾のカプリ島に身を寄せていたそうです。ただし、マリオとのエピソードはアントニオ・スカルメタの小説でフィクションです。
パブロの人柄に惹かれたマリオは彼の詩集を熱心に読み、詩心を学びます。師弟関係の二人は次第に友情で結ばれてゆきます。心優しい詩人と向学心に富んだ善良な青年に美しい島と心洗われるような美作でした。
ただ、一目ぼれの島の食堂で働くベアトリーチェとも結ばれ息子を授かったマリオは集会の暴動騒ぎで命を落としたようで残念。驚いたのはマリオ役で共同監督、脚本のマッシモ・トロイージさんも心臓病を患っており撮影終了からわずか12時間後に41歳の若さで夭逝、これが遺作となったそうです、ご冥福をお祈りいたします。
【イタリアの小さな島で暮らす純朴な青年が、チリの高名な詩人と出会い、詩の素晴らしさを学び人間として成長する様を描いた美しくも切ない作品。】
■南イタリアの小さな島に、祖国・チリから亡命した高名な詩人、パブロ・ネルーダ(フィリップ・ノワレ)が滞在することになった。青年・マリオ(マッシモ・トロイージ)は、世界中から彼に届く届く手紙を配達するための専属臨時配達人として採用される。
彼はネルーダの人柄と知らなかった詩の世界に惹かれ、友情を育んで行き、その過程で恋する女性ベアトリーチェ・ルッソ(マリア・グラツィア・クチノッタ)を美しき言葉で射止め、人間としても見識を広げていく。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・マリオを演じたマッシモ・トロイージが、冒頭では漁にも出ない覇気のない青年であったのが、高名な詩人、パブロ・ネルーダの専属臨時配達人になり、彼から”暗喩”など、言葉や詩の素晴らしさを学ぶにつれ、表情が生き生きとなって行く様を、病を抱えながら瑞々しく演じてる。
彼の、詩の素晴らしさに気付き、様々な”暗喩”を天賦の才で紡ぎ出していく際の眼の輝きが素晴しい。
・そして、彼は居酒屋で働く美しき女性ベアトリーチェ・ルッソの心を射止めるのである。
・だが、パブロ・ネルーダはチリの情勢が変化した事で、帰国してしまうが、マリオは彼への想いを抱き続け、イタリアで共産主義の推進者となって行くのである。一方、マリオは又自分が住む島の様々な自然音を録音し、パブロに残していたのである。
<5年後。パブロ・ネルーダが夫人と戻ってきた時にマリオは居ない。だが、居酒屋にはベアトリーチェ・ルッソと、マリオソックリの男の子が笑顔で待っているのである。
そして、録音機から流れるマリオが録音していた島の美しい自然音。
今作は、イタリアの小さな島で暮らす純朴な青年が、チリの詩人と出会い詩の素晴らしさを学び人間として成長する様を描いた美しくも切ない作品なのである。>
郵便配達は自転車のベルを鳴らす
JR有楽町駅の隣のビックカメラは、元はデパートのそごうで、その7階に座席数1,100の読売ホールがあり昔は良く試写会に行った。「ディアハンター」や「クレイマー、クレイマー」、劇場公開が中止になった「ブラックサンデー」もここの試写会で観た。その8階に映画館が出来て20年経つがその映画館には入った事がなかった。
12月26日(木)
その8階の角川シネマ有楽町で「イル・ポスティーノ」を。
実在したチリの大詩人パブロ・ネルーダ(1971年にノーベル文学賞を受けた)がチリを追われイタリアのカプリ島に身を寄せた史実を元にした小説の映画化で製作30周年記念4Kデジタルリマスター版のリバイバル公開。初見。
ノーベル文学賞候補にも上がるチリの大詩人パブロ・ネルーダが祖国を追われ南イタリアの小島に滞在する事になり、世界中から彼宛に届くファンレターを山の上の彼が住む家に配達するために臨時配達人が募集される。
漁師の息子のマリオ(マッシモ・トロイージ)は父親の漁を手伝っているが、漁師が好きではない。郵便局の募集に応募して配達人になる。
郵便配達人として手紙を届けるうちにネルーダ(フィリップ・ノワレ)に詩について教えてもらい、詩の隠喩を教わり自分も詩作に励むようになる。
マリオは島の食堂で働くベアトリーチェに恋をするのだが、…。
マリオに覇気が無いと思ったら演じたマッシモ・トロイージはアカデミー賞にもノミネートされたが、心臓病で撮影終了の12時間後に41歳で亡くなった。
思った程私の心には響かなかった。マリオがネルーダの事を思っていても、チリに帰る事が出来たネルーダからは秘書の事務的な手紙しか来なかったり、やっと島を訪れたネルーダのラストも今ひとつ感動を呼ぶものが無かった。音楽がモリコーネじやなかったから?
あの録音に使っていたカセットテープみたいな機器はイタリアには本当にあったのかしら?
幸せな人生では
島の、結構いい年の、漁師の父と二人暮らしの独身男性マリオが、女性にモテたい一心で(イタリア男って…)、女性に大人気の亡命詩人パブロの事実上専属郵便配達員に応募する。
引っ込み思案というけれど、躊躇することなく面接にGO、思い立ったら行動が早い。
無事採用されてモテる秘訣を学ぼうと近づいたが、徐々にパブロの人柄と詩の魅力に取りつかれて、どっぷり傾倒していく。
マリオは少々オツムが弱い人に見えるが、心から湧き上がってくるものを表現するために言葉を探し、表現する。お世辞も媚びへつらいもない。感性が大変豊かで鋭いが、ようやく読み書きができる程度で学はないので、これは彼が持っている生来のギフトだ。
優れた詩人であるパブロにはマリオの感じること、言わんとすることが、すんなり理解できる。一見噛み合わないようだがちゃんと噛み合っているふたりの会話が面白くて、時々可笑しい。
ふたりの関係は、師弟ではなくもっと対等で、トモダチ、がふさわしいと思う。
こころの奥底にある感覚や感性を、ああそれ、それだよね、と共有できる同志のようで、パブロはマリオを「親友」と呼ぶのはもっともなことだと思った。
但し、イタリア男性には女性を口説くのが人生の最大関心事のひとつだが、チリ人にはどうなんだろう?
ベアトリーチェは、あの美貌とスタイルとおっぱいなので、彼氏のひとりやふたり、3人4人くらいいるだろうと思ったら、耳元で詩を囁かれてメロメロになるほどのおぼこい純情娘!
叔母の鉄壁の守りがあるからなんですね、マリオはすでにいいトシなのにあんな若い美人と結婚、めっちゃ幸運なおじさんです。そしてやっぱり思い立ったら行動が早い。
パブロと交流しだしてからマリオにどんどん力が漲ってくるようで、引っ込み思案で弱々しい男から、共産党や共産主義を語るようにもなる。あきらかにパブロの影響だ。
パブロは誠実なヒトのようだし、マリオを親友と思う心に偽りはないと思うが、世界的有名人で忙しいので、マリオが彼を思うほどには心を残していないのが切ない。
マリオが作っていた「島の美しいもの」ひとつひとつが素晴らしい。
作品番号何番、と読み上げながらつぎつぎ現れる「美しいもの」
もうすぐ生まれる子どもの心音もある。この感性。いくつでも、ずっと見ていたかった。
郵便局長が全面協力、共産党嫌いの司祭様まで協力しちゃって微笑ましいが、あれがパブロのもとに送られることはなかったんですね
「網」の連想が「悲しい」になるのは、とうさんの網に収穫が少ないからだったようです。
親友の主義に沿った共産党の集会で、自作の詩を読み上げる。
美しいもの、の締めくくりは、この「詩の朗読」だったはず。
どれほど晴れがましいことだったか。群衆の足元に落ちた詩の原稿が哀しかった。
パブロ夫妻が居酒屋を訪れるところからの、マリオの最期を語るエピソードの見せ方が秀逸。
それでも、マリオの生涯は、幸せなものだったと思う。
頭も身体も弱そうだが、生きる知恵には長けている。
父がどれほどマリオを愛していたか、息子の結婚式で別人のように饒舌になったところでよく分かる。若く美しい、一目惚れの相手と電撃結婚して子宝にも恵まれ、臨時採用先の郵便局長はその後も良きトモダチ、仕事はあるし、なにより魂の親友と巡り合った。
残された人たちは、彼を愛していた分たまりませんが。
パブロ・ネルーダは実在の人物で、この映画はときの政権によって共産党が非合法化されたため、故国チリから国外逃亡を余儀なくされた彼のイタリア亡命時代を題材にしたものらしい。
舞台となった島も架空のもので、話自体はフィクションだろうが、このように膨らませたのが素晴らしい。
島の自然と風景、佇まいが美しく、効果的。
この映画の、もう一つの主役と言って良いくらい。
行ってみたいと思いました。
ポエジア 詠まれなかった詩
人が思わず詩を口ずさんでしまうのはどんな時だろう。愛しい人を想うとき、故郷の海の香りをかいだとき、さざ波の音を聞いたとき、まぶしいばかりの日の光に照らされたイタリアの故郷の大地を想うとき、そしていとおしい映画を見たとき、そんなときに人は心に詩が浮かんでくるのかもしれない。万物を感じ取る心があるのなら誰もが詩人となれるはず。
実在のチリの詩人パブロ・ネルーダが母国を逃れ、青の洞窟で有名なイタリアのカプリ島で暮らしていた事実をもとにした物語。
ネルーダは常に素朴な人たちのために詩を詠んだという。外交官でもあり共産主義者でもある彼は資本主義が生みだした貧困に苦しむ祖国の人民のために戦った。その波乱万丈の人生においてひと時の安らかな時間を彼はイタリアの小島で過ごし、そこで一人の郵便配達員と交流を重ねた。時が止まったかのようなのどかな島でネルーダは心豊かにその時を過ごせたことだろう。
漁業以外産業のない貧しく小さな島で数少ない読み書きができたマリオはネルーダ専属の配達員となる。日々の配達の中でネルーダと交流を深め次第にマリオは詩に魅了されていく。そして彼はネルーダの思想を受け継いでいく。
共産党の集会でマリオはネルーダから学んだ成果として詩を読み上げるはずだった。しかし弾圧により彼は帰らぬ人となってしまう。それを知ったネルーダはイタリアの弟子を想いただ彼を悼む。
マリオの遺したテープには島のあらゆる自然の営みの音が残されていた。それはそのまま詩に書き替えられるために残された島の記録。それを聞かされたネルーダはマリオとの想い出、そしてこの島でのひと時の暮らしを想い詩を詠んだことであろう。
そんなネルーダもチリで起きたクーデターにより命を落としてしまう。世界初、無血で民主的に社会主義国となったチリではあったがアメリカの謀略によるクーデターにより人民の希望は打ち砕かれてしまう。その後チリは独裁政権により多くの人民が虐殺され、暗黒の時代を迎える。世界初の新自由主義の実験場とされたチリはさらに貧富の差が激しくなりネルーダが目指した人民のための国の建設の夢は打ち砕かれる。
近年、バイデン政権下で当時の機密事項が公開されこの時のアメリカの詳細な関与が明るみになり、病死と言われていたネルーダの死も毒殺だったという事実が明らかとなった。
西欧諸国の植民地支配による搾取に苦しめられてきた人民のために戦ってきたネルーダの詩は同じく人民のために戦う革命家たちにも愛されてきた。キューバ革命のチェ・ゲバラも彼の詩を好んで読んでいたという。
資本主義的帝国主義に抗い続けたネルーダの精神は今も多くの人々に受け継がれている。
本作に入れ込みマリオ役を演じたマッシモ・トロイージの執念が本作を名作たらしめた。劇中でマリオが命を落としたように彼も撮影終了後の12時間後に帰らぬ人となる。心臓病を患いながら撮影に挑んでいたのであった。
革命に命を懸けたパブロ・ネルーダ、そして彼の物語を命を懸けて紡いだマッシモ。そんな映画にかかわった人々の魂が本作を名作たらしめたのだった。
「何でこいつが俺より先に…」 by E・モリコーネ(うそ)
実在したチリの詩人のイタリア亡命時代を元に描かれたヒューマンドラマ。
反体制の知識人が政治的迫害によって移り住んだ僻地で地元住民と交流するという物語の骨格は、F・ロージ監督の『エボリ』(1979)と似ているが、神すら降臨を躊躇する荒涼たる寒村に流刑されるドン・カルロと違い、本作のドン・パブロは妻を伴って亡命してきたナポリの小島でワインを嗜みながらタンゴのレコードに合わせてダンスに興じるなど、何だかバカンス気分。
一方で、観終わったあとに宗教的感動にも似た不思議な余韻を味わえる『エボリ』に対し、本作では予想外の結末が用意されている。
チリ出身の実在した詩人パブロ・ネルーダに扮するのはフランスのベテラン俳優フィリップ・ノワレ。『ニュー・シネマ・パラダイス』(1989)の映写係アルフレードとは異なる役柄の知識階級を優雅かつインテリジェンスに演じている。
家業の漁師を継ぐことを嫌っていた地元の男性マリオは文字が読めるおかげで、亡命中のネルーダ宛てに世界各国から集まる膨大な郵便物を届けるための彼専属の配達夫として雇われることに。
当初は相手にしていなかったマリオの感性に気付いたネルーダは彼に詩作の手ほどきをし、マリオは次第に詩藻を開花させるが、彼のなかで目覚めたのは詩のセンスだけでなく…。
マリオとネルーダの心の交流や、島の美しい娘ベアトリーチェとのロマンス、許されて帰国が叶うネルーダとの別れなどの人間模様が南イタリアの眩しい陽光の下、穏やかに紡がれるので、ラストのマリオの悲劇は唐突な印象。
ネルーダの影響で共産思想に傾倒していったマリオが共産党の集会で詩の朗読を試み治安部隊の暴行を受け死亡する結末は、チリに帰国後ピノチェト政権によって虐殺同然に命を奪われるネルーダの暗喩なのだろう。
作中のネルーダはマリオの詩の才能に着目するあまり、自身に感化されて彼が左翼思想に芽生えたことに気を払っていない。
妻に捧げた詩をベアトリーチェとの逢瀬で使ったマリオを咎めた際に、「詩は創った人のものではなく、詩を必要とする人のためにある」と反論されたネルーダは一本取られたぐらいの反応しか示していないが、マリオのこのセリフは彼が共産主義に目覚めたことの証左でもある(詩の箇所を物質的な価値の言葉に置き換えれば分かりやすい)。
素朴な演技でマリオの純朴さや一途な人柄を体現したマッシモ・トロイージが本作の撮了12時間後に他界した逸話は有名。結果的に本作は実在のネルーダだけでなく、トロイージへのレクイエムにも。
ラストシーンで後悔に苛まれて海辺をさまようネルーダの姿は、トロイージを作品に殉じさせたことへのM・ラドフォード監督自身の自責の表明にもみえる。
作品に抱く感慨は人それぞれだろうが、自分はこの映画のラストがS・レオーネ監督の『夕陽のギャングたち』(1971)と、どうしても重なってしまう。
亡くなったトロイージの主演男優賞を含め、本作は複数の部門でオスカーにノミネートされたが、最終的には作曲賞のみ受賞。
音楽を担当したのはルイス・エンリケ・バカロフ(媒体によって名前の表記がさまざまだが、作品のオープニング・クレジットに従えば上記どおり)。
アルゼンチン出身ながら人生の大半をイタリアで過ごした彼はマカロニ・ウエスタンのサントラで多くの傑作を残し、共作もあるエンニオ・モリコーネとは師弟関係(だったと思うんだけど、今SNSで調べても詳しい話出てこなくて…。でも、使い回しのマエストロぶりはモリコーネ譲り?!)。
本作以前のバカロフの実績を知る人に「ほかの代表作は?」と訊けば、おそらく多くの人が択ぶのが「続・荒野の用心棒」(1966 原題 Django)。
短期間に低予算で製作され本来ならB級映画扱いの筈が、タランティーノをはじめとする多くの映像作家に愛され、ついにはリブートのTVシリーズまで登場した作品の魅力の一つは間違いなくバカロフが作曲したサントラにある。
同作に提供した哀愁漂う主題歌や情念まみれの曲と異なり、本作ではバンドネオンなどのタンゴの要素を採り入れた軽快で抒情豊かなサウンドを、波の音やウミネコの鳴き声などの効果音と調和するよう過剰にならない範囲で使用している。
悲劇的な結末で作品が暗い印象になるところを美しい音楽で和らげている点も、『夕陽のギャングたち』(モリコーネが作曲を担当)に通ずる。
本作でバカロフがオスカーを受賞したことを知って「モリコーネより先に?」と思ったのは、自分の率直な感想。
2017年没。
五歳年下のバカロフの訃報に接して、「何でこいつが俺より先に…」とモリコーネが思ったかは不明。
4Kデジタルリマスター版で久しぶりに観賞。
作品の性格上、セリフ過多なので、字幕が顔のアップに重ならないよう、もう少し工夫して欲しかった。
「詩は必要としている人のもの」なのか?
マリオがパブロの詩を使ってベアトリーチェを口説いたのが最後まで引っかかってしまった。「詩は必要としている人のもの」というのがマリオの考えだ。なるほど、そういう考えもあるかもしれない。共産主義的な言い方をするなら、詩という財産を共有する、ということかな。
それでもやっぱりマリオの考えには賛成できない。創作物というのは作り手の個人性が宿るもので、それを自分のものかのように使うのは作り手に対して敬意が無さすぎる。どれだけ稚拙な表現になっても、マリオは自分の感性を懸命に働かせ、必死に言葉を生み出してベアトリーチェを口説くべきだった。人の言葉を借りて思いを寄せる人を口説いても、嬉しいとは思えない。
ただ、最後の最後でマリオは詩人になったと思う。島の海や風、息子の心音を録音するという発想に感動した。彼の感じる島の美しさを、自分の声とともに残すという姿勢は正真正銘詩人。実際に島の風景や音、島民たちは様々な美しさを備えていたと思う。
悲しいラストだったが、海岸を歩くパブロの姿に深い余韻を感じる。
余計な情報が作品性を損なう
主演の、配達人役のマッシモ・トロイージはこれが遺作になったということを聞き、感動のハードルが上がってしまった。
知らずに見ていたら気にならないレベルだったと思いますが、とにかくしんどそうに動くんですよ。マッシモ・トロイージが。
恋人役の女優さんも、無駄にエロチックで、感動の方向性とは、やや違った方向に作品の評価は行ってしまったと思いました。
ことさらに「泣ける」を強調されると、こういう結果になりがちですね。
2017.5.4
タイトルなし
期待していたがそれほど感動せず。主人公にそれほど魅力を感じなかった。もっと若い人が演じれば違ったかもしれない。偉大な詩人を通して青年?が成長していくストーリー。ラストには亡くなっている。
美しいイタリアの島
大昔に観てなんとなくよかった映画、を再確認するべく再鑑賞。
良かった。
美しいイタリアの島に、突如降り立った偉大なる詩人ドン・パブロ。
仕事もなくパッとしないマリオの人生を、詩人が大きく変えることとなる。
詩人がチリに帰国して数年、残念ながら2人の再会は叶わなかったけれども、詩人は島を、マリオを、忘れてはおらず、マリオもそうと信じてた。2人の間にあった絆の深さと、素朴で美しい島の風景がじんわり絡み、心に残ります。
普段、詩にはあまり触れることもなかったけれども、ドン・パブロのわかりやすいレクチャーのおかげで、ちょっと興味が湧いてきました。なんか読んでみよう。
イタリア映画のあたたかさと残酷さ
まさにイタリア映画。雰囲気、景色、なんとも言えないあたたかさと残酷さ。
純粋なマリオが愛おしいキャラクター。ネルーダに影響を受けつつ、彼が去ったあとも彼に心酔するというわけではなく、忘れられたように思えても彼に感謝し続ける姿が良かった。
波の音や教会の鐘、夜空、お腹の子供の音など、島のきれいなものを録音するのが素敵だった。
涙が止まらない・・・
まずは地中海に面した島の風光明媚なところに心奪われる。漁業メインの小島。水道すら引いてなく、月1回くる給水船が頼り。そんな静かな村だから若者も少ないのだろうか・・・
映画館のニュースで見たパブロ・ネルーダ。彼が女性に人気だということも気になるマリオは憧れてしまう。パブロも共産党員、郵便局長も共産党員、いつしかマリオも共産党を名乗っているほどだけど、政治色はほとんどない。
一軒だけの郵便配達。週に1回映画が観れる程度の給料じゃ大変だろうに・・・と思いつつも、毎日配達し、詩について学んだことはかけがいのない財産。隠喩という言葉がそのままコミカルに使われているところも面白い。
島で一番美しいのは・・・ベアトリーチェ・ルッソ!君の笑顔は蝶のように広がる。印象に残る台詞ば多いけど、映画全体に渡ってそのまま詩だったようにも感じてしまう。
マリオとベアトリーチェの結婚後、島を去ったパブロ。どの記事を読んでも島の人のことに触れてない。寂しい思いもあったけど、第二の故郷のように感じていたことは間違いないのだろう。
残された録音されたマリオの詩。そして、自然をそのまま音で表現しようと集めた苦労も伝わってくる・・・個人的な思い出もあるし、なぜかこのエピソードが一番好きだ。
エンドロールに亡きマッシモに捧ぐ・・・などと書かれると涙が止まらなくなる。病気に蝕まれながらも製作にこぎつけたという執念はすごい。
いつ見ても名作!!純真と友情と愛は永遠です
大学生の時に劇場でみて、すっかりお気に入りに。DVDも買って、最近思い立ってまた見てみました。
本当にいつ見ても名作です。「
人は良いけど、無教養で怠惰な生活を送るマリオが郵便配達の仕事に就き、パブロネルーダへの配達を始めることが物語の始まりです。
マリオはネルーダと交流を深め、詩に触れることで豊かな感受性を持つようになり、成長を遂げていきます。
ネルーダが浜辺で隠喩について語るシーン、郵便物を届けに島を自転車でこいでいくシーン、とにかくすべてが島の美しさと映像の美しさに彩られていて、不思議な詩的な感覚すら覚える映像もとてもよかったです。
マリオはネルーダの詩に見せられつつ、島のレストランのウェイトレスのベアトリーチェに恋に落ちながらも、ベアトリーチェに愛を伝える言葉をしらない、ネルーダに愛を伝える詩を書いてほしいとせがむのですが、このだめっぷりも本当によいですね。
さらには、ネルーダが妻に送った愛の詩をベアトリーチェにささげてしまうほどのだめっぷり。
ネルーダが人の書いた詩をあたかも自分のもののように使うなんて…的な非難をマリオに浴びせますが、マリオは「詩は書いた人間のものではなく、必要としている人間のものだ」と言い返し、ネルーダは閉口。このシーンを最初に見たときは、「本当にだめな人だなぁ…」とがっかりしましたが、クライマックスへの伏線だったことも、とてもすばらしいな…と。
やがて、別れがきてネルーダは母国に帰ります。
ここでも、マリオはネルーダが自分との友情だったりを何か母国で話すのでは…それがニュースとして聞こえてくるのでは…手紙とかくるのでは…と期待を寄せつつ、きたのは「荷物をおくってくれ」という手紙。マリオはここでがっかりして、ネルーダとの友情について考えてしまいます。本当に、子供みたいに純粋で絵に描いたようなだめっぷりが本当に憎めなくて好きです。
ネルーダの家にいったマリオはネルーダの残したテープを聞くや否や、島の素敵な場所の音を集め、それを歌った詩を録音し始めます。
自分こそネルーダに感謝をしなくてはならないことに気づいた瞬間でしょうね。純粋だからこそ素敵です。
最後は労働者の集会で命を落とすわけですが、ここでマリオはひとつの詩を読むはずでした。
「詩は書いた人間のものではなく、必要としている人間のものだ」ということがここにつながっていたのでしょう。
ネルーダとの出会いによって、成長し、家庭を持つことができただけでなく、言葉を必要としている人のために詩を読むまでにいたったマリオがここで命を落とすというのが、なんとも悲しい終わりだなぁと何回見てもエンドロールでないてしまいます…
純粋な心と素敵な島の風景、詩的な映像、どれをとっても名作で、本当に最近こういう話ってでてこないよなぁ…と感じてしまいます。
全16件を表示