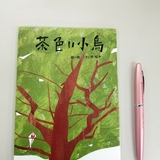「たかが14歳、されど14歳。命への責務。」火垂るの墓(1988) とみいじょんさんの映画レビュー(感想・評価)
たかが14歳、されど14歳。命への責務。
贖罪すべきこともあったかもしれないが、それでも少年は逃げなかった。
今なら中学2か3年生。家族なんて放って、自分のことに集中して、学業・趣味・友情・将来に思いを馳せ、没頭し、悩み、もしくは謳歌する年代。
反面、この映画で描かれているのは、国民学校初等科を11歳で卒業してすぐに働いていた子も多かった時代。16歳の特攻隊員・ひめゆり部隊員もいた。今よりは、”子ども”ではなく、自分のことは自分でと”半人前~一人前”の力が要求された時代。
高畑氏はこの時代を生きた。
だから、焼夷弾のシーンなど、他に類を見ない迫力のあるシーンとなっていると聞く。
悲惨さばかりではなく、笑いのある日常の両方の描写が、この映画の価値を高めているとも聞く。
けれど、当事者だからこそ暗黙の了解として描かなかったのか、わざと清太と節子の生活を際立たせるために描かなかったのか、意外に周りの人々の”生活”が描かれていない。『この世界の片隅に』他、この時代を扱った映画を見て、イメージしないとわからない部分も多い。
将校の家族として比較的良い環境で暮らしていた清太と節子。
そんな家族にも、その日暮らしの人にも、区別なく降り注ぐ焼夷弾。
戦争孤児となり、親戚の家を頼る二人。
確かに叔母はきついのかもしれない。将校家族の利益にあずかろうという姑息な気持ちもあったかもしれないが、それなりに面倒は見てくれていた。
終戦間際。食料等は配給制になる。頼ってきた孤児の分も出るの? 出たとしても、日に日に少なくなる。そんな中で家族に食べさせなきゃいけない主婦。日々のやりくりだけで頭痛いだろう。
それなのに、勤労奉仕もせずに好き勝手している清太。皆が滅私奉公を強いられ、拒否すれば特高に目をつけられた時代。隣組等で相互扶助/相互監視されていた時代。叔母としたらご近所の手前肩身が狭かったのではなかろうか。
もっと悲劇的な扱いを受けた人もいるという話もたくさんある。皆逼迫していた。
叔母だって余裕がなかっただろう。
反対に、大金を持っていること、将校の息子であることで、清太に驕りはなかったか?
終戦。
今までの価値観がすべてひっくり返った時代。大人も子どもも、皆混乱して、生きていくのが精一杯だった時代。
買い出し。闇市。絢爛豪華な花嫁衣装が米一合もしくは数本のサツマイモに化けた話を聞く。そんな中で、現在でも野菜高騰時にキャベツ等が畑から盗まれたニュースが記憶に新しいが、この頃だって闇市で売るための泥棒も多かった。盗みの実行者は戦争孤児たちが多かった。清太一人なら見逃してもくれるだろうが、おじさんには闇市のための盗みかはわかるまい。
頭を下げて分けてもらったら、節子を脇に置きながら手伝ったら、違う展開になったかもしれない。
後から、清太がこうすれば~、というのはたやすい。
でも、戦争がなければ、彼は両親と学校教育の庇護のもとで、必要な対人関係も学べたはずだ。
否、どうなんだろう。清太が親や学校から受けてきた教育は、”人の上に立つ者”としてのプライドではなかったか。こんな混乱・境遇に身を置くことは想定していなかった。
子どもが生きるために必要な力って何?学歴?勉強?特技?お金を稼ぐ力?
”社会性”という言葉一つとっても難しい。清太だって、以前の生活の中での”社会性”は身に着けていたのだから。
周りに合わせるだけでは心が死ぬが、一人では生きていけない。
自分の力だけでやれると思う独善。
周りの状況を見ない・聞かない傲慢。
何より自分の力量を客観視する力。何ができて、何ができないか。どういう力を借りなければいけないのか。借りっぱなしにならないためにはどうすればいいのか。
これは、日本の終戦前後の話だが、世界には、現代にも、こんな子どもたちはたくさんいる。
日常生活にも通じる。自分の首を絞めるようなチョイスが多い人っている(私か)。
「サポートを受けなさい」というのはたやすい。でも、サポートのネットワークから漏れる人って、サポートが提供するものと、自分のこうありたいのギャップが埋まらない人。”自分のこうありたい”を変えることって、結構難しい。
自分の想い・気持ちを大切にして、他との交流に拒否的・回避的になり、閉じた世界で生きる。
-清太であり、現代の若者に多いし、”孤独死”という言葉も頭をよぎる。
反対に、この映画では明確には描かれていないが、他の映画で表現されているように、周りに同調して同じ行動・思想しか認められなくなるのも恐ろしい。
-この時代の「お国のため、天皇陛下のために」という思想への強要であり、実は、いじめやパワハラが深刻になる構造に関与する。KYという言葉も”同調”しなければという思いに裏付けられている。
この、現代にも通じる二つの在り方を並べることで、第三のあり方に思いを馳せる映画なんじゃないか、なんて思う。
そして、
この原作は、野坂昭如氏の、妹さんへの贖罪・レクイエムと聞く。
誰かの命・人生を背負うことに重荷を感じるなんて、大人でもあり得ること。
「疎ましく思う」「投げ出したかった」なんて、誰でも一瞬頭をよぎる。
それでも目の前の存在を放り出すことができなくて、やるべきことをやるの繰り返し。
「もっとこうしてやりたいのにできない」と自分で自分を責めている人にとったら、映画鑑賞者の私達には愛おしい節子の表情・仕草・行動も、できない自分を責めているようで、嫌悪の対象となるだろう。
でも、捨てて逃げることもせず、頼る人もいないのに、野坂氏も清太も頑張った。
今の世、ネグレクトや遺棄する大人だっているのに。(せめて遺棄するなら福祉に相談するか赤ちゃんポストにしてくれ)
不幸にして、時代があんなだったから、節子(野坂さんの妹さん)は亡くなってしまったけれど、貴方のせいじゃない。それだけははっきり言える。今に置き換えれば、14歳の子どもが負う責任ではない。
単なる戦争犠牲者の悲話ではない。
この社会で生きようとした子どもを描いた映画。
人の助けを必要とする小さきものを守るために自分がどう動くのかとか、社会との接点・人との関わり方とか、アイデンティティとか、心の底の深い気持ちを揺さぶられる。
だから、映画としては、どこをとっても一級品だけれども、鑑賞するのがしんどい。
この映画から、何を読み取る・感じ取るかは個人の自由だと思う。
ただ、「こうあるべき」と言うのはいかがなものか。
それって、戦中の思想と一緒。あの頃だって、非国民を非難していた軍国の母は、時代に刷り込まれた「こうあるべき」を周りに押し付けていたのだから。今戦争している地域・宗教だって、己の「こうあるべき」を立証するために戦いを仕掛けているのが建て前なのだから。
いろいろな考え方・感じ方・生き方をお互い認め合えたらいいなと思う。
とみいじょんさま
コメント返信ありがとうございました。
コメントに問いかけがあると、詳しく返信しなければと感じてしまうので、ご興味が無ければスルーしてください。
「※アニメ映画化が決まった時に、原作者の野坂昭如氏が念を押したのは「絶対に僕(清太)を善人のようには描かないでください」。そのため高畑勲監督は、清太が批判されることを恐れていたそうです。」
↑この私のレビューには、未投稿の続きがあります↓
「清太の自己責任論は、清太の声優の発言から始まりました。高畑監督は、西宮のおばさんが正当化されて清太が批判されるのは、戦時中の全体主義に逆行すると懸念していました」。
今夜NHKの「クローズアップ現代」で、『火垂るの墓』の特集がありました。日テレとジブリの商業主義への、アンサーのような番組でした。ご興味があれば、NHKプラスで1週間無料配信しています。
正直に言うと、ジブリには殆ど思い入れが無いのです。日テレがジブリを買収してからは、海外190ヶ国でのドル箱コンテンツに成り下がったとさえ考えています。今の子どもたちには、『鬼滅の刃』を観て「命」について考えてほしいと思っています。
私の「行動」の一つには、「子どもたちの居場所」に関する仕事があります。守秘義務があるので、ここには詳しく書けませんが…。
とみいじょんさま
コメントとフォロバ、ありがとうございました。自分の薄っぺらいレビューやコメントが恥ずかしくなります🤭
『火垂るの墓』は、短編小説・アニメ映画・TVドラマ・実写映画・漫画・舞台…と、全ては見ていませんが、視点が異なるそうです。ドラマでは鬼のようなおばさんが正当化されていたり、実写では清太が優等生過ぎたり。
アニメ映画化に当たって、原作者の野坂昭如氏の願いは「清太を善人として描かないで欲しい」でした。そのため高畑勲監督は、清太が批判されることを恐れていたそうです😗
少し調べたのですが…『となりのトトロ』と『火垂るの墓』は、当初60分の企画が長くなってしまったというジブリらしい裏話(笑)。
バブル当時には『火垂るの墓』の動員が見込めなかったこと、『魔女の宅急便』以前は、同時上映の作品の内容に関わらず2本立てが配給の条件だったこと🤔
「ポリコレ」は、ディズニーアニメが凋落した理由の一つです。主人公の性別も人種も善悪も、よく分からない作品になってしまいました。
今年の『ミッション・インポッシブル』でも、大統領や軍の高官は女性、黒人やアジア人やマイノリティが不自然な比率で登場していました🧐
7年振り14回目の金ローの放送の後、気になっていることがあります。私のレビューは8月15日に71件目、週末の8月17日に99件まで増えて安心していました。
その後毎日新しいレビューを読んでいるのに、増えた分だけ減っているのか、トータルのレビュー数は増えたり減ったりです。削除されたのか、削除したのか分かりませんが…😶
とみいじょんさま、初めまして。
共感ありがとうございます。
レビューの多様な視点・深い考察・語彙力と筆致…フォローさせていただきました🙂
最近の戦争映画の大ヒットと言えば、『あの花が咲く丘で、また君と出会えたら。』のラノベ、『この世界の片隅に』のほっこり、『永遠の0』のVFX…🙄
『鬼滅の刃』でさえPG12なので、『火垂るの墓』のリアルな描写は、現在のレイティングやポリコレなら、どうなるのだろうと思います🫢
1988年の公開は『となりのトトロ』と2本立てだったので、想像もしなかった映画を観たショックで席から立てなくなってしまった子どもが、私を含めてたくさんいました🥹
レビューに書いてる方が何人もいますが、『火垂るの墓』で兄妹が餓死したのは「清太の自己責任」、そして「一度は観てほしい。二度は観たくない。」😗
ウクライナやガザの子どもたちの戦禍の報道を知りながら、「自己責任」という言葉が出てくるのは、つくづく日本は「平和な島国」だと思い知らされます🥺
「(映画の登場人物が)どうすればよかったのか」ではなく、「(映画を観た私たちが)どうすればいいのか」を考える、戦争映画はそのためにあると思います🤔
でも戦争映画の入口のハードルは低く広く、伝えること、忘れないこと、それでいいと思っています。そう考えて、8月15日にレビューを投稿しました🫡
※長文コメント失礼しました。
私も過去にこの映画を見ましたがいつか又観なければならない映画と思っています。
レビュー、とても参考になりました。
とても深掘りされていて改めてこの映画の良さが理解できた気がします。
先に米もいくらか渡しているにもかかわらず、その米を皆で食べて無くなると、軍需工場で働くいとこ達とご飯で差をつけられたのは、清太達の親なら憤ると思いました。我慢の限界だったかなと思いますが、屋根と壁のある家を出たのが不味かったとは思います。
清太に歩み寄ることも伯母から太に手伝いをさせるとかの歩み寄りもあれば、と。やはり、大人の方だと思ってしまいます。
こんばんは♪
お返事いただきましてありがとうございました😊
本作原作も読んでいます。
実際の妹さんは、もっと幼い赤ちゃんに近い年頃だったかな、と思います。
清太と妹さんの幸せを真に願うべく書いてくださったレビューですね。あの伯母さんの家を出ない方が二人共長生きしていたかもしれない、ですね。