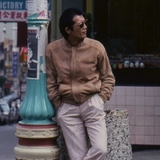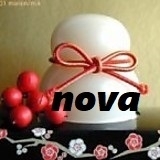日本のいちばん長い日(1967)のレビュー・感想・評価
全62件中、1~20件目を表示
大日本帝国の断末魔。
⚪︎作品全体
人は死が近づくと走馬灯が見えたり、時間の流れがすごくゆっくり見えるのだという。
科学的には立証されていないらしいし、これは素人考えなんだけれども、きっとそれは生き残るために常時とは異なる処理速度で脳が暴れているのだと思う。
1945年8月14日から15日は、国家として死が近づいた日だ。帝国主義の国家として成功した約50年くらいの年月を過ごし、促進剤であったはずの軍部が癌となり、原爆という致命傷を負い、今まさに死を迎えようとしている。
本作、『日本のいちばん長い日』で描かれるこの時間は、死にゆく国家の走馬灯であり、死を間際にした長く伸びる時間だ。
単純に死を受け入れるだけならば、8月14日の終戦詔書への署名と押印で完了しているはずだった。しかしこのアジアの一国家を列強へと押し上げた「大和魂」は、不幸にも安らかな死を受け入れられない。死を前に脳が暴れるがごとく、陸軍将校というエネルギーが死を拒む。
その死を受け入れさせるために、明治維新のような「国家の再興」という走馬灯を見させる必要がある。そして炎が消える直前に再び強くなるように、エネルギーを消費しなければならない。
宮城事件と呼ばれる陸軍将校のクーデターは、そうした死を迎えるための、大日本帝国にとっての最後の生体反応であり、断末魔だった。
本作の素晴らしいところは、この「大日本帝国の死」を看取る距離感で描いているところだ。
例えばもっと将校に心情を寄せて、国を愛する忠臣の物語にもできただろうし、露悪的に描くこともできた。もしくは終戦を進める鈴木貫太郎たちと軍部の対立を濃く描き、平和という正義と軍部の戦いという構図でドラマを作れただろう。
しかし本作はそうはせず、時間の経過と終戦までの出来事をドキュメンタリーチックに演出していた。そしてそこに「看取り」の情感があった。
本作を見る大半の人物は、この作品に登場する重臣や軍人とも違う、一般の人々だろう。一般の人々は玉音放送を聴いて大日本帝国の死を知り、そのまま日本国の再建へと進んでいってしまったわけだ。
日本人は「大日本帝国の死」は知っていても「どういう死に際だったのか」は知らないままだ。本作はそうした人々へ「日本の断末魔」を届ける役割を担ったのだと感じた。
終戦が決まったあと、本作に一般国民は出てこない。それぞれの職務をまとった重臣や軍人と違って、一般国民が死をどう受けとったかなんてものは描きようがないからだろう。
ここで描かれるのは終戦の評価ではない。大日本帝国がどんな死を迎えたのか、だ。
大和魂という精神力で作られたこの国家は、死に際まで人のように長い時間をかけて死んでいく。その生々しさを見事に描き切った大作だ。
⚪︎カメラワークとか
・畑中まわりのカメラワークは黒沢年男の芝居もあってちょっと情感強かった。陸軍省の誰もいない講堂で井田を説得するシーンは、井田に断られると畑中は立ち去っていくが、カメラをかなり引いてシルエットで二人を見せていた。
NHKで自身の主張を発信できないことがわかったあとに一度項垂れる畑中をシルエットで見せて、続くカットで真正面から畑中の腹を据えた顔を映す。帽子の紐をつけ直し歩き始める畑中。…かっこいい。
⚪︎その他
・年をとればとるほど思うけど、終わらせることっていうのは本当に大変なことだ。そんなことを思えるようになったからか、前見た時に感じた陸軍将校への「いい加減にしろよ」という気持ちはほとんどなくなった。
畑中の情熱に動かされる将校たちにも前は苛立ちを感じたけど、今はなんだか納得できてしまったな。
・詔書への署名が終わったあと「疲れた…長い一日だった」みたいなナレーションが入るけど、あれだけは何回聞いてもムカつく。何百万と人を死に追いやっておいて、たった一日で何を抜かしてんだ、みたいな。
・作中では語られてないけど、井田が戦後生き残ってて、しかも本土決戦論を改めてないところもムカつく。感情論だけど、お前も罰受けろよって思うなあ。
映画史に残る超大作、本当にすごい
緊迫の玉音放送
怒っている
二度とこの日が来ないことを望む
やめるのって大変なんだよ
戦争の虚しさとか陸軍の理不尽とか、優等生みたいな感想を言う者が多いですが、今でも明らかな不採算分野から撤退したり、赤字支店を閉鎖しようと言う時なんか頑強に抵抗する輩は大勢います。本質は変わってませんよ。
結果を知っているから、戦争反対なんて言いますが、正しくは敗戦反対です。勝ってたら反対しないでしょ?あの頃は一億火の玉みたいに考えている方が普通だった空気感だしね。
映画的には終戦日の反乱勢力を中心に描かれていますが、これだけの登場者を手際よいテンポで処理した演出力は監督の職人芸ですが、ある程度の予備知識がないと少し分かりづらいかもしれませんね。
軍人たちの混乱の日
半藤一利の原作もおすすめ
儚い日本陸軍の最後の足掻き 真夏の夜の夢
過去数回鑑賞
監督は『肉弾』『殺人狂時代』『座頭市と用心棒』『ダイナマイトどんどん』『ジャズ大名』『助太刀屋助六』の岡本喜八
脚本は『羅生門』『生きる(1952)』『蜘蛛巣城』『隠し砦の三悪人』『私は貝になりたい(1959)』
『切腹』『白い巨塔(1966)』『日本沈没(1973)』『砂の器』『八甲田山』の橋本忍
粗筋
終戦の御聖断
ポツダム宣言受諾
しかし一部あくまでも本土決戦に拘り終戦を拒否する近衛師団の若い軍人グループが決起を促しクーデター計画を開始した
なにかと言えば比較し批判するとお叱りを頂くがこれはどうみても比較するなと言う方が到底無理な話
2015年のリメイク版に比べると全体的にだいぶ熱さが伝わってくる
あちらはいい意味でも悪い意味でもクール
こっちは出演者の多くが戦争体験者
リメイク版の多くは戦後生まれ
そもそもこっちの監督は予備士官学校の生徒として空襲を体験し軍部を恨んだものだがあっちの原田某監督は戦後生まれで「日本はロシアを批判する資格はない」という的外れなニュアンスの発言をTVで発言したらしい典型的団塊パヨク
その違いは大きいのかもしれない
あっちを星一つの評価したレビュアーもいたが改めて岡本喜八版を鑑賞するとその気持ちわからないでもなく星3の自分を恥じたい気持ちだが今更数を減らすつもりはない
あっちは役所広司堤真一松坂桃李山崎努
いずれにせよ名優だが岡本喜八版の主な出演者に比べると見劣りしてしまう
三船敏郎加藤武黒沢年男笠智衆
その他に志村喬山村聡藤田進高橋悦史佐藤允天本英世などなど錚々たる顔と顔
特に黒沢年男の芝居が鬼気迫り狂気に満ちたその表情はとにかく凄い
暫く前からバラエティー崩れしており歌手のイメージも強く俳優としてはあまりピンとこなくなってはいるが彼もまた三船志村クラスに負けない名優といえる
怪奇俳優天本英世もあんな大きな声が出るんだな
男臭い汗臭い映画だ
漢の映画だドラマだ人生だ
女性俳優といえば日の丸の手旗を降り特攻機を見送るモンペのエキストラくらい
終盤に登場した鈴木首相私邸で働く女中役新珠三千代が記憶に残るくらい
あっちはNHKに松坂桃李の嫁の歯茎がいたし阿南の家族を描くことによって有名女性俳優が出演した
でもNHKはあっちが歯茎でこっちは昭和の大スター加山雄三だもんな
それだけでも格が違う
クーデーターを起こした近衛師団の連中の思想に共感はできないが大きな流れに贖う姿は天邪鬼の自分としては好感が持てた
彼らは狂ってるとか愚かだと評価する者も多いが正義感に駆られて罪の意識なく誹謗中傷を繰り返し徹底的に追い込み中には自殺者まで出してしまうネット民の方がよっぽど酷いじゃないか
彼らは自決したがネット民は居場所を突き止められ罪を問われたら「言論の自由だ」「違法というなら取り消す」「名前を明かさないでくれ」と泣き言をいうばかり
情けない
星5星4とあっちを高く評価した者はおそらくこっちを観たことがないんだろう
そうでなければありえない
もしそうならば頭を切り開いて中身を見てみたいものだ
今作で昭和天皇を演じたのは現・松本幸四郎の祖父
声だけで顔は出さない
堂々と本木雅弘が出演したリメイク版とは大きな違い
当時は畏れ多く特別な配慮でノンクレジット
僕は皇室制度廃止論者なのでそういう対応には多少怪訝な気分にはなるのだがまあ星5の評価は揺るぎない
配役
内閣総理大臣の鈴木貫太郎に笠智衆
外務大臣の東郷茂徳に宮口精二
海軍大臣の米内光政に山村聡
陸軍大臣の阿南惟幾に三船敏郎
厚生大臣の岡田忠彦に小杉義男
情報局総裁の下村宏に志村喬
農商務大臣の石黒忠篤に香川良介
大蔵大臣の広瀬豊作に北沢彪
司法大臣の松阪広政に村上冬樹
軍需大臣の豊田貞次郎に飯田覚三
大臣に山田圭介
大臣に田中志幸
内閣書記官長の迫水久常に加藤武
内閣嘱託の木原通雄に川辺久造
内閣官房総務課長の佐藤信次郎に北村和夫
内閣理事官の佐野小門太に上田忠好
総理秘書官の鈴木一に笠徹
海軍軍医の小林に武内亨
首相官邸警護の巡査に小川安三
外務次官に松本俊一に戸浦六宏
電信課長の大江晃に堤康久
情報局総裁秘書官の川本信正に江原達怡
宮内大臣の石渡荘太郎に竜岡晋
総務局長の加藤進に神山繁
庶務課長の筧素彦に浜村純
総務課員の佐野恵作に佐田豊
陸軍次官(中将)の若松只一に小瀬格
軍務局長(中将)の吉積正雄に大友伸
軍事課長(大佐)の荒尾興功に玉川伊佐男
軍務課員(中佐)の井田正孝に高橋悦史
軍事課員(中佐)の椎崎二郎に中丸忠雄
軍事課員(中佐)の竹下正彦に井上孝雄
軍事課員(少佐)畑中健二に黒沢年男
陸軍大臣副官(中佐)の小林四男治に田中浩
参謀総長(大将)の梅津美治郎に吉頂寺晃
第一総軍司令官(元帥)の杉山元に岩谷壮
第二総軍司令官(元帥)の畑俊六に今福正雄
参謀兼司令官副官(中佐)の白石通教に勝部演之
東部軍司令官(大将)の田中静壱に石山健二郎
参謀長(少将)の高嶋辰彦に森幹太
高級参謀(大佐)の不破博に土屋嘉男
参謀(大佐)の稲留勝彦に宮部昭夫
参謀(中佐)の板垣徹に伊吹徹
参謀(少佐)の神野敏夫に関田裕
司令官副官(少佐)の塚本清に滝恵一
近衛師団第一師団長(中将)の森赳に島田正吾
近衛師団参謀長(大佐)の水谷一生に若宮忠三郎
歩兵第一連隊長(大佐)の渡辺多粮に田島義文
歩兵第二連隊長(大佐)の芳賀豊次郎に藤田進
参謀(少佐)の古賀秀正に佐藤允
参謀(少佐)の石原貞吉に久保明
大隊長に久野征四郎
宮城衛兵司令所の伍長に山本廉
徳川侍従を殴る師団兵に荒木保夫
師団兵に桐野洋雄
師団兵に中山豊
陸海混成第27飛行集団飛行団長(大佐)の野中俊雄に伊藤雄之助
陸海混成第27飛行集団基地副長の児玉に長谷川弘
少年飛行兵に大沢健三郎
横浜警備隊隊長(大尉)の佐々木武雄に天本英世
航空士官学校の黒田(大尉)に中谷一郎
東京放送会館警備の憲兵(中尉)に井川比佐志
軍令部
軍司令部総長(大将)豊田副武に山田晴生
軍司令部副長(中将)大西瀧治郎に二本柳寛
海軍省軍務局長(中将)の保科善四郎に高田稔
厚木基地第三〇二海軍航空隊司令(大佐)の小園安名に田崎潤
厚木基地第三〇二海軍航空隊副長(中佐)の菅原英雄に平田昭彦
厚木基地第三〇二海軍航空隊飛行整備科長に堺左千夫
内大臣の木戸幸一に中村伸郎
枢密院議長の平沼騏一郎に明石潮
侍従武官長(大将)の蓮沼蕃に北竜二
侍従武官(中将)の中村俊久に野村明司
侍従武官(中佐)の清家武夫に藤木悠
侍従長の藤田尚徳に青野平義
侍従の徳川義寛に小林桂樹
侍従の三井安弥に浜田寅彦
侍従の入江相政に袋正
侍従の戸田康英に児玉清
侍従の岡部長章に関口銀三
日本放送協会会長の大橋八郎に森野五郎
国内局長の矢部謙次郎に加東大介
技術局長の荒川大太郎に石田茂樹
報道部長の高橋武治に須田準之助
放送員の館野守男に加山雄三
放送員の和田信賢に小泉博
技師の長友俊一に草川直也
技師に今井和雄
技師に加藤茂雄
鈴木首相私邸女中の原百合子に新珠三千代
政治部記者に三井弘次
佐々木大尉の後輩で横浜工高生(横浜必勝学生連盟)に阿知波信
ビラを拾う街の男に夏木順平
ビラを拾う街の浮浪児の兄に頭師佳孝
ビラを拾う街の浮浪児の弟に雷門ケン坊
枢密院会議の重臣に秋月正夫
枢密院会議の重臣に野村清一郎
ナレーターに仲代達矢
昭和天皇に八代目松本幸四郎
勝手に死ぬな
【日本のいちばん長い日】 岡本喜八 生誕百周年記念プロジェクト - その7
丁度79年前の8月14日、国民の知らぬ間に進んでいた敗戦の詔勅と玉音放送を巡る軍人と政治家の断末魔を描いた記念碑的名作です。小学校3~4年生で公開時に父親に連れられて観て以来の鑑賞となりました。おそらく、父親は「分かっても分からなくても息子に観せておきたい」と思ったのではないでしょうか。子供心にも、切羽詰まった熱気が満ちているのは感じられ、特に、日本刀で人を切ると噴水の様に血が噴き出す描写に驚き、帰ってからもそれが怖くて怖くて仕方なかったのをよく覚えています。モノクロ映像がその熱気を更に高め、薄紙一枚を差し挿む隙も無い程、全編緊張感に満ちた157分でした。脚本も監督も俳優も漲る熱量が半端ありません。
それにしても、と思います。既に日本がポツダム宣言を受諾する事を知りながら、特攻隊の出撃を命じた司令官が居たのです。戦後、その人は一体どんな言い訳をしたのでしょう。聞きたいな。そして、敗戦と共に割腹自殺して行った人々。責任を感じるのならば、「何があったのか」「どこで間違ったのか」「何故間違ったのか」「どうすればよかったのか」を後世の人間に伝える義務があった筈です。それなのに逃げるなんて卑怯だよな。
そして、本作中で二度、何の説明もなく倉田百三の『出家とその弟子』の岩波文庫が映し出されるシーンが2度ありました。僕も高校生の頃読みましたが、戦時下にあってあの本がどう読まれていたのか何か言葉が欲しかったです。
そして、本イベントの呼び物、上映後トーク、今回は春日太一さんによるタップリのお話でした。本作をも「戦争の中で置き去りにされた人々」と見る視点にはなるほど。そして、春日さんの最新刊で、本作の脚本をも担当した橋本忍さんの評伝「鬼の筆」にサインを頂き、大満足。
終戦の日に観て79年前を想う
1945年7月26日のポツダム宣言に明確な回答を行わなかった事から、これを無視したと連合国に受け取られ、広島と長崎に原爆を落とされ、中立だったはずのソ連まで参戦してきて、それでも本土決戦を主張する陸軍の大反対の中、8月14日正午、ポツダム宣言受諾決定した。それから、翌日15日正午の昭和天皇による玉音放送までの激動の24時間を描いた話。
広島・長崎への原爆投下で日本はもう勝てない事が決定的で、昭和20年8月14日、御前会議によりポツダム宣言の受諾が決定したのだが、陸軍が大反対。上司を殺してあんなに抵抗してたとは、少し驚きだった。もし玉音放送のレコードが発見されて壊されてたら8月15日の終戦は無かったかも、とまで思えるほどの迫力だった、
阿南陸軍大臣役の三船敏郎の苦悩、笠智衆のひょうひょうとした首相、50年以上前の若い加山雄三など超豪華で素晴らしい演技だった。もう1人、黒沢年男の熱血将校も素晴らしかった。
本作をたまたまだけど、終戦の日に鑑賞できたのも感慨深かった。
良くも悪くも、、、
今の政治家ども!せめてこれ観ろ!!
負けを認めて戦争を終われせる。
そんな今の感覚で考えればごく当たり前の事を決めるのに
なんでこんなに拘るのか!?
負けを認めて戦争を止めるとどうなるのか?
あえて今の人に一番わかり易い表現をすると
「風の谷のナウシカ」の中で
トルメキアが攻めて来て風の谷の住人に銃を向け
土地や物品や自由を奪って行く〜
あんな事が起こると思っているから止めるに止められ無い。
実際あんな生ぬるいもんじゃ無いけど〜
つまりは戦争は始めたら最後、降参しても
地獄しか待っていないって事ですね。
この映画の中で、
すでに死んでいった者たちに申し訳ないから
戦争を止めずに最後の一兵まで本土決戦するべきだと
言い張る兵士たち!
何だか今の官僚が
「一度始めた事業を止めると
前任者を否定する事になるから止められ無い」
みたいな論理で間違った事業を止めないのと
全くおんなじじゃないか!!
死んでいった者達に申し訳ないと本気で思うのなら
残された人たちを守るのがお前らのやるべき事ではないのか!
前任者が間違ったと思うのなら
正しい方向に修正するのが、後輩のやるべき事じゃないのか!
観ていて怒りがこみ上げた!
「生きる方が大変なのだ!」と言い残して自決した阿南陸相。
軍部を暴走を抑えてスムーズに終戦を迎えるための
一種の人身御供であり、
三船敏郎が演じているのでカッコ良く見えてしまうが
確かに死ぬ方が、狡いかもしれない。
で、月に8回程映画館に通う中途半端な映画好きとしては
2015年の原田監督版も映画館で観てますが
これはやはり別物としなければ
原田監督に分が悪すぎるでしょう。
何といってもこの映画は
昭和の名優がまだまだ現役バリバリの時代に作られてます。
つまりは実際に戦争を知っている人達や
その空気の残る時代に育った人達がやってる訳で
そこは緊迫感が違う。天皇への思いも違う。
そこはしょうがない。
逆に言えば、
敗戦日である昭和二十年八月十五日までの空気感を
リアルに感じられると思います。
超有名な映画ですが、そこそこ長いので
午前10時の映画祭の様な機会に映画館で観なければ
これだけ様々な鑑賞手段の増えた時代でも
なかなか手の出ない作品だけに
「午前10時の映画祭」運営の皆様に感謝です。
本当に面白かった!!
@もう一度観るなら?
「一回は映画館で観とか無いとね〜」
戦後77年
戦中戦後の映画はいろいろ見ていても、その多くは原爆投下から玉音放送で終戦というくだりでみることが多く、その間の「長い1日」については知りませんでした。今まさにウクライナで戦争が起こり、犠牲者が増え続けていても、止めることが容易ではないし、誰が何を目論んでいるのか真相はよくわかりません。ポツダム宣言の受諾が原爆投下の前であればと、過ぎてから思うことですが、その時点ではできなかった一面が今作でも描かれています。原爆は、本土決戦による甚大な被害を最小限に防いだハッピー爆弾とも言われ、複雑で滑稽な気分にさえなりますが、同じようなことが今、ウクライナで再現されているようで、77年前の教訓がどこかへ霧散してしまったかのような空しさを感じてしまいます。
歴史的な1日を淡々と見せるが、それが実に面白く興味深い
岡本喜八監督による1967年製作の日本映画。配給は東宝。
庵野秀明監督が本作を気に入って何度も見ていると聞き視聴。脚本が橋本忍とは知らなかった。それだけ、スピード感や数多くの有名俳優の扱い等、岡本喜八監督の色が強いと感じた作品。原作は読んでおらず、史実自体が大変に興味深く面白く、それを手際良くきちんと示そうという演出姿勢には感心させられた。
主役は歴史という感じで、血気にはやる井田正孝中佐(軍務課員) 役の高橋悦史以外は殆ど記憶に残っていない。まあ天皇陛下が後ろ姿だけで、正面から映さないのは印象に残った。
沖縄陥落し更に原爆2個投下された後の終戦日直前においても、即ち客観的には局地戦含めて勝利の見込みが全く無い様に思えるにも関わらず、未だ本土決戦を主張する陸軍の人間達には呆れ果ててしまった。軍人以外の庶民の命を尊重する気持ちがあまりに乏しい。そして何より、玉音放送阻止に動いていて、天皇に直接的に反旗を翻しているのに驚かされた。文民統制以前というか、陸軍はどういう教育をしていたのか?先進国の軍隊ではありえない。天皇制のためでもなく、自分達だけのためだけのための本土決戦。中国にロシアに、そして米国に戦争で負けて当然と思ってしまった。
映画とは直接関係無いが、畑中健二少佐及び椎崎二郎中佐が自決したのに、彼らの上官竹下正彦中佐(クーデターの元となる兵力使用計画を起草、原作者のネタ元らしい)は自衛隊幹部として大出世(陸相)し、映画で「宮城事件」の首謀者に見えた井田正孝中佐が戰後も生き残り電通関連会社の常務として出世するのが、何とも日本的で悲しい。責任取らされるのはいつも下っ端管理職で、上はお咎め無しなのか。
製作藤本真澄、田中友幸、原作大宅壮一名義で出版されたた半藤一利の同名ノンフィクション、脚本橋本忍。
撮影村井博、照明西川鶴三、録音渡会伸、整音下永尚、美術阿久根巖、編集黒岩義民、音楽佐藤勝、監督助手山本迪夫、渡辺邦彦。
出演者
内閣: 鈴木貫太郎男爵(内閣総理大臣) - 笠智衆、東郷茂徳(外務大臣) - 宮口精二、米内光政(海軍大臣) - 山村聡(特別出演)、阿南惟幾(陸軍大臣) - 三船敏郎、岡田忠彦(厚生大臣) - 小杉義男、下村宏(情報局総裁) - 志村喬、石黒忠篤(農商務大臣) - 香川良介、
広瀬豊作(大蔵大臣) - 北沢彪、松阪広政(司法大臣) - 村上冬樹、豊田貞次郎(軍需大臣) - 飯田覚三、大臣 - 山田圭介、大臣 - 田中志幸。
官邸: 迫水久常(内閣書記官長) - 加藤武、木原通雄(内閣嘱託) - 川辺久造、佐藤信次郎(内閣官房総務課長) - 北村和夫、佐野小門太(内閣理事官) - 上田忠好、鈴木一(総理秘書官) - 笠徹、小林海軍軍医 - 武内亨、首相官邸警護の巡査 - 小川安三。
外務省: 松本俊一(外務次官) - 戸浦六宏、大江晃(電信課長) - 堤康久。
情報局: 川本信正(情報局総裁秘書官) - 江原達怡。
宮内省関係者: 石渡荘太郎(宮内大臣) - 竜岡晋、加藤進(総務局長) - 神山繁、筧素彦(庶務課長) - 浜村純、佐野恵作(総務課員) - 佐田豊。
陸軍関係者:
陸軍省 若松只一中将(陸軍次官) - 小瀬格、吉積正雄中将(軍務局長) - 大友伸、荒尾興功大佐(軍事課長) - 玉川伊佐男、井田正孝中佐(軍務課員) - 高橋悦史、椎崎二郎中佐(軍事課員) - 中丸忠雄、竹下正彦中佐(軍事課員) - 井上孝雄、畑中健二少佐(軍事課員) - 黒沢年男、小林四男治中佐(陸軍大臣副官) - 田中浩。
参謀本部 梅津美治郎大将(参謀総長) - 吉頂寺晃。
第一総軍 杉山元元帥(司令官) - 岩谷壮、第二総軍 畑俊六元帥(司令官) - 今福正雄、白石通教中佐(参謀兼司令官副官) - 勝部演之。
東部軍 田中静壱大将(司令官) - 石山健二郎、高嶋辰彦少将(参謀長) - 森幹太、不破博大佐(高級参謀) - 土屋嘉男、稲留勝彦大佐(参謀) - 宮部昭夫、板垣徹中佐(参謀) - 伊吹徹、神野敏夫少佐(参謀) - 関田裕、塚本清少佐(司令官副官) - 滝恵一。
近衛師団 森赳中将(第一師団長) - 島田正吾、水谷一生大佐(参謀長) - 若宮忠三郎、渡辺多粮大佐(歩兵第一連隊長) - 田島義文、芳賀豊次郎大佐(歩兵第二連隊長) - 藤田進、古賀秀正少佐(参謀) - 佐藤允、石原貞吉少佐(参謀) - 久保明、大隊長 - 久野征四郎、宮城衛兵司令所の伍長 - 山本廉、徳川侍従を殴る師団兵 - 荒木保夫、師団兵 - 桐野洋雄、師団兵 - 中山豊。
児玉基地(陸海混成第27飛行集団) 野中俊雄大佐(飛行団長) - 伊藤雄之助、児玉基地副長 - 長谷川弘、少年飛行兵 - 大沢健三郎※、
横浜警備隊 佐々木武雄大尉(隊長) - 天本英世
航空士官学校 黒田大尉[注釈 5] - 中谷一郎
憲兵隊 東京放送会館警備の憲兵中尉 - 井川比佐志。
海軍関係者:
軍令部 豊田副武大将(軍令部総長) - 山田晴生、大西瀧治郎中将(軍令部次長) - 二本柳寛。
海軍省 保科善四郎中将(軍務局長) - 高田稔。
厚木基地(第三〇二海軍航空隊) 小園安名大佐(司令) - 田崎潤、菅原英雄中佐(副長) - 平田昭彦、飛行整備科長 - 堺左千夫。
宮城関係者:
重臣 木戸幸一(内大臣) - 中村伸郎、平沼騏一郎(枢密院議長) - 明石潮、
侍従 蓮沼蕃大将(侍従武官長) - 北竜二、中村俊久中将(侍従武官) - 野村明司、清家武夫中佐(侍従武官) - 藤木悠、藤田尚徳(侍従長) - 青野平義、徳川義寛(侍従) - 小林桂樹
三井安弥(侍従) - 浜田寅彦、入江相政(侍従) - 袋正、戸田康英(侍従) - 児玉清、岡部長章(侍従) - 関口銀三。
日本放送協会関係者:
大橋八郎(日本放送協会会長) - 森野五郎、矢部謙次郎(国内局長) - 加東大介、荒川大太郎(技術局長) - 石田茂樹、高橋武治(報道部長) - 須田準之助、館野守男(放送員) - 加山雄三、和田信賢(放送員) - 小泉博、長友俊一(技師) - 草川直也、技師 - 今井和雄、技師 - 加藤茂雄。
その他:
原百合子(鈴木首相私邸女中) - 新珠三千代、政治部記者 - 三井弘次、佐々木大尉の後輩・横浜工高生(横浜必勝学生連盟) - 阿知波信介、ビラを拾う街の男 - 夏木順平、ビラを拾う街の浮浪児・兄 - 頭師佳孝、ビラを拾う街の浮浪児・弟 - 雷門ケン坊、枢密院会議の重臣 - 秋月正夫、枢密院会議の重臣 - 野村清一郎、起田志郎。
ナレーター - 仲代達矢
特別出演
昭和天皇 - 松本幸四郎(八代目)。
日本にもあった国内テロ
昭和の俳優が勢揃いして熱演が臨場感をかき立て、常にストーリーに引き込まれる展開。見終わった後に残るのは疲労感(笑)。
生真面目で純粋な若者に対して、多角的な情報を与えないまま目標を与えると猪突猛進する。
この突破力が日清、日露戦争やWW2開戦当初の日本軍の強さだったろうし、欧米統治下にあったアジア諸国にも評価されたのだと思うが、歯止めがきかなくなるのが世の常。
戦後でも浅間山荘事件やオウムのように、主に左寄りの世界で世間を騒がせる暴走が起きているため、世論が若干右寄りに傾きかけているように思うが、自分の主義・信条・信念の前に左/右などは関係ないことを、あらためて思い知らされた。
戦後教育の中で、大日本帝国憲法から日本国憲法に変わり「主権万民」を誇らしげに語る教師から教えを請うたが、着地点が見出せない議論を締めくくることなど、万民にできるのだろうかと思った。
昨今言われる「分断」は、一権力者の暴政が引き起こしたものではなく、SNSによって、双方の主張が「見える化」されたことによるものが大きいと思っている。
歴史を見る限り分断は先鋭化していく。そう遠くない将来、日本もアジア諸国と変わらない内戦状態になる危険性は低くない。この作品を通じて、立憲君主制の形について、議論が深まればと思っている。
デジタルリマスター技術によって、映像、音声は極めて明瞭。個性派の俳優が競演することで醸し出される緊張感は、モノクロ映像によって引き立てられている。
国を憂う左右両翼の若者にお勧め。
全62件中、1~20件目を表示