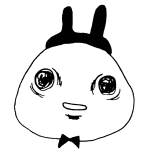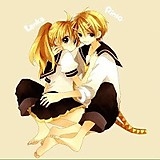12人の優しい日本人のレビュー・感想・評価
全81件中、1~20件目を表示
12人の優しい日本人
ロジックを組み立てる面白さ
言わずもがな、「12人の怒れる男」という名作中の名作のオマージュである。
あちらは、有罪11人、無罪1人からのスタートで、徐々に無罪が増えていく展開だった。
こちらは逆に、無罪11人、有罪1人からのスタート。果たしてどう展開するのかはお楽しみ。
もちろん、この映画は十分単体で見られるし面白い。でもやっぱり、前作を見ていると特に序盤ではニヤリとさせられる演出がある。というか、最初に決を採るところまではほとんど一緒なのでは?
怒れる男でもそうだが、結局真実は分からないし、視聴者にも答えは明かされない。あくまで推測の上で進行していく。
でも、ちりばめられたいくつもの要素を矛盾なくつなげていくのは、まるでミステリー小説を読んでいるかのよう。
「キサラギ」という傑作映画があるのだが、あれと似た空気を感じる。
ちなみに豊川悦司がやんちゃそうな役柄で出演している。めちゃくちゃ若くてすごく新鮮だった。あと塩見三省もでてる。のちにこの2人はアウトレイジでヤクザになるのかと思うとわらけてくる。
ヘンリー・フォンダの感想が聞きたい‼️
名作「十二人の怒れる男」の日本版リメイク、「もしも日本に陪審員制度が導入されたら?」という架空の設定で、12人の陪審員による殺人容疑者の判決をめぐっての議論が、次第に混乱に陥っていく姿を面白おかしく描いてます‼️最初は11人が無罪に対し、1人が有罪というオリジナルと逆パターンで始まる‼️有罪派の陪審員2号が他の倍 陪審員を説得、ところがそれまで傍観者だった11号が反証を開始する・・・‼️これは25年現在までの最高の三谷幸喜作品ですね‼️脚本のみだけど‼️ユーモラスの味付けに加えてミステリーとしても良く出来てる‼️交通事故死か自殺か、轢いたトラックのライトとクラクション、目撃者が聞いた被告の「死んじゃえ」のひと言などなど‼️ただ 一分の隙もない完璧なオリジナルに比べると、所々ほころびが目立つ‼️9号が有罪になびくきっかけなど、誰でも首をかしげる‼️それでも他の三谷作品に比べると断然出来が良く、それは多分12人の人物をうまく描き分けた中原俊監督の手腕でしょう‼️
話の展開は面白かったのですが結論が納得できなかった
有罪と無罪がコロコロ変わって行く事と登場する日本人の様子がうまく表現されていて面白かったのですが最後の結論に至った理由に疑問が残ったので評価を大きく下げました。
何故、被告人は被害者の飛び込みを主張しなかったのか?という部分です。
事件の根本的な部分に疑問を持ったのでこの議論自体が無意味に思えました。
何もかも日本人っぽい
あまり笑えませんでした
前作『櫻の園』で女子高の演劇部を描いた中原俊監督が、本作では【演劇自体をまるまる、そのまま映画化】した実験的な野心作。
新文芸坐さんにて『中原俊の愛いとおしき作品たち』と題した特集上映にて『櫻の園』『12人の優しい日本人』の2作品連続上映。
上映後『櫻の園』には中原俊監督・中島ひろ子氏・梶原阿貴氏・シネマ・ボンクラージュ代表 藤井秀男氏、『12人の優しい日本人』には中原俊監督・相島一之氏・豊川悦司氏・藤井氏の豪華で貴重なトークイベントも実施。
『12人の優しい日本人』(1991年/116分)
前作『櫻の園』で女子高の演劇部を描いた中原俊監督が、本作では【演劇自体をまるまる、そのまま映画化】した実験的な野心作。
映画化に適した演劇作品を企画のじんのひろあき氏と探し回ったあげく出会ったのが、三谷幸喜氏が主宰する劇団・東京サンシャインボーイズのために書き下ろした本作。
三谷幸喜氏はじめ、相島一之氏、豊川悦司氏、塩見三省氏、梶原善氏を知るきっかけになったのも本作ですね。
映画化に際して、三谷幸喜氏もじんの氏も映画用にリライトすることを監督に提案したそうですが、舞台脚本の完成度の高さを評価して一切改変せず、舞台脚本をそのまま生かしたようです。
制作過程も映画では異例の全キャストにクランクイン前に1ヶ月間のリハーサルをお願いしたそうで、豊川悦司氏は結局スケジュールが合わずに降板するキャストの代役で決まったそうです。
また本作の良さは互いの台詞が被るぐらいの高速テンポの台詞の掛け合いですが、実は公開当時は120分以内におさめなくてはならない業界の暗黙ルールがあったようで、監督から1.5倍ぐらいの早さの演技を求めたそうです。怪我の功名ですね。
ストーリーももちろん当時は日本に陪審員制度はありませんでしたが、シドニー・ルメット監督、ヘンリー・フォンダ主演『十二人の怒れる男』(1957)へのオマージュとしながらも、老若男女、様々な職業や生き様や思想も違う個性豊かな12人の陪審員が、日本人らしく他人の意見に流されたり、自分のエゴを押し付けたりしながら、次第に事件の真相、トリックを暴いていくプロセスが実に痛快で抱腹絶倒。
35年経った今回の上映でも場内ドッカンドッカンの笑いが絶えまなく起きていました。
加えて、評決が終わり一人ひとりノーサイドで退廷するラストシーンは「優しい日本人」の題名通りで涙腺崩壊、ホロリとさせます。
三谷幸喜氏も本作をきっかけに自身も『ラヂオの時間』(1997)で監督デビュー。
もし本作で映画用に脚本を書きなおしたら、以後の三谷監督の作風にも大きな影響があったかも知れませんね。
オバチャン
日本で陪審制に近い裁判員制度が施行されたのは2009年であり、 これはその19年前の作品である。 冒頭の飲み物の注文のシーンが延々と続く。 三谷幸喜らしいくだらなさだなと思った。
動画配信で映画「12人の優しい日本人」を見た。
1991年製作/116分/日本
配給:アルゴプロジェクト
劇場公開日:1991年12月14日
中原俊監督
三谷幸喜脚本
塩見三省(陪審員1号)
相島一之(陪審員2号)
上田耕一(陪審員3号)
二瓶鮫一(陪審員4号)
中村まり子(陪審員5号)
大河内浩(陪審員6号)
梶原善(陪審員7号)
山下容莉枝(陪審員8号)
村松克己(陪審員9号)
林美智子(陪審員10号)
豊川悦司(陪審員11号)29才
加藤善博(陪審員12号)
2025年の今から34年前の映画。
29才の豊川悦治のたぶん初出演映画。
出演者は豊川悦司が一番若いと思われる。
日本で陪審制に近い裁判員制度が施行されたのは2009年であり、
これはその19年前の作品である。
冒頭の飲み物の注文のシーンが延々と続く。
三谷幸喜らしいくだらなさだなと思った。
被告は若く美しい女性で。
夫を殺した罪に問われている。
陪審員たちは全員、被告に同情している。
そのせいで12人全員が無罪だと当初は考えていた。
裁判所で、事件の経緯について話し合う陪審員たち。
そうしているうちに徐々に、
計画殺人ではないか?
有罪かもしれない思う人が増えて行く。
自分の家庭と比して無実に納得できない者。
最後まで無罪だと信じ続ける者。
偏屈な紳士。
裁判に無関心な者。
勝手に進行役をやりたがる者。
などいろいろなキャラクターを見せる。
その反面、議論に一貫性や説得力が薄く、
グダグダな感じがあった。
三谷幸喜脚本作品は
「ギャラクシー街道」(2015)のような
どうしようもなく
くだらなくてつまらない作品が時々あると思うが、
この作品はまあまあ楽しんで見られたと思う。
満足度は5点満点で4点☆☆☆☆です。
メタメタに面白い
爆裂おもろい
議論を通じてそれぞれの人間性が見えてくるところがおもしろいですね。
有罪眼鏡は正義感が強く屈折しないけど嘘をついてまで自分を通し周りからは鬱陶しがられたり、
メモおばさまはしっかりしているように見えて、揺るがない自分がなく移ろいやすかったり、
角刈りおじさんは手数多いけど中身はカラっぽで感情と勢いだけだったり、
ヒゲおじさんは柔軟でより強い方について、人の意見を聞けて立ち回りが上手だったり
テンポが良く進んでいくので最後まで飽きずに観れました。
それぞれが自分の状況を事件に投影して、自らの認知を通して判断をしていておもしろかったです。
昔の音質の悪さも味があっていいね。
名前がわからない
事なかれ主義の悪い面を考えさせる作品
殺人罪の有罪、無罪を議論する陪審員の会議を題材にした作品。
12人のそれぞれ個性が際立った人達。でも、それぞれが身近にいると思えるほど没個性の人達。
初めは、皆が早々にというか、さっさと結論出して終わらせたいというの思いから結論を出す。
でも、1人が違和感を感じ主張し、また別の1人がそれを覆し、また別の1人がそれを覆す。
これを繰り返して議論を前に進めさせる。
ずっと同じ会議室の画の中で、話題が二転三転していく流れには面白さを感じた。
ただ、異論を言う1人が出てこなければ、早々に終わり、事実に向き合わずに結論を出したことを想像すると、それぞれの者の無責任感があとに残る。
これは現実の社会にも起こることがあり、またよくあることだと考えると、怖さも感じた。
事なかれ主義の日本人の悪い面が見えた作品だと思う。
舞台で見たい
演劇のよう
12人だけの空間。それも皆初めましてでニュートラル。
これだけ分かりやすい設定があるだろうか。
一緒に議論に参加しているような気になった。
ひとりひとりキャラ付けがしっかりしてるから、表情や会話の間、言葉がひとり歩きしてない。
古い映画ってのもあるけど、声の張り方も舞台上のようでメリハリがあって好き
「何か違う」が明確になっていくのが良かった
全81件中、1~20件目を表示