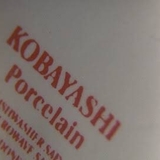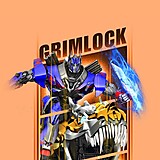ゴジラ対ヘドラのレビュー・感想・評価
全35件中、1~20件目を表示
これまでのエンタメ色は薄く
面白い曲が印象に残る
歌詞もストレートである
水銀 コバルト カドミウム
公害問題はこの様に消化しなければならないほど
深刻だったのだろうと想像して鑑賞した
途中ヘドラに完敗するゴジラ
あのヘドロ責めのインパクトがものすごい
定番である人間側のドジっ子ムーブを
ゴジラが合流して助けてくれる。
どちらかというとヘドラポジションだった
はずのゴジラはヒーローにかわっていた。
なんとも奇妙
これまたゴジラの異色作。 キャストほぼ知らん人。星由里子連れてこい...
か〜えせ〜 がクセになる
キャラクターデザインが良いと思って来たヘドラが映画館でかかるのであればぜひ観たい!!と、小学生の息子と日比谷の朝の回を観に行くと、想像していたよりもたくさんのお兄さん方がいらして、驚きました。
息子の周りにはゴジラを好きな子はほとんどいませんので、初めて自分以外のゴジラファンを目の当たりにした彼は嬉しそうで、興味深かったです。
内容というより、側の面白さが強い映画で、曲も有名なテーマ曲は流れませんし、ゴジラも畏敬のものではありません。そして、ヘドラの面白さや良さがとても際立ちます。
いろんな作風のあるゴジラだから好きだと息子は言うので、これがゴジラの楽しみ方の一つなのだろうなと思いながら、観ました。
「か〜えせ〜」と鼻歌を歌う妙な家族になりながら帰りました。足を伸ばしてよかったなと思います。
水銀コバルトカドミウム
ツッコミ所満載で楽しい サイケ、ヒッピーなゴジラ映画
ストロンチュームって何?「水銀,コバルト,カドニウム・・・かえせ!太陽を!」シリーズ異色作!復活した強いメッセージ性!必見!
「ゴジラシアター」に「ヘドラ」登場!
しかし、スクリーン、席数小さすぎ。
「FINAL WARS」が「プレミアムシアター」の上映もあったのに、この差!
やはり、マニア向けのマイナーという扱いか…。
ゴジラシリーズの第11作にして、円谷英二の名前がクレジットにない最初のゴジラ映画。
ゴジラともう一匹のライバル怪獣しか登場しない真っ向勝負の映画というのも、モスゴジ以来久々です。
日本万国博覧会の翌年1971年。世は、高度経済成長期の弊害である「公害」が蔓延し、ヒッピー、ゴーゴー、サイケデリック、LSD、ベトナム戦争の時代。
映画のオープニングでは、ヘドロに満ちた河川を背景に、本作を象徴する主題歌「かえせ!太陽を」が流れます。
「水銀,コバルト,カドミウム,鉛,硫酸,オキシダン・・・」と化学物質の名称と「かえせ!かえせ!」を連呼するメッセージ性の強い歌詞が印象的。
本作では、ゴーゴーバーのシーンなどでアレンジを変えて何度も登場します。
そして、ヘドロに汚染された駿河湾から公害怪獣怪獣ヘドラが出現。
有毒物質をまき散らしながら、自身の体を次々に変態、進化させ猛威を振るいます。
やがて、出現したゴジラもこの公害・化学汚染物質の塊のようなヘドラに大苦戦。
ゴジラの手は白骨化し、片目もつぶれ、飛行形態も繰り出し、闘いは果てしなく続く・・・。
☆
終盤、ゴジラがヘドラを千切っては投げるシーンでは、オープニングの歌が男声コーラスで「かえせー」とかかり、鳥肌ものの最も好きなシーンでした。
☆
ゴジラ映画も、陽気に楽しい時代は終わったかのように、暗く衝撃的な映像の連続です。
ヘドラが飛行した後は、硫酸ミストを散布し、校庭の子供たちはばたばたと倒れ、
ゴジラがヘドラを振り回すと、その体からはヘドロが飛び散り、それを浴びたサラリーマンが即死。
特撮も、円谷英二は青空が印象的なのに対して、本作の特技監督、中野昭慶の特撮はどんよりとした曇り空か夜が中心。
円谷英二がそれまで避けていた残酷な表現、汚い表現も見られるようになります。
公害怪獣へドラの登場は、当時の世相から必然でもあり、当時テレビでも、新マン('71年)のザザーン、宇宙猿人ゴリ(スペクトルマン)('71-'72)のへドロン、ネオへドロン、などの公害怪獣が続々登場していました。
また、ボディペインティング風の全身タイツで踊る女性や、ゴーゴーバーの壁に映るアメーバ状アート映像、
踊る若者たちの頭が突然「魚」になっていたり(「魚が出てきた日」の引用か?)と世相や時代の雰囲気を反映した場面が多くあります。
人間の生んだ公害の申し子ヘドラと闘うのが、同じく人間の生み出した原水爆の申し子のゴジラという皮肉。
本作は、ゴジラ映画が映画としてのメッセージ性を取り戻した作品でもあり、ゴジラが人間ににらみを利かすラストシーンにもあるように、
本作でゴジラは、正義の味方というよりは、大魔神のような中立の立場ともとれます。
「トリビアの泉」(古っ!)で「ゴジラが空を飛んだことがある」が出たときは寂しかった。
当時の少年たちは、みんな、ゴジラが空を飛んだことすら忘れてしまったのか・・・と。
子供の味方になったゴジラ
ヒーローゴジラ路線の始まりにして異色作
『ゴジラ:キングオブモンスターズ』のマイケル・ドハティ監督は、かつてこのサイトでのインタビューにて、こう語っている。
【……何にだって、どんな映画にだって、ゴジラを加えればより良くなると僕は思っている。】
実際、ゴジラ映画は
「何かしらのジャンルに、ゴジラを加えて面白くしたもの」
という体裁の作品が多い。『キングコング対ゴジラ』はサラリーマン喜劇にゴジラ(とコング)を加えたものだし、『ファイナルウォーズ』は、北村龍平監督お得意の中二病アクションに、ゴジラ(その他怪獣たくさん)を加えた欲張りセットな映画だった。
で……。
この『ゴジラ対ヘドラ』は、ATG(日本アート・シアター・ギルド)映画にゴジラを加えてより良くした作品といえる。冒頭のクレジットから禍々しいイメージが溢れ、その後も要所要所で、リアクションに困る奇抜な画作りが飛び出す。変な意味で全編気が抜けない。ゴジラじゃなかったら商業ベース作品として成立しないし、こんにちまで存在感を維持できてもいなかったろう。
それにしても、環境破壊による公害で生み出された怪獣ヘドラと、水爆実験で生まれたゴジラ。人間の愚行を元凶とする怪獣同士のタイマン勝負とは、どんな皮肉よりもエスプリが利いている。そんなところもATG映画みたいな強い苦味を感じさせる怪作だ。
キッズ向けゴジラってなんか苦手 (昭和生まれだけど) 科学者主人公...
キッズ向けゴジラってなんか苦手
(昭和生まれだけど)
科学者主人公+熱帯魚飼ってるはゴジラの王道でよい
海から上がってきて形態変化や電力集中作戦なんかは、後世にいろいろ影響を与えたとは思うけど、全体的になんか稚拙
ゴジラ映画の傑作
子どもの時は
バタバタ倒れるのを怖がりながらも、飛行、目玉くり抜きに興奮していた。齢を重ねて久々劇場で観返すと予算の無さが目立つ、アレは中国の軍隊か? あとサイケの不気味、シルバー仮面が更にムードを盛り上げる。
あまりテーマとかに触れたくなくなる、最大のシリーズ異色作。GMKなんか目じゃないですね。
追記 2025年3月31日BS録画視聴
♪Hg、Co、Cd・・で始まるオープニングや途中のバーホーベン顔負けのTV映像とか毛色が変わって面白い。オタマジャクシが合体するのもおお!と思ったけれど。海中態→陸上態→・・はシンゴジラに影響を与えたんじゃないか?
引きとアップの切り返しが下手、ヘドラを貫いた腕がTレックスの様に貧弱、ヒューズは無ぇだろう。昭和ガメラみたいなラストも凄い違和感。ネコよく骨にならなかったな・・。
目は口ほどに物を言う
ゴジラ一作目以来の
テーマを孕んだ作品ではないでしょうか?
大気汚染、環境破壊、公害が生んだ怪獣ヘドラ。
子供の頃に観た時は地味で暗い印象だったけど、
今観ると異色作、ヘドラのビジュアルもとても良い。
形態が何種類もあるのも素晴らしかった。
人間は自分達が生み出した怪獣なのに、
何も出来ない愚かさを露呈し、
ゴジラもヘドラも呆れてる感じがしました。
目は口ほどに物を言うとはよく言ったもので、
ヘドラの目はとても悲しく
人間たちに言いたい事がありそうな寂しい感じがした。
ゴジラも同じく人間には心底ガッカリしたような
ヘドラとの決着の付け方でした。
対決シーンはプロレス路線から時代劇路線に移行
と言う感じで少しおふざけは和らいだ感じはしたけど、
やはり驚くのは空飛ぶゴジラではないでしょうか?
色んな意味でゴジラシリーズを代表する作品では
ないでしょうか。
0035 自衛隊が送電線を振り切って壊すのはお約束
1971年公開
ゴジラ映画最初の劇場鑑賞。
音楽に知ってる曲が使われなかったのはなんだかなー
オープニングの唄もちょっと待ってよー。
公害を前面に押し出したのは理解できるが
いつの間にゴジラは正義の味方として
悪者を懲らしめる側に立ったんや?
それと空飛ぶのはやはりアカンやろ
60点
劇場鑑賞1971年8月1日 梅田劇場
パンフ購入
シン・ヘドラ待ってます
昭和ゴジラシリーズ11作目
もはや説明不要の大人気怪獣(?)ヘドラの作品
不穏なオープニングから始まり、不気味なヘドラが全編に渡って登場し、徐々に進化を遂げていく
ヘドラのヘドロを受けて白骨になるシーンなど、ショッキングなシーンも多い
子供の頃、VHSで見た時怖かったなぁ…
当時の公害問題を前面に出しており、社会風刺も効いている
その対比でヒーロー役に徹しているゴジラが空を飛んだりユーモア溢れており、とてもかわいい
SDGsが叫ばれている今こそヘドラを題材に一本映画を作れそうな気がする
土ヘドラ、森ヘドラ、海ヘドラ、街へドラが登場し、あらゆるヘドラが大暴れするシン・ヘドラいかがですか?庵野さん
ストーリー:☆☆☆☆★
怪獣・特撮:☆☆☆☆★
俳優の演技:☆☆☆☆★
音楽 :☆☆☆☆★
「超低予算ながらカルト的人気の秀作!レジェンダリーゴジラエグゼクティブプロヂューサー坂野義光唯一のゴジラ監督作にして異色作」
IMAX大画面で観たいゴジラ作品の一つ!
★独自採点(75):東宝チャンピオンまつり、円谷英二の没後初めて作られたカルト的人気の異色作。超低予算制作期間は5週間ながら生まれた驚異的作品(同じスタジオで二班同時に毎日30カット、凄すぎ)
特技主要スタッフのほとんどが東宝を辞職もしくは異動させられるなど、当時の東宝特撮の現場はほぼ崩壊状態のなかミニチュアはほとんどあり物のかき集め、ロケも開通前の環八で撮影など撮影途中で予算が尽きたがなんとか完成した奇跡の作品。予算が無い中制作田中の「これをやらなければもうゴジラは撮れない、なんとか撮る方法を見つけられないか?」という思いと、一度は特殊技術課を解体したが円谷英二の残した技術をなくすのはまずいという思いが強くなったエポックメイキングな作品。本作から実質爆破の中野こと中野昭慶が実質特技デビュー(日本沈没73’・対メカゴジラ74’以降からスケールアップ!)
制作田中友幸、監督坂野義光、特技中野昭慶(監督扱いではないが実質三代目ゴジラ特技監督の最初の作品)、音楽真鍋理一郎
通称:総進撃ゴジ流用(ヘドゴジ)・登場怪獣:ヘドラ(水中期・上陸期・飛行期・完全期)・防衛:自衛隊(63’自衛隊ヘリヘドラ討伐のため)・昭和46年7月24日封切り・85分・上陸地(田子ノ浦)・破壊地(富士市工業地帯・富士裾野)・特撮爆破炎上破壊規模A
飛行形態となって逃げるヘドラを追うゴジラの飛行シーンは賛否両論となったが、ヘドロ怪獣ヘドラ(井上泰幸デザイン)や当時流行のサイケデリックな映像などはいま見ても面白い、劇中でヘドラのアニメーションが出たり、従来の昭和ゴジラ作品のような防衛隊などの架空組織ではなく、自衛隊が久々に自衛隊の名前で登場するのも特徴である。前作が超子供向け作品だったことからは若干異なり70年代の公害問題を含んだテーマやヘドラのキャラクターデザインは大人も十分楽しめる出来で素晴らしい。コンビナートの爆破シーンの特撮なども迫力があり、個人的には昭和ゴジラの中でも大画面で見たい作品。ヘドラのヘドリューム光線に対抗したのかゴジラがスペシウム光線ポーズをとるシーンがあったりしたのも面白い。昭和ゴジラで怪獣タイマン対決は、『キングコング対ゴジラ』(1962年)のキングコング以来9年ぶり。
ラストの攻防、自衛隊が建造した巨大電極板にゴジラが火炎を放射、電流が流れ高圧電流を受けてヘドラが乾燥して一旦倒れる、体内からは一回り小さなヘドラが出現し、飛行して逃亡するヘドラをゴジラは放射能火炎を推進力として用いた飛行で追跡して墜落させ、再び電極板の間に押し込みながらその身をむしり、高圧電流と放射能火炎で完全に乾燥させて駆逐すると言う相当思い切った演出をみせ、「みどりを 青空を 青い海を 命を 太陽を 返せ」の歌の後、人間たちの一部である自衛隊員たちを睨みつけてから大地の果てへと帰っていった。
印象的なラストの葛飾北斎神奈川沖浪裏のショットは空も海も綺麗だった頃の日本の象徴、その後のもう一匹?というのは公害は簡単にはなくならないという警告の意味があったそうだ。
超低予算ながら第二次怪獣ブームもあり観客動員数は174万人、東宝も一大改革を行なった年、かつ製作の田中友幸が倒れた間に撮影されたが結果として(田中からはクレームあるも)高評価。
登場:田子ノ浦・港からダイビングあり・くぼみに落ちたゴジラにヘドラがヘドロを流し込むシーンは海ゴジラ (大戦争ゴジ)ラストは富士の平原へと消えて行く。
好きなショット:ゴジラのスペシウム光線ポーズ・赤い返り血を浴びたゴジラ
時代:(封切料金¥600※実勢価格約半額)カラーテレビ普及率40%超え(NHK放送全面カラー化)、仮面ライダー・帰ってきたウルトラマン第二次怪獣ブーム、71〜74第二次ベビーブーム、淀橋浄水場跡に京王プラザホテルが開業、多摩ニュータウン入居開始
1970:日本万国博覧会開幕、よど号ハイジャック事件、東京の消費者物価が世界一、日本初の歩行者天国が銀座、新宿、池袋、浅草で実施
<ファッション>
ノーブラ旋風、スケスケルック
<ヒット商品>
セリカ(自動車)、トミカ(ミニカー)、「anan」創刊
<流行語>
ウーマン・リブ、三無主義、しらける
<映画・演劇・テレビ・CM>
「昭和残侠伝死んで貰います」監督:マキノ雅弘
「座頭市と用心棒」監督:岡本喜八
「イージー・ライダー」監督:デニス・ホッパー
「明日に向かって撃て」監督:ジョージ・ロイ・ヒル
モーレツからビューティフルへ(CM:富士ゼロックス)
ディスカバー・ジャパン(CM:国鉄)
1971:マクドナルド日本第1号店が銀座店にオープン、円変動相場制移行
<ファッション>
ポロシャツブーム
<ヒット商品>
カラオケ
<流行語>
アンノン族、脱サラ(脱サラリーマンの略で、会社をやめ、独力で事業を起こすこと)
<ベストセラー・コミック・雑誌>
「nonno」創刊
「遊」創刊
「カムイ伝」第1部終了
映画・演劇・テレビ・CM
「儀式」監督:大島渚
「栄光のル・マン」監督:リー・H・カッツィン
「小さな恋のメロディ」監督:ワリス・フセイン
「八月の濡れた砂」監督:藤田敏八
『仮面ライダー』
深夜テレビ
「23時ショー」(テレビ朝日)
シリーズ中、異色の一作!カルトなゴジラ!
子供の頃、この映画の印象は変な映画でした。
ただ、手が骨になっちゃったり、片目が潰れたり、傷だらけになりながらも勝利したゴジラに感動した覚えがあります。
一番、印象に残っているのは、空を飛んだってことですけど・・・
何年かして、怪獣好きの子供にビデオを見せながら、改めて見直した時に、この作品の面白さを再度、実感しました。
公害への批判をストレートに押し出しながら実にその時代を描いています。 これはシリーズのどの作品にもいえるんですが、その時々の世相をストーリーや映像に織り込み、昭和史でも見ているようで、改めてゴジラシリーズを素晴らしい映画だと痛感しました。
そして、今回、改めて見直したんですが、やっぱり面白いですね。
水銀、コバルト、カドニウム~♪なんて、メチャクチャ変な主題歌から始まる。
作品全体からシュールでサイケな雰囲気が漂う。そして、当時の公害問題の世相が感じられる。
それから、この作品ではゴジラが完璧にヒーローとして描かれている。主人公の少年同様、自分達を守る正義の味方として、ゴジラを見ていたことを思い出す。苦戦の末に勝利するって言う王道のまんまだったことに納得。
当時のゴジラシリーズは、特撮部門とドラマ部門で2人の監督が指揮していたらしいのだが、この作品に関しては全てを1人で行ったらしい。だからだろうか、ゴジラのバトルシーンも、他の作品とは異なる緊張感みたいなものを味わえた気がする。
核の申し子 vs 公害の申し子‼️
この作品はゴジラ映画史上最も汚い作品(笑)‼️ヘドラは公害から生まれた怪獣‼️ヘドロという人間が生んだ死の世界から生まれ、ヘドラが通過すると死のイメージが広がる、どーしようもない邪悪な存在‼️冒頭の実際の公害映像も汚いし、クラブで歌い踊る若者たちの頭が奇形魚と化すイメージも変だし、ヘドラがヘドロ弾を発射するのはまるで「う◯こ」みたいだし‼️とにかく汚ーい‼️一方で、ヘドラが硫酸を噴出しながら飛行すると、その下で体育の授業中だった女子生徒たちがバタバタと倒れたり、ヘドロ弾で多数の人々が犠牲になる恐ろしい描写も‼️そんな汚さや恐ろしさを少しでも和らげるため、アニメーションが挿入されたり、飛行ゴジラというチョット微笑ましいというか、ユーモラスな描写もあってバランスが保たれているような印象があります‼️そして海で暮らしてるゴジラも、その海を人間に汚されているわけで、ヘドロまみれになりながらヘドラを倒した後の、人間たちへのガン飛ばしも印象的‼️とにかく、この「ゴジラ対ヘドラ」という作品は、怪獣映画で公害問題を扱ったこと自体異質だと思うし、多分二度と作られない作品として唯一無二の存在感を放っている作品ですね‼️
全35件中、1~20件目を表示